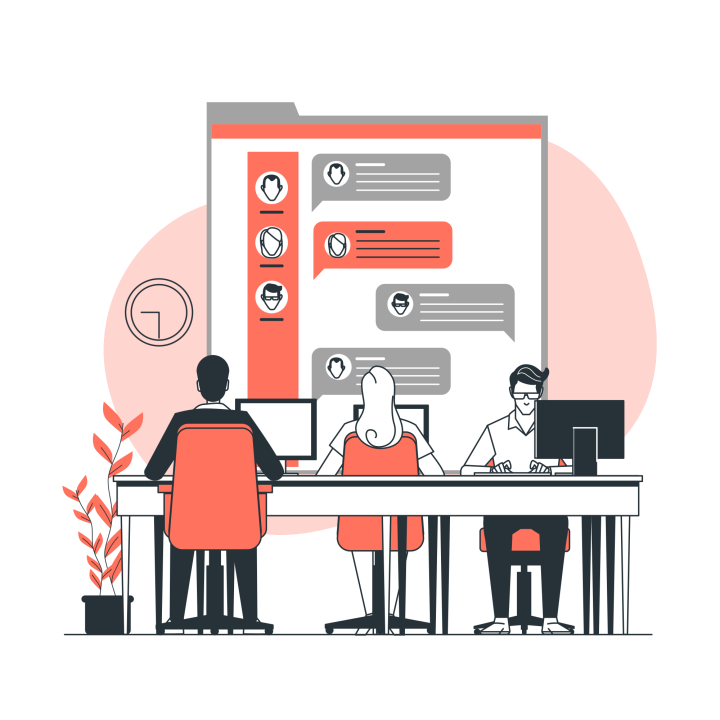災害や緊急事態が発生した際に企業がその影響を最小限に抑え、迅速に通常業務を再開できるようにするための計画、それがBCP(事業継続計画)です。
この記事では、BCPの基本的な意味から策定・構築方法、そして実際の対応や訓練に至るまでを事業継続計画の全体像をわかりやすく解説していきます。
事業の存続を左右する重要な取り組みであるBCPのポイントを押さえ、BCPの重要性について考える機会にしていきましょう。
食品商社営業からシステムエンジニアへと転職後、バックエンドエンジニア(Java, PHP)として尽力。開発リーダーを含む上流工程〜下流工程に携わる。IT関連記事から芸能・法律など幅広ジャンルにて執筆。
BCP(事業継続計画)とは

BCP(事業継続計画)とは、自然災害や人為的事故などの緊急事態が発生した際に企業が重要業務を継続または迅速に回復させるための予め定められた対策や手順のことです。
BCPの意味とは?
BCP(Business Continuity Plan)は、自然災害や人為的なトラブルが発生した際に迅速に通常の業務を再開できるようにするための計画です。
具体的には、2011年の東日本大震災のような大規模な災害時に企業がどのように対応し、どの業務を優先して再開するか、必要なリソースは何か、といった事項を事前に検討し、計画に落とし込むことを指します。
この計画には、リスク評価やビジネスインパクト分析(BIA)、復旧戦略の策定などが含まれます。
BCPの重要性
BCPの策定は単に災害時の対応策を準備するだけではなく、企業のレジリエンスを高めて事業の持続性を確保するために不可欠です。
例えば、西日本豪雨や新型コロナウイルス感染症の拡大などの予期せぬ事態が発生した際にも、事業を継続して顧客へのサービス提供を維持することができます。
また、BCPの存在は、取引先や顧客、投資家に対して、企業が危機管理に真剣に取り組んでいることを示すことができ、企業の信頼性やブランド価値を高める効果もあります。
さらに、BCPを策定する過程で企業の中核となる業務やプロセスが明確になり、効率的な運営にも役立ちます。
BCPの策定と構築

企業が直面する様々なリスクから事業を守りつつ緊急事態においても重要業務を継続するためには事前の準備が不可欠で、このために策定されるのがBCP(事業継続計画)です。
BCPの策定と構築は企業の存続だけでなく、顧客や社会への責任を果たす上で極めて重要なプロセスとなるでしょう。
ここでは、BCPを策定して実際に構築するための手順について、具体的なステップを解説していきます。
BCPの策定手順
事業継続計画を策定するには、体系的なアプローチが求められます。
初めにリスクアセスメントとビジネスインパクト分析(BIA)を行い、その結果を基に事業継続の目標と戦略を設定します。
そして、具体的な対応策を策定して実装に移ります。
このプロセスを通じて企業は潜在的なリスクに対する準備と対応の枠組みを構築し、事業の継続性を確保するための基盤を築きます。
リスクアセスメントとビジネスインパクト分析(BIA)
リスクアセスメントとビジネスインパクト分析(BIA)は、BCP策定の基礎となる重要なステップです。
リスクアセスメントでは、自然災害や人為的ミス、サイバー攻撃などの企業が直面しうる様々なリスクを特定し、それらのリスクがビジネスに与える影響の大きさと発生確率を評価します。
例えば、地震や洪水のリスクが高い地域に工場がある場合、そのリスクを特定してその影響を分析します。
ビジネスインパクト分析(BIA)では、特定されたリスクが実際に発生した場合に企業の重要な業務やプロセスにどのような影響を及ぼすかを評価します。
これには、業務の中断による収益損失、顧客満足度の低下、法的責任の発生などが含まれます。
BIAの結果は、どの業務が最も重要で最初に復旧させるべきかを決定する際の基礎となります。
事業継続計画の目標と戦略の設定
BCPの目標と戦略の設定では、リスクアセスメントとBIAの結果を基に事業継続のための具体的な目標とそれを達成するための戦略を策定します。
目標設定には、重要業務の復旧時間(RTO)やデータ損失を許容する最大期間(RPO)などの具体的な数値目標を定めることが含まれます。
例えば、顧客サポート業務のRTOを24時間以内に設定する場合、その時間内に業務を再開できるような準備が必要です。
戦略策定では、目標達成のために必要なリソース、プロセス、技術などを検討して事業継続のための具体的な計画を立てます。
これには、代替作業場所の確保、重要データのバックアップ体制の整備、緊急時の連絡網の構築などが含まれます。
対応策の策定と実装
対応策の策定と実装フェーズでは、策定された戦略を具体的なアクションプランに落とし込み実際に実装します。
これには、事業継続計画書の作成、必要なリソースの確保、従業員への教育訓練、そして計画のテストや演習などが含まれます。
例えば、災害発生時に従業員が避難するための手順や重要なデータを復旧するための手順など、具体的な対応策を文書化して関係者全員が理解しやすい形で共有します。
実装フェーズでは計画された対応策が実際に機能するかを確認するために、定期的なテストや演習を行います。
これにより、計画の不備や改善点を発見してより効果的な事業継続を目指します。
BCPの構築ポイント
BCPの構築においては、ただ計画を策定するだけでは不十分です。
その計画を実際に機能させるためには、組織全体の関与とリーダーシップ、必要なリソースの確保と管理、そして効果的なコミュニケーションと連絡手段の確立が不可欠です。
これらの要素が適切に組み合わさることで、緊急事態に迅速かつ効果的に対応し、事業の継続を確保することが可能になります。
リーダーシップと組織の関与
BCPの成功は、組織のトップからの強力なリーダーシップと全社員の積極的な関与に関わってきます。
例えば、ある大手製造業ではCEO自らがBCP委員会の議長を務め、定期的にリスク評価と計画の見直しを行っています。
このような取り組みにより組織全体にBCPの重要性が浸透し、各部門が自主的にリスク対策を講じる文化が根付いていきます。
また、従業員に対しては緊急時の役割と責任を明確にして、定期的な訓練を通じてその意識を高めていくことが大切です。
リソースの確保と管理
BCPを実行するためには、人的、物的、財務的なリソースの確保が必要です。
中小企業では限られたリソースの中で最大の効果を得るために、重要度と緊急度を基にリソースを配分しています。
例えば、IT企業ではデータセンターの二重化とクラウドバックアップを優先的に行い、事業の中核をなすシステムの稼働を保証しています。
また、従業員に対してはリモートワークの環境を整備し、物理的なオフィスが利用できない状況でも業務を継続できるようにしています。
コミュニケーションと連絡手段の確立
緊急事態発生時の迅速な決定と行動は、効果的なコミュニケーションと連絡手段によって支えられていることをわすれてはなりません。
サービス業の企業では、緊急連絡網を構築して災害発生時には自動的に安否確認が行われるシステムを導入しており、これによって従業員の安全確保と迅速な情報収集が可能となるため、状況に応じた適切な対応を行うことができます。
また、外部の関係者とのコミュニケーションも重視し、顧客や取引先に対しては定期的にBCPに関する情報を共有して信頼関係の維持に努めています。
BCPの対応と訓練
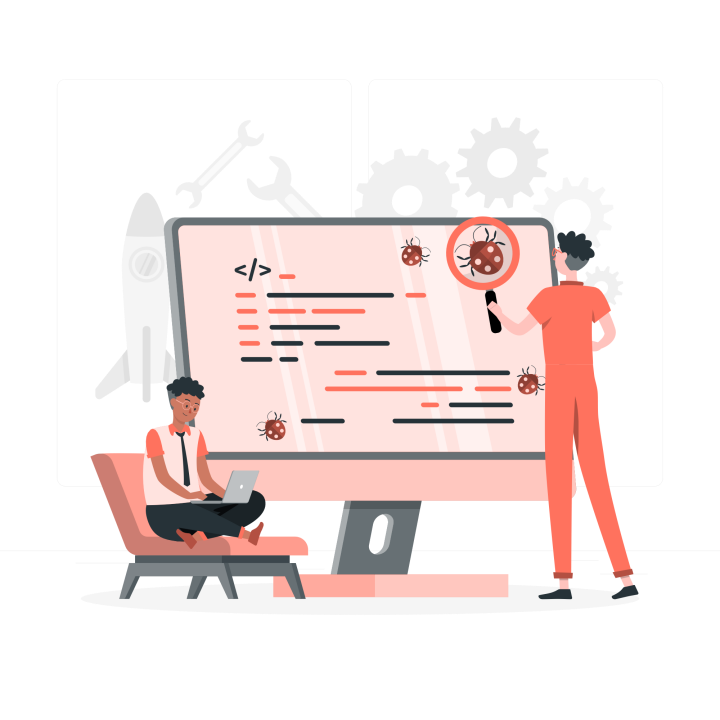
事業継続計画(BCP)の有効性は、実際の緊急事態における対応と定期的な訓練によって大きく左右されるでしょう。
計画がどれほど緻密であっても、実際の災害時や非常事態に適切に対応できなければ意味がありません。
また、訓練を通じて計画の不備を発見し、改善を繰り返すことが重要です。
ここでは、実際の対応と訓練の重要性に焦点を当て、効果的なBCPの運用方法について解説していきます。
BCPの実施と対応
実際の対応能力は事前の準備と訓練によって大きく変わるため、計画の実施とその後の対応はBCPの成功に不可欠な要素となります。
緊急事態が発生した際の具体的な対応策とインシデント管理と報告体制の整備について詳しく見ていきましょう。
緊急事態対応と行動ガイドライン
緊急事態対応と行動ガイドラインは、具体的な災害や非常事態が発生した際に従業員が迅速かつ効果的に行動できるようにするための指針です。
製造業の企業では、地震発生時の避難ルート、安全確認の手順、緊急連絡網などを明確に定めたマニュアルを作成し、全従業員に配布しています。
また、定期的な避難訓練を実施して実際の災害時にパニックにならずに冷静に対応できるよう訓練しています。
このように、事前に具体的な行動ガイドラインを設定して定期的な訓練を行うことで、緊急事態時の対応力を高めることができます。
インシデント管理と報告体制の整備
インシデント管理と報告体制の整備は、緊急事態が発生した際に迅速に情報を収集して適切な対応を行うための体制です。
IT企業などでは、サイバー攻撃を検知した際にインシデント対応チームが即座に活動を開始し、影響範囲の特定、被害の最小化、関係者への情報提供などを行います。
また、事後にはインシデントの詳細な分析を行い、報告書を作成して再発防止策を検討していきます。
このように、インシデント管理と報告体制を整備することで、緊急事態に迅速かつ効果的に対応して将来的なリスクを低減することが可能になります。
BCPの訓練と演習
BCP(事業継続計画)の策定後、その計画が実際の緊急事態において機能するかを確認するためには定期的な訓練と演習が不可欠であり、これを行うことで計画の有効性を検証して必要に応じて改善を行うことができるようになります。
訓練と演習を通じて従業員は緊急事態発生時の対応手順を身につけられるので、組織全体の対応能力を高めることにもつながる重要な事項となります。
ここでは、定期的な訓練の重要性とBCPの演習とシミュレーションの実施方法について詳しく説明していきます。
定期的な訓練の重要性
定期的な訓練は、BCPの有効性を保持しつつ継続的な改善を促進する上で極めて重要です。
例えば、ある製薬会社では年に2回、全従業員を対象にした避難訓練を実施しており、この訓練では地震や火災などの緊急事態を想定して、避難経路の確認、避難所での集合手順、緊急連絡網の使用方法などを徹底的に確認しています。
また、訓練後には参加者からのフィードバックを収集して計画の不備や改善点を特定しています。
このように、定期的な訓練を通じて従業員の危機意識を高めることで、計画の実効性を確保することができるようになるでしょう。
BCPの演習とシミュレーションの実施
BCPの演習とシミュレーションは実際の緊急事態を想定した訓練であり、計画の実践的な検証を行う機会となるでしょう。
例えば、ある金融機関ではサイバー攻撃によるシステムダウンを想定したシミュレーションを年に1回実施しています。
このシミュレーションではIT部門が主導となり、攻撃の検知からシステムの復旧、顧客への情報提供までの一連の対応を実際に行います。
演習を通じて対応プロセスのギャップやコミュニケーションの問題点を明らかにしていくことで計画の改善につなげています。
このようにして、実際に近い状況を作り出すことで計画の有効性を確認し、対応能力を向上させることができます。
BCPのまとめ

この記事では、BCPの基本概念から策定・構築、実際の対応や訓練に至るまでをわかりやすく解説してきました。
BCP(事業継続計画)は、災害や緊急事態において企業活動を迅速に再開して継続させるための重要な取り組みです。
リスクアセスメント、ビジネスインパクト分析、目標と戦略の設定、そして対応策の策定と実装がBCP策定の主要ステップであり、組織全体の関与とリーダーシップ、リソースの確保、効果的なコミュニケーションなどがBCPの成功に不可欠であることも理解しておく必要があるでしょう。
BCPに限らずITシステム全般に関してお悩みの方は、知識と経験が豊富なJitera社に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。