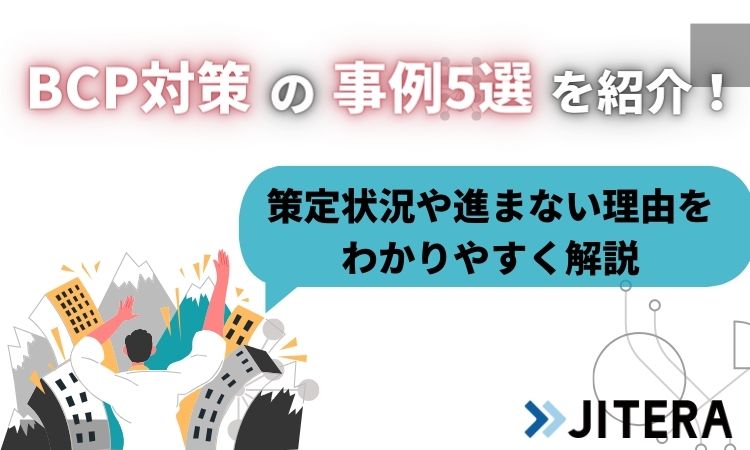災害やトラブルが発生したとき、あなたの会社はどれだけ早く立ち直れるでしょうか。
BCP(事業継続計画)は、災害大国日本で企業が生き残るための必須戦略です。
しかし、対策が進んでいない企業が多いのも現実です。
本記事では、BCP対策の成功事例5選を紹介し、その策定状況や進まない理由についてもわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、あなたの会社も災害に強い体制を築くための具体的なヒントが得られます。
国立の情報系大学院で情報工学、主にUI/UXを学んだあと、NTT子会社に勤務。 退社後はフリーランスとして、中小規模事業者様のIT化、業務自動化を支援しています。 DX推進の提案やPythonなどを用いた専用RPAツール開発のほか、市営動物園の周年企画などにもITエンジニアとして参画させていただきました。
BCP対策とは?

BCP(Business Continuity Plan : 事業継続計画)とは、企業が災害や事故などの緊急事態に遭った際に、重要な事業を継続または迅速に再開できるようにするための計画と準備のことです。
具体的には、下記が該当します。
- 緊急時の対応手順を整備
- 代替施設の確保
- 重要データのバックアップ
- 人員の配置
- サプライチェーンの維持
BCP対策を導入することで、企業は被害を最小限に抑え、迅速な復旧を図り、顧客や取引先からの信頼を維持できます。
特に中小企業においては、経営資源が限られているため、BCP対策の重要性が高まっています。
BCP対策が必要となった背景
実際にBCPが広まったのは、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロです。全世界の企業が、事業継続の重要性を考えるようになりました。
一方、日本国内でBCP対策に注目が集まったきっかけは、2011年に起きた東日本大震災です。
この震災の影響は長期間続き、大規模な範囲に壊滅的な打撃を与えました。
長期間に渡って様々なビジネス活動が停止し、BCP対策が不十分であった多くの企業はそのまま倒産にまで追い込まれることになります。
また、企業が存続の危機に晒されるケースは、自然災害にとどまりません。
テロ攻撃や大規模な情報漏洩、貿易摩擦や武力紛争など、社会には様々なリスクが存在し、予想外の緊急事態に直面します。
BCPの根幹は「事件や災害を完全に予測できないため、有事勃発の際に素早く事業を立て直せるように計画する」ことにあります。
したがって、BCPは危機そのものを防ぐことを目的とした防衛的な措置ではありません。
主に、早期復旧と危機発生中の事業継続に重点を置いた計画です。
BCP対策の事例5選

災害の完全な予測や対策は不可能なため、できるかぎり想定内に収めるよう努力することが大切です。
その際に、過去の事例は大いに役立ちます。
ここでは、過去のBCP対策事例を紹介し、そこから学べるポイントについて解説します。
- NTTによるBCP調査例
- 北海道経済産業局の北海道胆振東部地震調査報告
- トヨタL&F 福島株式会社の事業継続判断
- ソニー株式会社のグローバルBCP戦略
- 共栄資源管理センター小郡のBCP対策
上記5つの詳細を確認しましょう。
NTTによるBCP調査例
2011年の東日本大震災を受けて、NTT データ経営研究所が発表したBCP対策状況チェック項目としては、以下のようなものがあります。
- 初動段階での対策
- 災害・事故など発生時の体制設置計画
- 対策本部立ち上げ判断基準の設定
- 被災・被害状況の確認・連絡手段の策定
- 従業員・職員への退社・出動などの判断指針の策定
- 応急・復旧段階での対策
- 復旧方針
- 優先して復旧すべき業務・事業の選定
- 明確な復旧(いつまでに、どの程度まで、どの業務・事業を復旧させるか)への目標設定
- 自社リソースの復旧
- 自社施設・設備などについての復旧手順や代替策の用意
- 自社システムについての復旧手順や代替策の用意
- 人的リソース(従業員や職員など)についての代替策の用意
- 外部連携
- ステークホルダーとのサプライチェーンについての復旧手順や代替策の用意
- ステークホルダーとの金流や情報の連携についての復旧手順や代替策の用意
- マスコミや自社サイトなど、外部メディアへの情報発信手順や代替策の用意
- 教育と訓練
- 災害・事故が発生したことを想定した訓練や教育の実施
また、NTTが調査した結果、復旧計画が形骸化している企業が多く、資料内では
「BCP計画は万能であり、手順さえ定めておけば、あらゆる業務を早期に復旧可能である」という誤解は少なくない
と策定後に行うBCP維持活動の重要性について注記しています。
北海道経済産業局の北海道胆振東部地震調査報告
2018年に起きた北海道胆振東部地震は、各地に大きな被害をもたらしました。
その後札幌商工会が行った聞き取り調査では、地震による直接的な被害よりもむしろ、停電による影響が大きかったとした回答が上位を占めました。
- 停電・断水等により生産活動や営業活動に支障→461件
- 公共交通機関の運休による従業員の出社困難・帰宅困難→404件
- 停電により営業できず(節電により営業時間が短縮し)売上が減少→284件
その他、中小企業からの聞き取り調査では、以下のような意見を上がっています。
- BCP対策に防災商品の追加、安否確認の手段整理に加え、自家発電手段の検討を行っている(建設業)
- 従業員、顧客、ビジネスパートナーの緊急連絡手段に多く問題があることが分かり、見直しを実施した(情報通信サービス業)
そんな中、自家発電を行い事業を継続させた事例もあります。
| 施設名 | 発電方式 | 経緯 | 地域支援 |
| 北こぶし知床HOTEL&RESORT | A重油による発電 | 大雪に備え30年前から停電に備えた自家発電を導入しており、災害時も事業を継続 | 知床温泉旅館協同組合と連携し、域内ホテルと共に大浴場や宴会場を無料開放し、簡易避難場を提供 |
| そらちぶと調剤薬局 | LPガスによる発電 | 災害対応設備用に非常用発電機を導入していた | SNS告知を通じ、携帯充電サービスを開始 停電時でも市内で唯一薬局の営業継続が可能に |
| 札幌創世スクエア(商業ビル) | 天然ガスによる発電 | ビル内の天然ガスコージェネレーションシステムによる自律分散型システムによって、ビル内の主要機能が稼働 | 札幌市と連携し、観光客や帰宅困難者の受け入れ、充電スポットを提供 |
| 湯の杜ぽっけ(カフェ・特産品販売) | 天然ガスによる発電 | 豊富町産天然ガスによる自家発電で、町内で唯一停電を回避し、復旧まで営業を継続 | 豊富町温泉街と連携し、トイレ・水道・温泉・充電コンセントなどを無料開放し、災害情報とともに復旧までライフラインを提供 |
元々は大雪に備え用意した発電設備が、大地震という想定外の事態に活躍し、域内復興に大きく貢献しました。
またBCP対応がうまく行った企業が、地域内の組織と連携することでより効果的な復興支援を果たしたことも重要な教訓になりました。
トヨタL&F 福島株式会社の事業継続判断
2019年の東日本台風では、多くの企業が想定外の洪水災害に見舞われました。
その中でもこの記事では、トヨタL&F福島の例を取り上げます。
同社は会社を郡山中央工業団地へ移転する際に、過去の教訓からBCP対策として地盤のかさ上げや防水壁の設置による水害リスク対策を行っていました。
しかし、東日本台風は未曾有の大洪水を巻き起こし、洪水は谷田川の決壊によって防水壁を超え、本社が浸水します。
阿部賢輔社長も当時を振り返り、
「移転時にハザードマップを参考にした水害対策を行ったが、谷田川の決壊は想定外だった」
と述懐しました。
しかし、この想定を遥かに超える浸水に対し同社は、現在地で事業を継続することを決定します。
事前の水害対策を更に推し進める形で、以下のような対策を実行しました。
- 地盤のさらなるかさ上げ
- 防水壁の強化
- 事前取り決めの優先度に沿った重要設備の移設
また、この教訓を元に新たにBCPを改善し、訓練などを通じたブラッシュアップと社内への浸透に努めています。
事前にどれだけ対策を行っても、未曾有の大災害は想定を超えてきます。
しかし、事前の対策経験があるからこそ、事態に直面しても冷静な判断の元、事業継続の道が開けると言えます。
参考:「事業継続の意志をハード強化とBCPに込めて」
参考:朝日新聞
ソニー株式会社のグローバルBCP戦略
ソニーは、多国籍企業としてそのグローバルな生産ネットワークを守るために、地震や洪水などさまざまな災害への対応策を事業継続計画に組み込んでいます。
この計画には、代替生産拠点の設定や従業員の安全確保に関する厳格な方針を含みます。
2011年の東日本大震災やタイの洪水、2016年に発生した熊本地震において、エレクトロニクス業界にも大きな影響が発生しました。
しかし、生産中断の影響を最小限にとどめられたのは、これまでの経験を生かした入念なBCP戦略があったからです。
また、建物や設備の火災早期発見・延焼拡大防止等の仕様については、ソニーグループ指針に基づき策定しています。
具体的には、以下のような措置です。
- 半導体製造事業所では毎年セルフチェックを行う
- 定期的に本社担当部門による現地調査を受ける
これらを通じた課題抽出・改善計画立案等のPDCAサイクルを確立することで、より確実なリスク低減を実現しました。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に対しても、危機管理体制を立ち上げるなど、事業影響を最小限にとどめるための対応を実施しています。
このようにソニーは、事業中断に備えた危機管理・事業継続の体制をつねに整えています。
その実効性を高めるための取り組みが、早期復旧の強化につながるBCP対策です。
共栄資源管理センター小郡のBCP対策
BCP対策の策定により、企業価値向上に成功したケースがあります。
福岡県の有限会社共栄資源管理センター小郡では、BCP策定後、取引先との契約維持、地域からの信頼感向上、社員の意識改革などのメリットがありました。
同社がBCP対策を重視するようになったきっかけは、台風による災害廃棄物処理の経験です。
策定したBCPでは、以下の4つに想定災害を分類しました。
- 震度6強程度の地震
- 猛烈な台風
- 火災
- 感染症による集団感染
そして、具体的な対策は以下の通りです。
- 清掃車の車庫を3棟に分散
- 発電機・太陽光発電・電気自動車による電気供給の確保
- クラウド及び自社サーバによるデータ管理保存
- NTT及びケーブルテレビ回線による通信回線の確保
- 防災関連用品の備蓄
- 購買先・供給先の多様化
- 緊急連絡網とSNSによる社員の安否確認
また、災害時の優先業務を定め、公衆衛生に関わるごみを1週間以内に収集することなどを定めました。
このような被災時の事業継続は、他社との差別化や信用力向上につながります。
BCP(事業継続計画)の作成ステップ

では、事業の継続を行うためにはどのような計画を行うべきでしょうか。
BCP作成手順は、以下のステップ通りに実行するのがおすすめです。
- 1. 目的設定
- 2. 重要業務の洗い出し
- 3. リスクに優先順位をつける
- 4. 実現可能な具体策を決める
- 5. BCPの運用・維持
それぞれ確認しましょう。
1. 目的設定
まずは、BCPの目的を明確にしましょう。
計画の策定を急ぐあまりに、他社の指標や出来合いのテンプレートをそのまま流用しても、実効性はありません。
災害時には多くの情報錯綜や混乱が起こり、通信や交通が遮断されます。
自社のビジネス形態や実情、社風に沿った実効性のある計画を勘案しなければなりません。
例えば、以下のようなポイントを明確化することで、自社の方針や目的設定が明確化しやすいです。
- 社員や顧客を守るために行うこと
- 自社の信用を守るために行うこと
- 自社の経営理念やビジネス方針のもとに行うべきこと
目的設定で重要なのは、「自社のビジネスを如何に復旧し、継続するのか」です。
「なぜ、BCP策定をするのか」という目的を見失わないよう、ビジネスの継続性を念頭に自社に適した基本方針を決定しましょう。
2. 重要業務の洗い出し
BCP対策の策定では、業務の継続優先度を洗い出すことが重要です。
この作業は、部署横断的なプロジェクトチームを編成して進め、事務局や総務部が調整支援を実施する場合もあります。
また、全社員への情報共有や、取引先・協力会社との連携も検討します。
プロジェクトチームは、緊急事態発生後に維持・復旧すべき事業、データ、システムの優先度を取りまとめましょう。
判断基準は、売上や損害の大きさ、市場影響力の維持などです。
目的に応じて、ブランド力、雇用、地域協賛など、重視する指標も異なります。
洗い出した指標と優先度に基づき、分類する事業は以下の通りです。
- 緊急事態中も維持するべき事業
- 緊急事態後、すぐに復旧するべき事業
- 事態が落ち着いてから復旧計画を行う事業
- 最悪縮小や廃止もやむを得ない事業
優先度の高い事業からテコ入れいていきます。
3. リスクに優先順位をつける
事業の優先度を付けたあとは、それぞれに起こりうるリスクの洗い出しです。
洗い出し手順は、一般的には以下の通り進めます。
- 1.起こりうるリスクの種類を分類する
- 2.各部署へリスニングを行い、プロジェクトチームが取りまとめてリスクを洗い出す
- 3.取りまとめた「起こりうるリスク」について、共通の認識として確認・周知する
リスクの分類は、業種や企業の形態によって異なりますが、以下のような分類される場合があります。
| リスクの種類 | リスクの形態 |
| 災害に関わるリスク |
|
| 国際・国内情勢に関わるリスク |
|
| IT/ICTインシデントに関わるリスク |
|
| 人に関わるリスク |
|
| 経営に関わるリスク |
|
リスクの洗い出しが終われば、整理したリスクの優先度を付けます。
自社の重要業務がどのようなリスクに弱いのかを確認し、優先すべき初動対応を決めておきましょう。
未曾有の緊急事態は予測の付かない被害をもたらすため、影響度や発生確率などを整理することが重要です。
その結果として、緊急事態に直面した際に冷静な判断ができるようになります。
例えば、自然災害発生した場合、優先されるのは人命の安全確保です。
そのため、安全確保と情報収集、正確な情報の共有が重視されやすくなります。
一方サイバー攻撃の初動では、人命への直接的な影響は比較的少ないため、現状の確認や復旧計画の認識共有が重視されやすいです。
4. 実現可能な具体策を決める
リスクが明確になったところで具体的な対策の策定を行います。
明確化した事業優先度やリスク優先度と、自社の事情や関連企業との連携を勘案して、具体策を検討しましょう。
具体策は業種や目的によって大きくアプローチが変わりますが、基本的には
- 人に対する策
- モノに対する策
- 金に対する策
- 組織体制に対する策
- 情報に対する策
の5つに振り分けて考えると具体策を整理しやすいです。
人的リソースはどうか
社員の復帰がスムーズでなければ早期復旧は叶いません。
- 従業員の被災状況の把握
- 被害時の少人数またはシステムダウン時でのオペレーション方法
- 出社できない社員への対応
などは明確にしておくべきです。
施設や設備の復旧計画はどうか
重要施設や内部設備が損壊した場合、早期復旧が困難になります。
また、交通や通信規制によるインフラ障害でも復旧が遅れます。
基本的に損壊した施設や設備はすぐには修理できません。
代替策や緊急時の物流、金流手段の確保は明確にしておくべきです。
資金面はどうか
どのような災害を想定する場合にも、事業が完全に中断した場合、どの程度の損害が発生するのかを把握しておく必要があります。
その間のキャッシュ・フローを確保しておけば、復旧作業に集中することが可能です。
- 保険による損害補償
- 補助金・助成金などの公的な支援制度
- 商工会を始めとする地域の支援や連携
についても把握しておきましょう。
社内体制はどうか
緊急事態後は多くのヒトやモノやコトが混乱しているため、被災後に自社の全ての事業を一度に戻すことは不可能です。
経営陣は社員と協調しながら速やかに優先順位を判断し、的確に復旧指示を出さなくてはいけません。
そのための連絡体制、担当者の明確化、緊急時に意思決定を代行できる仕組みなどは整えておくべきです。
情報やシステムの取扱はどうか
業務に必要なデータやITシステムが損失していた場合も事業の継続は困難です。
また災害時には、現場が混乱しやすいため正確な情報の収集と管理が非常に重要となります。
- 被災中の情報収集と周知を行うための体制
- データのバックアップ計画や冗長性をもたせた分散システムの検討
の2点は明確にしておく必要があります。
例えば、遠隔地に重要データのバックアップがあれば、広域災害や局所的なシステムダウン中でもスムーズに事業を継続しやすいです。
5. BCPの運用・維持
BCP対策は計画を策定したあとが本番です。
「計画したら終わり」ではなく、常にPDCAを回し、BCPの運用・維持・改善を行わなければいざというときに使い物になりません。
策定した計画は、常にPDCAを回し、現状にあった運用・維持のための継続的な改善努力を行う必要があります。
平常時として、以下のようなPDCAサイクルを回せるような体制を作りましょう。
- 現在の事業状況を把握する
- 必要なBCPの準備や事前対策計画を検討する
- 定期的なBCP実行テストを行う
- BCP体制の維持または更新を行う
- BCPの周知状況や社内のBCP対策文化の浸透度を確認し、緊急時対応を定着させる
- 1に戻る
実際に災害が起きたあとも、うまく対策が機能したかどうか検証を行う必要があります。
日本におけるBCP対策の策定状況

帝国データバンクの調査(2023年5月)によると、企業の「BCP策定率」は18.4%です。
一方で「策定意向あり」は48.6%と、新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた2020年をピークに、3年連続で5割を下回っているのが現状です。
※帝国データバンク
事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査
調査期間は2023年5月18日~5月31日 調査対象は全国2万7,930社
新型コロナウイルス感染拡大で、一時的に企業の取り組み意識が高まりましたが、時間の経過とともに相対的に優先順位が低下していると言えます。
BCPを「策定していない」企業にその理由を調査したところ以下の回答がありました。
- 「策定に必要なスキル・ノウハウがない」42.0%
- 「策定する人材を確保できない」30.8%
- 「策定する時間を確保できない」26.8%
企業規模別に見ると、大企業では「策定する人材を確保できない」と36.4%が回答。
それに対して、中小企業では「必要性を感じない」と21.6%が答えています。
BCP策定への取組みに対する意識や優先順位は、新型コロナの流行時をピークに下がる傾向にあります。
しかし、BCPの準備を怠ることで、災害や事件などの突発的な外的要因が企業活動に与えるマイナスの影響は、計り知れないほど大きくなります。
BCP対策の事例から見る注意するべきポイント

BCP対策の事例から学ぶ注意点として、以下の点があります。
- 会社全体で実行する
- PDCAサイクルを回す
- 外部との協力を仰ぐ
- リソースを確保する
- コミュニケーションを適切に取る
詳細は以下の通りです。
会社全体で実行する
BCP対策を成功させるには、全社的な取り組みが不可欠です。
事業継続に関わる重要な計画であるため、経営層から従業員に至るまで、全社員がそれぞれの役割と責任を明確に理解し、進める必要があります。
トップのリーダーシップのもと、全社一丸となってBCP対策に取り組むことが、その効果を最大限に発揮するための鍵です。
そのため、一部の部署や担当者だけでは、十分な成果を上げることはできません。
会社全体で意識を共有し、協力し合える環境を作ることが何よりも大切です。
トップダウンとボトムアップのアプローチを適切に組み合わせ、全社員の理解と協力を得ながら、着実に進めましょう。
PDCAサイクルを回す
BCPの実効性を高めるには、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を継続的に回していくことが重要です。
まず、BCPを策定(Plan)したら、実際に運用(Do)します。そこで得られた知見や課題を評価(Check)し、改善点を洗い出します。
そして、その改善点を反映させてBCPを更新(Act)する流れです。
このサイクルを繰り返すことで、BCPは常に最新の状態に保たれ、実効性が高まっていきます。
事業環境の変化や新たなリスク要因の発生などに応じて、BCPを柔軟に見直していく必要があります。
机上の計画では想定しきれない問題点も、実践を通じて明らかにすることが可能です。
経営層は、このサイクルを確実に回すための体制と資源を整え、全社的な取り組みとして推進していくことが求められます。
外部との協力を仰ぐ
BCPの策定と運用において、外部との協力関係を築くことは重要です。
BCP対策の専門家から適切なアドバイスを受けると、計画の質を高め、実効性が向上します。
業界団体や自治体との連携も、情報収集や資源の確保などの面で大きな助けになるのではないでしょうか。
また、同業他社との情報共有も有効です。
お互いの知見を持ち寄ることで、BCP対策の幅が広がり、より実践的な計画を立てられます。
災害時には、連携先と協力することで事業が継続しやすくなります。
リソースを確保する
BCP対策には、人材や時間、資金が必要です。
まず、社員をBCP関連の教育や訓練に参加させ、社内でリソースを育成します。
ソフトウェアやツールを活用すれば、BCP対策がより効率化になります。
また、リソースの確保において、外部との連携も有効な手段の一つです。
業界団体や他企業と協力し、リソースを共有・分担することで、各社が限られたリソースを優先度の高い部署に集中できます。
さらに、政府や自治体が提供する支援制度も積極的に活用しましょう。
自治体によっては、BCP実践を促進するための助成金制度を設けているところもあります。
コミュニケーションを適切に取る
緊急事態発生時の迅速な決定と行動は、日頃からの効果的なコミュニケーションと連絡手段によって支えられています。
あるサービス業の企業では、緊急連絡網を構築して災害発生時には自動的に安否確認が行われるシステムを導入しています。
その結果、従業員の安全確保と迅速な情報収集ができるため、不安になりません。
また、外部の関係者とのコミュニケーションも重視し、顧客や取引先に対しては定期的にBCPに関する情報を共有します。
日々、信頼関係を構築しておけば、緊急時には迅速かつ正確な情報伝達ができるようになります。
従業員間、経営層、外部関係者との連絡手段を確立し、定期的にコミュニケーションを取りましょう。
まとめ:BCP対策は事例をもとに検討しよう

本記事では、BCP対策の事例5選を紹介し、その策定状況や進まない理由について解説しました。
BCP対策は、実際の事例から多くを学ぶことで、より現実的で効果的な計画を立てられます。
この記事を参考に、機動的なBCP対策を実現し、企業のリスクを最小限に抑えましょう。
株式会社Jiteraでは、ITシステムについてお悩みの企業様に導入や改修のサポートを行っています。
豊富な国内実績をもつエンジニアによって、お客様のお悩みに合わせた解決手段を提案しています。
是非一度、株式会社Jiteraにご相談ください。