スマートフォンの普及により、アプリ市場は急速に拡大していますが、ユーザー獲得競争は激化しています。
そんな中、企業は効果的なプロモーションで認知度やダウンロード数を伸ばし、収益を向上させることが求められます。
この記事では、アプリマーケティングの基本から成功事例までを解説し、ターゲット設定、コンテンツマーケティング、KPI設計・測定、販売戦略との連携などを紹介しています。
自社アプリの弱点を克服し、効果的な施策を実行しましょう!
現役のシステムエンジニアとして10年程度のキャリアがあります。 Webシステム開発を中心に、バックエンドからフロントエンドまで幅広く対応してきました。 最近はAIやノーコードツールも触っています。
アプリマーケティングとは
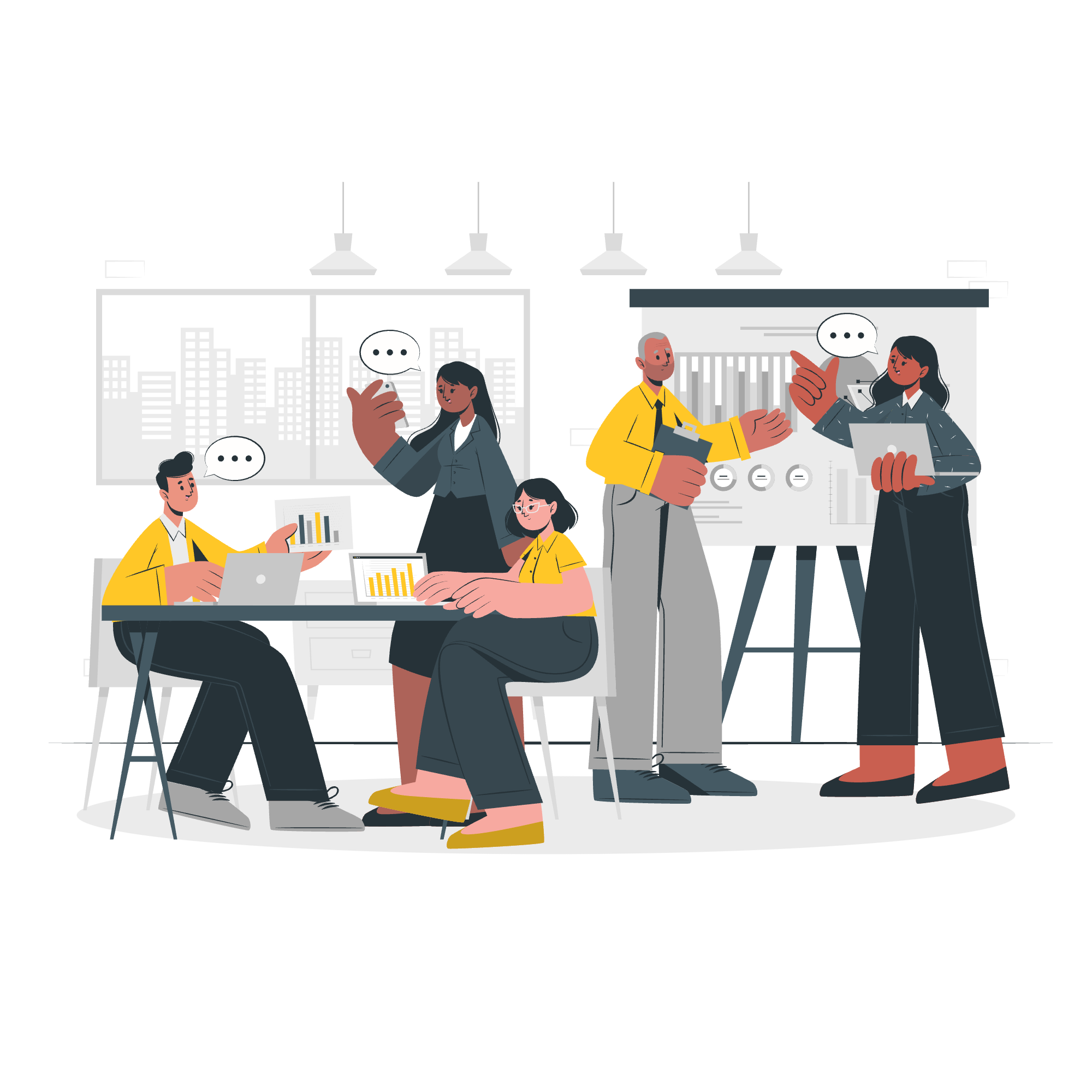
アプリマーケティングとは、スマートフォンやタブレットなどのアプリケーションを対象としたマーケティング活動のことです。アプリの認知やダウンロード数の増加、アクティブユーザーの獲得・維持などを目的としています。
ここではアプリマーケティングの基本、デジタルマーケティングやWebマーケティングとの違いを紹介します。
アプリマーケティングの基本
アプリマーケティングは、アプリを単なる製品としてではなく、サービスと捉えて継続的に価値を提供し続けることが大切です。ユーザー満足度を高めることで、口コミ効果が期待でき、継続的な運用改善がビジネス成長につながります。
具体的には、アプリリリース後も市場動向やユーザーニーズを把握し、UI/UXの改善や新機能の追加など継続的にエンゲージメントを高める施策が必要です。アプリ単体で完結するのではなく、関連するコンテンツ制作やSNSとの連携などを行うことも重要なポイントです。
アプリマーケティングが成功すれば、高いロイヤリティを得られるため、単なるインストール数やダウンロード数だけでなく、アクティブユーザーの割合や使用頻度といった指標こそが成功のKPIとなります。ユーザー保有率を高めて、生涯の価値を最大化することがアプリマーケティングの重要なポイントです。
デジタルマーケティングとの違い
デジタルマーケティングは、ウェブやSNSを通じたマーケティング活動の総称です。
ターゲティング広告やSNS広告、メールマーケティング、Webコンテンツ制作など多岐にわたります。効果測定がし易く、データを活用した改善がしやすいです。
デジタルマーケティングとアプリマーケティングの違いを以下にまとめました。
| 比較項目 | デジタルマーケティング | アプリマーケティング |
| 対象範囲 | ウェブ、SNS等のデジタルメディア全般 | スマートフォンに特化 |
| 主な施策 | ターゲティング広告、SNS広告、メールマーケティング等 | アプリストア広告、SNS運用、プッシュ通知 |
| 特徴 | データをもとに最適化しやすい | アプリのダウンロードと継続利用が主目的 |
| KPI | サイトへの誘引数、売上高等 | アクティブユーザ数・ダウンロード数等 |
ウェブマーケティングとの違い
ウェブマーケティングはウェブサイトを対象としたマーケティングです。
ウェブサイトを起点として、検索エンジン対策(SEO)やサイト改善などを行います。コンテンツマーケティングとの親和性が高く、有益なコンテンツ制作を行うことが多いのが特徴です。
ウェブマーケティングとアプリマーケティングの違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | ウェブマーケティング | アプリマーケティング |
| 対象範囲 | ウェブサイトに特化 | スマートフォンに特化 |
| 主な施策 | 検索エンジン最適化(SEO)、サイト改善等 | アプリストア広告、SNS運用、プッシュ通知 |
| 特徴 | コンテンツマーケティングとの親和性が高い | アプリのDLと継続利用が主目的 |
| KPI | サイトへの流入数、滞在時間等 | アクティブユーザ数・ダウンロード数等 |
アプリマーケティングは、こうしたデジタルマーケティングやウェブマーケティングと範囲が重なる部分もありますが、スマートフォンアプリに特化している点で異なります。アプリ固有のKPIであるアクティブユーザーや、リテンションを重視し、アプリストア最適化から口コミ拡散まで総合的な施策が必要になります。
このようにアプリマーケティングは、デジタル領域における個別プラットフォームとして独自のアプローチが求められる分野であるといえます。
アプリマーケティングの目的

スマートフォンアプリのマーケティングにおいても、ウェブサイト同様にコンテンツマーケティングは欠かせません。ユーザーに役立つ情報や解説を発信することで、アプリの認知や宣伝効果を高められるのです。
ターゲットユーザーに役立つ価値あるコンテンツを継続的に提供することが、アプリマーケティングにおけるコンテンツマーケティングの基本中の基本です。
アプリ認知度が向上
解説記事や使用レポートなどのコンテンツを作ることで、アプリの存在を多くの人に知ってもらえます。
例えば、レストラン予約アプリの場合、予約機能の便利さや混雑状況確認のメリットなどを、実際の利用者体験と共に紹介する記事が効果的です。写真付きで分かりやすく解説することで、他のユーザーの共感を得られます。
加えて、業種別メディア等へのプレスリリースを実施し、アプリ紹介の記事を掲載してもらうのも良い例です。対象領域の影響力あるメディアで取り上げられることで、業界内での認知度アップが図れます。
こうしたコンテンツマーケティングの継続実施が、検索エンジンへの自然集客にもつながります。関連キーワードでの検索ランキングが上昇すれば、更なる利用促進へと結びつきます。
アプリダウンロード数の増加
コンテンツからのアプリダウンロード促進で、アプリストアにアクセスが集まり、インストール数の改善につながります。
加えて、アプリ認知度の向上が、口コミ拡散へと繋がる好循環も生まれます。あるアプリ利用者が、SNSでその便利さをシェアした結果、友人知人がさらにインストールにつながる、という口コミ拡散効果は計り知れません。気軽に試せる環境づくりが、インストール数の増加の近道です。
こうした繋がりの結果として、インストール数・有料会員数が増えていくため、マーケティングとコンテンツは車の両輪として機能するのです。
アプリの利用促進
機能解説の動画コンテンツなどで、使い方を理解してもらうことが利用促進の近道です。
単にアプリをインストールしてもらうだけでなく、実際に活用してもらうことが重要です。そのためには、初心者向けの使い方ガイド動画や機能紹介記事などが効果的です。
スマホアプリの場合、UIや操作体系を理解することがハードルになりがちです。具体的な利用シーンを動画やイラストで紹介することで、「こんなふうに活用できるのか」とユーザーの理解が深まります。
加えて、ある一定期間の無料体験期間を設定したり、記事公開と連動したプロモーションを実施することで、より気軽に試してもらえる仕掛けづくりが大切です。
理解促進と試しやすさの両面を高めるコンテンツ活用が、アプリの継続利用に強く結びつきます。
新規ユーザーを獲得する
SNS広告や口コミ拡散などの施策で、まだアプリを利用していない新規層へ効果的にリーチしていきます。
例えば、リリース直後はPR配信やインフルエンサーマーケティングを活用し、デジタルメディアの露出を高める戦略が効果的です。目新しさを武器に、話題づくりを行うことで、サービスの存在感を高めます。
次いで、継続期にはFacebook/Twitter広告やYoutubeプロモ動画などの配信を通じたウェブからの集客方法を使用します。メディアランニング的なアプローチで、徐々に認知を広げていきます。その際、リターゲティング機能を使い、一度サイト訪問者だったユーザーに再度刺激することでコンバージョン率の向上が図れます。
このように、新規獲得には初期PRから中期SNS広告まで、フェーズに応じたプロモーション施策を継続的に実行することが求められます。
既存ユーザーのエンゲージメントを高める
メルマガ配信やアプリ内プッシュ通知を活用し、すでにダウンロードした既存ユーザーとの関係強化を図ります。
既存ユーザーに対しては、まず機能改善の通知やイベント案内といった、定期メールの発信が効果的です。またアプリ内メッセージを使った注意喚起で、久しぶりのユーザーに再訪問を促すこともできます。
加えて、オウンドメディアの作成や動画コンテンツの共有などを通じて、サービス関連情報の接触機会を増やすことが大切です。
このように、既存ユーザーに対する関与度を高めるには、単なる注意喚起のみならず、有益な情報提供による快適な体験の実現が欠かせません。こうしたUX設計視点も、忘れずに活動していきましょう。
アプリマーケティングの方法・手順
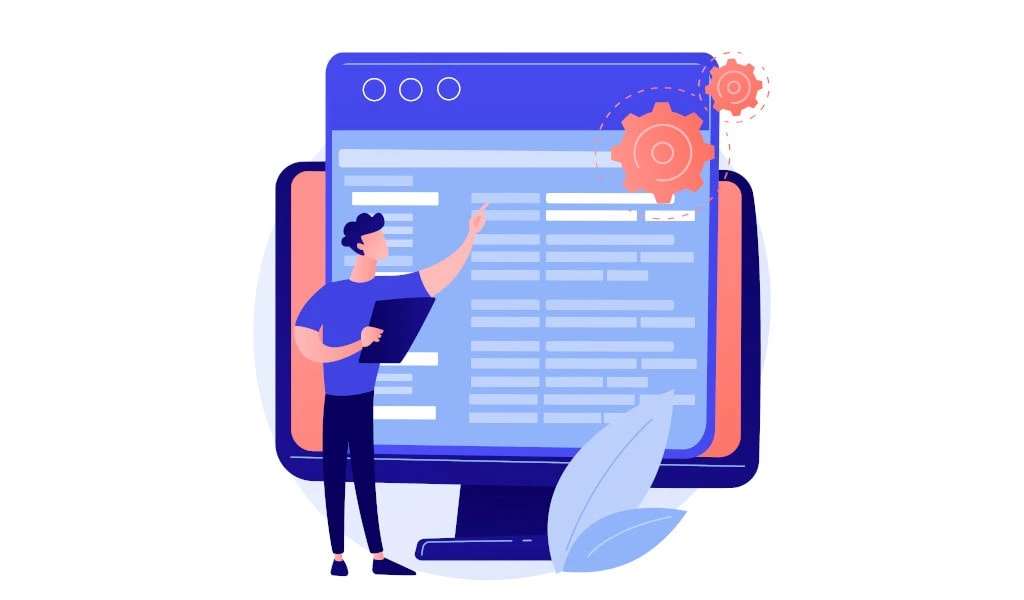
アプリマーケティングを成功させるためには、体系的で戦略的なアプローチが不可欠です。単にアプリをリリースするだけでは、多くの競合アプリに埋もれてしまいます。
効果的なマーケティング戦略を構築し、実行するためには、明確なKPIの設定、ターゲットユーザーや競合アプリの徹底的な分析、そして多様なプロモーション戦略の実施が求められます。さらに、データ分析を通じて戦略を継続的に見直し、改善を図ることが重要です。
ここではアプリマーケティングの方法や手順を紹介します。
KPI・目標を決める
まずは、アプリマーケティングの目標となるKPI(重要成果指標)を設定します。
これにより、マーケティング活動の成果を具体的に測定し、進捗を評価する基準を設定できます。
KPIは、アプリのダウンロード数、アクティブユーザー数、セッション時間、インアプリ購入数、リテンション率などが含まれます。例えば、ダウンロード数の目標を設定することで、一定期間内にどれだけのユーザーにアプリをインストールしてもらうかを明確にし、その目標達成に向けた戦略を立てられます。
アクティブユーザー数やセッション時間のKPIは、ユーザーがアプリをどれだけ頻繁に利用しているか、どれだけの時間を費やしているかを把握するために重要です。
これらの指標を設定することで、アプリの利用状況を詳細に分析し、改善点を見つけ出すことが可能になります。
競合アプリやターゲットユーザーを分析する
次に行うのは、競合アプリやターゲットユーザーの詳細な分析です。
競合分析では、競合アプリの強みや弱み、マーケティング手法を詳細に調査し、自社アプリとの差別化ポイントを明確にします。例えば、競合アプリのダウンロード数やユーザーレビューを調査することで、どの機能や特徴がユーザーに支持されているかを把握します。
また、ターゲットユーザーの分析においては、デモグラフィック情報(年齢、性別、地域など)やユーザーの行動データ(アプリの利用時間、頻度、人気の機能など)を収集します。これにより、ターゲットユーザーのニーズや行動パターンを深く理解し、彼らにとって魅力的なアプリを提供するための情報が得られます。
これらの分析に基づき、ターゲットユーザーに向けた効果的なマーケティング戦略を策定していきましょう。
SNS、SEO、ASO、広告キャンペーンなどの戦略を立てる
アプリマーケティングにおいては、多様なプロモーション戦略を組み合わせることが成功の鍵となります。
まず、SNSを活用する戦略では、Facebook、Instagram、Twitterなどのプラットフォームを利用してアプリの認知度を高めます。これらのソーシャルメディアでターゲットユーザーに直接アプローチし、エンゲージメントを高めることが重要です。
また、SEO(検索エンジン最適化)を実施することで、アプリ関連のコンテンツをWebサイトに掲載し、検索エンジンでの表示順位を上げ、自然流入を増やします。
さらに、アプリストア最適化(ASO)も重要です。アプリのタイトル、説明文、キーワード、スクリーンショットを最適化することで、アプリストアでの検索順位を向上させ、ダウンロード数を増やします。
広告キャンペーンでは、Google AdsやFacebook Adsを利用してターゲットユーザーにリーチし、アプリのダウンロード促進を目指します。これらの広告は、細かく設定されたターゲティングオプションを利用することで、効果的に潜在ユーザーにアプローチできます。
| SNS | 特徴 | ユーザー層 | 広告形式 |
| 広範なターゲティングオプション、詳細なユーザーデータ、ビジュアル広告に強い | 幅広い年齢層、特に30-50代 | 写真・動画広告、カルーセル広告、ストーリーズ広告 | |
| ビジュアルコンテンツに特化、若年層に人気、インフルエンサーマーケティングが効果的 | 若年層(18-35歳)、ビジュアル重視ユーザー | 写真・動画広告、ストーリーズ広告、ショッピング機能広告 | |
| リアルタイム性が高い、ハッシュタグで拡散力が高い、ニュース性が高いコンテンツに向いている | 20-40代、トレンドに敏感なユーザー | プロモツイート、プロモアカウント、プロモトレンド広告 |
データを分析し、戦略の見直しを繰り返す
マーケティング活動を実施した後は、データを詳細に分析し、戦略の見直しを繰り返すことが重要です。
まず、収集したデータをもとに、どの施策が効果的だったか、どの部分に改善の余地があるかを分析します。
また、ユーザーの行動データを分析して、アプリの利用頻度やセッション時間に関する状況を把握します。これに基づいて、アプリの機能やUI/UXを改善し、ユーザー体験を向上させるための施策を実行します。
分析結果に基づき、マーケティング戦略を見直し、必要な修正を加えることで、アプリのパフォーマンスを継続的に向上できます。このプロセスを繰り返すことで、アプリマーケティングの効果を最大化し、持続的な成長を実現していきましょう。
アプリマーケティングで集客するコツ
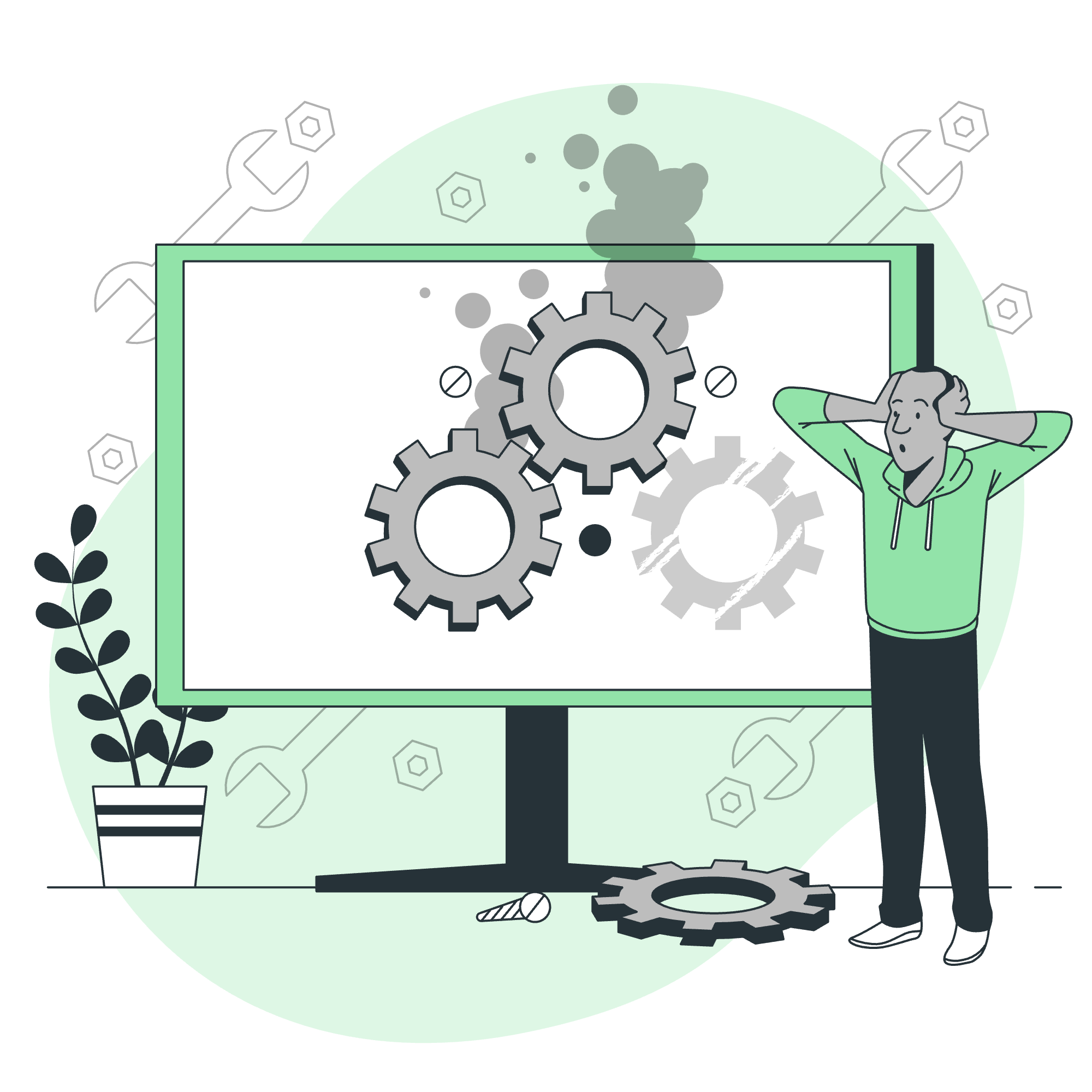
アプリの成功は、単に優れた機能やデザインだけではなく、効果的なマーケティング戦略にかかっています。多くのアプリが市場に溢れる中で、いかにしてターゲットユーザーにリーチし、ダウンロードを促し、継続的に利用してもらうかが鍵となります。
このため、宣伝や集客方法を工夫して、アプリの認知とダウンロードを増やす施策を継続的に展開することが重要です。
ここでは、アプリマーケティングで集客するためのコツを詳しく解説します。ターゲットユーザの明確化からプロモーションまで戦略的に宣伝、集客する方法を見ていきましょう。
ターゲットユーザーを明確にする
事業領域や提供サービスに合ったターゲット属性を設定します。年代、性別、職業、関心事などを、具体的にリストアップすることがポイントです。
このターゲット属性は、人口統計的特性に加えて、ライフスタイルや価値観など精神的・心理的属性も合わせて明確化する必要があります。都会的な情報感度の高い層、新しいことにオープンな層、など特徴づけられる心理面の属性を付加することで、より具体的かつ的確なターゲティングが可能となります。
具体的には、SNSやWebサイト上でのターゲティングだけでなく、実際に飲食店頻繁利用者を対象としたアンケートやヒアリング調査を行うことで、よりリアルな消費者インサイトを得られます。アプリマーケティングは統計よりも購買心理が成功の鍵を握っているため、可能な限り実態調査を行うことが理想的です。
アプリの価値を訴求する
ユーザーが解決したい課題と、その解決策であるアプリの機能・効果を明確に表現し訴求します。ターゲットニーズとのフィット感を高めることが重要です。
こうした課題に対して、アプリが提供するソリューションを具体的に示していくことが大切です。「待ち時間ゼロのテイクアウト」「混雑状況が分かる店選び」など、ターゲットが感じる痛みに合わせた機能を強調することで訴求効果が高まります。
併せて、「時短で便利」「ストレスフリーで楽しい」といったメリットを感性的なメッセージと共に訴求していくことも重要です。
広告・宣伝など、施策を継続する
単発のプロモーションでは、効果が薄れます。認知向上から利用促進まで段階的アプローチを継続することで効果が得られます。
併せて、リターゲティング広告やSNS広告などを活用し、集中的なインストールキャンペーンを定期的に展開します。既にダウンロードしたユーザーに対しては、メールマガジン送付や、アプリ内メッセージを活用したリエンゲージメント施策も欠かせません。
このように継続的なプロモーションを行うことで、新規獲得から継続利用まで強固なマーケティングサイクルを構築できるでしょう。
アプリマーケティングのKPI設定と測定方法

アプリマーケティングにおいて、成果測定のために重要な数値基準をKPIと呼びます。主なKPIとその測定法を解説します。
アクティブユーザーに関するKPI
1日1回以上アプリを開くDAUや、月に1回以上のMAUを指標として利用者数を測定します。アプリ分析ツールを用いることが多いです。
DAUは、直近1日のアクティブユーザー数で、実際にアプリの操作やコンテンツ閲覧などのアクションを行ったユニークユーザー数のことです。MAUは、月間でのアクティブユーザー数です。DAU/MAU比率を出すことで、ユーザーの活性度が分かります。
アプリ分析ツールとしては、GoogleアナリティクスやGameAnalyticsなどが主流です。これらを活用することで、DAUやMAUはもちろんのこと、ユーザー属性、エリア分布、利用機能分析など、きめ細かな計測が可能となります。
アクティブユーザー数そのものや、DAU/MAU比率を改善することが重要で、アプリのサービス内容拡充やUI改善などを行う目安になります。定期的にデータを確認し、数値目標の達成状況を評価していきましょう。
※DAU・・・Daily Active Usersの略称で、日次アクティブユーザー数を指します。直近1日で実際にアプリを利用した総ユニークユーザー数です。
※MAU・・・Monthly Active Usersの略称で、月間アクティブユーザー数を指します。直近1ヶ月で実際にアプリを利用した総ユニークユーザー数です。
収益に関するKPI
有料会員数や、1会員当たりの支出額ARPPUなどを指標とします。自社の課金設計に応じた、KPIを設定することが大切です。
主な指標として、月間課金額や有料会員数、課金会員の維持率が挙げられます。これらの数値を向上させることが、収益改善に直結します。
当然ながら、売上高そのものも最も重要な指標ですが、単価向上を図るためにはLTV(生涯価値)を意識する必要があります。ユーザー満足度を高めることで、1人当たりの通時支出金額が増えていくため、マーケティングと課金施策は車の両輪として両立させることが極めて大切です。
分析ツールから得られるデータをもとに、有料会員特典の改善や購入促進キャンペーンなどを行い、ARPU(1会員平均売上高)とARPPU(1支払会員平均売上高)の向上に力を入れることが重要です。
※ARPU・・・Average Revenue Per Userの略称で、1ユーザー当たりの平均売上高のこと。月額課金型アプリでこの数値を向上させることが重要です。
※ARPPU・・・Average Revenue Per Paying Userの略称で、1支払ユーザー当たりの平均売上高を指します。課金ユーザーに着目した指標です。
アプリ内イベントに関するKPI
アプリ内の主要アクション(登録、購買、コミュニケーション等)の発生件数から判断することも多く、測定しやすい指標です。
アプリ上で発生する、様々なイベントを測定できます。新規登録数、課金数、コンテンツ購入数といった主要事象を指標化し、日次・週次・月次で推移を把握することが大切です。
加えて、これらの数値を基準化したコンバージョン率も重要な判断材料になります。
各指標をアプリ分析ツールで計測したデータをExcel等で集計し、目標達成状況や前月比較などの定量評価を定期的に実施しましょう。改善すべき数値がある場合、マーケティング施策で対応していきます。
アプリマーケティングの成功事例

様々な業界でアプリを活用したプロモーションが実施され大きな成果を上げています。代表的な事例をいくつかご紹介します。
マクドナルド

マクドナルド
24時間営業店舗の情報やメニューの確認が可能な公式アプリをリリース。
マクドナルドは、スマートフォン向けアプリ「マックデリバリー」をリリースしました。このアプリ上から24時間営業の近隣店舗情報や、商品メニュー、クーポン等が簡単に確認できるようになっています。
特に、深夜営業している店舗の検索機能は好評で、アプリから即座に注文することも可能です。支払い方法としてQRコード決済も追加される等、非対面型の利用シーンに対応したサービス内容となっています。
無印良品

無印良品
無印良品は、シンプルで機能的な商品とサービスを提供することで人気の生活雑貨ブランドです。
ネットショップでは、全サイズ展開や一定額以上での配送料無料サービス、店舗・コンビニ受取など受取方法の選択肢を豊富に用意しています。また、お気に入り登録した商品が割引対象になると、メール通知するなど情報提供に力を入れています。
このように、利便性とコストパフォーマンスの両立を図る施策が高く評価されている理由といえます。シンプルさと、機能性を追求し続ける姿勢が支持されている事例です。
メルカリ

メルカリ
スマートフォンから気軽に購入できるフリマアプリとして大ヒットしたメルカリは、効果的なマーケティング手法が注目されています。
さらに、2022年夏には、缶バッジコレクション企画をタイアップで提供したことで、利用意欲を刺激するプロモーションも展開しています。様々な切り口で効果的なアプローチを試みている施策が参考になります。
コカ・コーラ

コカ・コーラ
コカ・コーラは、商品購入後の特典付与など、アプリを活用した販促キャンペーンを実施しています。
特に「Coke ON」というスマホアプリが有名です。「Coke ON」では、自販機などで商品を購入するとスタンプが付与され、15スタンプを貯めることで、1つ無料で商品を購入できます。このように、お得感のあるサービス内容とすることで利用者のエンゲージメント向上を図っています。
また、手軽に始められるミニゲームも充実しており、アプリ上で楽しみながらコカ・コーラブランドとの接点を増やす工夫がなされている事例です。
PUBG Mobile

PUBG Mobile
PUBG Mobileは、eスポーツとのコラボ企画を精力的に展開し、大型イベントも積極的に支援しています。
アジア競技大会「ASIAN GAMES 2022」の正式種目採用に加え、世界最高峰のトーナメント「PUBG MOBILE Global Championship」を毎年開催するなど、eスポーツシーンでの存在感が高まっています。
こうしたゲーム競技とのコラボレーションに注力する姿勢が、「PUBG MOBILE」全体のブランド力・話題性向上につながっていると考えられます。単なるアプリ運営に留まらず、エンターテインメント領域全体での活躍が期待されます。
マネーフォワードME

マネーフォワードMEは、個人の家計簿や資産管理を一元的に行えるアプリです。銀行やクレジットカードと連携することで、日々の入出金が自動集計され、使途別の分析や残高推移の把握が可能です。
2022年9月のアンケート調査では、家計簿アプリ・資産管理アプリの利用率ナンバーワンとされており、利便性とセキュリティの高さが支持されています。家計の見える化と改善サポート機能を併せ持つ個人マネー管理アプリの代表格と言えるでしょう。
スマートフォンアプリマーケティング特有の課題

スマートフォンアプリは、WEBサービスと比べるとユーザー数や継続率の獲得が難しいという課題があります。単なるアイデアや機能の良し悪しだけでなく、実行力のある運営がとても大切です。
このため、アプリそのものの完成度を高めるとともに、各フェーズで求められるマーケティング力が問われます。リリースから継続運用に至るまで、多くのハードルが存在します。こうした課題への対処こそが、成功への近道と言えるでしょう。
ダウンロード数の獲得が難しい
スマートフォンアプリは膨大な数があり、ユーザーの選択肢が多すぎます。そのため、ダウンロード数を伸ばすことが非常に難しくなっています。適切な集客方法や宣伝を行い、ユーザーに認知してもらうことが不可欠です。
アプリのダウンロード数増加には、サービス内容そのものの磨き上げが基本中の基本です。速度感や操作性といった基本機能の改善に加え、差別化要素を明確化するUI/UXの改良が欠かせません。市場変化や顧客データから得られるインサイトを踏まえ、継続的に改善を重ねることが大切です。
加えて、全般的な認知度向上に繋がるプロモーションも合わせて推進する必要があります。アプリの価値訴求力を高める映像コンテンツ制作やSNS広告運用で、対象ユーザーへ効果的に訴求していきましょう。
このように、サービス面とプロモーション活動の両輪で継続的に改善を重ねることが、アプリの定量面であるダウンロード数拡大につながっていきます。
アクティブユーザーの維持が難しい
一度ダウンロードされても、その後のアクティブユーザーの確保が課題となります。アプリの価値を常にアップデートし、プッシュ通知などでユーザーとのタッチポイントを保つ必要があります。
アプリへのロイヤリティを高めるには、単にアカウント登録してもらうだけでなく、実際に活用してもらうことが欠かせません。そのためには、インターフェースと機能面の改善に注力する必要があります。
スマートフォンは、PCと違い操作性が制限されるため、直感的でストレスフリーなUIを実現することが重要視されます。可能な限り簡潔な画面設計、わかりやすいアイコンを配置する等、ユーザビリティ向上がアクティブ率アップの近道です。
機能面でも、実用性・娯楽性を高める施策が大切です。市場や利用データから需要を把握し機能拡充していく等、継続的改良を推進しましょう。
競合アプリとの差別化が難しい
スマホアプリ市場の類似サービスは数多く存在するため、単なる機能面だけの差別化は難しくなりがちです。そこで重要になるのが、「スピード感とアイデア力」です。
競合他社よりも速いサービスイタレーションを実現することで、一時的にでもリードを奪うことができます。続いて、顧客との距離感で培ったノウハウやアイデアを業務アプリ等の形で武器化し、事業特化型の強みを確立していきます。この先行スピードと継続改良が差別化力の源泉となるのです。
マーケティング面でも、SNSを活用した情報拡散力が差別化ポイントとなり得ます。双方向性の高いSNS運用で、ユーザーとの距離感を近づける施策にも注力していきましょう。
まとめ:アプリの開発やマーケティング戦略ならJiteraに相談

スマートフォンアプリのマーケティングには、継続的運用とデータ分析が欠かせません。利用者理解とサービス改善を、車の両輪として回していくことが成功のコツです。
アプリのダウンロード数を増やし、ユーザーのエンゲージメントを高めるためには、KPIの設定、競合分析、ターゲットユーザーの理解、SNSやSEO、ASO、広告キャンペーンの実施、そして継続的なデータ分析と戦略の見直しが不可欠です。
スマートフォンアプリ開発会社を選ぶ際は、豊富な実績を持つ株式会社Jiteraにお気軽にご相談ください。
生成AIを活用したアプリ開発の実績を持つJiteraなら、AIを活用したマーケティング支援が可能です。膨大な市場データを瞬時に分析し、最適なマーケティング施策の立案やKPI設計をサポートします。また、予算に応じてスピード感のある開発も実現できます。
Jiteraのプラットフォームを利用することで、アプリの開発からマーケティング戦略まで一貫した支援を受けることができ、ビジネスの成長につながります。アプリ開発やマーケティング戦略にお悩みの方は、ぜひJiteraにご相談ください。







