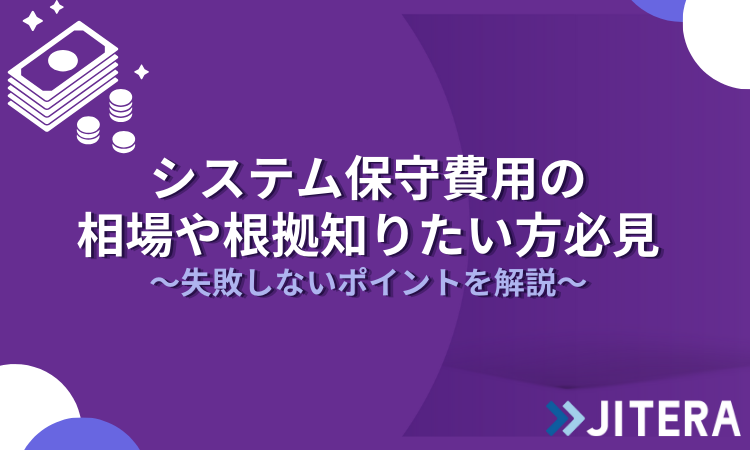システムリプレイスとは、既存のシステムを新しいシステムに置き換える作業のことを指します。
本記事では、システムリプレイスの目的や期間、メリット、ほかにも失敗しないためのポイントなどを解説。
本記事を読んで、自社にどのようなシステムリプレイスが必要か検討する参考にしてください。
PHPを独学で勉強した後にWeb業界に参入。大手企業でプログラマーとして活躍後、自社サービスの立ち上げ、大手検索エンジンサービスの保守運用作業、ソーシャルゲーム開発などに携わりながら、SE・管理職の道を歩んで現在に至る。現在は、管理職に携わる傍ら、これまでの経験を活かした執筆活動を続けている。
システムリプレイスとは

システムリプレイスとは、既存のシステムを新しいシステムに置き換える作業のことを指します。技術の深海やビジネス環境の変化に伴い、古いシステムでは業務効率が低下したり、保守コストが増大したりするため、最新の技術やシステムに更新する必要があります。
ここでは、以下の項目を見ながら、システムリプレイスに関してより深く理解していきます。
- リプレイス(Replace)とは
- なぜシステムリプレイスが必要なのか?
システムリプレイスは、単なるシステムの更新だけでなく、業務フローの見直しや改善を含むことも多く、企業にとっては大規模かつ重要なプロジェクトとなることが一般的です。
リプレイス(Replace)とは
リプレイス(Replace)とは、文字通り「置き換える」という意味で、何かを新しいものに交換することをさします。
リプレイスは、物理的な物品だけでなく、システム・プロセス・コンポーネントなど、幅広い対象に適用されることが多いです。たとえば、古いソフトウェアを最新バージョンに置き換えることや、壊れた部品を新しい部品に交換することもリプレイスと呼びます。
特にIT業界では、システムやインフラを効率的に適用するために、技術的な老朽化やコスト削減を目的としたリプレイスが重要な戦略です。
なぜシステムリプレイスが必要なのか?
システムリプレイスは、おもに技術的老朽化やビジネス環境の変化に対応するのが目的です。
古いシステムは、パフォーマンスの低下やセキュリティリスク、保守コストの増大を招きます。また、技術サポートの終了や最新技術への非対応なども、業務に支障をきたす可能性があるでしょう。
さらに、ビジネスプロセスの変化や新しい市場ニーズに適応するためには、柔軟かつ効率的なシステムが必要です。
システムリプレイスを行うことで、競争力を維持し、生産性や業務効率を向上させることができます。
システムリプレイスのメリット

システムリプレイスとは、既存システムを新しいシステムに置き換える作業であることがわかりました。では、システムリプレイスを行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、以下の項目に分けて、システムリプレイスのメリットを解説します。
- システムの性能や効率が上がる
- 長期的に見て運用・保守の費用が削減できる
- 最新のセキュリティや法規制に対応できる
システムリプレイスを行うことで、さまざまなメリットが得られます。
システムの性能や効率が上がる
システムリプレイスのメリットの一つは、システムの性能や効率が上がることです。
最新の技術やインフラを導入することで処理速度が向上し、大量データの取り扱いや複雑な業務処理がスムーズに行えるようになります。また、操作性の向上や自動化機能の追加により、従業員の業務効率の向上が期待できるのもメリットの一つ。
ほかにも、人的ミスの減少や作業時間の短縮が期待でき、全体的な生産性の向上につながります。
長期的に見て運用・保守の費用が削減できる
長期的に見て運用・保守の費用が削減できるのが、システムリプレイスのメリットの一つです。古いシステムは、対応する技術者やパーツの入手が難しくなり、保守コストが年々増加する傾向があります。
また、システム障害が頻発することで修理やダウンタイムにかかる費用も無視できません。最新のシステムにリプレイスすることで、保守性が向上し、トラブルの発生頻度が減少します。
さらに、クラウド技術や自動化ツールの導入により、メンテナンス作業も簡素化され、長期的にはコスト効率の良い運用が実現できるでしょう。
最新のセキュリティや法規制に対応できる
システムリプレイスのメリットの一つに、最新のセキュリティや法規制に対応できることがあります。
古いシステムでは脆弱性がみつかりやすく、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高いです。新しいシステムにリプレイスすれば、最新のセキュリティ技術や暗号化技術を取り入れて、これらのリスクを軽減できます。
また、法令や業界標準のセキュリティ要件に適合したシステムを導入することで、データ保護やプライバシーに関する法規制に遵守しやすくなるメリットも。
システムリプレイスを行えば、企業のコンプライアンス強化や顧客データの安全管理も確実に行えるようになります。
以下の記事では、おすすめのセキュリティ対策やウイルス対策ソフトに関して解説しています。ぜひご一読ください。
「リプレイス」と「マイグレーション」の違い

システムリプレイスには、システムの性能や効率が上がるなど、さまざまなメリットがあることがわかりました。次に、「リプレイス」と似たような言葉である「マイグレーション」との違いをみていきましょう。
以下は、「リプレイス」と「マイグレーション」との違いを簡単に表にまとめたものです。
| 項目 | リプレイス(Replace) | マイグレーション(Migration) |
| 言葉の意味 | 既存のシステムを完全に新しいものに置き換える | 既存システムやデータを別の環境やシステムに移行する |
| 特徴 | 完全なシステムの刷新を伴い、根本的な再構築が行われる | 既存のシステム構造を維持しつつ、新しい環境やバージョンに移行 |
| メリット | 最新技術を取り入れた効率的なシステムを構築できる | データやプロセスを保持し、リスクを抑えつつ移行できる |
| デメリット | 初期コストや時間が大きく、業務に一時的な影響が出る可能性 | 新しい環境との互換性や予期しない問題が発生することがある |
ここでは、以下の項目に分けて、マイグレーションの目的やリプレイスとどちらを選ぶべきかを解説します。
- マイグレーションとは?
- マイグレーションの目的
- どちらを選ぶべきか?
既存システムの状況に応じて、どちらの対応を選ぶべきかを判断しましょう。
マイグレーションとは?
マイグレーションとは、システムやデータを別の環境やプラットフォームに移行する作業をさします。
たとえば、オンプレミスのシステムをクラウド環境に移行する場合や、旧バージョンのソフトウェアを新バージョンにアップグレードするなどです。
マイグレーションでは、既存のデータやアプリケーションを維持しながら、より新しい技術や環境へ移行するため、業務の継続性が重視されます。
マイグレーションを行えば、システムの性能や可用性が向上し、将来の技術変化にも柔軟に対応できるようになるでしょう。
また、以下の記事では、クラウドマイグレーションに関して詳細に解説しています。ぜひ、ご一読ください。
マイグレーションの目的
マイグレーションの目的は、システムやデータを新しい環境に移行することで、業務効率やパフォーマンスを向上させることにあります。
古いシステムやプラットフォームでは、パフォーマンス低下やサポート終了、セキュリティリスクが高まるもの。マイグレーションを実施すれば、最新の技術やインフラへ移行でき、多くの課題を解決できます。
たとえば、オンプレミスのシステムをクラウドに移行することで、柔軟なリソース管理やコスト削減が可能となり、運用の効率化の実現が可能です。
また、法規制や市場の変化に対応するために、新しいセキュリティ基準や業務要件に適応させることも目的の一つ。
マイグレーションは、既存システムの枠組みを活かしつつ、長期的な競争力や持続可能性を強化する手段となります。
どちらを選ぶべきか?
リプレイスとマイグレーションのどちらを選ぶべきかは、組織のニーズやシステムの現状によって異なります。
リプレイスは、システム全体を新しく構築し直すため、技術的に大幅な進化を求める場合や、既存システムが老朽化して修復が難しい場合に最適です。最新技術を導入し、パフォーマンスやセキュリティを最大化したい場合は、リプレイスが効果的でしょう。
マイグレーションは、既存のシステムやデータを保持したまま、新しい環境に移行できるため、コストや時間を抑えつつリスクを最小限にしたい場合に適しています。現行システムがまだ有効で、全体の刷新が必要ない場合は、マイグレーションを選択するとよいでしょう。
システムリプレイスに強いシステム開発会社6選

ここからは、以下の項目に分けて、システムリプレイスに強いシステム会社を6社、紹介します。
- 株式会社Jitera
- NTT東日本
- シースリーインデックス株式会社
- IIMヒューマン・ソリューション株式会社
- 株式会社e-JAN
- バレットグループ株式会社
自社でシステムリプレイスをベンダーに依頼したいと検討する際は、これらの会社を候補に挙げて検討するのがおすすめです。
Jitera

システムリプレイスに強いシステム開発会社として、Jiteraが注目されています。
Jiteraは、高品質なシステム開発を提供する技術力が強みであり、特に先端技術を駆使したリプレイスプロジェクトに対応しています。
システムリプレイスは、既存のシステムを最新技術に置き換えるため、複雑なプロセスやデータの移行が必要とされますが、Jiteraはこのような課題を効率的に解決するためのノウハウを持っています。また、クライアントのニーズに合わせた柔軟な対応力と、迅速な開発サイクルも評価されています。
システムリプレイスでお困りの方は、ぜひ、Jiteraにお気軽にご相談ください。
NTT東日本

NTT東日本は、大規模かつ複雑なプロジェクトに対応できる技術力と実績があります。通信インフラに関する豊富な経験を活かし、安定したシステム移行に強みを持つ会社。
さらに、最新技術の導入やセキュリティ対策にも注力し、顧客の業務ニーズに応じたカスタマイズが可能です。
NTT東日本は全国規模のサポート体制を持ち、業界に特化したソリューションを提供できる点でも強みがあります。綿密なプロジェクト管理と信頼性の高い運用が期待できるでしょう。
シースリーインデックス株式会社

シースリーインデックス株式会社は、企業のITインフラや業務システムの最適化に豊富な経験を有しています。最新技術を活用した効率的なシステム移行が得意。
コンサルティングから開発、運用まで一貫したサポートを行い、顧客のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
システム移行時のリスク管理やスムーズな運用に力を入れており、信頼性の高いサービスが期待できます。
IIMヒューマン・ソリューション株式会社

IIMヒューマン・ソリューション株式会社は、企業のITシステム刷新において豊富な実績を有しています。
中長期的な視点からのシステム移行を得意としており、現行システムから新システムへのスムーズな移行が多くの顧客から高評価。
最新の技術トレンドや業務要件に応じた柔軟なカスタマイズを行い、顧客のビジネス課題に対応する最適なソリューションを提供しています。
コンサルティングから開発、運用までの一貫したサポート体制も特徴的な会社です。
株式会社e-JAN

株式会社e-JANは、セキュリティを重視したクラウドサービスの提供に特化しています。
安全かつ効率的なシステム移行をサポートし、顧客のITインフラを最新技術に基づいて最適化できるのが強み。また、リプレイス後の運用に必要なセキュリティ対策や運用サポートにも注力しており、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援します。
幅広い業種での実績があり、カスタマイズされたソリューションを提供することが可能です。
バレットグループ株式会社

バレットグループ株式会社は、デジタルマーケティングやeコマース分野において豊富な実績があります。最新の技術を活用し、クライアントのビジネスニーズに応じた柔軟で効果的なシステム移行を提供。
移行プロセスにおいては、業務継続性やデータの安全性を重視したアプローチを採用し、リスク管理に注力しています。
顧客の声を反映してカスタマイズされたソリューションを提供することが得意です。
システムリプレイスの工程・進め方

システムリプレイスは、既存システムが老朽化して修復が難しい場合に適していることがわかりました。次に、システムリプレイスの工程をみていきましょう。
ここでは、以下の項目に分けて、システムリプレイスの工程や進め方を解説します。
- 企画・準備のためのプロジェクトチーム立ち上げ
- 現状分析と目標設定
- 要件を洗い出す(要件定義)
- ベンダーの選定
- リプレース先の環境構築とシステム開発
- 移行準備とリハーサル
- 本番移行(カットオーバー)
- 継続的な運用・保守
システムリプレイスは、企画や現状分析、目標設定などが重要となる作業です。一つ一つの項目を理解して、システムリプレイスが失敗とならないようにしましょう。
企画・準備のためのプロジェクトチーム立ち上げ
システムリプレイスを進めるために、企画・準備のためのプロジェクトチームの立ち上げを行います。このプロジェクトチームは、システムリプレイスの目的や範囲を明確にし、実行可能な計画を作成する役割を担うチームです。
メンバーは、IT部門・業務部門・経営層からの代表者で構成し、異なる視点を取り入れることが重要となります。
現状分析と目標設定
プロジェクトチームを立ち上げたら、次に現状分析と目標設定を行います。
まず、現状分析では、既存システムのパフォーマンスや機能、ユーザーの満足度を詳細に評価。システムの利用状況やトラブルの履歴、保守コストなどをデータとして収集し、問題点を明確にします。
次に、目標設定では、現状分析で得た情報をもとにリプレイスの具体的な目標を設定。目標は、業務効率の向上・コスト削減・セキュリティの強化など多岐に渡りますが、SMART原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き)に基づいて設定することが望ましいでしょう。
要件を洗い出す(要件定義)
システムリプレイスを進めるにあたって、要件を洗い出すことは重要なプロセスの一つです。
要件定義では、現状分析や目標設定をもとに、新しいシステムに求められる具体的な機能や性能を明確にします。
関係者からのヒアリングを通じて、業務上のニーズやユーザーの期待を把握し、どのような機能が必要かをリストアップ。リストアップした要件は、機能要件と非機能要件に分類されます。
特に、非機能要件は、システムの運用において重要な要素となるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
ベンダーの選定
要件定義でシステムのニーズが明確になったら、複数のベンダーをリストアップします。選定基準は、技術力・過去の実績・提供するソリューションの適合性・サポート体制・コストなどです。
次に、選定候補となるベンダーに対してRFP(提案依頼書)を送付し、提案を受け取ります。提案依頼書では、各ベンダーの提供可能な機能やサービス、価格の比較が必要です。
さらに、デモンストレーションやプレゼンテーションを通じて、実際の製品やサービスの質を確認することも重要となるでしょう。
リプレース先の環境構築とシステム開発
リプレース先の環境構築とシステム開発は、システムリプレイスの進め方における重要なフェーズの一つです。
まず、リプレース先の環境構築では、新システムが稼働するためのインフラやプラットフォームを整備します。たとえば、サーバーの設置・ネットワーク設定・セキュリティ対策などで、クラウド環境を利用する場合は、適切なサービスや設定を選定する必要があるでしょう。
次に、システム開発では、要件定義に基づいて具体的なソフトウェアの設計と実装が行われます。開発手法には、アジャイルやウォーターフォールなどがあり、プロジェクトの特性に応じた方法を適用するとよいでしょう。
移行準備とリハーサル
システム開発が完了したら、移行準備とリハーサルを行います。
移行準備では、旧システムから新システムへのデータ移行計画を策定。データのクレンジグや整形、マッピングを行なって移行するデータの正確性と整合性を確保します。
リハーサルでは、実際の移行作業を模擬的に実施。移行手順やスケジュールを確認し、問題点を洗い出します。
本番移行(カットオーバー)
移行準備とリハーサルが終われば、いよいよ本番移行(カットオーバー)です。
旧システムから新システムへの切り替えを実行し、業務を新しい環境で行います。本番以降の成功には、事前の計画と準備が不可欠です。
カットオーバーは通常、業務の影響が少ない時間帯に実際されます。
移行手順に従ってデータを新システムに移行し、必要に応じて最終データの検証を実施。システムが正しく動作しているか、データが正確に移行されているかを確認するためのテストを実施します。
移行後は、旧システムを停止し、全てのユーザーが新システムにアクセスできるように設定。加えて、移行直後は問題が発生する可能性が高いため、サポート体制を強化し、迅速に対抗できる準備を整えます。
継続的な運用・保守
本番移行後の、継続的な運用・保守もシステムリプレイスにおける重要なフェーズです。新システムが稼働した後、運用・保守の体制を整えることで、システムの安定性と効率性を確保します。
システムの安定性と効率性を確保するために、定期的なメンテナンス計画を策定し、システムのパフォーマンスを監視しましょう。
次に、ユーザーからのフィードバックを収集し、システムの改善点を把握することが重要です。また、ユーザーサポートやトレーニングを継続的に行い、システムの使用方法や新機能についての理解を深めます。
4つのシステムリプレイス方式

システムリプレイスを進めるためには、計画から開発、さらには本番移行後の運用・保守も重要であることがわかりました。では、システムリプレイスにはどのような方式があるのでしょうか。
以下は、4つのシステムリプレイス方式の特徴やメリット、デメリットをまとめたものです。
| 移行方式 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 一括移行方式 | 旧システムから新システムへの完全な切り替えを一度に行う | 短期間で全ての移行が完了し、運用がスムーズになる | 移行時のリスクが高く、問題発生時の影響が大きい |
| 段階移行方式 | システムや機能を段階的に移行する | リスクを分散し、問題を早期に発見・対処できる | 移行が長期化し、コストが増加する可能性がある |
| 並行移行方式 | 旧システムと新システムを同時に運用し、徐々に新システムに移行 | 旧システムがバックアップとして機能し、リスクが低い | 並行運用のため、管理や運用コストが増加する |
| 試行方式 | 新システムを小規模で導入し、評価後に本格的に移行 | 実際の使用感を確認でき、リスクを最小限に抑えられる | 本格導入まで時間がかかり、スケールに制限がある |
ここでは、以下4つのシステムリプレイス方式を詳細に解説します。
- 一括移行方式(ビッグバン方式)
- 段階移行方式
- 並行移行方式(パラレル方式)
- 試行方式(パイロット方式)
- それぞれの方式が適しているケース
それぞれのシステムリプレイス方式を見て、自社にあったシステムリプレイスを実施しましょう。
一括移行方式(ビッグバン方式)
一括移行方式(ビッグバン方式)とは、旧システムから新システムへの移行を一度に行う手法です。システムリプレイスした時点で、全てのデータや機能が新システムに切り替わります。
ビックバン方式の特徴は、移行作業が短期間で完了すること。新システムが迅速に稼働し、業務がスムーズに進む利点があります。
一方で、移行時に問題が発生した場合、業務全体が停止するリスクも伴う点に注意が必要です。
ビックバン方式は、システムの変更が急務である場合や、旧システムが廃止される状況で選ばれることが多い方式となっています。
段階移行方式
段階移行方式は、既存システムから新システムへ移行する際の手法の一つで、段階的に移行を進めるのが特徴的です。段階的に移行することで、リスクを低減し業務への影響を最小限に抑えることができます。
リプレイスを実行するために、まずは既存システムの機能を分析し、必要な機能を新システムに移行する順序を決定。移行は通常、重要度や使用頻度の高い機能から始められ、その後、徐々に他の機能を追加していきます。
段階移行方式は、全体の移行が完了するまでの期間中も業務が継続できるため、ビジネスの安定性を保ちながら、新システムへの移行が可能です。
並行移行方式(パラレル方式)
並行移行方式(パラレル方式)は、既存システムと新システムを同時に運用する手法です。既存システムを維持しつつ、新システムを段階的に導入します。
並行移行方式では、移行中のリスクを軽減し、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。既存システムが稼働しているため、新システムに問題が発生しても業務が中断されるリスクが低いのがメリット。
ただし、並行運用はコストやリソースの負担が増加するため、慎重な計画と管理が必要となります。
試行方式(パイロット方式)
試行方式(パイロット方式)は、新システムを部分的に導入し、その性能や機能を実際の業務環境で試験する手法です。特定の部門や機能に新システムを導入し、限定的な範囲で運用することで、問題点や改善点を洗い出します。
試行方式は、リスクを抑えながら新システムでの効果を検証できるのがメリット。ただし、試行期間中は限られたリソースで運用するため、リソース不足となる可能性がある点に注意です。
それぞれの方式が適しているケース
それぞれの方式が適しているケースを表にまとめました。
| 移行方式 | 適しているケース | リスク |
| 一括移行方式(ビッグバン方式) | 短期間での導入が求められる場合、業務停止の影響が少ない場合 | 移行時に全機能が一斉に切り替わるため、トラブル発生時の影響が大きい |
| 段階移行方式 | 大規模なシステムや複雑な機能を持つ場合、段階的な確認が必要な場合 | 移行プロセスが長期化し、各段階での管理が必要になる |
| 並行移行方式(パラレル方式) | 移行中のリスクを最小限に抑えたい場合、業務継続が重要な場合 | コストやリソースの負担が増加し、運用が複雑になる |
| 試行方式(パイロット方式) | 新システムの検証やフィードバックを重視する場合、リスクを抑えたい場合 | 限定的な導入であり、全体への適用時に追加の問題が発生する可能性がある |
それぞれの方式で適しているケースがあるのと同様にリスクも含んでいる点に注意が必要です。
システムリプレイスに関するFAQ

システムリプレイスには、4つの方式がありそれぞれ適しているケースとリスクを含んでいることがわかりました。ここからは、システムリプレイスに関する質問に回答します。
- システムリプレイスにかかる費用は?
- どのくらいの期間で完了する?
- システムリプレイスに失敗してしまったら?
システムリプレイスに関する疑問を解消した上で、システムリプレイスを実施することが重要です。
システムリプレイスにかかる費用は?
システムリプレイスの費用は、一般的に数百万円から数千万円とされていますが、具体的な費用はシステムの規模や複雑さによって異なるため、事前の詳細な見積りが重要です。
システムリプレイスの費用の算出には、おもに以下のような要素を検討する必要があります。
- ソフトウェアライセンス
- ハードウェア費用
- 導入・カスタマイズ費用
- 教育・トレーニング費用
- 移行費用
- 運用・保守費用
これらの要素を総合的に考慮して費用を算出する必要があります。
以下の記事では、システム保守の費用相場などを詳細に解説しています。ぜひ、ご一読ください。
どのくらいの期間で完了する?
システムリプレイスの完了期間は、プロジェクトの規模や複雑さ、導入方式によって大きく異なります。一般的には数ヶ月から1年以上かかることが多いです。
また、システムの規模ごとに完了する期間を一覧表にまとめてみました。
| システム規模 | リプレイス期間 |
| 小規模システム | 簡単な業務システムや特定の機能のリプレイスであれば、数ヶ月で完了することがあります。 |
| 中規模システム | 複数の機能や部門に関わる場合、6ヶ月から1年程度の期間が必要です。この間に、システムの設計、開発、テスト、トレーニングが行われます。 |
| 大規模システム | 大規模な企業システムや複雑な業務プロセスが絡む場合、1年以上の期間がかかることもあります。段階的移行や並行運用を行う場合は、さらに時間が必要です。 |
システムリプレイスを成功させるために、プロジェクト計画段階での詳細なスケジュール策定が、スムーズな移行を実現するために重要です。
システムリプレイスに失敗してしまったら?
システムリプレイスに失敗してしまった場合、企業にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
まず、業務が中断したり効率が低下したりすることがあり、顧客満足度が低下し、信頼を失うリスクがあるでしょう。また、データの損失や不正確な情報が発生することで、意思決定に支障をきたすことも。
さらに、失敗による追加のコストが発生し、修正や再構築のために多くの時間とリソースを要することになります。場合によっては、既存システムに戻す、ロールバックが必要となり、更なるコストがかかるでしょう。
システムリプレイスに失敗しないポイント

システムリプレイスで失敗をすると、企業にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかりました。では、システムリプレイスに失敗しないようにするためには、どのようにするとよいのでしょうか。
ここでは、以下の項目に分けて、システムリプレイスで失敗しないポイントを解説します。
- 要件定義を正確に定義する
- リスク管理と対策を決めておく
- 品質保証と業務の継続計画を明確にする
- 長期的な開発費用の管理をする
- 最新技術の活用を十分に検討する
- 信頼できるベンダーやパートナーを選定する
それぞれの項目を理解して、失敗しないシステムリプレイスを実施しましょう。
要件定義を正確に定義する
システムリプレイスに失敗しないためには、要件定義を正確に行うことが重要です。
要件定義は、システムの目的や機能、業務プロセスを明確にし、企業や利用者のニーズを的確に反映させるための基盤となります。不足した要件や不明確な要件があると、後々トラブルや追加費用が発生するリスクが高まるため注意が必要です。
要件を明確にすることで、開発や導入の精度が上がり、システムリプレイスの成功に繋げられるでしょう。
以下は、要件定義書に関して詳しく解説している記事です。ぜひ、こちらもあわせてご一読ください。
リスク管理と対策を決めておく
リスク管理と対策を決めておくことは、システムリプレイスを失敗しないために重要なポイントの一つです。
リプレイスプロジェクトは複雑で、予期せぬ問題が発生する可能性が高く、リスクを特定し、それに対する対策を準備しておくことが重要。対策を準備しておけば、トラブル時の影響を最小限に抑えることができます。
リスク管理と対策を決めておくことで、問題が発生しても被害を最小限に抑え、プロジェクトの成功率を高めることができるでしょう。
品質保証と業務の継続計画を明確にする
システムリプレイスに失敗しないためには、品質保証と業務の継続計画を明確にすることが重要です。
品質保証では、新システムの機能や性能が要件を満たしているかをテストやレビューで確認します。
業務の継続計画(BCP)では、移行中に発生するダウンタイムや障害を最小限に抑えるための手段を策定し、問題発生時でも業務が滞らないようにすることが重要です。
長期的な開発費用の管理をする
長期的な開発費用の管理をすることは、システムリプレイスを失敗しないために重要なポイントの一つです。
リプレイス全体にかかる費用を明確にし、開発やカスタマイズ、保守にかかるコストを正確に見積もります。さらに、システムのライフサイクル全体を考慮し、運用・保守っ費用や将来的なアップデート、拡張に備えた予算も確保しましょう。
費用が膨れ上がることを防ぐために、進捗に応じて定期的な予算の見直しや、コストコントロールを行い、無駄を抑えることが大切です。
最新技術の活用を十分に検討する
システムリプレイスで失敗しないためには、最新技術の活用を十分に検討することが重要です。
クラウド技術、AI、自動化ツールなどの最新技術を導入することで、システムの柔軟性や効率が向上し、長期的な運用コストを削減できる可能性があります。
ただし、新技術を採用する際は、業務ニーズに合致しているか、既存のインフラと適合するかを慎重に検討し、必要に応じて専門家の意見を取り入れることが重要です。
技術の進化を見据えたシステム設計が、将来的な安定運用につながります。
信頼できるベンダーやパートナーを選定する
信頼できるベンダーやパートナーを選定することは、システムリプレイスを失敗しないための重要なポイントです。
経験豊富で、プロジェクトの規模や業界に精通しているベンダーを選ぶことで、的確な提案やサポートが受けられます。過去の実績や顧客からの評価を確認し、長期的に協力できるパートナーかどうかを判断しましょう。
また、技術面だけでなく、コミュニケーション能力や柔軟な対応力も重要です。
システムリプレイスのまとめ

今回は、システムリプレイスに関して、以下のことがわかりました。
- システムリプレイスとは既存のシステムを新しいシステムに置き換える作業のこと
- システムの性能や効率が上がるのがシステムリプレイスのメリット
- システムリプレイスには企画準備のためのプロジェクトチームが必要
- システムリプレイスには4つの方式がある
システムリプレイスには4つの方式があり、既存システムの状況に応じて実施方式を選ぶ必要があります。ただ、どのような方式が自社にあっているかわからないこともあるでしょう。
システムリプレイスに関する質問やご相談などがあれば、株式会社Jiteraにお問合せください。自社のリプレイスに関して詳細をヒアリングさせていただき、適切なアドバイスをいたします。