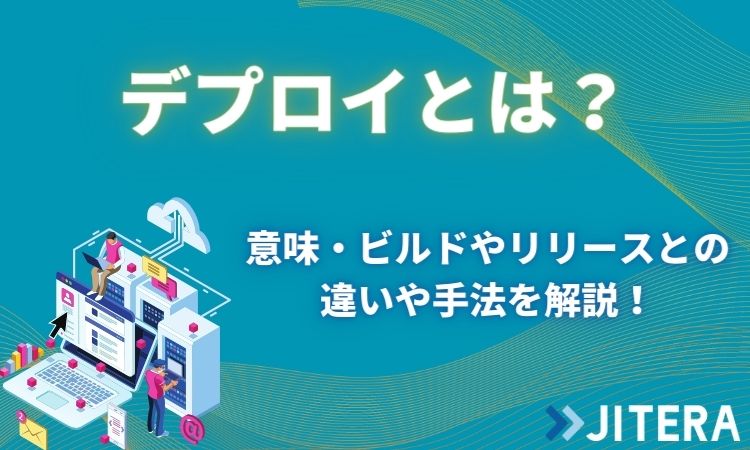ゲーム開発の現場でよく出てくる「ビルド」という用語の意味を知っているでしょうか。
「現場ではなんとなく使っている」
「実際に何が行われているかは知らない」
プログラミング習得中の方はもちろん、現役のプログラマーであっても詳しくは説明できないことも少なくありません。
ゲーム開発において欠かせない「ビルド」。
本記事ではその重要性や仕組みを、ビルドに欠かせない外部ツールやゲームエンジンを交えながら解説していきます。
実際の仕組みやどんな処理が施されているのかなど、開発者やゲームパブリッシャーを目指す方であれば押さえておきたいポイントを学んでいきましょう。
ビルドでお困りのことがありましたら、株式会社Jiteraにお問い合わせください。
システムやアプリの開発を幅広く手がけ、独自のAI技術を活用した高品質かつ迅速な納期での開発を得意としています。
システムエンジニア(SE)、プログラマー、ウェブサイト作成業務、ネットワークエンジニアなどを経験。 現在、フリーマルチライターとして活動中。最近はAI活用方面に没頭中。
ゲーム開発における「ビルド」とは

ビルドとは、人間が読み書きできるソースコード(プログラムの元になる文字列)を、コンピューターが実行できる実行ファイルに変換する作業のことです。
この変換には複数の工程があり、ソースコードのチェック、前処理、コンパイル、リンクなどの作業をすべて含めてビルドと呼びます。
開発においてはこのビルド作業を繰り返し行うことで、プログラムの動作確認やバグの発見、修正を効率的に行えます。
おおまかには「動作する実行ファイルを作る」といった意味ですね。
ただゲーム開発やスマホゲーム制作に限っては「ビルド=成果物」といった意味で使われるケースもあります。
一般的な使い方とは混同することがありますのでご注意を。
本記事では、「デプロイされたファイル=成果物」として扱い、「ビルド」はゲーム開発の工程の一つとして解説を進めていきます。
ビルドの意味
ビルドは、設計図に基づいて実際に建物を造る「ビルディング」がもとになった単語です。
それが製造業やソフトウェア開発に転じて、製品を組み立てる工程や、部品を組み合わせて完成品を作る工程を「ビルド」と表現するようになりました。
ゲーム開発で例えてみると、ゲームのコンセプト・ストーリー・キャラクターデザイン・ワールドなど構想する工程が「設計」、建築の土台となる基礎工事が「コーディング」、実際に外装や内装を建築していく工程が「ビルド」といったところでしょう。
事前の設計図通りに部材を組み立て、様々な職人(プログラム)の技術を組み合さって、プレイ可能なゲームとして出力されます。
ビルドはゲーム開発において主軸となる大事なプロセスです。
ビルドの使い方
「プロジェクトのビルドに失敗した」「ビルドが通らない」などの表現からわかるように、ビルドはコマンドやツールを使って実行するものです。
例えば、IDE(統合開発環境)のメニューから「ビルドする」で実行したり、ターミナルのコマンドラインなどから「make」という命令で実行したりします。
ビルドが実行されると、次の工程を自動で行います。
まずソースコード中の#includeなどの前処理命令を置換し、続いて関連するソースコードがバイナリと呼ばれる機械語に変換(コンパイル)されます。
ビルドではソースコードに間違いがないかコンパイラによってチェックされ、構文エラーや型の不整合があればビルドはただちに停止し、エラー箇所をログとして出力します。
正常にコンパイルが完了すると、このコンパイル済みのコードと外部ライブラリが結合(リンク)されて、実行可能なゲームファイルとして生成されます。
生成されたゲーム実行ファイルは、実際のUI表示、操作の受付、操作に応じたリアクティブな反応やアニメーションなど、実装されたプログラムに従って動作を行います。
開発現場での「ビルドしておいて」は、記述したソースコードがエラーなく動作するか、そして出力された実行ファイルの動作チェックまで含めた意味で使われることがあります。
厳密な「ビルド」は実行ファイルの生成までを指すので、上記とは意味合いが異なる点に注意しましょう。
ゲーム開発におけるビルドの目的・重要性とは

ゲーム開発においてビルドは非常に重要で欠かせないプロセスです。ビルドをする目的は以下の通りです。
- バグの発見と修正が効率的にできる
- テストやリリース作業を自動化できる
- 開発全体の効率化が図れる
ビルド時に構文チェックやテストが自動で行われるため、バグの早期発見と修正が容易になります。
また、後述するCI/CDツールやIDEの機能を活用すれば、ビルドから各種テスト、インストーラ作成などの運用作業を自動化できるのため、目的に応じたビルドができるよう適切に環境構築をしていくことも大事でしょう。
バグやエラーの発見ができる
ビルド時にコンパイラによるコード解析が行われるため、ソースコードの構文エラーや型の不整合などのバグの発見が期待できます。
また、ビルド後にユニットテストやインテグレーションテストを行うことで、実際の実行時にバグが発生しないかも合わせて確認してくれます。
こうしたテストを継続的に行うことで、バグの早期発見と修正が可能になり、ゲームの品質が向上するでしょう。
例えば、UIアニメーションなどごく単体ユニットでこまめにビルドを行い、モック(模型:ごく単体の機能だけを実装した実行ファイル)を作成したとします。
ここで検出されたエラーやバグは原因の切り分けが比較的容易で、単体ユニットごとに手早く修正が可能です。
ですが、ユニットテストやモックの作成を飛ばしてユーザーからのインタラクティブな操作まで一気にビルドしたケースでは、コード解析にも時間がかかり、原因の特定や修正の切り分けも不十分になりがちです。
ビルドをこまめに行わずに開発を進めると、結果的にデバックの工程などで多くのチェックエラーや手戻りが発生することになり、工数がかさむ要因にもつながります。
テストやリリースの作業を自動化できる
近年のビルドツールは、単にプログラムを生成するだけでなく、テストの自動化やリリース資材の作成まで行うようになっています。
具体的には、ユニットテストやインテグレーションテストを段階を踏みながら自動でビルドを実行します。
さらにプラグインを活用することで、アプリケーションのインストーラや商品の概要、プレイ方法のレファレンスなどを統合した配布用パッケージまで自動で生成する機能を搭載させられるのです。
従来であれば、頻繁なビルドの実行やモックの作成、リリースの準備といった手間はゲーム開発において課題となっていました。
自動化の仕組みを導入することで手間から開放され、ゲームの「おもしろさ」をつき詰めるコア部分の開発業務に専念できるようになります。
効率的なゲーム開発ができる
ビルド機能を搭載したCI/CDツール(Continuous Integration/Continuous Delivery)を十分に活かすことで、ゲーム開発全体の効率化が図れます。
通常、ソフトウェア開発では複数の開発者が関わり、お互いのコードの変更を統合(インテグレーション)していく必要があります。CI/CDツールであれば、開発者がコードを変更するたびに自動でビルドやテストを実行してくれるため、他の開発者の変更に影響がないかをすぐに確認でき、開発工程の大幅な短縮につながるのです。
そうして頻繁に実行可能ファイルを作成することで、誰もが最新の状態をすばやく確認できるため、開発の全体像を把握しやすくなります。また、小さなバグを見つけた時点で直ちに修正に着手でき、後から大規模な修正が発生するリスクも低減できるのです。
ひとりひとりが行った変更を逐一確認しながらビルドを行う必要がなくなり、コンフリクト(バグの要因となるコードの差分エラー。複数の開発者による合同開発にて発生する)を早期に発見して回避できます。
ゲーム開発がより一般にまで浸透してきた背景として、これらビルドツールの発展と普及が大きく貢献しています。
ビルドと似たゲーム開発の関連用語

開発において「ビルド」が絡まない開発はありませんが、現在のゲーム開発環境においてはほとんどが自動されているため、あいまいな概念になりつつあります。
ビルドと似た関連用語として「コンパイル」「リンク」「デプロイ」などがあります。「ビルド」はいったいどこまでに含まれるのか、それぞれの違いについて見てみましょう。
| 用語 | 説明 |
| ビルド | ソースコードから実行可能なプログラムを生成する一連の作業。コンパイル、リンク、デプロイなどの工程から構成される。 |
| コンパイル | ソースコードを機械語に変換する作業。ビルドのメイン機能。 |
| リンク | オブジェクトファイルやライブラリを結合して実行可能ファイルを生成する作業。ビルドの最終段階。 |
| デプロイ | ビルドされた実行可能ファイルを配布や公開する作業。ビルドとは別の作業。 |
ゲーム開発においてのビルドは、ソースコードからプログラムを実行可能な状態に変換する包括的な作業です。
ファイリングされたソースコードのバイナリ変換作業である「コンパイル」、オブジェクトファイルやライブラリの結合を意味する「リンク」といった個別の工程が「ビルド」の中にすべて含まれているイメージになります。
デプロイとは、開発者が作成したアプリケーションやウェブサイトを、実際に運用するサーバーや環境に配備することを意味します。
ゲーム開発で例えれば、パッケージングしたアプリケーションやアセットをゲームパブリッシャー向けに配布したり、steamなどのプラットフォームで販売するためのデータをサーバーにアップロードすることであり、ビルドとは明確に区別されます。
開発会社によっては、ビルド=デプロイとひとまとめに呼称しているところもありますのでご注意ください。
ゲーム開発におけるビルドの仕組み

ビルドではソースコードから実際に実行できるゲームファイルを生成するための複雑な作業が行われています。
ここではその仕組みについて、順を追って詳細に解説します。
ソースコードの静的解析
ビルドの最初の工程では、ソースコードの構文チェックなどの静的解析が行われます。ゲームのソースコードはC++やC#などのプログラミング言語で記述されていますが、その構文が適切であるかコンパイラによって検証されます。
静的解析では下記のようなチェックが行われています。
構文チェック
プログラミング言語の文法ルールに沿ってソースコードが書かれているかをチェックします。構文エラーが検出された場合、ビルドは停止します。
型チェック
変数や関数の型が適切に使われているかどうかを確認します。型の不整合があればエラーになります。
デッドコードチェック
実行される可能性のないコード(デッドコード)を検出します。
未使用変数チェック
定義されたものの使用されていない変数を見つけます。
ゲーム開発では規模が大きくなるほどソースコードが冗長化したり複雑になったりするため、静的解析機能に優れたツールは重宝されます。
コンパイルのための前処理命令
静的解析が完了すると、プリプロセッサという専用のツールがソースコード中の前処理命令を置換します。
前処理命令とは、他のファイルの内容を現在のソースコードファイルに取り込む命令です。代表的なものとして#includeが挙げられます。
例えば、#include <stdio.h>とすれば、stdio.hというヘッダファイル(入出力関数などが定義されている)の内容が現在のソースコードに含まれるようになります。
「グラフィック/UI」「コア機能」「内部数値のコントロール」「キャラクターアセット」「モーションアセット」のように実装ユニットごとにファイルを分けることで、ソースコードの可読性が向上し開発が効率化されるのです。
前処理命令の結果は一時ファイルに出力され、次のコンパイル工程へと渡されます。
ソースコードのコンパイル
前処理が終わると、本格的にソースコードが機械語にコンパイルされます。
コンパイラがソースコード中の文法を解析し、コンピューターが実行できるバイナリ命令列に変換していきます。ゲーム開発ではグラフィックス処理に特化した命令(物理演算など)もこの時点でコンパイルされるのです。
コンパイルの結果生成されるオブジェクトファイルには、関数やデータ構造の実体が含まれています。.oや.objなどといった拡張子が主なオブジェクトファイルです。
実行可能なゲームアプリケーションは、これら複数のオブジェクトファイルから構成されています。
オブジェクトファイルとライブラリのリンク
最後に、オブジェクトファイルがリンク(結合)されて実行可能ファイルが生成されます。
リンク工程では、生成されたオブジェクトファイルと、データベースに用意されている外部ライブラリを結合するリンカーによって、最終的な実行可能ファイルが生成されます。
オブジェクトファイル同士、または外部ライブラリとの間で相互に参照されている関数やデータの実体が確定され、メモリ上の配置が決定されます。
クラウド上のデータを扱うオンラインゲームは、このリンカーによって外部サーバーのライブラリなどを参照し、データの保証性を実現しています。
この過程でリンクエラーが発生した場合は、参照先が見つからないなどの問題がリンカーエラーとして出力されます。修正後にリンクが正しく成功すれば、ゲームの実行可能ファイルが生成されます。
以上がビルド中に内部的に行われている処理の流れです。
これらビルドはほとんどがツールによって自動で行われますが、仕組みを理解しておくことでバグ特定や早期修正などに役立つ可能性があります。
ゲーム開発のビルドを支援するツール

包括的なビルドを実現するためには、ツールの活用が重要になります。今回はその中でもネームバリューのあるツールについて紹介します。
- Jenkins
- Incredibuild
これらのCI/CDツール(Continuous Integration/Delivery)を利用すれば、ビルドからテスト、デプロイまでを自動化できます。
具体的にはソースコードの変更をトリガーにビルド作業を動作させることで、修正→テスト→実行ファイル生成→リリースまでを一元化し、効率的な開発フローを構築できます。
詳しく紹介していきましょう。
Jenkins

Jenkinsは、オープンソースのCI/CDツールとして広く利用されています。
コミット時(ソースコードの変更や修正・リポジトリ統合など)にビルドを自動で実行し、静的解析やユニットテストなどの検証作業を行えます。
Jenkinsではビルドに加え、リソース制御、通知設定など多様な機能を自由に設定できるため、ゲーム開発現場のビルドプロセス構築にも適しています。
Jenkinsの大きなメリットは、プラグインの存在です。1,300を超えるプラグインが公開されており、さまざまなツールとの連携で自動化が実現できます。
複雑な一連のデプロイ手順も柔軟に設定できるのが魅力ですが、いかにカスタマイズするかが効率化の鍵になるため、扱いが難しいツールともいえます。
| 公式サイト | Jenkins |
| 主な機能/特徴 |
|
| 費用 |
|
Incredibuild

Incredibuildはビルドの高速化に特化したツールで、CPUリソース分散技術により並列処理を最適化します。
従来の単一的なビルドに比べて、複数のコア、マシン間でのビルド処理を並列分散できるため、大規模プロジェクトのビルド時間を大幅に短縮できます。
ゲーム業界をはじめ、CAD/CAEなどの描画処理を伴う大規模ソフトウェアの開発現場で広く利用されています。
Incredibuildの実装はソースコードの修正なしで利用でき、既存環境のビルドツールチェイン(コードエディタ、コンパイラ、リンカ、ライブラリ、デバッガといった機能群を搭載したツール)と併用できるのが特徴です。
| 公式サイト | Incredibuild |
| 主な機能/特徴 |
|
| 費用 |
|
設計からビルドまで。優秀なおすすめゲームエンジン3選

ゲーム開発でビルドを含む一連の作業をスムーズに行うには、優れたゲームエンジンを選ぶことが重要です。
例えば、下記のようなゲームエンジンが現代の主流となっています。
- Unity
- Unreal Engine
- GameMaker
Unityではビルドのオプション設定から実行まで、UnityEditorからGUIで行えます。WebGLやモバイルアプリのビルド、クラウドビルドにも対応しています。
Unreal EngineもUnrealEditorからさまざまなビルド設定ができ、オンラインゲームのビルド/パッケージングにも対応。ソース管理やクラッシュ分析などの開発支援機能もあります。
GameMakerは2Dゲーム向けエンジンで、ドラッグ&ドロップ方式のビルドが可能。ウェブやモバイルアプリへのビルドとデプロイを同時に行える機能を搭載しています。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
Unity

Unityは2Dと3Dの両方に対応する、有名な汎用ゲームエンジンです。
C#をベースとしたコーディングで開発が行え、VisualStudioなどの統合開発環境と連携できます。
ビルドの仕組みについても機能が充実しており、UnityEditorから簡単にビルドを実行したり、各種のオプションを設定したりできます。
ビルドではスタンドアロンゲームだけでなく、WebGLやiOSアプリなどのビルドも柔軟に行えます。さらにCloudbuildなどのサービスを活用すれば、ビルドの自動化やデプロイをクラウド上で実行可能です。
| 公式サイト | Unity |
| 主な機能/特徴 |
|
| 費用 |
|
| 主なゲームタイトル |
|
Unreal Engine

Unreal EngineはEpicGamesが開発したゲームエンジンで、リッチな3Dグラフィックスが特徴です。
国内外問わず、有名な3Dゲーム作品が思い浮かぶ人も多いことでしょう。
C++をベースとしていますが、ビジュアルスクリプティングツールのブループリントも用意されています。
一般的にはプログラマーしか使用できなかったスクリプトを、ゲームに視覚的に追加することができるシステムです。
ソースコードの明確な記述も必要がなく、直感的に実装できます。
ビルドに関してはUnrealEditorからワンクリックで実行でき、豊富な設定項目からビルドのカスタマイズも可能です。
オンラインゲームのビルド、パッケージング、デプロイについても高度なサポートを提供しており、マルチプラットフォームに渡っての開発が可能です。
UnrealEngineにはソースコントロール機能、クラッシュ解析ツールなども統合されており、ゲーム開発のさまざまな側面をサポートしています。
| 公式サイト | Unreal Engine |
| 主な機能/特徴 |
|
| 費用 |
|
| 主なゲームタイトル |
|
GameMaker

GameMakerは2Dゲーム開発に特化した統合環境で、直感的なドラッグ&ドロップ形式でのゲーム制作が特徴です。
簡単な操作でプロトタイプの試作から本格的なゲーム開発まで対応でき、ビュワーやデバッガも内蔵されています。
ビルドについても、UIからワンクリックで実行可能です。
特にWebプラットフォームのビルド機能が充実しており、HTML5やFacebookゲームなどを簡単に自動生成できます。
またモバイル端末へのビルド時は、各プラットフォームのアプリストアへのデプロイを直接行えるなど、リリースフローの一元化にも対応しています。
| 公式サイト | GameMaker |
| 主な機能/特徴 |
|
| 費用 |
|
| 主なゲームタイトル |
|
ビルドとはゲーム開発の重要なプロセス!ツールの活用で効率アップを

ゲーム開発の現場で欠かせない「ビルド」。
ソースコードから実行可能ファイルを生成するだけでなく、バグ発見、テスト自動化、開発の効率化にも大きく影響をあたえるプロセスです。
現代のゲーム開発においては柔軟なビルド構造を実現するためにも、ツールの選定が不可欠でしょう。
CI/CDツールを導入することで、ビルドからテスト、デプロイまでを自動化して開発フローを最適化できます。
ゲームエンジン自体が提供するビルド機能も重要です。
Unityや Unreal Engineのように優れたエンジンを選ぶことで、ビルド設定からリリースフローまでをシームレスに実行でき、開発者がビルドに費やすコストを最小限に抑えられます。
ゲーム開発におけるビルドは、いまやそのほとんどが自動化がされています。どんなツールを使えばいいか迷ってしまうかもしれませんが、あらためてビルドについての基礎知識を学び、適切な自動化ツールやエンジンとの連携にお役立ていただければ幸いです。
当社Jiteraでは、アプリ・システム開発を積極的に行っています。
小さなスタートからビジネスを確実に前に進めるアプリ開発やシステム開発をサポートさせて頂いております。
IT案件やアプリ・システム開発依頼、本記事で取り扱ったゲーム開発のビルドツールなど、ご相談やご質問がありましたら、Jiteraまでお気軽にお問い合わせください。
AIの最新動向を踏まえた最適なソリューションをご提案いたします。