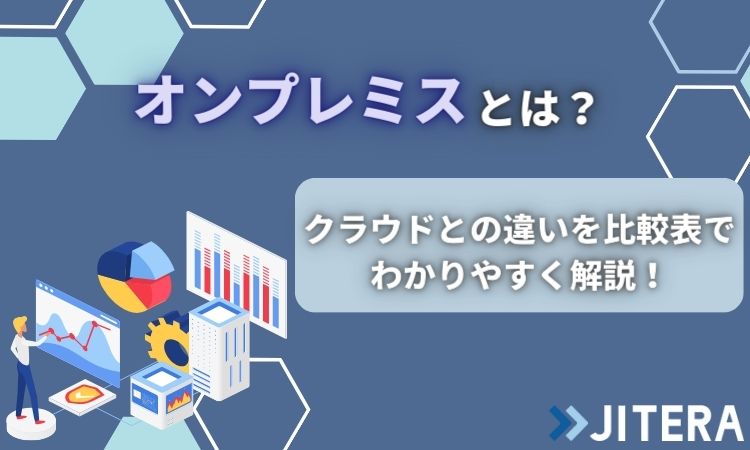昨今、消費者行動の変化に伴い物流需要が高まっています。そこで物流管理の効率化やコスト削減をしたいと考えている人は少なくないでしょう。そんな物流企業の人に必見なのが「TMS(輸配送管理システム)」です。
TMSは、従来の属人的な物流プロセスの標準化だけでなく、コスト削減や効率化が期待できるため昨今業界内で注目があつまっています。
本記事では、そんなTMSの機能やメリット、WMSとの違いに焦点を当てて紹介していきます。TMS導入を検討している人はぜひ本記事を参考にしてみてください。
金融機関常駐SEとして、常駐先の社内システム開発に携わっている現職SE。 開発に関する上流から下流まで経験。最近ではSalesforceなどのSFAツールを用いたシステム開発に着手。
TMSの基本概要

そもそもTMSとは何なのか、分からないという人は少なくないでしょう。
こちらでは、TMSの基本概要として、TMSの定義と機能、役割、利点、ビジネスにおける重要性を解説していきます。
TMSの定義と機能
TMSとは、Transport Management Systemの略称で日本語で「輸配送管理システム」の意味を持ちます。
物流企業の輸配送を効果的かつ効率的に管理するためのシステムがTMSの定義です。物流センター全体を管理するWMSと同じく物流システムの1つとして、現代の物流業界を支えています。
TMSの基本的な機能は、配車・配送の管理や配送時の進捗管理、配送で発生する運賃計算などの業務の自動化を行う機能が備わっています。
経理や運営担当の業務を自動化するだけではなく、これまで無駄になっていた配送スペースをTMSによる情報管理でなくし効率化を図ることが可能です。
最適な配送管理が期待できるため、ドライバーの負担を軽減して業務品質や生産性を向上させることができます。
TMSの役割と利点
TMSの役割は、属人化傾向の多い配送業務の標準化とより効率的な配車管理を行い業務の効率化を図ることです。
物流業界では従来、経験豊富な担当者によって配送管理されることが少なくなく、属人化傾向にありました。
また昨今の、ドライバーの高齢化問題や若手人材の不足問題が物流業界全体の問題となり、配送業務の標準化・効率化の必要性が高まり、TMSなどの物流システムの導入が考えられています。
TMSの利点は、前述の通り荷物を着荷主につなげるまでの情報を管理・活用することで運送業務全体の品質改善や生産性の向上ができることです。
運送会社や各車両の状況を管理した上で最適な車両に配送業務を割り振ることができるため、ドライバーの負担の軽減効果が期待できることが利点といえるでしょう。
TMSのビジネスへの重要性
TMSは、物流業界が人材不足という課題を抱える中、高まる物流需要に対応してビジネスを展開する上で重要なシステムと言えます。
昨今のデジタル化による企業のDX化でECサイトなどの販売チャネルが増加し、働き方改革・コロナ禍などで消費者行動が変化した影響でECサイトを利用した購買需要が高まりました。
その影響で、これまで以上に物流需要が高まっているのが現状です。そこで物流業界の人材不足による運送可能車両の減少は至急取り組むべき課題として上がっています。
TMSの各種機能は、前述のとおりこれまで属人的に行われてきた配送手配をシステム化して、適切な車両に適切なタイミングで荷物を割り振ることが可能になります。
物流業界のビジネスが抱える課題解決をサポートしてくれる機能が多数搭載されているため、TMSのビジネスへの高い重要性がうかがえます。
TMSの主な機能

前章では、おおまかにTMSの機能について触れましたが、こちらではTMSの主要機能についてみていきます。
輸送計画の最適化
TMSでは、輸送計画の最適化機能として配送会社や車両、交通状況、その他条件などの情報を管理・活用し荷物を最適な運送会社・車両に割り当てる支援を行います。
従来、輸送計画にて運送会社や車両を割り当てる際には、経験則に基づいた属人的な判断が少なくありませんでした。
ただ、あくまでも人力にとる判断となるため、過剰積載になったり逆に運搬料が少なく車両内のスペースが余ってしまう可能性があります。
TMSに収集した配送会社や車両、交通状況、庭先条件(着荷主が提示した荷物納入時の条件。例えば、時間指定や車両制限、待機時間、納品方法など)の情報を元に最適な車両へと荷物を機会的に判断してマッチングさせるため、ドライバーの負担を均一化して、作業効率を全体で底上げする効果が期待できるでしょう。
配送ルートの最適化
配送業務において、配送車両や配送順番、配送経路を計算し最適な配送ルートを作成していく機能です。
1つの配送車両が1日の配送業務で配送する荷物はさまざまで、配送先が複数ある場合がめずらしくありません。
各配送先で時間指定や車両制限などの庭先条件が指定されている場合があり、例え近くのエリアを走行していたとしても指定された条件通りに配送を行う必要があります。
これまでは、庭先条件に応じて長時間待機するなどのケースが珍しくなく、作業効率低下の原因でした。
TMSの配送ルートの最適化機能では、配送車両の状況や荷物の各種指定情報を活用してどのルートを通って配送を行えば一番効率的かを示してくれます。
車両追跡と監視
車両追跡と監視機能では、配送の進捗情報を把握するために車載端末やドライバーに支給されるスマートフォンからトラッキングを行い、荷物の位置情報だけでなく車両の運行状態なども監視します。
荷物の配送進捗をリアルタイムで確認できるため顧客からの問い合わせへの対応がスムーズになり顧客満足度向上につながることが魅力です。
また運行状態を確認することでドライバーがきちんと休憩しているのか、速度超過をしていないかなどを確認でき、配送品質の向上が期待できます。
輸送費用の管理
輸送費用の管理は、荷物の配送にかかる運賃を自動で計算したり、燃料などかかった経費情報をオンラインで管理できる機能です。
配送にかかる運賃の計算は複雑で、配送距離や時間、エリア間の規定運賃に加えて、さまざまな条件で運賃の割増や割引が設定されています。
TMSでは、前述のとおり配車や運送に関するデータを管理されており、各データを活用することで運賃の自動計算が可能です。
1日に消費した燃料費と荷物の運搬にかかった業務量などを計算して各車両の生産性を数値化することもできます。
正確な運賃計算は、既存の物流システムが抱える課題をコスト面で考えることができ、コスト削減効果が期待できるでしょう。
TMS導入のメリット

物流業界の企業にて、TMSを導入するメリットは多いです。こちらでは、TMS導入のメリットをみていきましょう。
輸送効率の向上
TMSを導入することで輸送効率を向上させることができます。
TMSでは、配送会社や車両の状態、交通状況、荷物に指定された庭先条件などさまざまな情報を参考に、各荷物の配送に適した配送会社や車両を自動的に割り当てることが可能です。
また、荷物割り当てと同時に、その日の配送業務の最適ルートを作成してくれるためドライバー全体の輸送効率の向上が期待できます。
効率的に配送業務を行えるよう車両の積載状態を考慮して、ルートまで導き出してくれるため属人化傾向にあった物流業界の標準化が図られることもポイントです。
TMSを導入することで上記のような輸送効率の向上ができるためメリットといえるでしょう。
コスト削減と費用節約
TMSを活用してコスト削減と費用節約ができることがメリットです。
物流業界のコストの多くは配送時の人件費や走行に使用する燃料費などの配送コストが占めていると言われており、コスト削減には効率的な輸配送計画を行うことが求められます。
前述の通り、TMSでは輸送計画や配車を各種情報を元に最適な車両に割り当てることが可能です。また荷物の積載率も向上されるため、輸送に必要なトラック台数を削減することもできます。
車両の手配台数を削減するだけでも燃料代や人件費が節約されるためコスト削減と費用節約が実現可能です。そのため、コスト削減と費用節約はTMSの大きなメリットといえるでしょう。
顧客サービス向上
TMSを導入することで顧客サービス向上が実現できます。
TMSの車両追跡・監視機能を活用することで、常に配送車両の状態を可視化でき、顧客からの荷物の問い合わせに対してスムーズに対応可能です。
これまでは、問い合わせを受けた後にドライバーに確認を入れる作業が必要でしたが、TMS導入でリアルタイムにオンラインで輸送状況を把握できるようになったことで問い合わせ対応の品質向上だけでなく顧客満足度の向上に繋がります。
ビジネスプロセスの最適化
TMSは物流業界のビジネスプロセスの最適化に役立つことがメリットです。
これまで人の手で行われてきた輸送計画や荷物の振り分け、配送順番の指定、輸送ルートの確立などの業務は、一部のベテランがノウハウや勘を基に決定してた物流企業は少なくありません。
比較的属人化しやすいビジネスプロセスのため、人によって業務効率や品質に違いが生じやすいことが課題にあります。
TMSの導入は、そんな担当者間の業務効率や品質の差をなくすことに役立ち、さまざまな意思決定プロセスの自動化によって属人的だったビジネスプロセスも最適化が可能です。ビジネスプロセスの最適化は今後入ってくる人材を即戦力として迎えることにも役立つため、TMS導入のメリットといえるでしょう。
TMSとWMSの比較

前述にも述べたように物流システムにはTMSの他にWMSというシステムがあります。WMSは、「Warehouse Management System」の略称で倉庫管理システムという意味です。
ただWMSと聞いてもどんなシステムか分からない人、TMSと何が違うのか分からない人は少なくないでしょう。こちらでは、TMSとWMSの違いについてみていきましょう。
| システム名称 | TMS(輸配送管理システム) | WMS(倉庫管理システム) |
| システムの役割 | 配送業務全般の管理・支援 | 倉庫内作業全般の管理・支援 |
| 主な機能 | ・配送計画 ・配送進捗確認 ・運賃計算管理 ・実績管理 |
・在庫管理 ・入荷管理 ・出荷管理 ・棚卸管理 |
TMSとWMSの役割と範囲の違い
TMSは荷物の出荷後に着荷主に配送されるまでの配送業務全般を管理・支援する役割をもち、WMSは倉庫に入荷された荷物が出荷するまでの倉庫内作業全般の管理・支援をする役割です。管理する範囲が配送か倉庫かの違いとなります。
具体的には、TMSは配送計画作業や配送進捗状況確認、運賃計算管理作業、運送実績管理WMSは、在庫管理や入荷管理、出荷管理、棚卸管理がそれぞれの対応・管理範囲です。
各システムは、コスト削減も役割として期待されており、適切に活用することでTMSは車両やドライバーなどにかかる経費が、WMSは倉庫管理に割かれる人件費などのコストが削減できるという違いがあります。
配送業務全般の管理・効率化をしたい場合はTMSを、倉庫全般作業の管理・効率化をしたい場合はWMSの導入を検討しましょう。
TMSとWMSの連携と相互補完性
TMSとWMSは同じ物流システムとして連携することで相互補完性が高まり多くのメリットを得られます。
それぞれ役割や対応した業務範囲が異なりますが、例えば連携させることで入荷から配送までの物流プロセスを一貫して管理できるなどもメリットです。
特にTMSとWMSがデータ連動を行い相互補完性を確立すれば、WMSに登録した内容がそのままTMSに引き継がれるため、TMSとWMSで二重登録などの無駄な作業を減らせることがポイント。物流プロセス全体を意識した計画を立てることができ、更なる効率化を目指すことができます。
物流プロセス全体の効率改善を目指したい場合は、それぞれにデータ互換性のあるTMSとWMSの導入を検討するとよいでしょう。
TMSとWMSの導入時の選択ポイント
物流システムであるTMSとWMSは、現在さまざまな種類がリリースされています。自分の会社の目的に適したシステム選びをするうえで以下のポイントを重視して選ぶことが大切です。
- 優先順位の高い機能が備わっているのか
- システムの提供形態
- 他システムとの互換性や拡張性があるか
優先順位の高い機能が備わっているのか
TMSやWMSには前述で紹介した機能以外にもパッケージによってさまざまな機能が搭載されています。
ただたくさんの機能が搭載されていても自社の物流プロセスの改善に必要な機能が搭載されていなければ導入しても意味がありません。
そのため、TMSやWMSを選ぶ際にはどんな機能が欲しいか優先順位をつけてから選ぶとよいでしょう。
システムの提供形態
システムの提供形態の確認もTMSとWMSを導入する際の選択ポイントの1つです。
TMSやWMSの提供形態は主に、オンライン上に提供されたサービスを利用する「クラウド型」か自社リソースを活用して自社システムとして構築・運用する「オンプレミス型」、TMSやWMSの機能を持ったソフトウェアを購入してインストールする「インストール型」があります。
その中でも、導入検討段階の方にはクラウド型がおすすめです。クラウド型は基本的に従量課金制となっているため、試しに導入して上手くいかなくても利用をやめればそれ以降の金額は発生しません。
他システムとの互換性や拡張性があるか
TMSとWMS以外にも他システムとの互換性や拡張性があるかも確認することが重要です。
物流システム導入前に使用していたシステムと互換性があればスムーズなデータ引継ぎでシステムの移行ができます。導入初期は優先度の高い機能を中心に導入が進みますが、将来的にその他の機能を追加したい需要も高まることが少なくありません。
複数の業務でシステム導入をしたり、さまざまな機能を都度追加したりしたいと考えている方は、導入検討しているTMSとWMSの拡張性も確認しましょう。
TMS導入のステップ

TMS導入を検討しようと考えていても、具体的にどのようなステップで導入していけばよいか分からない人も少なくないでしょう。
こちらでは、TMS導入の具体的なステップについて解説していきます。
TMSの導入前の調査と計画
TMSを導入する際に始めに行うのが導入前の調査と計画です。自社の物流プロセスの配送部門の実態を調査して評価や課題を特定します。
前述の通り数多くリリースされているTMSから自社にあったシステムを選定するには、自社の配送プロセスの実態を掴み課題を理解することが重要です。調査を行い自社の配送プロセスの評価や特定された課題をもとに適切なTMSを選定していきます。
調査結果をもとにTMSの導入計画をたてましょう。TMS導入の要件を定義して、ベンダーの選定やTMS導入にあたっての予算調整、スケジュールの策定、TMSの利用戦略などの計画が重要です。戦略的に計画を立てることでTMS導入の成功をサポートしてくれます。
TMSの導入プロセスとシステム構築
TMSの導入プロセスとシステム構築では、導入計画で作成した要件定義をもとにTMSの設計・構築を行います。
システム構築では、ベンダーが提供するTMSを自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズする作業と自社の配送業務でこれまで用いられてきたデータの整理や書類のデータが必要です。
カスタマイズ作業では、計画段階でたてた要件定義書を基に作成された設計書にのっとって構築していきます。
構築後は試験運用を行い、正しく動作することや改善点を検証してシステムの精度を高めていく作業も重要です。
TMSの運用と最適化
試験運用が完了してシステム構築が済んだらTMSの運用開始です。
運用開始後は、リアルタイムモニタリングや各配送情報によるデータ分析を活用して配送プロセスの効率向上をはかります。
配送プロセスだけでなく、実際の本番運用を通してシステムやプロセスの改善を行い、TMSの効率向上も行うことが可能です。
運用と最適化のサイクルを繰り返すことで、業務全体の品質や効率向上に役立ちます。TMSを最適化し続けることで、流動的な消費者行動の変化にも対応できる体制を整えましょう。
TMSの運用管理とベストプラクティス
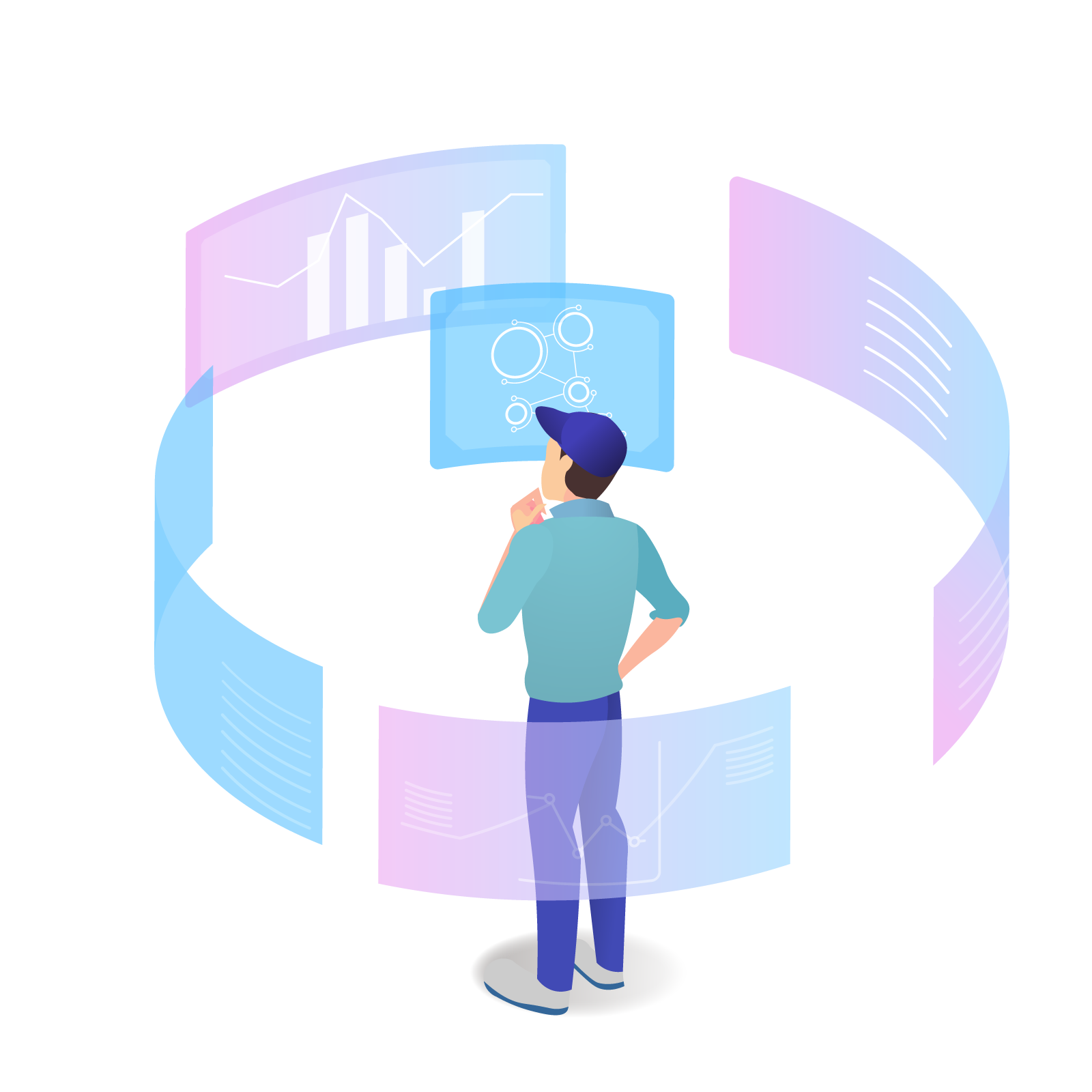
TMSを効果的に活用し続けるためには、運用管理とベストプラクティスの導入が必要不可欠です。ただ、どのように運用管理したり、ベストプラクティスを導入したりすればいいか分からない人も少なくないでしょう。
こちらでは最後にTMSの運用管理とベストプラクティスについてみていきます。
TMSの定期的な監査と更新
TMSを導入した企業は、定期的にTMSの運用を監査して機能やデータの正確性を評価することが求められます。
TMS導入後も試験運用では出てこなかった問題や性能向上のための気づきを得ることができるためです。
リアルタイムモニタリングでドライバーの進捗をトラッキングし続けることができ、交通状況や庭先条件によっての最適なルートの変化などに対応できます。
さまざまな気づきを監査によって得ることでTMSの問題点や性能の改善点を見出すことで、常に最適化されたTMSに更新し続けることができ、配送プロセスの最適化も図れるでしょう。
TMSのトレーニングとスキル向上
TMSを最適に利用するためにもTMSのトレーニングとスキル向上を図ることは重要なベストプラクティスの1つです。
前述の通り、従来の物流業界はベテランのノウハウや勘による意思決定が少なくないビジネスプロセスとなっていました。
TMSの導入によってそんなビジネスプロセスに大きな変更が起きるため利用ユーザーへの理解とトレーニングが必要不可欠です。
またTMS導入後もさまざまな機能追加が予測されるため、なおさらトレーニングの重要性が高まります。
トレーニングとスキル向上は誤操作によるヒューマンエラーも削減し、より効果的にTMS利用ができるため定期的なトレーニングの実施でスキル向上を図りましょう。
TMSのセキュリティとデータ保護の確保
TMSでは、配送に関するさまざまなデータが一元管理されます。
その中には、荷物に関する情報も含まれているため、TMS利用を続けるうえでセキュリティ対策とデータ保護の徹底によるデータの機密性や整合性、可用性の確保が必要不可欠です。
セキュリティ対策として、定期的なシステム監査を行うことでセキュリティを評価しデータ保護の脆弱性がないかを調査します。また複数システムで連携している場合は、各システムでデータの整合性が取れているかの確認も重要です。
どんなシステムにも言えますが、データのセキュリティやデータ保護性能の高さはそのままシステムや組織への信頼性に繋がるため、定期的なTMSのセキュリティとデータ保護の確保のための行動を欠かさないようにしましょう。
TMSのまとめ

TMS(Transport Management System)は物流システムを支えるシステムの1つです。配送プロセスの管理や自動化に効果的で、同じく物流システムの1つであるWMSと合わせることで物流プロセス全体の一貫管理ができます。
TMS導入によるメリットも多く、輸送効率の向上やコスト削減などさまざまな物流プロセスの課題に対応することが可能です。
変化の激しい物流業界にリアルタイムで対応していくサポートをしてくれるため、今後の物流企業で導入が勧められるシステムといえるでしょう。
いざ自社にTMSを導入しようと考えてもシステム導入に不安を感じる人は少なくありません。当社では、TMS導入にあたって不明点や困ったことがあれば質問や相談にお答えいたします。TMSに関する質問や案件などの依頼があれば、ぜひJiteraまでお問い合わせください。お問い合わせフォームはこちらです。