2024年4月に施行される法律改定の影響で全事業者の対応が義務化された「ウェブアクセシビリティ」。ウェブアクセシビリティと聞いても何か分からない人や達成基準などのガイドラインが分からない人は少なくないでしょう。
本記事では、ウェブアクセシビリティの基本概念や国の定めるガイドライン、義務化に関する詳細まで解説していきます。
この記事を通してウェブアクセシビリティの基本的な考えや達成基準について理解して、自社のウェブアクセシビリティの確保の参考にしてみてください。
金融機関常駐SEとして、常駐先の社内システム開発に携わっている現職SE。 開発に関する上流から下流まで経験。最近ではSalesforceなどのSFAツールを用いたシステム開発に着手。
ウェブアクセシビリティとは?
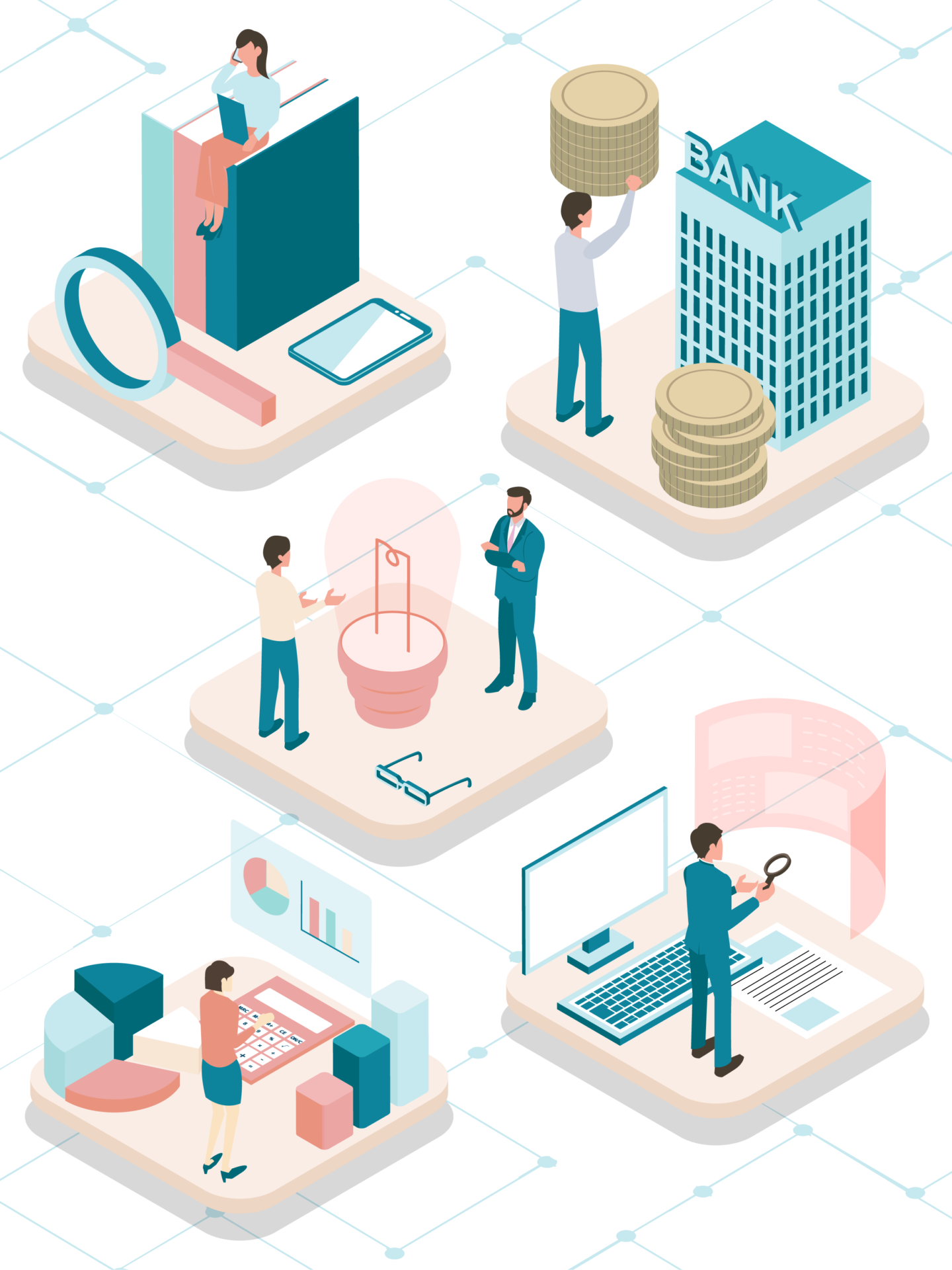
ウェブアクセシビリティとは、ウェブコンテンツが高齢者や障害の有無に関わらず利用できる状況の幅広さを意味します。
昨今さまざまなコンテンツがウェブから出されており、中にはウェブでしか扱わないようなコンテンツもめずらしくありません。
そのため、高齢者や障害者の人も含むすべての人が利用できるアクセシビリティの考え方がウェブにも求められるようになっています。
こちらでは、ウェブアクセシビリティの基本概念とそのガイドラインについて見ていきましょう。
ウェブアクセシビリティの基本概念
ウェブコンテンツを高齢者や障害者を含むあらゆる人にとって利用可能な状態であることがウェブアクセシビリティの基本概念です。
社会全体でのデジタル活用を進めるために必要不可欠な概念となります。
行政サービスなどもデジタル化が進んでいる影響で、誰もが平等に受けるべきサービスがウェブコンテンツに増えており、障害の有無やその度合いや年齢、利用環境でサービスの利用範囲が狭まってはいけません。
そのため、ウェブアクセシビリティを確保して、あらゆる人に平等にサービスを提供するためのコンテンツ作成が求められます。
誰もが利用可能なコンテンツとしてウェブアクセシビリティを担保するには、主に以下の観点でのコンテンツ作成の要素が重要です。
- 目が見えなくてもコンテンツの操作や理解ができること
- キーボードのみで操作できること
- 色弱の人にも正しく情報が伝わること
- 耳が聞こえなくても、音声や動画コンテンツが理解できること
上記の要素を抑えて初めてウェブアクセシビリティが確保されたウェブコンテンツと言えるでしょう。
ウェブアクセシビリティの基礎については、こちらでより詳しく解説しているためぜひ参考にしてみてください。
ウェブアクセシビリティのガイドライン
ウェブアクセシビリティには、WCAG(ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン)と呼ばれる事実上国際規格となっているガイドラインが存在します。
WCAGでは、ウェブコンテンツを障害のある人や加齢により能力が変化した高齢者にとって利用しやすいものにするための基準や定義を網羅していることが特徴です。
WCAGには原則と呼ばれるウェブアクセシビリティの土台となる4つの原則があり、それぞれ「知覚可能」、「操作可能」、「理解可能」、「堅牢」となり、以下のような特徴を持ちます。
- 知覚可能:利用者が提示されている情報を知覚できなくてはならない。
- 操作可能:利用者がインターフェースを操作できなければならない。
- 理解可能:利用者がUIの操作や情報の理解ができなければならない。
- 堅牢:利用者が技術の進歩に応じてコンテンツへのアクセスができなければならない。
上記の原則の下にガイドラインが設定されており、各ガイドラインには達成基準が設けられています。また各ガイドラインには達成のための参考達成方法が文章化されており、達成方法を参考にすることでコンテンツ作成に活かすことが可能です。
現在WCAGはWCAG 2.1としてウェブアクセシビリティ基盤委員会にて日本語訳版が公開されています。WCAG 2.1の詳細を確認したい場合はこちらからご確認ください。
ウェブアクセシビリティの具体例
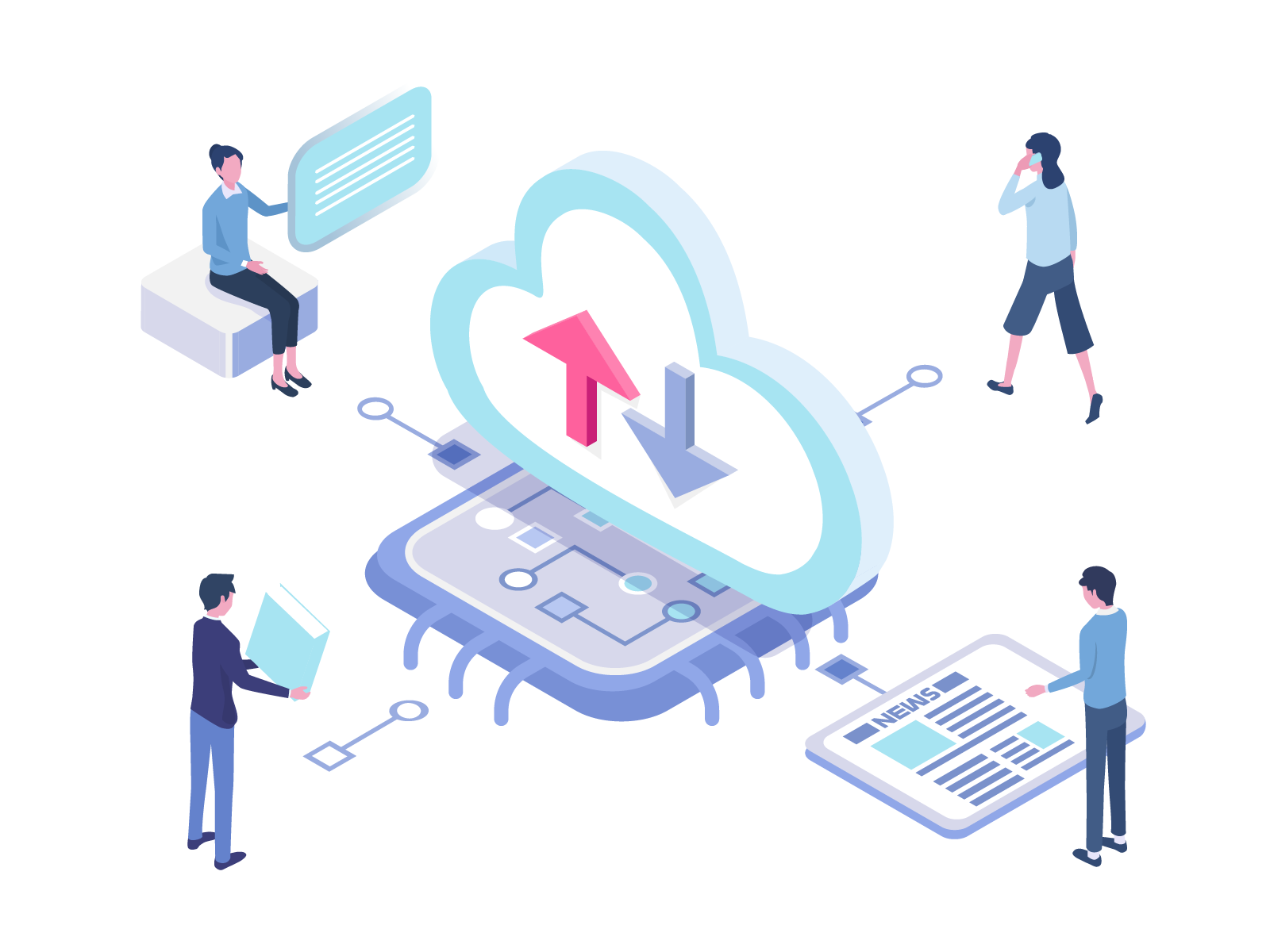
ウェブアクセシビリティのガイドラインだけでは、具体的な技術導入方法のイメージがつきづらい人は少なくないでしょう。こちらでは、ウェブアクセシビリティ確保のための技術対応の具体例について解説していきます。
字幕・手話・音声読み上げ
字幕・手話・音声読み上げは、それぞれ聴覚や視覚に障害がある人や加齢による聴力や視力の低下の人のウェブアクセシビリティを確保するための技術対応です。
これは、あらゆる利用者がウェブコンテンツの知覚や理解を促すための対応となります。
字幕
字幕では、映像コンテンツや音声コンテンツの文章化を行い、聴覚障害者の人や加齢による聴覚の低下を感じる人がウェブコンテンツを知覚、理解するサポートを行います。
例えば音声解説を含む映像コンテンツは、聴覚に障害や衰えがある場合適切に情報を理解することは難しいです。
そのため、映像や音声コンテンツに字幕などのキャプションをつけることで視覚的に音声で説明されている内容を理解できます。
手話
手話も字幕と同じく、聴覚障害者の人や加齢による聴覚の低下を感じる人に向けた対応です。
主に字幕のない映像コンテンツや音声コンテンツに実装されており、例えばリアルタイムでストリーミング配信されている映像コンテンツでは、発信されている情報を手話通訳者が同時通訳することで手話通訳に慣れた人でも理解できるように工夫されています。
自然言語が手話の人は、読解力が限られる場合があり、字幕では不十分になるケースが少なくありません。そのため手話はウェブアクセシビリティ確保の有効的な方法の1つといえるでしょう。
音声読み上げ
音声読み上げは、視覚に障害を持つ人や加齢による視力の低下を感じる人に向けた対応です。
主に、映像コンテンツの説明や文章のみのコンテンツなどの視覚的な情報へのアクセスをサポートするために実装されています。
例えば文章形式で記載されている行政コンテンツを音声読み上げ機能で読み上げることで視覚障害者や視力に衰えを感じる人でも情報を平等にアクセス可能です。
色・コントラスト・輝度の調整
色・コントラスト・輝度を調整することは、色を用いて視覚的にウェブアクセシビリティを確保することができる方法の1つです。主に、色覚異常の利用者でも問題なく色を使って伝える情報などの視覚的コンテンツを利用するための対応になります。
色はウェブコンテンツの訴求力やユーザービリティ、アクセシビリティを高めるうえで重要なデザイン手法の1つです。しかし色のみで情報を伝える場合に、色覚異常やロービジョンの利用者が近くできない場合があることが少なくありません。
例えば、文章コンテンツにて重要語句やリンクを含む文字列を色付けして区別させている場合、色覚異常を持つ人は他の文字と色で見分けることが難しい場合があります。
そこで、WCAGでは、視覚的に提示されるコンテンツは少なくとも3:1のコントラスト比を求めることで色覚異常を持つ人が情報を見逃さないように促すことが求められています。
またコントラスト比を設定するうえで重要な考え方が色の輝度(明るさ)の調整です。同じ明るさの色を使った場合、色覚異常を持つ人はそれぞれの区別ができない場合があります。
例えば天気図や等高線などでは、輝度を明るいものから段階的に暗くしていくことで区別されるようにデザインされていることが特徴です。
色やコントラスト、輝度で区別するにも限度があるため、文字の字体の調整や下線などを引くなどの工夫を取り入れることでより幅広く情報を知覚できるようになります。
互換性の確保
ウェブアクセシビリティの担保には、特定のデバイスやブラウザに依存しない互換性が確保されたウェブコンテンツ作成が求められます。
近年では、情報へのアクセス手段がPCだけではなく、スマホやタブレットと多岐にわたり、さらに使用されるブラウザもさまざまです。
例えば、PCブラウザ用に調整されたウェブコンテンツを利用する場合、スマホで見ると小さすぎたりそもそも対応しておらずアクセスできなかったりする場合があります。
複数のデバイスやブラウザに対応するためにも、異なる画面サイズや解像度に対応できるよう開発することが重要です。
特定のデバイスやブラウザだけに依存しているウェブコンテンツはウェブアクセシビリティが担保されているとはいえません。そのため、ウェブコンテンツ作成時には、互換性の確保が重要といえるでしょう。
わかりやすい指示やエラー表示
ウェブアクセシビリティを高めるうえで、わかりやすい指示やエラー表示は有効です。ウェブコンテンツを利用する上で、明確な指示がないとユーザーは次のアクションが分からなくて困惑してしまいます。
また、入力作業が必要なコンテンツ利用時に詳細なエラー表示がないとエラーに気づけずコンテンツを十分に活用できません。
例えば、確定申告などでウェブ申告をする場合に、どこにどの数値を入力するかなどの明確な指示やエラーメッセージを表示させることであらゆる人がスムーズに申告できるように工夫されています。
デジタル化であらゆる申請がウェブコンテンツに置換しつつある昨今では、幅広い世代で利用できるようにわかりやすい指示とエラー表示をすることが重要といえるでしょう。
ウェブアクセシビリティの義務化

2024年4月に施行される「改正障害者差別解消法」の法改正によって、全事業者のウェブアクセシビリティ確保の義務化が決まりました。
そのため、これまで提供してきたウェブコンテンツにウェブアクセシビリティが確保されているかの確認や、確保されるように再設計などの対応が全事業者に求められます。その他にもさまざまな影響が考えられるでしょう。
こちらでは、ウェブアクセシビリティ義務化の詳細や義務化による影響について解説していきます。
義務化の詳細
2024年4月に施行される「改正障害者差別解消法」にて全事業者を対象に「合理的配慮」が努力義務から義務化されたことで、ウェブアクセシビリティの確保が義務化されます。
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じようにあらゆることが保証されるとともに教育や就業、行政サービスなどを平等に利用できるように各障害特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。
ウェブアクセシビリティは、合理的配慮の措置の中でも「環境の整備」に含まれており、デジタル庁が提供している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」の実施基準に則って対応していくことが求められます。
ウェブアクセシビリティの実施におけるガイドラインには、国際規格である「WCAG」と国内規格である「JIS X 8341-3:2016」が用いられていることが特徴です。
デジタル庁では、2つあるガイドラインの中でも国内規格であるJIS規格に対応したウェブサイト作りを推奨しており、ウェブアクセシビリティ確保する上で主に以下の4区分に分けての達成基準が設けられています。
- 達成しないと利用者に重大な悪影響を及ぼすもの
- 必ず達成しなければならないもの
- 状況に応じて確認すべきこと
- 導入に慎重な検討が必要
上から順番に対応していくべき達成基準が設けられており、特に「達成しないと利用者に重大な悪影響を及ぼすもの」や「必ず達成しなければならないもの」は、ないと利用者に悪影響や平等な情報取得の機会を損なう可能性があるためガイドラインを参照して、詳細な達成基準を抑えておくことが重要です。
ウェブアクセシビリティ義務化による影響
ウェブアクセシビリティの義務化によって、全事業者は負担が重すぎない範囲(「過重な負担」※のない範囲)での合理的配慮の提供が求められています。
※「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
| 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) 費用・負担の程度 事務・事業規模 財政・財務状況出展:内閣府|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト「合理的配慮の提供」 |
義務化によって主に以下のような影響が出ると予測されます。
- ホームページの再設計や更新
- 開発コストの上昇
- アクセシビリティ対応とテストの継続
それぞれを理解して、ウェブアクセシビリティ確保対応に備えましょう。
ホームページの再設計や更新
アクセシビリティ確保の義務化によって、全事業者は従来のホームページの再設計や更新を行う必要があります。
これまで努力義務の範疇で行われてきた合理的配慮が今回の改訂で義務化したため、達成できていなかった基準も含めて見直す必要性が発生しました。
特にホームページの再設計は、従来の営業プロセスにも影響があるだけでなく多くの工数を必要とする作業です。
そのため、ウェブアクセシビリティ確保のためのホームページ再設計や更新が全事業者に与える影響は大きいといえるでしょう。
開発コストの上昇
ウェブアクセシビリティ確保の義務化によって、開発コストの上昇が考えられます。
ウェブアクセシビリティ確保のために音声読み上げ機能や字幕生成機能などさまざまな機能の追加が求められるでしょう。
ガイドラインで求められる達成基準に基づいた開発を行うとなると大規模な開発とコストが必要になります。従来のサービスへの適応だけでなく、今後開発を予定しているサービスにも適応させなくてはならないため、将来にわたっての開発コストの上昇が予測されるでしょう。
アクセシビリティ対応とテストの継続
開発後も障害を持つ人からの意見をヒアリングしてアクセシビリティ対応とテストの継続を行い更なる改善に取り組まなくてはいけません。
ウェブアクセシビリティの基準は今後も更新されていき、都度対応していくことが求められます。
また、一度にすべてのシステムのウェブアクセシビリティの確保をしていくことは工数の関係でも難しく、コツコツとアクセシビリティ対応をしていくことになります。
今後もアクセシビリティ対応とテストの継続を前提として企業の対応が続いていくことが予測されるため、ウェブアクセシビリティの義務化による影響の1つといえるでしょう。
まとめ

ウェブアクセシビリティの確保とは、障害者や高齢者などを含むあらゆる人にとってウェブが使いやすい状態です。特に障害や加齢による衰えで視覚や聴覚が上手く使えない人でも理解できるようなシステムづくりが求められています。
ウェブアクセシビリティの達成基準はさまざまでそれぞれガイドラインに定義されています。そのため、まずはデジタル庁が発行しているガイドラインを参照することがおすすめです。
ウェブアクセシビリティの確保は2024年4月施行の「改正障害者差別解消法」によって義務化されます。そのため全事業者が、自社のシステムにウェブアクセシビリティが確保されているのか確認・改修が必要です。また、今後開発されるシステムにもウェブアクセシビリティを考慮する必要が出てくるため開発がより複雑化していくでしょう。
自社システムのウェブアクセシビリティ確保のためのシステム開発や改修を考えている場合は、株式会社Jiteraに一度ご相談してみてはいかがでしょうか。お問い合わせフォームはこちらです。








