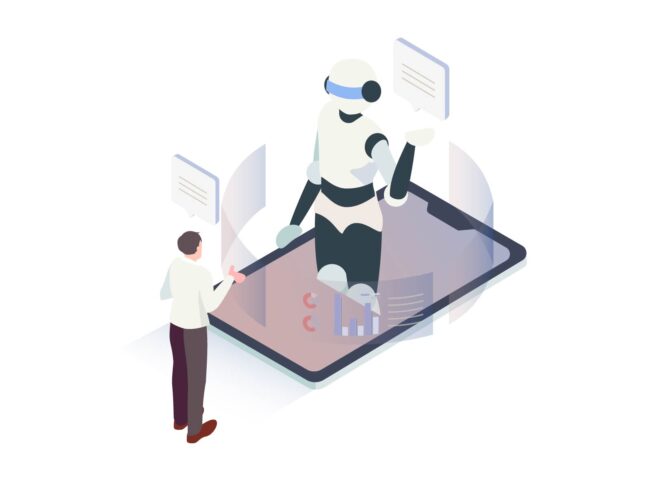データ管理の重要性は理解しているものの、実際に着手するとなると、以下のような状況に陥っていませんか?
- 何から始めればいいのか分からない
- 他の業務に追われて後回しになってしまう
会社でデータ管理はどうしても後回しになる業務です。担当者は日々の業務に追われ、なかなか着手できない状況に陥ってしまいます。
また、データ管理の重要性は理解していても、具体的にどのように進めればいいのか分からないなど、多くの問題が存在するのではないでしょうか。
そこで本記事では、このような課題を抱える方に向けてデータ管理の概要や、メリット・課題について詳しく解説します。
データ管理を効率的に進めるためのコツも紹介するので、最後までお読みください。
大学卒業後、インフラ系エンジニアを3年経験。その後、営業会社に転職し通信系の商材をメインに取り扱う。副業でアフィリエイトやWebライターを始め、2021年11月に独立。光回線や格安SIM、BtoBマーケティング、取材案件の執筆が得意。
データ管理とは?
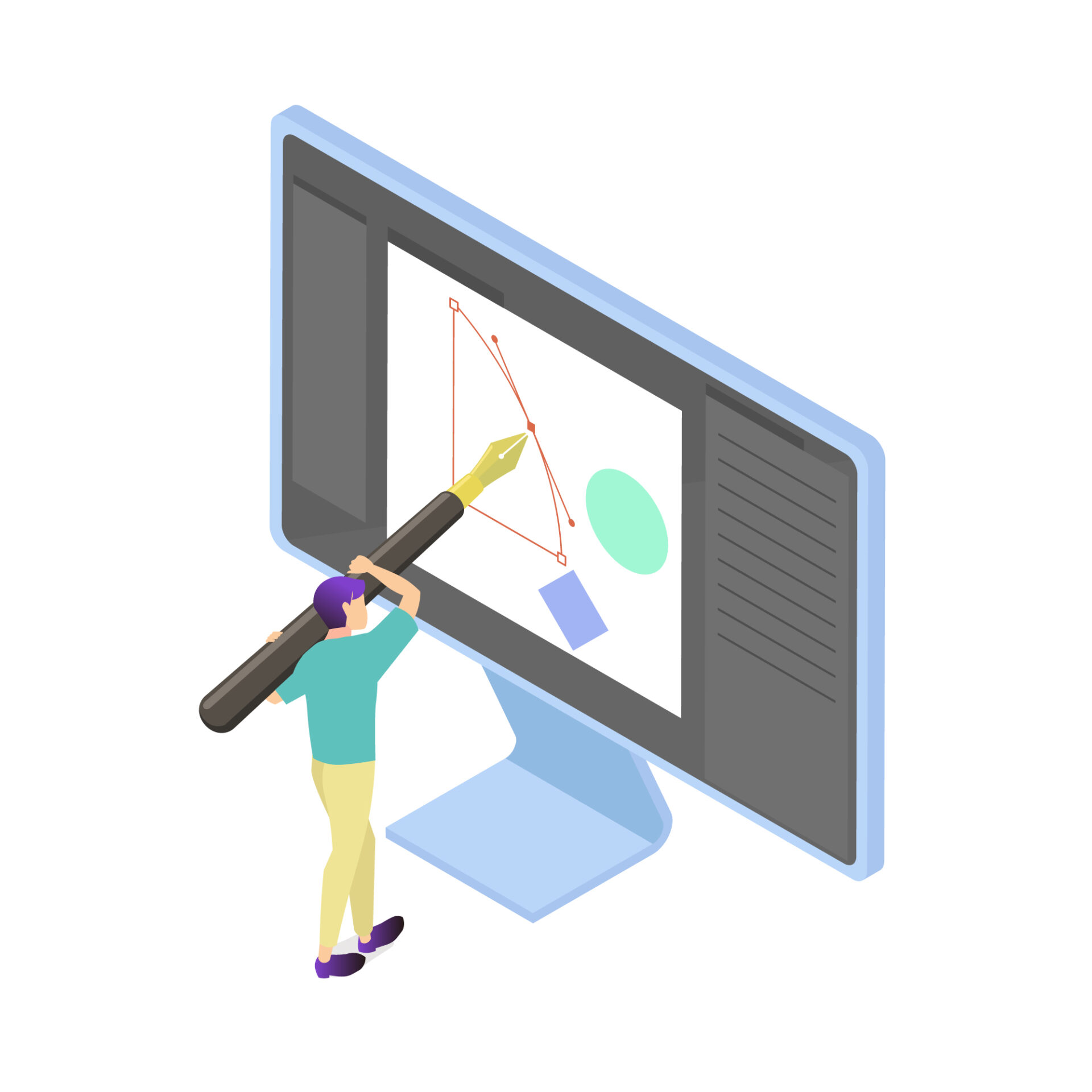
データ管理とは、組織や個人が持つデータを効率的かつ安全に取り扱うための一連の活動のことです。
具体的には、データの整理や保存、品質管理、データ保護などが含まれます。
データ管理の目的は、データの価値を最大限に引き出し、ビジネスの意思決定や問題解決に役立てることです。
そのために、データを適切に分類し、必要な情報に素早くアクセスできるように調整する必要があります。
その上で、品質を維持し、不正確さや矛盾のないデータを提供することも欠かせません。
また、データ管理では、データの安全性確保も大きな課題です。
機密情報の漏洩やデータの紛失を防ぐために、アクセス権限の設定やバックアップの実施など、セキュリティ対策をしなければなりません。
効果的なデータ管理を実現するには、組織全体でデータの重要性を認識し、一貫したルールやプロセスを確立しましょう。
データ管理を支援するためのツールや技術を活用し、作業の効率化や自動化を図ることも検討してください。
データを可視化するために、具体的な方法は以下の記事をご参照ください。
データ管理の役割は?

データ管理は、組織にとって重要な役割を果たします。
なぜなら、情報を効率的に活用し、組織の目標達成をサポートできるからです。
適切に管理されたデータは、ビジネス上の意思決定に欠かせない資源となります。
例えば、顧客データの販売履歴を分析する場合を想像しましょう。
頻繁に購入する顧客がいる場合に、特別な割引やプレミア特典を提供すれば、LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できます。
このようなキャンペーンがホームページやメルマガで告知されれば、対象顧客だけでなく、ほかの顧客も購入意欲を刺激し、結果的に売上増加につながる可能性があります。
また、データ管理は、業務の効率化にも貢献するものです。
さまざまな部門で発生するデータを一元的に管理すると、情報の検索や共有がスムーズになり、無駄な作業を削減できます。
データの重複や不整合も防止できるため、ミスを大幅に減らすことが可能です。人の目に頼る必要がありません。
さらに、リソースの最適化にも役立ちます。
データを活用して業務プロセスを可視化すると、ボトルネックの特定や改善点の発見がしやすいです。
適材適所の人員配置をするためのデータとなり、組織全体のパフォーマンスを最大化できます。
このように、データ管理は今後、企業が成長するために不可欠と言えるでしょう。
データ管理を適切に実施する4つのメリット

データ管理を適切に実施できると、以下のようなメリットがあります。
- データを活用すると売り上げにつながる
- 一元管理すると生産性が向上する
- データが漏洩するリスクが減る
- 組織のサイロ化が解消する
それぞれ見ていきましょう。
データを活用すると売り上げにつながる
データを分析し、活用すると、売上増加につなげることが可能です。
例えば、顧客データから購買行動や嗜好を把握し、パーソナライズされたおすすめ商品を提示したり、効果的なキャンペーンを打ち出したりすれば、顧客の購買意欲を高められます。
また、販売データを分析すると、人気商品や売れ筋商品を特定することが可能です。
在庫管理や商品開発に反映させられるため、活用しない手はありません。
結果として、効果的なクロスセルやアップセルにつなげられます。
データをもとに効果のある提案を試せるため、実施する価値は十分にあるのではないしょうか。
一元管理すると生産性が向上する
データを一元管理すると、業務の効率化ができるため、生産性の向上につながります。
異なるシステムやデータベースに散在していたデータを統合すれば、情報の検索や共有がスムーズになり、業務スピードをアップすることが可能です。
異なるシステムやデータベースに散在していたデータを統合することで、情報の検索や共有がスムーズになり、業務のスピードアップにつながります。
例えば、ある企業では、下記のシステムがバラバラで分散していました。
- 顧客情報が営業部門のCRMシステム
- マーケティング部門のMAツール
- カスタマーサポート部門の問い合わせ管理システム
この状態では、各部門が持つ顧客情報を横断的に検索したり、統合的に分析したりすることが困難です。
そこで、同社はデータ統合プロジェクトを立ち上げ、各システムのデータを一元的に管理するデータウェアハウスを構築しました。
その結果、それぞれの部門のデータ確認が簡単になり業務効率が大幅に改善されます。
データが漏洩するリスクが減る
適切なデータ管理は、データ漏洩のリスクを減らすことが可能です。
機密情報や個人情報を含むデータを適切に保護し、アクセス権限を管理することで、不正アクセスや情報流出を防止できます。
これまでワードやエクセルをメインにして顧客情報を管理していた会社であれば、顧客管理ツールを導入するとセキュリティ面が向上し、ユーザビリティーも改善できます。
また、定期的なバックアップやデータの暗号化などの対策を講じることで、万が一の事態にも安心です
クラウドサービスでは、自動バックアップ機能を提供しているサービスが多く、仮に個々のデバイスが故障しても、データを失うことはありません。
高度な暗号化技術により、たとえデータが外部に流出したとしても、ファイル自体が暗号化されている場合があります。
その結果、第三者が内容を解読することは極めて困難です。
組織のサイロ化が解消する
データ管理を適切に実施すると、組織内のサイロ化を解消できる場合があります。
- サイロ化とは、部門間の情報共有が不十分で、各部門が独自のデータを持ち、全体最適ではなく部分最適になってしまう状態のこと。
データを一元管理し、部門横断的に活用できれば、組織全体で情報を共有がしやすくなります。
これまで他部門で入手しにくかった情報も確認できるようになれば、問題解決のスピードを早めることが可能です。
このような環境であれば、意思決定の質が向上し組織のパフォーマンスが高まります。
データ管理をする際の3つの課題
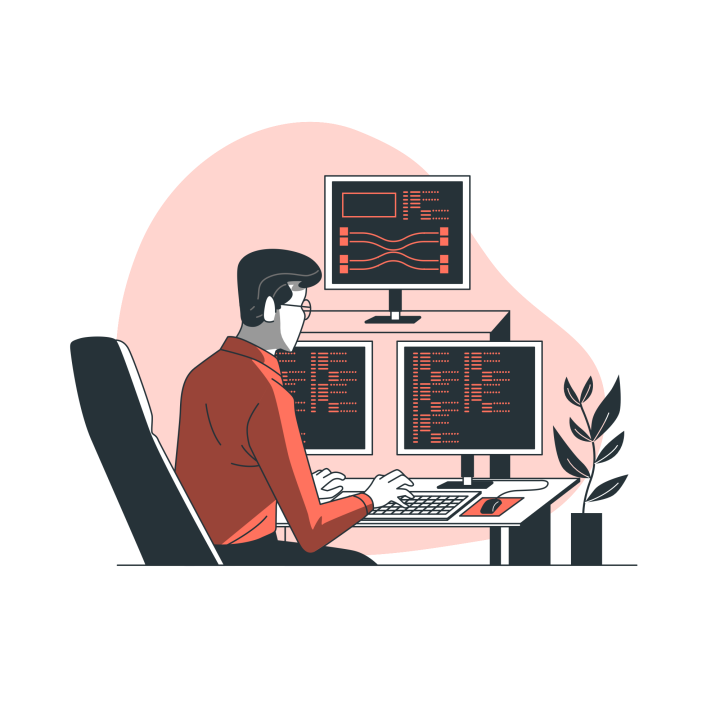
データ管理には多くのメリットがありますが、以下の課題には考慮する必要があります。
- システムを刷新する場合がある
- ITツールを使える人材が不足している
- データの整合性を維持する必要がある
詳細は以下の通りです。
システムを刷新する場合がある
効果的なデータ管理を実現するには、既存のシステムを刷新する必要がある場合があります。
古いシステムを利用していると、データの統合や分析が難しく、維持管理のコストも高い場合があります。
新システムと連携する際も、データ形式が異なるなどの理由で簡単に進められないケースも珍しくありません。
しかし、長期的な観点から見れば、業務の効率化やデータ活用につながります。投資対効果は十分に見込めるため、遅かれ早かれ実行したほうが良いです。
また、システム刷新の際は、現場の意見を取り入れながら、段階的に進めることをおすすめします。
システムを主に活用するのは現場のスタッフです。
彼ら・彼女らの要望に応じたシステムにすることで、導入後の混乱を最小限に抑え、円滑に運用できるようになります。
ITツールを使える人材が不足している
データ管理には、専門的な知識とスキルが必要です。
しかし、ITツールを使いこなせる人材が不足していると、導入が進みにくくなります。
なぜなら、新しいシステムを導入すると、使用方法を勉強しなければならないからです。
特に、これまでの方法に慣れてしまったスタッフからすると、面倒になってしまいます。
また、専門家の雇用やトレーニングのコストが負担になる場合があります。外部の研修やオンライン学習の活用をするだけで、企業にとっては大きな負担です。
ツールの選定を誤ってしまうと、社員がキャッチアップするまでに時間がかかってしまいます。
そのため、導入するシステムやツールは、事前に十分に検討し社員に共有しましょう。
データの整合性を維持する必要がある
データは正確で一貫性があり、信頼できる状態にすることが大切です。
データの整合性が取れていないと、せっかく導入したツールも活用できなくなってしまいます。
例えば、顧客情報が重複していたり、住所や電話番号に誤りがあったりすると、マーケティングキャンペーンの効果が減少してしまいます。
また、販売データの入力漏れや誤入力があると、需要予測や在庫管理に支障をきたします。
経営層が不正確なデータを元に意思決定を行ってしまうと、大きな損失につながりかねません。
データ連携の設計を適切にするなどの対策が必要です。
データ管理を効率化するためのコツ

データ管理を効率化するには、以下のようなコツが存在します。
- 目的を決める
- データごとにライフサイクルを決める
- 後回しにしない
いずれも重要なポイントなのでチェックしてください。
目的を決める
データ管理を始める前に、まず目的を明確にすることが大切です。
データを収集し、保管する理由を自問自答してみましょう。
「なぜデータが必要なのか」「どのようにデータを活用するのか」といった問いに答えを出すことで、データ管理の方向性が見えてきます。
目的が明確でないと、とりあえずデータを溜め込んでしまい、情報量が多すぎて管理できなくなってしまうケースが少なくありません。
必要のないデータまで保管していては、業務の効率が下がってしまいます。
目的に沿って、保管するデータの条件を決めることが重要です。
例えば、顧客データを管理する場合、以下のような具体的な基準を設けます。
- 直近1年以内に取引のあった顧客
- 年間売上が100万円以上の顧客
- 年間5回以上購入した顧客
この基準に当てはまらない顧客データは、思い切って削除するのも1つの方法です。
データごとにライフサイクルを決める
データ管理には、作成から廃棄までのサイクルがあります。
データの種類や重要度に応じて、適切なライフサイクルを設定することが重要です。
例えば、顧客の注文データは、商品の発送が完了した時点で、保管の必要性が低くなります。
一方、契約書などの法的文書は、契約期間が終了した後も、一定期間保管しなければなりません。
データのライフサイクルを決める際は、法的な保管義務やデータの利用頻度、ストレージのコストを考慮しましょう。
適切なライフサイクル管理により、必要なデータへのアクセスやコンプライアンス問題の防止、データの信頼性と整合性の維持が可能です。
後回しにしない
データ管理の改善は、早めに取り組むことが重要です。
「今は忙しいから後でやろう」と思っていると、いつまでも先延ばしになってしまいます。
データ管理の課題は、放置するほど大きくなる一方です。
例えば、不要なデータを削除せずに放置していると、ストレージの容量が圧迫され、システムのパフォーマンスが低下する恐れがあります。
また、古いデータが残っていると、分析の精度が下がるだけでなく、セキュリティ上のリスクにもつながります。
データ管理の改善は、今すぐ取り組みましょう。
確かに、データ管理の仕組みを構築するまでに一定の時間と労力が必要です。
しかし、一度確立したデータ管理の仕組みは、業務の効率化と意思決定の迅速化につながるため、長期的におすすめです。
データ管理はツールと委託開発の組み合わせがおすすめの理由

データ管理を効果的に実行するには、ツールの活用と委託開発の組み合わせがおすすめです。
- ツールを使うと基本的な機能をすぐに導入できるから
- 委託開発で自社に不足している技術を補えるから
上記2つの理由を詳しく説明していきましょう。
ツールを使うと基本的な機能をすぐに導入できるから
データ管理ツールを導入すると、基本的な機能をすぐに利用できます。
例えば、データ収集や保管、検索、分析などの機能は、多くのツールに標準で備わっています。
これらの機能を自社で一から開発するとなると、多大な時間と労力が必要です。
ツールを活用することで、開発コストを抑えつつ、短期間でデータ管理の基盤を整えられます。
また、ツールには、セキュリティ対策や性能向上のための機能も用意されている場合が多いです。
専門知識がなくても、一定レベルのセキュリティと性能を確保できます。
ただし、ツールだけでは、自社固有の要件に完全に対応できません。そこで、委託開発を組み合わせることをおすすめします。
委託開発で自社に不足している技術を補えるから
委託開発を活用すると、自社に不足しているデータ管理の技術やノウハウを補うことが可能です。
データ管理には、高度な専門知識が必要とされます。特に、ビッグデータの処理や高度な分析には、専門的なスキルが欠かせません。
自社だけで人材を確保し、育成するのはハードルが高いです。
しかし、委託開発であれば経験豊富な外部の専門家の力を借りられます。
プロの知見を使えば、自社の要件に合わせたカスタマイズや、高度な機能の実装が可能です。
また、自社の開発チームと外部の専門家が協働すれば、自社にノウハウをストックできます。
ツールと委託開発の組み合わせは、それぞれの長所を活かしつつ、短所を補い合える優れた方法です。
Salesforceと連携したシステムを開発した事例

株式会社Jiteraには、Salesforceと連携したシステムを開発した事例があります。
通信機器のレンタルサービスを展開する「WOW WORKS株式会」では、注文管理に関する業務をエクセルで実施していました。
そのため、発生した問題点は以下の通りです。
- 人的ミスが発生しやすい
- 非効率で人件費がかかってしまう
そこで、Jiteraに委託開発を依頼し、Salesforceと連携する注文管理システムを構築しました。
Jiteraは、Salesforceの標準機能を活用しつつ、企業の要件に合わせたカスタマイズを実行。その結果、注文受付から発送までの業務自動化に成功し、大幅な効率化を実現しました。
この事例は、ツールと委託開発を組み合わせると、自社に最適なデータ管理システムを構築できる点を示しています。
特に、Salesforceのような高機能なツールと、Jiteraのような専門性の高い開発会社の組み合わせは、データ管理の課題解決に非常に有効です。
導入事例の詳細は下記をご参照ください。
>>人の手→Salesforce連携ソフトウェアで注文管理。Jiteraに決めた理由
まとめ:データ管理を進めるメリットは大きい
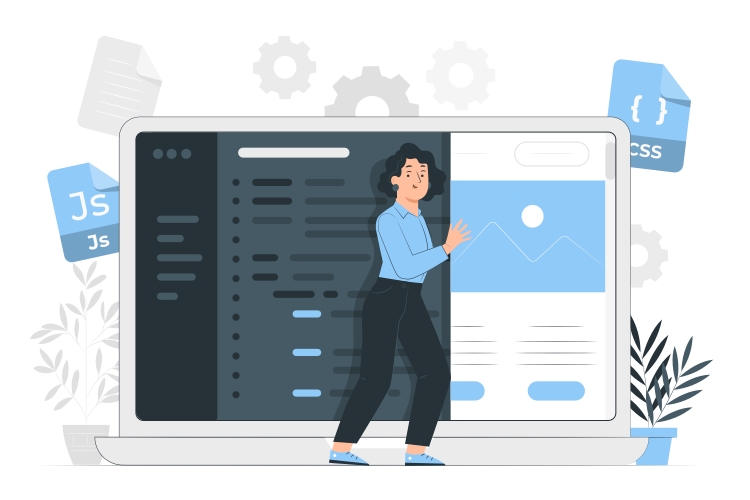
データ管理を進めるメリットは計り知れません。
初期コストはかかりますが、長期的にはプラスになる場合が多いと言えます。
ツール導入やシステム開発を進めるにあたって課題はありますが、一歩ずつ改善を積み重ねることで、企業の競争力を高める鍵となるのではないでしょうか。
特に、ツールの活用と委託開発の組み合わせは、効果的なデータ管理を実現するための有力な選択肢です。
株式会社Jiteraでは、AIを活用したシステム・アプリ開発が得意です。データ管理ツールと連携し、高品質な開発を目指します。