ChatGPTを皮切りに次々と生成AIが誕生し、今では業務で活用されるほどに進化が進みました。生成AIを活用する企業では業務の効率化やコストの削減、さらには新しいアイデアの創出などさまざまな分野で活用を進めており、生成AIを活用していない企業と差別化を図ろうとする動きが見えます。
この記事では、ITインフラ分野における生成AIの活用にフォーカスし、メリットや利用するための注意点などについて解説します。最後には実際の活用事例もご紹介しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
月間120万pvの生成AI専門メディアを運営 LLMを利用したメディアの検閲業務の自動化やノーコードツールを用いた最新情報調査/トレンドワードによるタイトル最適化などを行う。
ITインフラ分野でも活躍中の生成AI

ITインフラ分野における生成AIの活用範囲は広く、ソフトウェア開発時などのコーディングやテスト、新人教育、カスタマーセンターでの自動応答など、その活用方法は多岐に渡ります。
コールセンター業務においては、今や世間一般的にも生成AIが活用されていることが認知されつつあり、今後は技術が進化して精度が上がることが予想され、さらに導入が進んでいくでしょう。
また、コーディング分野においても、デバッグ・テスト段階での導入や自然言語入力からコードを生成できたりと、スキルが高くなくても生成AIにアシストしてもらいながら開発できる環境も整いつつあります。
このように、スキルを持った人材が不足している分野でも、生成AIを活用すれば足りないスキルを補うことができるだけではなく、工程によっては自動化することも可能です。
ITインフラ分野で生成AIにできること5選
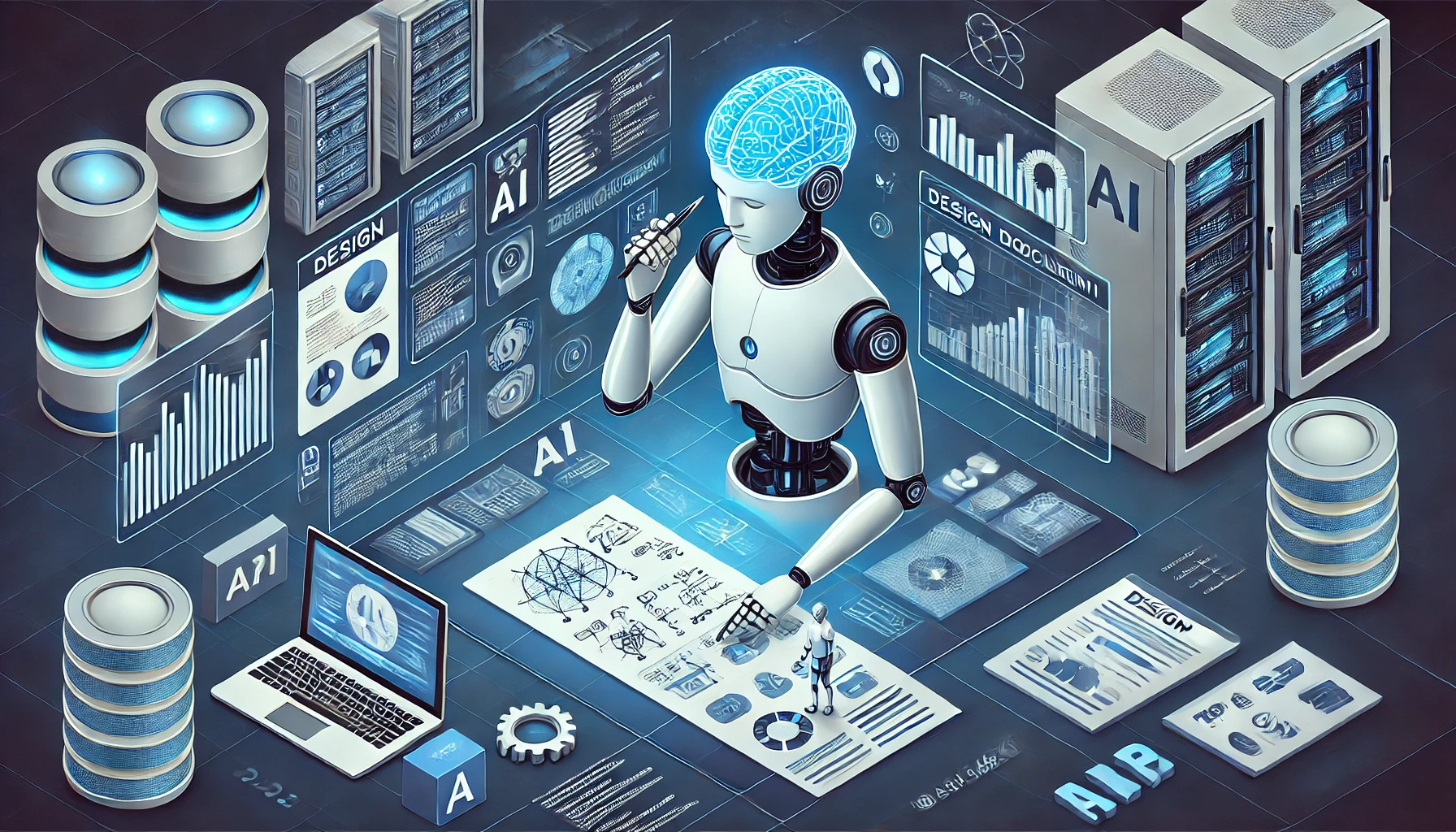
さまざまな企業で導入が進み注目を浴びている生成AIですが、ITインフラ分野においてはどのようなシーンで活躍しているのでしょうか。
ここでは、ITインフラ分野で生成AIにできることについて解説します。
新人教育・ヘルプデスク業務の自動化
新人教育やヘルプデスク業務は生成AIを活用すれば、自動化できる部分が多く導入している企業はたくさんあります。新人教育で言えば、生成AIを使って教材を作ったり、AIチャットボットによる質疑応答させたり、プログラマーであれば、書いたコードの添削など、業務に合わせた対応が可能です。
また、ヘルプデスク業務であればよくある質問をリストアップし、生成AIに学習させることで簡単な対応であれば解決まで対応できます。もし、対応できない内容だったとしても一次対応として機能するため、オペレーターの負担を軽くすることができます。
例えば、GPT3.5に「オンプレミスで使えるおすすめの小型LLMについて、具体的なモデル名を教えて」と質問すると下記のような回答が返ってきます。

回答をみていただければわかる通り、GPT3.5では適切な回答を得ることができませんでした。
それに対して、必要な情報を組み込んだChatGPT APIとLangchainで作ったチャットボットを使えば、下記の通りに希望の情報を出力することができます。

このように、生成AIに自社独自の情報やよくある質問などを学習させることで、問い合わせ件数をグッと減らすことができるでしょう。
設計書レビューの自動化
システム開発において重要な作業である設計書のレビューも生成AIを活用すれば自動化することが可能です。
設計書のレビューでは、開発過程で起きた過去のミスを繰り返さないために企業独自のチェックリストを作成し、そのチェックリストの内容に沿ってレビューを進めていく企業が多いでしょう。
そのため、設計書レビュー工程はある程度マニュアル化されている企業が多いですが、チェックリストだけではカバーできない部分も多く、一つ一つ細かく確認する必要があるため時間がかかる工程です。
そんな時間のかかる設計書レビュー工程に生成AIを活用すれば、瞬時にチェックを行うことができ、問題点も出力できるため作業効率をあげることができます。
例として、設計書をChatGPTにアップロードし、「添付した設計書に矛盾している部分はありますか?」と質問してみました。

すると上記のように、説明不足であるところや不明瞭な部分など瞬時に指摘してくれました。もっと、細かくプロンプトを入力すればより詳細に詳しくレビューすることも可能なので、いろいろ試してみることをおすすめします。
フロー・構成図の生成
フロー・構成図を作成するには、全体の構造を把握し視覚的にわかりやすく表現する必要があります。そのため、円形や長方形などの図形や矢印、アイコンなどを用いて作られることが多く、図の構成を考えたり、画像の選定を行ったりと、どうしても時間がかかってしまう作業です。
しかし、生成AIを活用すれば、自然言語でのプロンプトを打ち込むだけでアイコン付きの構成図を生成することが可能です。また、構成図は自分で作りたいけど、アイコンや画像を探すのが苦手という方でも、画像生成AIを使えば、希望のアイコンや画像を簡単に生成できるので、探す手間を削減することができます。
フローや構成図の作り方はさまざまありますが、今回はChatGPTを活用して作った流れを紹介します。
まず、下記のようなプロンプトを入力し、開発フローの大枠をChatGPTに作ってもらいます。

上記のプロンプトに対して下記のような出力がされました。

内容をみる限り、重要なポイントを抑えつつプロジェクトの進め方もわかりやすく出力してくれました。これだけでもChatGPTを使う価値はあると思いますが、この出力結果を基に開発フローを図式化してみましょう。
図式化するためにはChatGPTに「上記の開発フローを図式化してください」と入力します。

すると、上記のように開発フローを図式化することができました。
このように、特別なソフトを使わなくても生成AIだけでフローや構成図を瞬時に作ることができます。明確に細かく言語化できるようになれば、さらに詳細なフローや構成図を生成することができるので、効率的に作業を進めるためには、生成AIの導入を検討した方が良いでしょう。
SQLの生成
データベースへのアクセスや定義付けなどを行うためにはSQLを利用することが多いでしょう。そのためデータベース関連の操作を行いたい場合は、SQLの知識が必要不可欠です。
ところが、ChatGPTなどの生成AIを活用すれば自然言語からSQLを生成することができるため、多少曖昧なプロンプトからでもSQLを生成することができます。
例として、SQLのテーブルを生成する際の雛形をChatGPTで作ることができます。作り方も簡単で「テーブル作成時に利用するSQL文の雛形を作ってください」とプロンプトを入力するだけで下記のようなSQL文を生成できます。

このように、曖昧な自然言語プロンプトからでも、しっかりとSLQ文を生成することができました。また、SQL文を生成するだけではなくわかりやすいように各要素の説明までしてくれていますね。
また、SQLの知識を持ったエンジニアでも、最終チェックや部分的なアシスタントとしてSQL文を生成してもらうなど、幅広く生成AIを利用できます。
その他コーディング全般
生成AIを活用すれば、プログラミング技術がなくても自然言語からコーディングを行うことができます。今では、専門知識がない人でもプログラミングしたい工程や果たしたい目的を言語化できれば、独自のアプリケーションやシステムを構築することができるようになりました。
例えば、プログラミング関連の業務全般を自動化できる「Cursor」というツールに、「電卓アプリのJavaScriptコードを生成してください」とプロンプトを送ってみます。

すると、上記のように指定した言語でコードを生成してくれました。このようにプログラミングの知識がなくても、簡単かつ瞬時にコーディングを行うことができます。
コーディングにおける生成AIの利用方法はそれだけではなく、自分で書いたコードのチェックやコーディングの学習など、エンジニアの学習ツールとしても利用できます。
また、コーディングに強い生成AIツールも続々と出ていますが、GPT-4と比較すると性能が劣る場合もあるので、コーディングツール選びは慎重に行いましょう※1
ITインフラ分野で生成AIを導入するメリット3つ

前述の通り、ITインフラ分野でも生成AIが活躍する場面は多く、今や多くの企業が導入を進めています。そんな注目を集めている生成AIですが、なぜ次々と導入を検討する企業が増えているのでしょうか。
次に、ITインフラ分野で生成AIを導入するメリットについてご紹介します。
メリット1.コストを削減できる
単純作業やよくある質問の回答、品質チェックなど生成AIに代替えできる業務はたくさんあり、それらの業務を生成AIに任せることで、人件費やツール代などのコストを削減できます。
例えば、ヘルプデスク業務でいうと、よくある質問などマニュアル化されている内容を学習させた生成AIにヘルプデスク業務の一時対応を任せることができます。よくある質問や簡単な問い合わせなどは生成AIの回答で解決するものも多く、必要な時だけオペレーターが対応というスタイルであれば、人件費を削減することができるでしょう。
メリット2.業務時間を短縮できる
生成AIは膨大な学習データの中から、瞬時に入力されたプロンプトに沿った内容を出力してくれます。そのため、様々な場面で業務時間を短縮することが可能です。
特に、システム開発を行う際には、工程も多く細かい作業もたくさんあるため、生成AIを上手く活用できれば大幅に業務時間を短縮できるでしょう。
メリット3.誰もが専門的なスキルを身につけられる
専門的なスキルを身につけるためには独学でも可能ですが、誤った解釈をしてしまったり、わからないところが解決できないまま学習が進まないということもあるでしょう。そのため、セミナーや勉強会などに参加した方が理解度も高く、より正確にスキルを身につけることができるので、誰かに質問できる環境の方が専門的なスキルを身につけるためには好ましいです。
しかし、業務が忙しく日程が合わないためセミナーや勉強会に参加できなかったり、先輩社員に質問しようと思っても、忙しそうで質問できないということも多々あるでしょう。
そんな問題も生成AIを使えば解決できます。例えば、日々進化するプログラミングの学習に生成AIを活用することで、書いたコードの間違いを指摘してもらったり、アドバイスをくれたりすることができます。
そのほかにも、新人研修の際に生成AIを用いた教材を導入している企業も多いので、専門的なスキルを身につけるためには、生成AIを活用するのもおすすめです。
ITインフラ分野で生成AIを導入する際の注意点3つ

業務効率を上げ、コストも削減できるなど、生成AIをITインフラ分野で導入することで得られるメリットはたくさんあります。しかし、生成AIの特性をしっかり理解していないと思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。
ここでは、ITインフラ分野で生成AIを導入する際の注意点についても解説します。
注意点1.誤った情報を生成するかもしれない
生成AIは日を追うごとに進化し精度出力制度は上がっていますが、まだまだ事実と異なる不正確な情報を出力する可能性があります。この現象を「ハルシネーション」といい、生成AIを使う上で注意すべきポイントの一つです。生成AIに学習範囲外の知識を与えるRAG Fusionを活用するなど、ハルシネーション対策を行うこともできますが、それでも100%ハルシネーションを起こさないというわけではありません。※2
このように、誤情報が出力される可能性があるため、生成AIから出力された情報を鵜呑みにすると思わぬ問題に発展することがあります。特に正確性が求められる用途で使用する場合は、追加の確認や校正を行うことが必要でしょう。
注意点2.セキュリティ面でリスクがある
生成AIは大量のデータを基に学習しているため、学習データの中に個人情報や機密データを含んでいる可能性があります。そのため、生成AIを活用したコンテンツの作成やプログラミングを行った際に、思わぬ形で機密データが外部に漏れる危険性があるのです。
そのため、生成AIを活用して作られたコンテンツやシステムは、リリース前に必ず外部に漏れてはいけない情報が含まれていないか確認する必要があるでしょう。
注意点3.ソースコードの著作権に関して
生成AIを活用してシステム開発を行う場合、生成されるソースコードの著作権や使用権に関する問題に注意を払う必要があります。生成AIが他社製品などのソースコードを参考にして新しいコードを生成した場合、その過程で著作権に触れる可能性があるからです。
このため、生成AIを活用してシステム開発を行った場合は、ソースコードの参照元などを確認する必要があるでしょう。
ITインフラ分野における生成AIの活用事例2選

生成AIにはメリットだけではなく、利用するために注意すべき点があることがわかりました。では、その点を踏まえて、各企業ではどのように生成AIを業務に取り入れているのでしょうか。
最後に、ITインフラ分野における生成AIの活用事例についてみてみましょう。
事例1.GMOインターネットグループ株式会社
GMOインターネットグループ株式会社では、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」をスローガンに積極的に生成AIを業務に導入しています。2024年3月11日〜15日にかけて、GMOインターネットグループの国内パートナーの5,857人を対象に生成AI活用調査を実施したところ、約78%の国内パートナーが業務に生成AIを活用していると回答しました。※3
サポート分野での利用においては、一次対応をAIチャットに置き換えたことで、1ヶ月あたりの対応問い合わせ数を、前年比で1ヶ月あたり189件も削減することに成功しました。その他の分野でも生成AIを活用することで、グループ全体の業務効率向上に成功しました。
事例2.株式会社みずほフィナンシャルグループ
株式会社みずほフィナンシャルグループでは、社会インフラでもある銀行システムに障害が発生した際の復旧対応を効率化するために、日本アイ・ビー・エム株式会社のビジネスに特化したAIおよびデータ・プラットフォームであるIBM watsonxの実証実験を実施。その結果、イベント検知におけるエラーメッセージの監視と対応において98%の精度を実現しました。※4
これにより、熟練のオペレーターでも原因の特定から復旧までにかなりの時間がかかる復旧作業を、watsonxを利用することで、復旧までの最短手順を案内することが可能となり、復旧スピードの向上が期待できる結果となりました。
株式会社みずほフィナンシャルグループでは、対象となるシステムを拡張して検証を進め、最終的には運用の自動化を目指しています。
まとめ:ITインフラ分野に生成AIを活用して業務を効率化

生成AIをITインフラ分野に活用することで、得られるメリットは多いでしょう。しかし、生成AIは新しい技術ということもあり、使いこなせない人が多いのも現状です。
ですが、今後はITインフラ分野に生成AIを活用するのが当たり前という未来が来ることが予想されます。そのため、生成AIを活用している企業とそうでない企業ではさまざまな部分で差がつく可能性もあるでしょう。そのような時代の流れに取り残されないためにも、早めに生成AIを活用することをおすすめします。
新しい技術を導入するためには、活用方法やコストの問題、社員の教育などさまざまな問題に直面するでしょう。しかし、生成AIを活用することで得られる利益やメリットもたくさんあるので、少しでも生成AIに興味があるのであれば、これを機に生成AIの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
参考記事






