今まさに、多くの企業がオンプレミス環境からクラウドへシステムを移行しています。
そんな中、いよいよ自社もクラウドを導入していこうと思った矢先にマルチクラウドという言葉を見つけ、混乱してしまっている方も多いはずです。
ただでさえクラウド上に今まであったインフラを構築していくというだけで理解し難い中、マルチクラウドやハイブリッドクラウドなどの言葉が出てきて翻弄されてしまいますよね。
しかし、マルチクラウドとはそこまで難しいことではなく、システムを構築する上での一つの形であるということを抑えてしまえば怖くはありません。
今回ご紹介する内容は、マルチクラウドとは一体どのようなものなのかをわかりやすくご紹介していきますので、安心してください。
マルチクラウドとは?
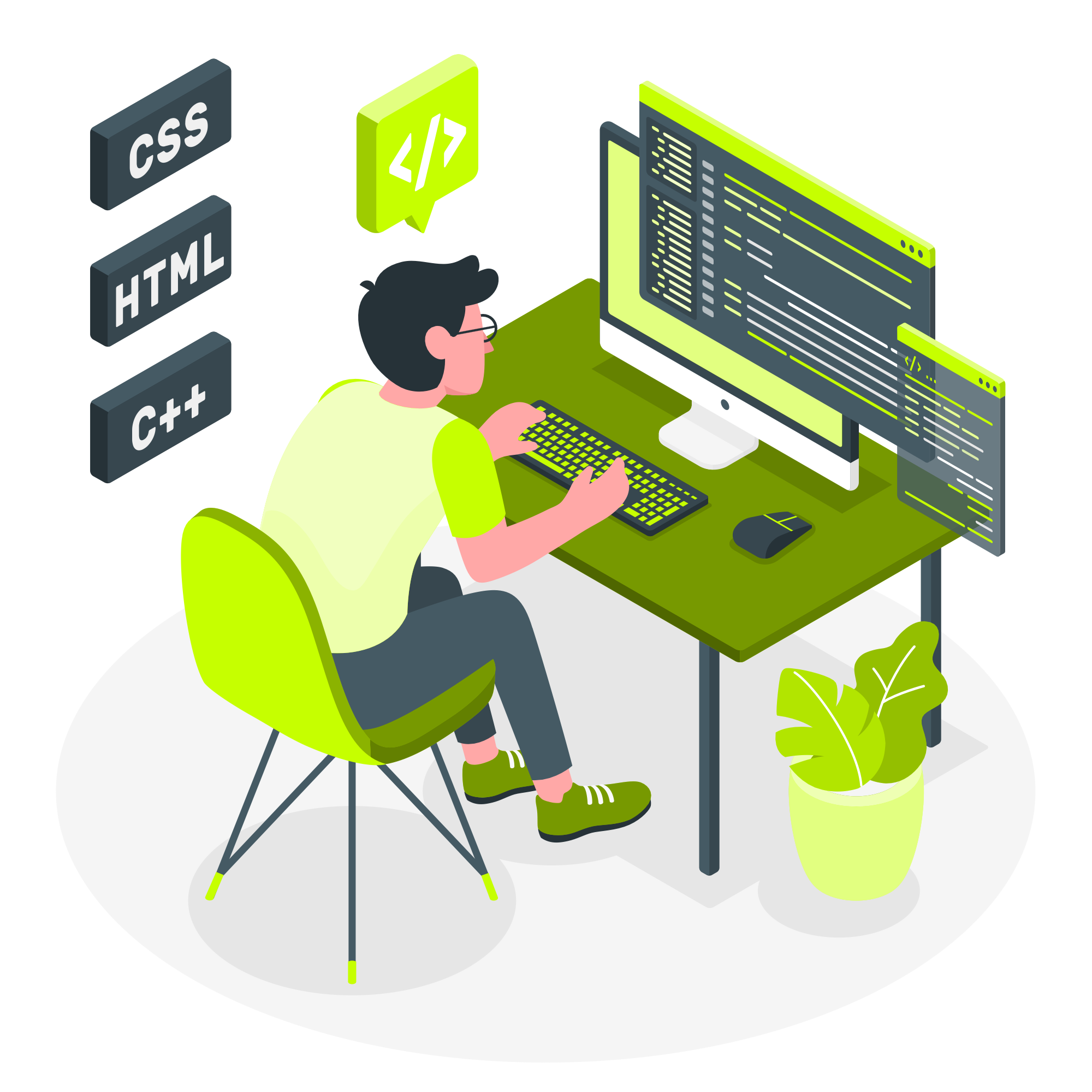
マルチクラウドという言葉をご紹介する上で、「マルチ」という単語が理解できていればきっとマルチクラウドの理解も簡単だと思います。
マルチクラウドを理解し、導入することが業務の効率化を可能にし、さらには現在どの企業も抱えているエンジニア不足を解消していく足がかりにもなるのです。
現在デジタルトランスフォーメーションにより、益々IT産業の業務は増加します。
マルチクラウドを理解し、エンジニア不足の解消に向けた一歩を踏み出しましょう。
マルチクラウドの概要
「マルチ」という単語の意味は「複数の」という意味です。
つまり、複数のクラウド環境を導入するというのが、「マルチクラウド」という言葉の意味です。
複数のクラウドとは、ある一部ではAmazon AWSを使用し、一部ではMicrosoftのAzureを使用するといった感じです。
このように、サービス提供会社が提供しているパブリッククラウドを複数使用することによって可能性の幅を広げるのがマルチクラウドの狙いです。
一見複雑そうに感じるマルチクラウドですが、蓋を開けると複数使用していればマルチクラウドの分類に入るという単純なものなのです。
ハイブリッドクラウドとの違い
マルチクラウドを調べていくと必ずセットで出てくるのがハイブリッドクラウドです。
ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウド以外の環境を組み合わせてできているクラウド環境のことです。
ハイブリッドカーを見ると電気とガソリンのように、二つの動力源で車を動かしているものを意味します。
同じように、ハイブリッドクラウドであればオンプレミス環境や自社で作成したプライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせたものがハイブリッドクラウドとなります。
プライベートクラウドやオンプレミス環境はセキュリティ対策を強固にすることが容易であることが多く、重大な機密情報を守るためにハイブリッドクラウドにするケースもあります。
また、場合によってはハイブリッドクラウドは低コストで運用することができるため、コストを抑えるために使用されることもあります。
このように、全てパブリッククラウドで構築するよりもコストやセキュリティ面で優れている場合に使用されることが多いのです。
マルチクラウド管理のメリット
クラウド環境で構築を行う際に、なぜ複数のクラウド環境を利用して構築を行うか理解し難いかもしれません。
しかし、マルチクラウドには大きなメリットがあるのです。
確かに単一のパブリッククラウドで構築を行うことも多いのですが、マルチクラウドのメリットに適合する場合はマルチクラウドを選択します。
マルチクラウドにはどのようなメリットがあり、どのような場合に利用した方が良いのかをご紹介していきます。
h3:ITチームの負担が軽減される
ITチームの中でも、パブリッククラウドのどれが得意なのかは人によって異なります。
先の例では、AWS経験が長い人が半数、Azure経験が長い人が半数いた場合、どちらの環境で構築しても半数の人は使いにくいまま作業を行うことになります。
そこでシステムを半分に分けてしまい、AWSチームとAzureチームに分けて業務を行うことによって、作業効率は格段に上がります。
1つのプロジェクトで複数のサーバやネットワークを構築するので、人数の割合によって環境を分けることができれば効率が上がり、エンジニアの負担が軽減されるということなのです。
コスト管理が改善される
マルチクラウドで環境構築を行なった後は、当然ですが利用しているパブリッククラウドの各社から請求書が来ます。
そこで割り振っている割合以上に費用が請求された場合、もしかすると構成自体に問題があるのではないかとすぐに気づくことができます。
逆に単一のパブリッククラウドで構成している場合、クラウドを利用したのであればこれくらいの請求なのかと気づかないこともあります。
今はベンダによっては費用と稼働システムを見てコスト削減の提案をしてくれることもありますが、コスト分析が行いやすくなるのはマルチクラウドが圧倒的です。
ベンダロックインを排除できる
ベンダロックインとはプロジェクトを進めてく上で一つのベンダに依存してしまうことを言います。
単一パブリッククラウドで構築を行うと、ベンダロックインが起こる可能性が高く、思わぬトラブルを招きかねません。
Azureを利用していたが利用費が高くなった、複雑化しすぎて利用しにくくなり効率が落ちた、などの問題が出た際に、AWSに移行しようにもエンジニアがいない状態では移行もできません。
マルチクラウドで複数ベンダを利用している場合、どちらにも移行することが可能になるのでリスク回避にもつながるのは大きなメリットです。
マルチクラウド管理の課題4選

マルチクラウドのメリットをご紹介してきましたが、逆に不安要素も存在します。
デメリットを知ることで、マルチクラウドを導入する際には何をしなければならないかという点も見えてくるはずです。
まずはデメリットを洗い出し、その解消のために何を行えば良いのか、メリットと天秤にかけた場合どちらが優位になるのかを検討することによって、導入する際のリスク軽減につなげることができます。
管理の複雑さが増す
単一パブリッククラウドを利用している場合は、管理するのも簡単です。
システムを一覧表示させることができたり、一括設定を行うこともできることもあるので管理が容易ですが、マルチクラウドだとそうはいきません。
利用しているクラウドシステムが複数になればなるほど個別に管理しなければいけなくなり、システム監視に関しても各クラウドを見張らなければならないのです。
単一パブリッククラウドでは一人で監視できても、複数となるとその分だけ監視する人を増やさなければならないのはデメリットですね。
仮に一人で複数を監視できる人がいたとしても、各管理画面から状況を確認しなければならないため、時間はかかってしまいます。
クラウドサービス選定に時間がかかる
現在たくさんのクラウドサービスが展開しているため、どのクラウドサービスが自社に適しているかを選定するのに時間がかか流可能性が高いです。
また、プロジェクトを進めていくにあたって委託や派遣でエンジニアを探している場合、確保にも時間がかかるケースがあります。
運用が始まってしまえば業務の効率化が期待できるかもしれませんが、要件定義の段階で時間が従来よりもかかってしまいます。
どの機能をどのクラウドサービスにするかは、従来の単一パブリッククラウド選定よりも苦労する覚悟を持たなければなりません。
ソフトウェア環境の統合が難しい
単一パブリッククラウドであれば、共通のソフトウェアを使用していることも多いかもしれません。
しかし、マルチクラウドを採用すると、ソフトウェアによってはクラウドが対応していないことがあるため統合することが難しいことがあります。
ソフトウェアの操作に関してはそこまで問題はないかもしれませんが、サポート期間などのEoS管理が難しくなってきます。
管理表の作成やアップデートなどのメンテナンスにずれが生じるなど、業務が増える可能性があります。
現在使用しているソフトウェアが使用するクラウドに対応しているのかなどを事前に調べてみると解決できる事案もあります。
セキュリティ問題などが生じやすい
単一クラウドであればファイアウォールで外部と遮断した環境を構築したり、場合によっては完全に外部からのアクセスを遮断した環境を構築し、極秘資料を取り扱うこともできます。
しかし、マルチクラウドではそれらの極秘資料を一旦外の環境に出してファイルのやり取りを行わなければならないケースがあります。
こうなってしまうと、セキュリティリスクは上がってしまいます。
いくらアクセス制限を引いていたりIP制限をしていたとしても、退職者などのアカウント削除の漏れなどの人為的なミスからセキュリティ問題を引き起こす可能性はあります。
マルチクラウド管理を実現させるまでの流れ

マルチクラウド管理を実際に導入する際に、どのような手順が必要であるかをご紹介していきます。
もしかすると自社に適合するかもしれないと思った際には、一度検討してみて実際に導入するとどんなメリットがあるのかを考えてみることが重要です。
マルチクラウド管理の手順を理解し、導入のシュミレーションを行うことで、リリースまでの期間なども予想することができるので計画的にプロジェクトを進めることができます。
マルチクラウドの利用目的・目標を決める
まず最初に、「なぜマルチクラウドを利用するのか」という点に注目して自社には有益であることを確認しましょう。
マルチクラウドは複数のパブリッククラウドを使用することによるデメリットも存在することをご紹介しましたが、それを超えるメリットがあることを明確にする必要があります。
利用目的がはっきりすることによって、どのようなシステムを構築していくかという点もはっきりしてきます。
逆に見切り発車でプロジェクトを進めてしまうと、余計に時間がかかったり剪定を失敗するなどのリスクも高くなります。
迷った時に立ち戻れるくらい確固とした利用目的・目標を決めましょう。
利用目的・目標に合うクラウドサービスを選定する
利用目的・目標が決まったら、次にクラウドサービスを選定していきます。
クラウドサービスによって得意分野は異なりますので、目的に合ったサービスの選定が必要になります。
単にバックアップを取る場所を分けたいのであれば単一クラウドサービスでリージョンを分ければ解決しますのでマルチクラウドは必要ありませんが、クラウドサービスの障害時にも稼働できるようにするのであれば同じようなサービスを選ぶ必要があります。
システム稼働の利用料やエンジニアの確保など、様々な要因を洗い出すことによってどのサービスが最も適合してるのかが見えてくるはずです。
データの移行計画を立てる
マルチクラウドを稼働させるためには、既存のシステムを移行しなければいけません。
もちろんサービスを止めなければいけないので、メンテナンス日としてシステム停止を周知しなければなりません。
それでも、理論上は移行できたとしても実際に移行するとトラブルがあり移行が失敗することも多々あります。
そのため、他のクラウドサービスへの移行手順の準備や環境構築を行なった後は、検証環境で実際に移行が可能であるのかチェックすることが必要です。
限られた工数の中、さらに移行経験があまりないスタッフで行うことは不安かもしれません。
多くの場合、スポットでビジネスパートナを雇うことで人員を確保することもありますが、現状ではそれすら探しにくい状態です。
その場合、外部に外注として移行を依頼することもありますので、状況によって判断してください。
導入後は必要に応じて見直す
マルチクラウド導入を終えても必ず見直しは必要になります。
いざ運用してみると、予想と違う場面が多々あります。
クラウド環境のリソース不足や、予想外にコストがかかってしまう点などは基本的なことですが、それらを定期的にチューニングしていく必要があります。
システム構築はリリース後にどれだけチューニングできるのかが重要となってきますので、少しずつ理想の形にしていきましょう。
現在はクラウドサービス内でもアドバイザーとして自動で変更の提案をしてくれるものも多いですが、機械的な提案には限界があります。
人の目によってチューニングできる人材育成も必要となることは覚えておきましょう。
マルチクラウド管理のまとめ

現在マルチクラウド管理を採用している企業は増えてきているので、クラウド環境にシステムを置くだけではなく使いこなしてきていることが伺えると思います。
プロジェクトはいかに効率よく業務を進め、いかにリスクとコストを下げるのかが注目されています。
クラウドサービス自体も次々と新しいサービスが出てきており使い勝手が良くなっていますが、得意不得意を正しく理解し、複数のクラウドサービスを使うことが急務となっています。
とはいえ、自社分析には限界があることも多いです。
しっかりとした着眼点を持った第三者に相談すると、業務が劇的に良く変化することもあります。
新規でマルチクラウド管理の導入を検討している方や、現在のマルチクラウド管理に疑問があり、修正していきたいとお考えの方がいらっしゃれば、一度jitera社にご相談ください。
必ず、お力になれるはずです。






