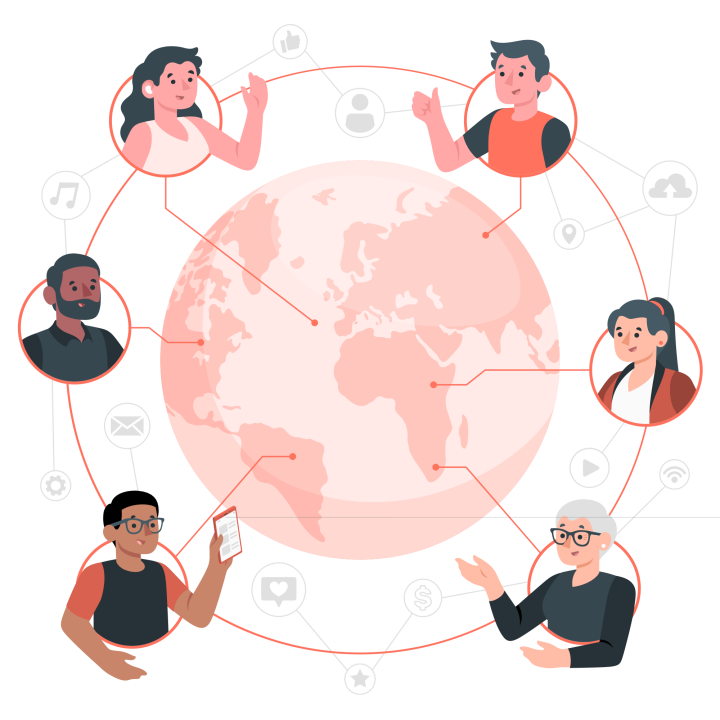ITがビジネスのあり方を大きく変える現在。続々と新しい技術が登場し、世の中の仕組みが大きく変わろうとしています。そして、その裏には必ずITが存在しています。ITをどう活用するかによって、ビジネスの勝敗が決することも当たり前になりました。そして、IT活用の方向性を定めるIT戦略の重要性は高まっています。
戦略には「経営戦略」「財務戦略」など、さまざまな戦略があります。また、ITの分野でも「DX戦略」「デジタル戦略」などがあります。では、IT戦略とは何で、担う役割は何でしょうか?今回は、IT戦略の重要性やメリット、失敗例を参考に、成功のポイントをわかりやすくご紹介します。
コンサルティング業界に20年以上在籍。IT戦略・構想策定など上流系が得意。
IT戦略とは?

IT戦略とは、ITツールを経営戦略の一部として、いかに活用できるかを考えた方針のことです。IT戦略は、効果的なITの導入や活用につながります。「戦略」というと、大企業や政府を相手に、コンサルタントが作るものというイメージがあるかもしれません。また、大規模なITシステム導入が前提というイメージがあるかもしれません。しかし、IT戦略を策定することは、企業規模や導入するシステムの規模に関係なくメリットがあります。
IT戦略の重要性
IT戦略は、企業を取り巻く外部環境や内部環境を分析し、いま取り組むべき経営課題をもとにして策定します。IT戦略は、経営戦略を実現に導くための一部です。効果的なIT戦略は、ビジネスの成功に直結するIT施策につながります。IT戦略なくIT施策を計画・遂行すると、日ごろ目に付く課題ばかりを優先的に着手し、長期的な経営課題の解決に直結しない施策にばかり手を取られてしまうことになりかねません。
IT戦略に取り組むメリット
ビジネスの生産性向上が見込める
IT戦略に基づいてIT施策を推進することは、ビジネスの生産性を向上することが見込めます。IT戦略は、ITツールを経営戦略の一部として活用することを考えます。IT戦略を策定することで、施策によるビジネス上の効果を、事前にシミュレーションすることができます。逆に言えば、ビジネスに効果的でないIT施策を見出し、当面取り組まないといった判断も行えます。IT戦略は、各施策の効果的な優先順位を明らかにします。
BCP対策としても有効
IT戦略に取り組むことは、BCP対策を考えるうえでも有効です。BCPとは、日本語で「事業継続計画」といいます。BCPは自然災害やテロなどの緊急事態に遭遇した時に、損害を最小限に止めつつ、中核となる事業の早期復旧を可能とするために策定する計画です。
ITにおいても、IT戦略を定めておくことにより、何が自社にとってビジネス上で優先順位が高いのかを明確にすることができ、BCPにおける対応優先度の策定にも流用することができます。
ミニマムから開始できる
IT戦略は、必ずしも新しいITツールを導入することを前提としていません。また、大規模なシステム構築をすることも前提ではありません。投資余力の小さな中小企業であっても、すでに使っているITツールを有効活用したり、小規模なITツールの導入から着手することもできます。段階的に進めていくことも可能です。IT戦略は、規模の大小にかかわらず、策定することで効果的なIT施策を推進することを助けます。
IT戦略の手順
IT戦略を作るのは、高度な専門知識を持つコンサルタントだけである、と考えてはいませんか?確かにコンサルタントのサポートは心強いものですが、コンサルタントがいなければできないものでもありません。それよりも大事なのは、自社の置かれている状況を正しく把握し、客観的・論理的に戦略を考えることです。ここからは、IT戦略を策定する手順をご紹介します。
1. ビジョンや目標の決定
IT戦略は一般的に、経営幹部や経営企画などが、IT担当役員とともに策定します。IT戦略は経営戦略の一部ですので、経営戦略が定めるビジョンや目標をもとに、ITツールの活用などを通じて何を実現するのかを策定します。経営戦略とIT戦略には、整合性があることが求められます。経営戦略を成功に導くためのIT戦略として、どのような姿を目指すのか、計画を立てるための指針となるものを作ります。
2. 現状分析・課題の洗い出し
経営戦略を実現するために、ITの観点では何が必要かを分析し、課題の洗い出しを行います。ここでも重要なのが、経営戦略との整合性です。ITツールは、日ごろ運用しているとさまざまな課題が発生します。それらを洗い出しても、日ごろの運用改善には役立つかもしれませんが、経営戦略の実現にはつながらないかもしれません。経営戦略から「1. ビジョンや目標の決定」で導き出した、ITとしてのビジョンや目標に対するギャップを洗い出すことが重要です。
3. 課題の解決策となるIT戦略を立案
「2. 現状分析・課題の洗い出し」で洗い出した課題を解決するために、どのようなITツールで何を実現するかを立案します。たとえば、自社の顧客情報があちこちのExcelファイルに散逸していて、他の部門と共有できていないケースでは、顧客情報管理システムを導入して顧客情報を統合管理することが有効といった具合です。また、市場の動向や、最新の技術トレンドを調査しておくべきでしょう。調査には、専門のコンサルタントの力を借りるのもよいでしょう。
4. 解決策に必要なITシステムの選定・リソース確保(予算、人材、技術)
IT戦略を実現するためのシステムを選定します。選定においては、システムに要求する事項をまとめた「RFP1」を作成し、システムベンダーからの回答を受け付けることが一般的です。RFPを複数の候補ベンダーに提示し、回答結果を比較して、要求事項に最も適合するシステムを選択します。また、システムの開発・導入・運用に必要な予算・人材と、技術リソースを確保します。技術リソースとは、開発ツールなどのITツール、サーバーなどのIT基盤などがあります。
- Request for Proposalの略 ↩︎
5. コストパフォーマンスの検証
ITシステム導入によるコストパフォーマンスを検証します。コストには「イニシャルコスト」と「ランニングコスト」があります。ITシステムの導入による効果と比較し、十分な効果がコストの観点でも得られるかを検証します。
| コスト | 含まれるもの |
| イニシャルコスト | システム開発費用 ソフトウェアライセンス費用 システム導入支援費用 データ移行費用 サーバー購入・設置費用 ネットワーク構築費用 |
| ランニングコスト | サーバー運用保守費用 ソフトウェア運用保守費用・ライセンス費用 |
6. ITシステムの導入・効果検証
ITシステムの導入を行います。システム導入のためのプロジェクトを組成し、機能や品質・コスト・スケジュールの目標を策定したうえで、策定した計画に沿ってプロジェクトを遂行し、ITシステムを稼働します。プロジェクトには、自社の要員だけでなく、システムベンダーや外部コンサルタントなどが加わる場合もあります。システムの稼働後は、一定期間の運用を経て、当初見込んでいた導入効果が達成できているかを検証します。
IT戦略に用いられるツールとは?

IT戦略に用いられるツールとして代表的なものには、業務管理ツール、顧客管理(CRM)ツール、生産管理システムの3つがあります。
| ツール | 利用目的 | 代表的な機能 |
| 業務管理 | 管理業務を効率化する | 会計システム 経費精算システム 人事システム 勤怠システム |
| 顧客管理(CRM) | 顧客情報を一元管理する | 顧客管理システム カスタマーサポートシステム マーケティングオートメーション(MA) |
| 生産管理 | 製品の製造工程を管理する | 生産管理システム 原価管理システム 品質管理システム |
業務管理ツール
業務管理ツールは、人が行うさまざまな管理業務を効率化します。代表的なものに「会計システム」があります。会計システムは、伝票(仕訳)を登録すると、自動的に集計して財務会計・管理会計に必要な数値の集計や、財務諸表などの書類を作成します。
「経費精算システム」は、社員が日々使用する経費を事前・事後に申請し、経費としての出費を認めるシステムです。所定の承認者に承認依頼を行い、承認をするワークフロー機能が備わっていることが多いです。
また、各システムは互いに連携することもあります。例えば経費精算システムは仕訳を会計システムに、勤怠システムは社員の勤怠を集計して人事システムに連携しています。
顧客管理(CRM)ツール
顧客管理ツールはCRM(Customer Relationship Management)ともいい、顧客情報の一元管理により、営業活動や顧客サポート活動を効率化するツールです。たとえば、自社の製品を購入した顧客に対し、サポート部門が適切なタイミングで保守点検の案内を行うなど、社内の複数の部門が連携して顧客にサービスを提供するための情報基盤として利用することができます。
顧客管理の一元管理による効果は、単に業務の効率化だけにとどまらず、顧客満足度の向上にもつながります。マーケティングオートメーションは、顧客情報をセグメントし、新しいサービスの案内などを送付する作業を効率化します。顧客との接点を増やすことで、新たな収益の獲得にもつながります。
生産管理システム
生産管理システムは、製品の生産活動に対して利用するシステムです。どの工場で、どの製品をどれだけ生産するかを計画します。受発注システムなどをもとに需要を予測し、生産ラインの製造能力や在庫の状況を見ながら生産計画を策定します。生産においては原材料などの管理を行いながら生産量を把握し、品質管理を経て完成品を倉庫に保管し、配送の計画に基づいて出荷します。
これらの活動は一連の流れで実施されており、各システムが相互にデータの連携を行いながら進行を管理しています。一連の流れはSCM(Supply Chain Management)ともいい、生産管理システムはSCMを構成するシステムの一種です。
IT戦略を立てるときの注意点は?

IT戦略を立てて施策を推進しても、当初計画したほどの効果が得られないこともあります。IT戦略のよくある失敗例として、以下のようなケースがあります。
- 当初計画していた導入効果が得られなかった
- 当初見込んだコスト・スケジュールを大幅に超過した
- 導入したITツールを社員が使ってくれない
- 導入したITツールが、自社の業務と合わず使いにくい
企業が抱える問題の確認や課題解決が目的である
ITツールは、IT戦略が定義した何らかの目的を達成するために導入されるものです。しかし、ITツールの導入が目的になってしまうケースもみられます。たとえば、業界でデファクトスタンダードとされているシステムの導入により、競合他社に追随しようという活動などがあります。同業の競合先といえども、自社と同じ課題を持っているとは限りません。競合先と同じシステムの導入によって自社の課題が解決できるとは限りません。
また、システム導入が進むと、当初想定していなかったトラブルにより、計画変更を余儀なくされることがあります。そのとき、IT戦略が策定した目的が計画変更の指針となります。
自社の規模や予算に合わせて戦略を策定する
IT戦略を策定するうえでのポイントは、コストパフォーマンスや導入効果を数値で具体化することです。高い性能を持つシステムは、一見便利かもしれませんが、自社には必要のない、余分な機能が多く搭載されているかもしれません。導入したITツールを社員が使ってくれないとか、ITツールが自社の業務に不要な機能が多くて使いにくいと不満が続出するケースは、自社の規模に対して規模が大きすぎるシステムを利用しているかもしれません。
また、ITツールの導入は、必ずしも一度に、一斉に行う必要はありません。段階的な導入も視野に入れつつ、自社の規模や予算に合わせてIT戦略を策定するべきです。
情報セキュリティのリスクが高まるおそれがある
ITツールの導入では、新たな情報セキュリティリスクが発生する可能性があります。ITとセキュリティは切っても切れない関係にあります。システムのセキュリティのみならず、社員に対する継続的なセキュリティ教育も重要です。セキュリティ対策にはハッカーなど、外部からの攻撃に対してだけでなく、内部犯行など、社員に対しての対策も重要です。
また、サイバー攻撃は常に進化しており、対策も常に最新化していかなければなりません。一度きりの実施ではなく、継続的な対策が必要です。ただ、このように注意喚起すると、いっそIT化しなければいいのではと思うかもしれません。しかし、紙の台帳などでは見えなかった”隠れたセキュリティ事故”が、IT化によって見えやすくなったのだと考えるべきでしょう。
IT戦略を成功させるには?

IT戦略を成功させるには、先人の知恵を活用するのが一番です。他社事例を参考にする、フレームワークを活用するなどの方法が考えられます。ここでは、IT戦略を策定するうえで知っておくと便利な情報源やツール、フレームワークなどをご紹介します。コンサルタントを活用するのも1つの方法ではありますが、その際はコンサルタントに丸投げせず、自分たちの意志を吹き込んだIT戦略を協同で策定するべきです。
デジタルトランスフォーメーション銘柄を参考にする
他社のIT戦略の成功事例を参考にするものです。積極的に情報を公開している企業では、自社のIT戦略を自社ホームページなどで紹介しています。公開セミナーで講演したり、システムベンダーの情報発信の中で参考になる情報があるかもしれません。探し方のコツは、自社と共通の課題に取り組んでいる企業を、業種業態にかかわらず幅広く調べることです。
同業の取り組みを調べることも重要ですが、同業からの情報ばかりを参考にしていると、他社と同じITツールを導入しようとか、他社よりも高機能なITツールを導入しようといった思考に陥りがちです。これはまさに、ITツールの導入が目的化してしまっている例です。幅広い情報に触れることで、自社の置かれた状況に近い事例が見つかるかもしれません。
まずはクラウドサービスを利用する
クラウドサービスをまず使おうというのは、手段が目的化していないか?と思うかもしれません。ここでお伝えしたいのは、IT戦略をミニマムで始めたいときに、クラウドサービスの利用を有効な手段として頭に入れておこう、という主旨です。システムを導入するうえで、サーバーを用意することは必須です。しかし、そのサーバーを自社で持とうとすると、保守担当への負荷が高まることを考えなくてはいけません。
現在では、クラウドサービスのセキュリティも高くなり、自社でセキュリティ対策を実施するよりも安価で安全なシステム構築ができるようになっています。サーバーインフラはクラウドでミニマムに用意し、必要に応じて拡張する選択肢も考えましょう。
IT戦略の要点をまとめたロードマップ作成アプリを利用する
IT戦略は経営戦略の一部ですので、経営戦略の策定で用いられるさまざまなフレームワークを活用することができます。ここでは、IT戦略の実現に向けてどのようなロードマップを策定するのかを補助してくれるアプリとして、IT戦略ナビをご紹介します。
IT戦略ナビは「どのようにITを活用したら、ビジネスが成功するか?」を示した”仮説ストーリー”を1枚の絵にまとめた「IT戦略マップ」を作成します。同時にITの導入プランを作成することもできます。IT戦略マップ・プランは、IT戦略を実行する時の”意思統一ルール”、社員の”モチベーションアップツール”として活用することができます。
かつては、こうしたマップは巨大な紙に書き込まれ、オフィスに掲示されていたものです。リモートワークが当たり前となったいま、掲示する場所もオフィスの中からPCやスマホの中に移っていくべきなのでしょう。
AWSクラウド導入フレームワーク(AWS CAF)を利用する
AWS CAFは、初めてAWSを導入する企業向けのフレームワークです。「ビジネス」「人材」「ガバナンス」「プラットフォーム」「セキュリティ」「オペレーション」の6つの分野に対してガイダンスが用意されています。
各々のガイダンスには詳細を記載したホワイトペーパーも用意されています。英文のため読みづらいかもしれませんが、6つの視点に基づいて検討を行う必要があると考えれば、IT戦略を策定するうえでは十分に活用できるのではないでしょうか。
また、AWSは事実上のグローバルスタンダードです。そのためAWS CAFに従って戦略を策定することは、グローバルスタンダードに沿ったIT戦略の策定プロセスに追随しているということが言えるかもしれません。
IT戦略のまとめ

IT戦略は、ITツールを経営戦略の一部として、いかに活用できるかを考えた方針であることをご説明しました。IT戦略は、経営戦略を成功させるために策定するものであり、企業規模の大小にかかわらず有用です。自社の規模や予算に合わせて、ミニマムな施策から開始することも可能です。
また、さまざまなフレームワークがあり、これらを活用することで自社のIT戦略のグランドデザイン、ロードマップの策定をサポートする仕組みが用意されています。しかし、それでも初めてのIT戦略の策定には、不安なところもあるのではないでしょうか?
株式会社Jiteraでは、IT戦略に関するご質問や、案件のご相談に対応しています。実績豊富なJiteraでは、貴社のIT戦略策定における的確なアドバイス、フレームワークの活用などを伴走型でご支援することができます。