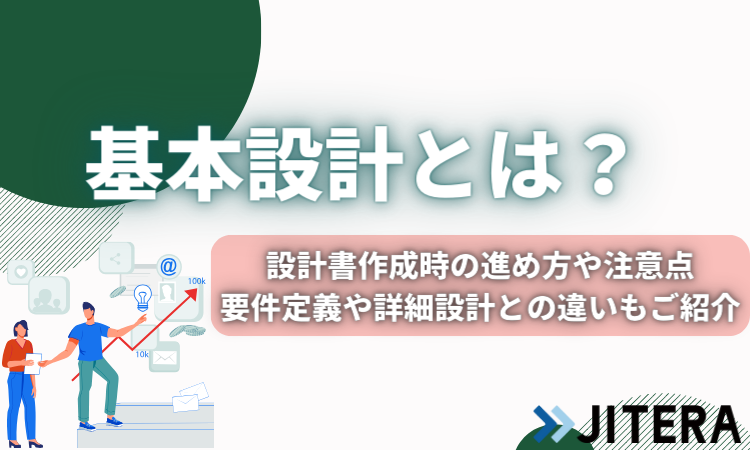詳細設計書は、開発チームが具体的な実装に取り組む際の重要な指針となります。
この記事では、詳細設計書の役割や内容、効果的な書き方について、具体的な例を交えながら解説します。ITシステム開発にかかわる方だけではなく、システム開発会社を経営するマネジメント層にも役立つ情報をまとめました。
小中規模プロジェクトを中心にSEやコンサルとして活動。クラウド導入やスタートアップ、新規事業開拓の支援も経験しました。
詳細設計書とは
 詳細設計書は、システム開発プロジェクトにおいて、基本設計を具体化し、実装レベルまで落とし込んだ設計書です。主にアプリケーションやサーバの内部構造、データの流れ、各機能の詳細な仕様などを記述します。
詳細設計書は、システム開発プロジェクトにおいて、基本設計を具体化し、実装レベルまで落とし込んだ設計書です。主にアプリケーションやサーバの内部構造、データの流れ、各機能の詳細な仕様などを記述します。
開発者が実際にコーディングを行う際の指針となり、システムの品質や保守性を確保する上で重要な役割を果たします。
詳細設計書に含まれるのは以下のような項目です。
- システムの全体構造
- モジュール間の関係
- データベース設計
- 画面遷移
- 処理フローなど
具体的な内容は後ほど紹介します。これらの情報を含むことで開発チーム全体が同じ認識を持ち、効率的に作業を進めることができます。また、将来の保守や機能拡張の際にも、詳細設計書は重要な参考資料となります。
詳細設計書と基本設計書の違い

詳細設計書と基本設計書は、システム開発プロセスにおいて異なる役割を持ちます。以下が、両者の主な違いです。
| 項目 | 基本設計書 | 詳細設計書 |
| 目的 | システムの全体像を定義 | 実装に必要な詳細を定義 |
| 対象読者 | 経営者、プロジェクトマネージャー | 開発者、プログラマー |
| 記述レベル | 概要的、抽象的 | 具体的、技術的 |
| 内容 | システム要件、概略アーキテクチャ | モジュール設計、データ構造、アルゴリズム |
| タイミング | プロジェクト初期段階 | 基本設計の後、実装前 |
基本設計書がシステムの全体像や要件を定義するのに対し、詳細設計書はそれをさらに具体化し、実装レベルまで落とし込みます。
例えば、基本設計書では「ユーザー認証機能を実装する」と記述するのみです。しかし、詳細設計書では認証のアルゴリズムやデータベースの構造、エラーハンドリングの方法など、より詳細な情報を記述します。
詳細設計書が必要な理由

詳細設計書は、システム開発プロジェクトを成功に導くための重要な文書です。その必要性について、以下に具体的な理由を挙げて解説します。
実装方法(内部設計)を具体的に定義するため
詳細設計書は、システムの内部構造や処理の流れを具体的に定義します。
開発者は明確な指針に基づいてコーディングを行うことができ、実装の一貫性や品質を確保できます。
例えば、データベースのテーブル構造やAPIの仕様など、実装に直結する情報を詳細に記述することで、開発者の解釈の違いによるミスを防ぐことができます。
システムの全体構造を明確にするため
詳細設計書には、システムの全体構造やモジュール間の関係が明記されます。
開発チームはシステムの全体像を把握しながら、各部分の開発を進めることができます。
例えば、マイクロサービスアーキテクチャを採用する場合、各サービスの役割や連携方法を明確に定義することで、整合性のとれた開発が可能になります。
保守性を向上させるため
詳細設計書は、将来の保守や機能拡張の際にも重要です。
システムの内部構造や処理の流れが詳細に記述されているからです。後から開発に参加した人員や保守担当者が素早くシステムを理解し、効率的に作業を行うことができます。
例えば、バグ修正や新機能追加の際に、関連するモジュールやデータの流れを簡単に特定できます。
開発者間の共通認識のため
詳細設計書は、開発チーム全体で共有される文書です。
チームメンバー全員が同じ認識を持って開発を進めることができ、コミュニケーションでの混乱を防ぐことができます。
例えば、フロントエンド開発者とバックエンド開発者が、APIの仕様や画面遷移について共通の理解を持つことで、スムーズな連携が可能になります。
詳細設計書の主な内容

詳細設計書には、システムの実装に必要な様々な情報が含まれます。ここでは、一般的な詳細設計書に含まれる主な項目について解説します。
システム概要
システム全体の目的や機能、主要なコンポーネントについて簡潔に説明します。基本設計書の内容をベースに、より具体的な情報を追加します。
例えば、使用する技術スタックやシステムの全体アーキテクチャ図などを含めることで、開発者がシステムの全体像を把握しやすくなります。
アーキテクチャ設計
システムの全体構造やコンポーネント間の関係を詳細に記載します。使用するフレームワークやライブラリ、サーバ構成、ネットワーク構成などの情報も含めます。
例えば、マイクロサービスアーキテクチャを採用する場合、各サービスの役割や連携方法、データの流れなどを図示して説明します。
モジュール設計
システムを構成する各モジュールの詳細な設計を記載します。モジュールの責務、主要なクラスやメソッド、データ構造などを定義します。
例えば、ユーザー認証モジュールの場合、認証アルゴリズムやセッション管理の方法、エラーハンドリングの仕様などです。
データベース設計
システムで使用するデータベースの詳細な設計を記載します。テーブル定義、リレーションシップ、インデックス、制約条件などを含めます。
例えば、ECサイトの場合、ユーザーテーブル、商品テーブル、注文テーブルなどの構造や関連性を図示し、各フィールドの型や制約です。
インターフェース設計
システム内部や外部システムとのインターフェースを定義します。API仕様、データフォーマット、通信プロトコルなどです。
例えば、RESTful APIを使用する場合、各エンドポイントのURIやHTTPメソッド、リクエスト・レスポンスの形式、認証方法などを明確に定義します。
テスト設計
システムの品質を確保するためのテスト計画を記載します。具体的には単体テスト、統合テスト、システムテストなどの方針や具体的なテストケースを定義することです。
例えば、ユーザー登録機能のテストケースとして、正常系や異常系のシナリオ、入力値、期待される結果などを詳細に記述します。
詳細設計書でよく使われる図表

詳細設計書では、システムの構造や動作を視覚的に表現するために、様々な図表が使用されます。ここでは、UML(Unified Modeling Language)を中心に、よく使われる図表について解説します。
UMLとは
UMLは、ソフトウェアシステムを視覚的にモデリングするための標準化された図法です。
システムの構造や振る舞いを様々な視点から表現することができ、開発者間のコミュニケーションツールとして広く使用されています。
UMLには複数の図が定義されていますが、詳細設計書でよく使用されるものをいくつか紹介します。
クラス図
クラス図は、システムのクラス構造を表現する図です。クラス名、属性、メソッド、クラス間の関係(継承、関連、集約など)を図示します。
例えば、ECサイトのユーザー管理システムでは、「User」「Address」「Order」などのクラスとその関係を表現します。
コンポーネント図
コンポーネント図は、システムを構成する主要なコンポーネントとその関係を表現する図です。各コンポーネントの役割や依存関係を視覚化することで、システムの全体構造を把握しやすくなります。
例えば、Webアプリケーションの場合、「フロントエンド」「バックエンド」「データベース」などのコンポーネントとその連携を図示します。
画面遷移図
画面遷移図は、ユーザーインターフェースの画面遷移を表します。各画面と画面間の遷移条件や方向を図示することで、システムの操作フローが理解しやすくなります。
例えば、ログイン画面からマイページへの遷移、商品一覧から商品詳細への遷移などです。
状態遷移図
状態遷移図は、システムや特定のオブジェクトの状態変化を表します。各状態とその間の遷移条件、遷移時のアクションを図示することで、システムの動的な振る舞いを理解しやすくなります。
例えば、注文プロセスにおける「カート」「注文確認」「支払い完了」などの状態遷移です。
シーケンス図
シーケンス図は、オブジェクト間の相互作用を時系列で表現します。メッセージのやり取りや処理の流れを視覚化することで、システムの動的な振る舞いを理解しやすくなります。
例えば、ユーザー認証プロセスにおける「クライアント」「認証サーバ」「データベース」間の相互作用を表現します。
論理ER図
論理ER図は、データベースの論理的な構造を表します。エンティティ(テーブル)、属性(カラム)、エンティティ間の関係を図示することで、データモデルを理解しやすくなります。
例えば、ECサイトのデータベースでは、「ユーザー」「商品」「注文」などのエンティティなどです。
詳細設計書の書き方のポイント

効果的な詳細設計書を作成するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。ここでは、詳細設計書を書く際の重要なポイントについて解説します。
明確でわかりやすい記述をする
詳細設計書は、開発者が直接参照する文書です。そのため、曖昧な表現や専門用語を使いすぎず、誰が読んでも理解できる明確な記述を心がけましょう。
例えば、「適切に処理する」ではなく「エラーログを出力し、ユーザーにエラーメッセージを表示する」というように具体的に記述します。
また、必要に応じて図表や例を用いて説明を補足すると、より理解しやすくなります。
一貫性を保つ
詳細設計書全体で用語や表記方法、図表のスタイルなどの一貫性を保つことが重要です。読み手の混乱を防ぎ、ドキュメント全体の品質が向上します。
例えば、「ユーザー」と「ユーザ」が混在しているような表記ゆれを避け、統一した表現を使用します。また、図表のフォーマットや色使いなども統一し、視覚的な一貫性にも気を付けましょう。
網羅的に記述する
詳細設計書は、システムの実装に必要なすべての情報を網羅しなければなりません。主要な機能だけでなく、エラー処理やエッジケースなども漏れなく記述しましょう。
例えば、ユーザー登録機能を設計する場合を見てみましょう。この場合、正常に登録できるケースだけでなく、既存ユーザーとの重複や入力値のバリデーションエラーなどの異常系も含めて記述します。
また、セキュリティ対策やパフォーマンス要件なども忘れずに記載することで、実装段階での問題を最小限に抑えることができます。
【図解サンプル】詳細設計書の例

詳細設計書の具体的なイメージを掴むために、サンプルプロジェクトを例に解説します。ここでは、シンプルなタスク管理Webアプリケーションの詳細設計書を想定して説明します。
サンプルプロジェクトの概要
ここでは、タスク管理Webアプリケーションを例してサンプルを提示します。
タスク管理Webアプリケーションとは、個人やチームがタスクを管理できるツールです。ユーザーはタスクの作成、編集、削除、進捗管理ができ、チームメンバーとタスクを共有することもできます。
主な機能として、ユーザー認証、タスクCRUD操作、タスク一覧表示、タスク検索、チーム管理などを付けることにしましょう。
サンプルの設計書構成

この記事での詳細設計書のサンプルは、以下のような構成で作成します。
| 項目 | 具体内容 |
| システム概要 | プロジェクトの目的と主要機能 全体アーキテクチャ図 |
| アーキテクチャ設計 | 使用技術スタック システムコンポーネント図 |
| データベース設計 | ER図 テーブル定義 |
| API設計 | RESTful APIエンドポイント一覧 リクエスト・レスポンス形式の詳細 |
| 画面設計 | 画面一覧と画面遷移図 各画面のワイヤーフレームと主要コンポーネント |
| セキュリティ設計 | 認証・認可方式 データ暗号化方針 |
| テスト計画 | 単体テスト、統合テスト、E2Eテストの方針 主要機能のテストケース |
各セクションでは、必要に応じて図表を用いて視覚的に情報を表現しましょう。開発者はシステムの構造や動作を具体的にイメージしながら実装を進めることができます。
では、タスク管理Webアプリケーションのサンプル例を紹介します。実際は図や表を交えながらより詳細に記載する必要がありますので、イメージとして捉えて頂けたらと思います。
システム概要
目的:個人やチームが効率的にタスクを管理するWebアプリケーション
主要機能:ユーザー認証、タスクCRUD、タスク一覧・検索、チーム管理
アーキテクチャ
フロントエンド:React
バックエンド:Node.js, Express
データベース:PostgreSQL
認証:JWT
データベース設計
データベース設計ではER図を使用してテーブル間の関係を示すことが多いです。
Users テーブル
Tasks テーブル
API設計
API設計ではエンドポイントごとの詳細な仕様を表形式で記述するとよいでしょう。
POST /api/auth/register
- 機能:新規ユーザー登録
- リクエスト:{ username, email, password }
- レスポンス:{ id, username, email, token }
GET /api/tasks
機能:ユーザーのタスク一覧取得
ヘッダ:Authorization: Bearer <token>
レスポンス:{ tasks: [{ id, title, status, due_date }] }
画面設計
- ログイン画面
- タスク一覧画面
- タスク詳細・編集画面
- チーム管理画面
セキュリティ設計
- パスワードのハッシュ化
- JWTによる認証
- 入力値のバリデーション
テスト計画
- 単体テスト:各コンポーネントとAPI関数
- 統合テスト:フロントエンドとバックエンドの連携
- E2Eテスト:ユーザーシナリオに基づくテスト
各項目は詳細をしっかり記載することで、開発中の混乱を防ぎます。上記のサンプルを例にし、チームのスキルや理解力に合わせた詳細設計書を作成しましょう。
まとめ:詳細設計書は開発の成功を左右する重要な文書

詳細設計書は、システム開発プロジェクトの成否を左右する重要な文書です。
適切に作成された詳細設計書は、開発チームに明確な指針を提供し、品質の高いシステムを効率的に構築することを可能にします。
解説したポイントを押さえ、プロジェクトの特性に合わせた詳細設計書を作成することで、開発プロセスを大きく改善できるでしょう。
近年、AIを活用した開発支援ツールの進化により、詳細設計書の作成や管理がより効率的になっています。AI技術の導入に関心をお持ちの方は、ぜひ株式会社Jiteraに相談してみてください。
効率よく開発ができる、AIを活用したシステム開発ツールJiteraも取り扱っています。