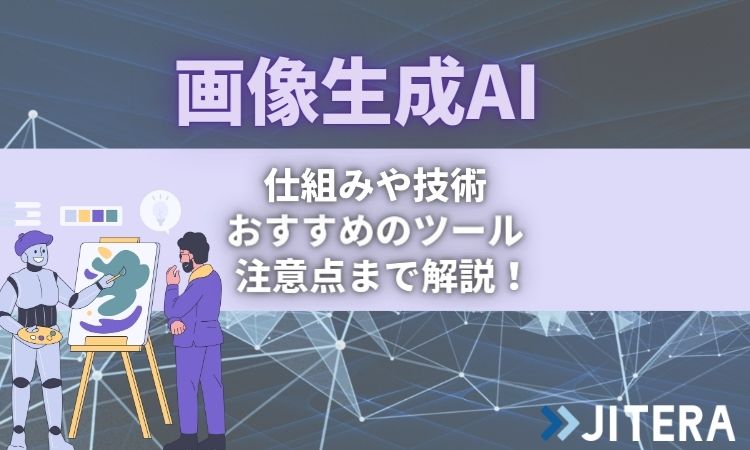もしもスケッチブックに書いたアイデアがそのまま実装できたなら?
Uizardはデンマークの企業が開発したUI設計ツール。
「誰にでもカンタンにデザインを」をコンセプトに開発されたユーザビリティが特徴のサービスです。
魔法使いをあらわす「Wizard」をもとに、魔法のようなUI設計になぞらえて「Uizard」としています。読み方はそのまま「ウィザード」
UIデザインに精通していなくても、プログラミングができなくても、簡単にアプリやウェブサイトのユーザーインターフェースを作成できます。
生成されたデザインはHTML/CSSやjavascriptといったフロントエンドのコードにも自動変換されるため、0から1の開発に効果を発揮します。
アイデアとイメージさえあれば、よりダイレクトで理想的なアプリ・サービス開発を支援してくれることでしょう。
本記事では、Uizardの使い方や登録方法、料金設定、利用できる機能などをご紹介していきます。
ぜひ最後まで読んで、新規アプリ・サービス開発に役立ててみて下さい。
システムエンジニア(SE)、プログラマー、ウェブサイト作成業務、ネットワークエンジニアなどを経験。 現在、フリーマルチライターとして活動中。最近はAI活用方面に没頭中。
Uizardとは?

Uizardは、人工知能を搭載したアプリケーションおよびウェブサイトのUIデザインツールです。
デザイナーでなくてもプログラミング知識がなくても、このツールを使えば誰でも簡単にUIデザインを作成できます。
「Magic」という、名前の通り魔法のようなAI生成機能がUI設計を強力にサポートします。
たとえば、手書きのスケッチから自動でデザインを生成し、作成したデザインからフロントエンドコードの自動生成まで、直感的なUI操作のみで実現することができます。
スケッチが苦手であれば、文章プロンプトによるイメージの指定だけで、洗礼されたデザインを提案してくれたりと、ビジネスアイデアのスタートアップを円滑に推し進めてくれます。
「デザインができないから」「コードが書けないから」といったボトルネックになりがちな部分を幅広くカバーしてくれるでしょう。
もちろんシンプルなUIデザイン設計機能も実装されていて、AI生成+UIでの微調整といったように、デザイナーとしての経験やプログラマーの実践的な知識も十分に活かせるサービスになっています。
Uizardの特徴

Uizardには生成AIを活用した様々な機能が備わっています。主な特徴をいくつかご紹介します。
- 手書きのスケッチをデザインに自動変換
- 作成したデザインから自動でフロントエンドのコードを生成
- チーム内での共有や協調作業ができる
- 多機能:色の調節からレイアウトの微調整
- テンプレートが豊富
それぞれ解説していきましょう。
手書きのスケッチをデザインに自動変換
Uizardでは手書きのスケッチからデザインを自動生成できます。スケッチを撮影またはアップロードされたデータを元にUIデザインを作り出し、編集可能な状態まで整えてくれます。
なので、完全にデザインの知識がなくても、思いつきのアイデアを簡単に形にできます。
推奨されるスケッチの形式はありますが、とてもシンプルです。
ペイントツールを開き、適当に直線や斜線、インプットボックスやよく見かけるアイコンを盛り込めば、それだけでアプリのインターフェースが完成します。
提示された画面をそれぞれリンクでつないでいけば、あっという間に画面遷移まで想定したモックアップが完成します。
著者もサンプルを作ってみましたので記事の後半にご紹介します。
作成したデザインから自動でフロントエンドのコードを生成
Uizardで作成したデザインは自動的にフロントエンドのコード(HTML/CSS/JavaScript)に変換されます。つまり、一から開発者が手作業でコーディングする必要がなく、時間とコストを大幅に削減できます。
手描きのスケッチをスキャンし、画面遷移まで想定したモックアップがあれば、コードの実装はほとんどいりません。
各画面のアイコンと生成された画面を繋ぐだけで、リンクが自動的に生成されますし、動的なアクション(ページ遷移するときの装飾や動き)もテンプレートから指定するだけで実際に動作する生成物が出力されます。
チーム内での共有や協調作業ができる
Uizardはクラウド上のツールなので、同じプロジェクトにチーム内の複数人がアクセスし、デザインの変更やコメントのやり取りができます。リモートチームでも円滑な協調作業が可能です。
Uizardでプロジェクトを共有すれば、Slackやchatworkのように共同のワークスペースで作業できます。
「こんなデザイン考えたんだけど、どうかな」とスマホで写真を取ってアップロードすれば、忠実なUIを生成してくれる。
しかもコーディングも並列で行われるので、迅速で、視覚的にもわかりやすく情報共有ができます。
多機能:色の調節からレイアウトの微調整
Uizardには多様な機能が備わっています。主なものとしては、色の調節、レイアウトの微調整、アニメーションの追加、リスポンシブデザインへの対応などがあげられます。もちろん細かな部分まで調整可能ですし、知識があれば自身でコードの追加も可能です。
「Magic」の機能である「AutoDesigner」を使うことで、レイアウトの雰囲気やベースカラーを指定して全画面を一気に作り上げることもできます。
例えば、「暗めの青を軸にしたシックなイメージ」や「黄色やオレンジをベースにした明るく華やかなイメージ」のように抽象的な概念を指定することで、フォント、カラー、デザインなどイメージに合致したUIが生成されます。
これらはプロンプトで指定もできますし、テンプレートからも選べます。1分ほどで気軽にモックアップを生成していけるのが強みです。
もちろん、生成後もそのままUizard上で微調整が可能ですので、理想的なデザインに近づいていくことでしょう。
テンプレートが豊富
Uizardにはさまざまなカテゴリーのデザインテンプレートが用意されており、ロゴ作成やランディングページ、eコマースサイトなど、目的に合わせてテンプレートを選んで利用できます。
このテンプレート機能が強力で、ほとんどのアプリで頻出するヘッダーメニューや、入力フォーム、検索機能などのフォーマットが揃っています。
しかも内部的な機能が実装されている状態です。
設計者は出来上がった画面をパズルのように組み合わせるだけで、WebページやアプリケーションのUIを完成させることができます。
生成AIで原型を作成→生成した原型にさらに生成AIでコンテンツを加えてモックアップを洗礼させていくことで、よりオリジナリティあるUI設計が実現できるしょう。
Uizardの料金プラン

Uizardには無料プランと有料含めて3種類のプランが用意されています。
無料プランでも制限はあるもののほとんどの機能が使え、有料プランだとそれらの制限を撤廃して利用することが可能です。
ただし、無料プランはプロジェクト数制限が厳しいため、試験的にテストをしてみる場合でも後述する「UizardPro」プランで触ってみることをオススメします。
筆者の場合、「Magic」による「スケッチからUI実装する自動生成機能」を試しただけで無料プランの限度機能を使い切ってしまいました。
Uizard Free(無料)
無料プランでは最大2つのプロジェクトを作成でき、400のコンポーネントまでが利用可能です。
機能面を体感するだけであれば、まずはこちらのプランから使ってみましょう。登録が完了すれば自動的に無料プラン開始となります。
コンポーネントとは、例えば画面内に生成されたパーツの数などに応じてカウントされるもので、テキストボックス配置で1コンポーネント消費、といったように増えていきます。
たとえば入力フォームの数が想定より増えたり、複雑なコード実装が要求される場合、その分だけコンポーネントがカウントされます。特に生成AI系の機能はコストが高めとなっています。
「magic」の機能を十分に体感した場合は、無料プラン以外の選択肢も考慮にいれる必要があるでしょう。
| 料金 | 無料 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
Uizard Pro(月額$12.00)
月々12ドルのUizard Proプランだと、最大100プロジェクトまで作成でき、コンポーネント数も気にする必要はなくなります。
そして全てのテンプレートが開放されるため、機能面での制限はなくなっています。
無料プランと比べ作成できるプロジェクト数が圧倒的なので、個人利用であってもProプランをオススメしています。
| 料金 | 月額$12.00 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
Uizard Enterprise(月額$39.00)
Enterprise プランでは全ての機能が無制限で利用可能です。
Pro以下のプランであったプロジェクト数上限やメンバー数上限もありません。全て無制限での利用が可能です。
さらに、専任の顧客サポートチームが24時間体制で質問に対応してくれます。
優先的に対応窓口がある点から、プロジェクトに関わる人数が多い大型企業向けのプランとなっています。
| 料金 | 月額$39.00 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
個人利用であれば「Uizard Pro」プランが十分に活用できるでしょう。
Uizardの無料アカウント作成手順

Uizardを実際に使ってみるには、まずアカウントを作成する必要があります。
スマートフォンからも登録可能ですが、本記事ではパソコンのブラウザーー上からの登録を前提として説明を進めます。
「magic」を含めた生成AI系の機能をフルに活かすためにも、可能限りパソコンからの操作が望ましいでしょう。
無料プランからでも始められるので、手順をご紹介します。
公式サイトにアクセス

Uizardの公式サイトにアクセスします。
ブラウザー上でのサービスのため、環境構築に時間やコストをかけずに済むメリットがあります。
トップページの右上にある「Sign up for free」ボタンが目印です。
そちらをクリックしてアカウント作成の画面に移りましょう。
Sign up for freeをタップ

トップページ右上の「Sign up for free」ボタンをクリックすると、新規登録のページに移動します。
メールアドレス登録、googleアカウントもしくはMicroSoftアカウントによるサインアップが可能です。
とくにこだわりがなければ、googleアカウントでの登録が手軽でしょう。
その場合、次の「サインアップ」以降の手順は必要なく、公式サイトにアクセスするだけで自動的にログイン状態となります。
サインアップ

新規登録ページで必要情報(メールアドレス、パスワードなど)を入力し、規約に同意して「Create Account」ボタンを押せば登録完了です。
登録が完了するとログイン画面に移動します。
メールアドレスとパスワードを入力してサインインすれば、Uizardの無料版を使えるようになります。
Googleアカウントを利用した場合は、ログイン画面を飛ばしてそのままメイン画面に移ります。
完了

無事ログインが完了しいくつかのカンタンな質問(どんなアプリを作成したいか、個人利用か、法人利用かなど)に答えていくと、上記のような画面に推移します。
著者の場合は「モバイルアプリのUI・UX開発」を選んだところ、初期設定として上記のスマートフォン画面風のテンプレートが表示されました。
ただし、ここの質問に答えきってしまうとプロジェクト数を1消費されて上記の画面が作られますので、ご注意下さい。
無料プランを十分に活用する場合は、質問をスキップしてプロジェクトの新規作成から開始するのが望ましいでしょう。
UizardのAIを使った機能:Magic

Uizardが誇る最大の特徴は、UIデザインの様々な場面で活躍する人工知能機能「Magic」です。
これら機能群は、デザインに関する作業を効率化し、生産性を飛躍的に高めてくれます。
手書きのスケッチやアイデアの段階から、Magic が人工知能を駆使して理想のデザインを生み出してくれます。
下記の機能の一部をご紹介します。
- Scan Wireframe Sketch:スケッチからコンテンツ生成
- Wireframe Mode:テンプレートからコンテンツ生成
- Scan Screenshot:WEB画面からコンテンツ生成
- Smart Themes:最適なテーマ生成
- Attention Heatmap:ユーザーが画面のどこに注目するかを視覚的に表示
- Text Assistant:テキストの自動修正・生成
- Image Assistant:イメージの自動修正・生成
- Autodesigner:入力プロンプトから、網羅的にコンテンツ生成
単に生成だけでなく、ユーザーの視線の行く先を予測したり、調和の取れたカラーパレットやレイアウトを提案したりと、デザインの質を高める最適化機能も備えています。
Magicによって、発想から実装、完成に至るまでの一連のデザインプロセスを、包括的にサポートをしてくれます。
それぞれ詳しく紹介していきましょう。
Scan Wireframe Sketch

Scan Wireframe Sketchは、手書きのスケッチからUIデザインを自動生成する機能です。
スケッチを撮影またはアップロードするだけで、瞬時にデザインが作られます。
デザインされた画面に上記画像のような直感的なリンクを生成すると、既に一つのWebページとして機能します。
画面下部に存在する「ホームアイコン」や「プロフィールアイコン」も、元々はスケッチブックに手書きをしたものです。
ですが、しっかりアイコンとして認識し、読み取ってくれています。
他にもXやInstagramなどのアイコンも模倣してくれるようです。
SNS連携が欠かせないアプリ開発にはもってこいでしょう。
ただし、読み取っただけでリンクまで生成してくれるわけではないのでご注意を。
Wireframe Mode

WireFrame Modeは、シンプルなワイヤーフレーム スタイルのUIを自動生成する機能です。
コンテンツの配置を意識した基本的な枠組みが仕上げられます。
上記の画面は「ブラウザー上でのログイン画面」とだけ指定を与えたところ、20秒ほどで作成されました。
よくウェブ上で見かけるシンプルな設計ですが、短時間でこれだけのHTML/CSSコードが作成されたことには驚きです。
テキストプロンプト指定のほかにも、Uizardからのオススメに従ってテンプレートを構築する方法もあります。
Scan Screenshot

Scan ScreenshotはスクリーンショットからUIデザインを生成する機能です。参考にしたいサイトやアプリの画面をキャプチャすれば、それに近いデザインを作れます。
先程のWireFrame Modeで生成したログイン画面を参照に、プロンプトから「ユーザー一覧、コンテンツ、タグを表示する画面」と指定したところ、上記画像のようにコンセプトをそのままにデザインしてくれました。
「magic」内の機能を用いて生成した画面を、さらに「magic」で洗礼させていくといった使い方がUI開発において大幅な時間短縮につながりそうです。
ただし無料版ではAI生成回数に制限があるので、機能を十分に活かす場合は課金の検討が必要です。
おおよそ5回ほど生成したところ「引き続き利用する場合、UizardProへのアップグレードが必要」といった旨のメッセージが表示されました。
Smart Themes

Smart Themesは、あらかじめ設定されたテーマに基づいて、魅力的でモダンなデザインを自動生成する機能です。
適切なカラーパレットやタイポグラフィ、レイアウトなどが適用されます。
Scan Screenshot機能で生成したコンテンツを元に、プロンプトで「暗め(dark)」を指定しましたところ上記の画面が生成されました。
今回はカラーベースのみの指定でしたが「モダン」や「ファンシー」、「クール」など抽象的な指示も与えられるので、試行錯誤にはもってこいでしょう。
ただし、こちらの機能も無料プランでは制限があるようです。
Attention Heatmap

Attention Heatmapは、ユーザーの注視度合いを視覚的に把握できる機能です。
デザインのどの部分がユーザーの目を引くか分析し、改善のヒントが得られます。
今回はコンテンツ数の少ないサイト例ですのであまり代わり映えはしませんが、画面内に情報が敷き詰められるコンテンツ(ブラウザーゲームやキュレーションサイト)などであれば有効活用ができるでしょう。。
タイポグラフィによる強弱のバランスをチェックするときや、文字の大きさを変えたり、縦書き横書きなどを混在させたりする場合などにも有効活用できそうです。
Text Assistant

Text Assistantは、UIデザインに則ったテキストに自動補正してくれる機能です。
はじめAIのみですと、判別不可能な文字列が生成される場合があり、手動での修正が必須ではないかと感じました。
しかし、この機能を使うことで、コンテンツ内のテキストメッセージが自然な文脈になるよう訂正してくれるのです。
対象のテキストを選び直上のツールバーに表示されている「Suggest」を押下すると、直ちに修正候補が表示されます。
こちらも無料版では機能制限があり、1プロジェクトに対して5回までのようです。
英語が苦手なユーザーにとっても、ありがたい修正機能となっています。
Image Assistant
![]()
Image Assistantは、コンテンツ内にある画像からカラーパレットやスタイル、レイアウトを分析し、よりテーマに基づいたデザインを生成する機能です。
今回作成したモックアップで、左上のロゴアイコンを変更することにしました。
こちらにImage Assistantを使用したところ、見慣れたSNSのアイコンが候補にあがりました。
あとは気に入ったイメージを選択するだけで該当の画像に置き換わります。
このようにコンテンツに対して、最適な提案をしてくれています。
他にも自動生成されたイラスト(海)を再生成すると様々なバリエーション(海+灯台、海+アシカなど)を提供してくれました。
Autodesigner

Autodesignerは、与えられた条件に基づいて最適なデザインを自動生成する機能です。
現在BETA版ではありますが、Uizardの最も強力な機能でしょう。
ここまで紹介した「magic」機能郡のほぼすべてを実行し、0→1のコンテンツ生成を実行してくれます。
プロンプトとテーマを指定すると、プロジェクトを新規に作成し自動的に生成したものを配置します。
こちら仕様上、無料プランで使うことが難しいため、ほぼUizardPro以上限定の機能といえるでしょう。
ここまでの機能に魅力を感じましたら、ぜひUizardProプランを検討してみてください。
Uizardのまとめ

以上、Uizardの使い方や登録方法、料金設定、利用できる機能を解説してきました。
Uizardは生産性の高いUIデザインツールであり、AIによる優れた支援を行ってくれます。
UIデザインの知識やスキルがなくても、誰でも手軽にウェブやアプリのインターフェースを作成できるのが最大の魅力です。
Uizard社が掲げている「デザインの民主化」をカタチにしたサービスでもあります。
個人事業主の方や小規模開発において、効率的なシステム開発を行いたいがデザインリソースが不足しているクライアントやユーザーにこそオススメでしょう。
特に、Uizardコンテンツ内で生成したものをさらに生成AIにかけていくといった使い方が革新的で、こちら一本でも十分に生産性を高められるように感じます。
無料プランからでも機能の一部が使えるので、ひとまず登録して実際に触れてみることをおすすめします。
生産性の向上を肌で感じることができるでしょう。
当社Jiteraでは、要件定義を書くだけでAIが生成するツールにて、アプリ・システム開発を積極的に行っています。
小さなスタートからビジネスを確実に前に進めるアプリ開発やシステム開発をサポートさせて頂いております。
IT案件やアプリ・システム開発依頼、そのほかにもご相談やご質問がありましたら、Jiteraまでお気軽にお問い合わせください。
AIの最新動向を踏まえた最適なソリューションをご提案いたします。