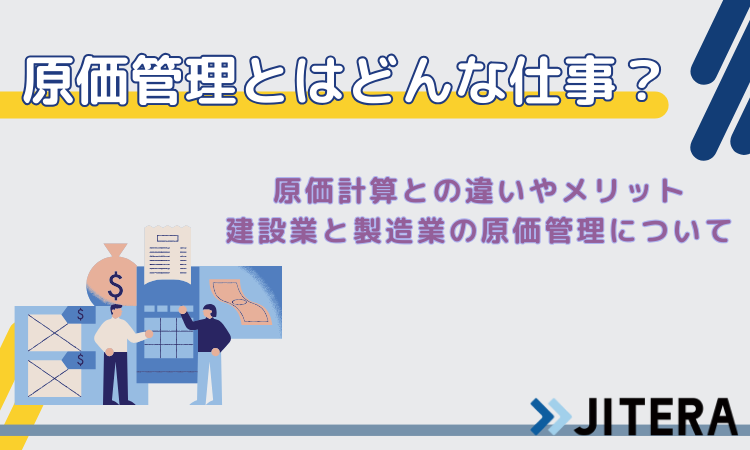原価管理とは、商品を製造する上で必要な管理項目です。
しかし、主にどんな作業を行う必要があるのか把握できていない人も多いでしょう。また原価管理と似た「原価計算」という言葉も存在します。
そこで、本記事では原価管理とはどのような仕事なのか、原価計算との違いやメリットなどを解説していきます。
建設業と製造業の原価管理についても触れていくので、ぜひ参考にしてください。
近畿大学理工学部生命科学科を卒業後、独学でReactやNext.jsを中心としたフロントエンド開発に特化し、2022年10月よりフリーランスエンジニアとして活動。ヨーロッパや東南アジアを旅しながら、いろんな文化や人との出会いを楽しみつつ、クリエイティブなUI/UX設計に取り組んでいます。
原価とは?基本知識

原価とは、商品やサービスを提供する際に発生するさまざまな費用のことを指します。一般的には材料費として認識されがちですが、実際にはオフィスの家賃、人件費、外注費など、多岐にわたるコストが含まれます。
原価の要素
原価の要素は「原価要素」と呼ばれます。原価要素を把握したうえで適切に管理されなければ、多くの商品を販売しても期待される利益を得ることは困難です。
原価を構成する要素はいくつかあり、一般的に以下のように分類されています。
| 分類 | 内容 |
| 発生形態 | 材料費、労務費、経費 |
| 製品との関わり度合い | 直接費、間接費 |
| 生産量(操業度)との関係 | 変動費、固定費 |
原価管理とは、これら多岐にわたる製品やサービスの提供に伴って発生するコストを正確に把握し、効果的に管理することにより、利益率の改善や賢明な経営判断を支援する業務です。
「コストマネジメント」とも呼ばれるこの業務は、単にコストを記録するだけでなく、それを比較・分析し、企業の利益を最大化するための重要な戦略的役割を担っています。
各費用を構成する要素を分解し、各原価要素にアプローチした対応を取ることで大幅な増益に繋がります。
原価の種類と違い
| 原価の種類 | 主な内容 |
| 製造原価 | 直接材料費、直接労働費、製造間接費 |
| 売上原価(販売原価) | マーケティング費、物流費、販売促進費 |
| 仕入原価 | 商品購入費、輸送費、保険料など |
各原価は企業活動の異なる段階で発生し、その管理は企業の利益に直結します。適切な原価計算と管理を行うことで、経営の効率化を図り、より高い利益を目指すことができます。
製造原価は、製品を生産するために直接かかる原価です。これには、直接材料費、直接労働費、製造間接費が含まれます。
売上原価は、販売された商品の生産にかかったコストです。これは主に製造業で使用される概念で、販売された製品の製造原価に相当します。一方、販売原価は商品を市場に提供するために発生する費用で、広告費や販売員の給与などが含まれます。
仕入原価は、商品を外部から購入する際にかかるコストです。これには商品の購入費用の他に、運送費や保険料などが含まれることがあります。
原価管理における業種間の違い

原価管理で管理する項目は、一定ではありません。
業種が変わると管理する経費も異なるため注意が必要です。
| 費用 | |
| 製造業 | ・材料費 ・変動費 ・固定費 ・労務費 ・設備費 ・動力費 |
| 建設業 | ・工事を行う上で発生する外注費 ・資材費 |
| IT業 | ・労務費 ・外注委託費 ・経費 |
| 広告業 | ・労務費 ・広告運用費 ・業務委託費 ・外注費 |
製造業の場合
製造業の場合は、「材料費」「変動費」「固定費」「労務費」「設備費」「動力費」などが、管理すべき原価項目として重要視されています。
これらの各種項目について原価を調査した上で、それぞれの管理目標・改善の方向性を決めていくことが必要です。
高度経済成長時代から1990年代にかけては、原価管理が重要視されておらず、「モノを作れば売れる」時代でした。
2000年代からグローバル化が進んだことで、製品も多様な選択肢から消費者が選べる時代になったことで、「値段の安さ」も重要視されるようになっています。
このような理由から、製造業で「原価管理」は重要なのです。
建設業の場合
建設業で原価として計算される費用は「工事を行う上で発生する外注費」「資材費」などがあります。
だた、建設業における原価管理は、「工期」「資材価格」の変動が大きい上に、原価対象となるものをカテゴリごとに分解すると項目も細かいことから、正確な原価把握は人為的な仕組みでは難しいです。
Excelを用いた原価計算だと、入力・計算ミスなども多く発生してしまうため、原価管理システムの導入が求められます。
IT業の場合
多くのIT業で原価として計算されるのは「労務費」「外注委託費」「経費」の3つです。
プロジェクトマネージャーやエンジニア、プログラマー、デザイナーなど数多くの人が業務に関わり、これが労務費として計上されます。
またシステム開発やデザインなどを社外のスタッフに依頼する場合に発生するのが外注委託費です。
経費は、IT業には不可欠なパソコンやサーバー、ソフトウェアなどの費用や、サーバーの保守費、通信費、打ち合わせなどで発生した飲食代も含まれます。
広告業の場合
広告業の場合は「労務費」「広告運用費」「業務委託費」「外注費」などが原価として挙げられます。
広告の作成を行う際に発生する、カメラや照明などの機材、撮影スタジオの費用や広告を長期で運用していく上での保守費用などが発生します。
また広告を社外の専門家やクリエイターに発注した場合、業務委託費や外注費なども発生し、複雑な原価管理を必要とします。
原価管理のメリット

原価管理の最も基本的な目的は、利益を正確に計算し、報告することです。企業が製品やサービスからどれだけの利益を得ているかを知るためには、製造原価や販売原価など、関連するすべてのコストを把握する必要があります。
原価管理は、企業が経済的な意思決定を行うための重要なプロセスです。正確な原価計算と効果的な管理を行うことで、利益の最大化、適切な価格設定、そして継続的なコスト削減が可能となります。
経営戦略の計画ができる
生産・サービスに関連する直接的な費用の「無駄」と「効率性」を把握できる上、価格の設定からその企業の損益計算にまで影響を与えるのが原価管理です。
そのため、原価管理は企業の財務状況を正確に把握する手段としても機能します。コストの動向を追跡し、それが予算や過去のパフォーマンスとどのように比較できるかを分析することで、経営陣はリアルタイムで経営状況を評価し、必要に応じて迅速に対応できます。
原価管理は、価格戦略を最適化することも可能にし売上の増加にも寄与するのです。
適切な原価管理により、将来のビジネス戦略と投資計画を策定するための確かなデータが得られます。市場の変動や業界の動向を考慮したうえで、コスト効率の良い方法で事業を展開する計画を立てることが可能です。
また、企業は財務状態を正確に評価できることで、株主や投資家に対して透明な報告を行うことが可能です。
すべての原価情報を正確に集計することで、利益の計算ミスを防ぎ、投資家や関係者に対する信頼性の高い財務報告を提供できるのです。
原価管理は効果的な経営判断を行う上で、企業にとって欠かせないプロセスです。このシステムを利用することで、企業は安定した成長を実現し、市場内での競争力を維持することが可能になります。
利益の計算と最大化ができる
原価管理を行う主な目的のひとつは、利益の最大化です。
世界的な物価の高騰によって仕入価格が増加しているにも関わらず、販売価格を一定にしていた場合、売上が増加したとしても1商品の利益は減少してしまいます。その結果、全体の利益が大幅に減少する可能性があるのです。
コストを詳細に把握し、無駄な支出を削減することで、利益率を向上させることができます。これにより、企業は持続可能な成長を達成し、競争上の優位性を確保することができます。
価格設定の判断材料になる
原価情報は、製品やサービスの価格を設定する際の重要な基準となります。市場競争力を保ちつつも、適切な利益を確保する価格を見つけるためには、原価を精密に管理し分析する必要があります。
価格設定が適切でない場合、売上は伸び悩み、または利益が損なわれる可能性があります。商品を構成する費用の変化を捕捉できれば、利益が残るような最適な価格設定が可能です。
市場と消費者のニーズに基づいて、適切な価格帯を設定し競争力を強化したり、原価と市場条件を考慮し、利益を最大化する価格を決定することで利益確保をしたりします。
コストマネジメントができる
原価管理は、不要な支出を削減し、効率的なリソースの配分を促進するためにも利用されます。コストを定期的に見直し、最適化することで、企業はより効果的な運営が可能となり、競争上の優位性を保つことができます。
具体的には、無駄なコストを特定し、削減することで全体の効率を向上させることやリソースの最適化です。
原価管理は利益計算の正確性を保ちながら、競争力のある価格設定と継続的なコスト削減を実現するための重要なプロセスです。これにより企業は経営の健全性を保ち、長期的な成長と発展を目指すことができます。
原価管理とはどんな仕事?他業務との違い

原価管理とは具体的にどんな仕事を指すのでしょうか。ここでは、原価にかかわる他の業務との違いを見ていきます。
原価計算
| 違い | |
| 原価管理 | 原価計算の結果から最適な原価設定をしたり改善を行ったりする作業 |
| 原価計算 | 特定の製品製造やプロジェクトが完了するまでにかかる |
原価計算は、特定の製品やプロジェクトが完了するまでにかかるコストを具体的に算出する作業です。この計算には直接材料費、直接労働費、製造間接費などが含まれ、製品単位でのコストが明確にされます。
原価計算が「いくらかかったか」を算出することに焦点を当てるのに対し、原価管理はこれらの計算結果をもとに最適なコスト設定を行い、実際の原価と目標原価との差異を分析し、利益改善へとつなげる管理業務を指します。
つまり、原価計算はデータの収集に関わる一方、原価管理はそのデータを基に戦略的な判断を下すプロセスです。
原価分析
原価分析は、企業が製品やサービスにかかる具体的なコストを詳細に調べるプロセスです。
この分析によって、コストの発生源となる要因を明確にし、不必要な支出を特定します。
具体的な手順には、直接コストと間接コストの分類、変動コストと固定コストの識別、そして実際の支出と予算の比較が含まれます。
この過程を通じて、企業はコスト削減の機会を見つけ出し、効率性を向上させることが可能となります。最終的には、コスト効率の改善を図りながら利益を最大化することが目的です。
予算管理・利益管理
| 違い | |
| 原価管理 | 原価計算の結果から最適な原価設定をしたり改善を行ったりする作業 |
| 利益管理 | 利益を向上させるために行う管理 |
予算管理は企業が将来の支出を計画し、それに基づいて資金を割り当てるプロセスです。一方、利益管理は利益を最大化するために設定された目標に基づき、収益とコストのバランスを取る作業です。
つまり、利益管理はどうすれば利益を増やせるのかを第一目標に置き、さまざまなデータから利益を向上させるための管理を指します。
原価改善
原価改善は、生産プロセスの効率化や材料選定の最適化、エネルギー利用の改善などを通じてコストを削済むことを目的とします。これにより、製品の単価を下げることができ、競争力のある価格設定が可能になります。
法令遵守
法令遵守は、原価管理のプロセスにおいて非常に重要です。企業は会計基準や税法を遵守し、透明で正確なコスト報告を行う必要があります。これにより、外部の監査に対して企業の信頼性を高めることができます。
原価管理は、単に数字を追うだけでなく、それを基に企業全体の戦略的な決定を行うための重要な業務です。これを効果的に行うことで、企業は財務の健全性を保ちつつ市場での競争力を維持することが可能となります。
原価管理の流れと損益計算方法

原価管理の大まかな流れは以下の通りです。
- STEP1:標準原価の設定
- STEP2:実際の原価の把握
- STEP3:標準原価と実際の原価の差異を分析
- STEP4:原価率の改善
- STEP5:損益を計算
STEP1:標準原価の設定
まず過去のデータや市場のデータから、商品の製造やプロジェクトにおいて目標にすべき原価、標準原価の設定を行います。
標準原価とは、製品やサービスを製造・販売するために必要な費用を、過去の経験や実績に基づいて算出した計画的な原価です。標準原価を設定することで、以下のメリットがあります。
- コストの目標となる指標となる
- 実際の原価との差異を分析することで、改善点を見つけられる
- 損益計算や予算管理に役立てられる
標準原価は、製品やサービスの種類、製造方法、市場環境などを考慮して、慎重に設定する必要があります。標準原価の設定には、様々な手法があります。代表的な手法としては、以下のものがあります。
- 過去の原価実績に基づく方法
- 工程別原価計算に基づく方法
- 目標原価設定法
STEP2:実際の原価の把握
実際の原価とは、製品やサービスを製造・販売するために実際に発生した費用です。標準原価と比較することで、コストパフォーマンスを評価することができます。
実際の原価を把握するには、以下の方法があります。
- 会計帳簿に基づく方法
- 原価計算書に基づく方法
- 現場でのデータ収集に基づく方法
売ったものに基づき、最適な計算方法を選びましょう。
STEP3:標準原価と実際の原価の差異を分析
予測した原価と実際にかかった原価との差を確認し、分析を行います。
- 差異額の分析
- 差異率の分析
- トレンド分析
標準原価と実際の原価の差異を分析することで、コスト削減や効率化のためのヒントを得ることができます。原因や差異が発生した理由を突き止め、改善策を実施しましょう。
STEP4:原価率の改善
分析結果をもとに原価率の改善を行います。原価率とは、製品やサービスの販売価格に対する原価の比率です。原価を削減するには材料費や労務費、経費の削減が有効です。
原価率を低く抑えることは、利益向上につながります。
STEP5:損益を計算
損益計算は、企業の収益管理プロセスの最終段階であり、企業が利益を出しているか、または損失を被っているかを判断するための重要なステップです。
この段階では、全体的な収益と総原価を用いて損益を計算します。以下はその具体的な計算方法です。
損益を計算するには、以下の簡単な式を用います:
損益計算の公式:損益 = 総収益 – 総原価
- 総収益:期間内に得られた全ての収入の合計です。
- 総原価:その収益を生み出すためにかかった全てのコストの合計で、具体的には直接材料費、直接労働費、製造間接費などが含まれます。
この利益情報は、経営判断や戦略策定に役立つ重要な指標となります。
この5つが大まかな流れであり、原価管理を的確に行うことで、コストを抑え更なる利益を生み出すことが可能です。
原価を下げるコストマネジメントのコツ

原価管理は、企業が効率的に運営を行い、競争力を維持するために不可欠です。特に、株式会社Jiteraのような企業では、厳密なコスト管理が直接的な利益向上につながります。
以下に、原価を効果的に下げるための戦略を紹介します。
原価が高い項目を特定する
原価削減を成功させるためには、まず何にどれだけの費用がかかっているかを把握することが重要です。株式会社Jiteraでは、全ての支出を詳細に分析し、特にコストが高くなっている領域を特定します。
このプロセスには、購入部品、製造工程、物流コストなどが含まれます。具体的には、最も費用のかかる材料を特定し、その使用量を減らすか、より安価な代替品に切り替えることでコストを削減します。
この段階では、データ分析ツールを使用して、コスト生成の原因となっている具体的な要素を明確にすることが求められます。
収益性・損益を把握する
効率的な原価管理には、各製品やサービスの収益性を理解することが不可欠です。Jiteraでは、定期的な収益性分析を実施して、各製品の損益分岐点を把握し、どの製品が利益を生んでいるか、またどの製品が損失を出しているかを評価します。
これにより、不採算製品の生産調整や廃止、利益を生む製品への投資強化を行うことが可能になります。この情報は、戦略的な価格設定やプロモーション計画にも活用され、収益の最大化を目指します。
品質や顧客サービスに影響のないコストを削減する
原価削減の際には、品質や顧客満足度を維持しながら不要なコストを見つけ出すことが重要です。Jiteraでは、生産プロセスの無駄を削減し、エネルギー効率の良い機器への投資、または低コストの供給者との契約により、コストを抑えつつも品質を保つよう努めています。
例えば、過剰な包装材の使用を見直すことや、必要以上の在庫を抱えないようにすることが挙げられます。これにより、経費は削減されつつも、顧客からの信頼を損なうことはありません。
原価管理システム・ツールを活用する
最新のテクノロジーを活用することで、原価管理の効率は大きく向上します。Jiteraでは、ERPシステムを導入して原価計算と在庫管理を自動化し、データの一元化を図っています。このシステムにより、リアルタイムでのコスト追跡が可能です。
企業独自のニーズに合わせた原価管理システムの開発もひとつの解決策です。また、自社の具体的な要件を反映したカスタマイズされた原価管理ツールを開発しています。
これにより、特定の業界やプロセスに最適化されたコスト管理が可能となり、効率と精度の両面で優れた結果を出しています。
まとめ:原価管理とは利益を最大化する業務

原価管理とは、製品やサービスの提供に必要なコストを計画的に管理し、企業の利益を最大化するための重要な業務です。
このプロセスを通じて、企業は各種原価を詳細に把握し、適切な価格設定とコスト削減策を行うことができます。
また、原価の種類には製造原価、売上原価、仕入原価があり、業種ごとにその適用方法や管理技術が異なり、効率的な原価管理には、標準原価の設定から実際の原価把握、差異分析、改善策の実行に至るまでの一連の流れが含まれます。
最終的には、これらの取り組みが経営状況の正確な把握、利益の増加、そして持続可能なビジネス戦略の構築に寄与するのです。
製造業や広告業など業種ごとに管理しなければならない原価は変わるため、自社に合ったシステムを選ぶことが重要になります。
株式会社Jiteraは専門的なアドバイスを通じて、貴社の原価管理と利益最大化の取り組みをサポートを得意とする企業であり、ITシステムの導入に悩む事業者様へのサポートを徹底的に行っています。
お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することで、ビジネスの成功をサポートします。
原価管理システムの開発や導入に関するご質問やお手伝いが必要な場合は、ぜひ、株式会社jiteraにお問い合わせください。