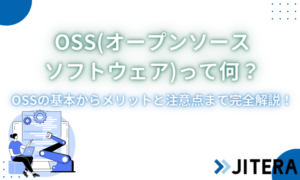スーパーコンピュータは、大規模な科学技術計算やデータ処理、解析に使用されるコンピューターのことをさします。
この記事では、スーパーコンピュータの仕組みだけでなく、その性能や用途、値段に関することも解説しています。
この記事を読んで、自社でどのようにスーパーコンピュータを活用するかの参考にしてください。
小中規模プロジェクトを中心にSEやコンサルとして活動。クラウド導入やスタートアップ、新規事業開拓の支援も経験しました。
スーパーコンピュータとは

スーパーコンピュータは、並列処理や特殊なハードウェアやソフトウェアアーキテクチャを使用して、大規模な問題を高速かつ効率的に解決できるコンピューターです。これらのコンピューターは、気象予測・気候モデリング・宇宙船設計・核兵器シミュレーション・医療薬品開発など、多くの分野で活用されています。
また、金融取引の高速処理やビッグデータ解析などの産業応用にも使用されているものです。
一般的に大規模な施設内に設置され、膨大な電力と冷却装置を必要とします。また、その設計・製造・運用には膨大なコストがかかるため、一般的に大学・研究機関・政府機関・大企業などの組織が所有・運用していることが多いです。
スーパーコンピュータの構成要素

スーパーコンピュータは、以下のような構成要素から成り立っています。様々な要素が組み合わさって高性能な計算を実行し、複雑な問題を解決する能力を実現しているのがスーパーコンピュータです。
プロセッサ(CPU/GPU)
プロセッサは、スーパーコンピュータの計算力の中心となる部分であり、複数のプロセッサが搭載されています。
一般的には、中央処理装置(CPU)とグラフィックス処理装置(GPU)が組み合わさって使用されることが多いです。
メモリ
プロセッサが、計算を実行する際に使用するデータや命令を一時的に保存するために、メモリが搭載されています。
高性能なスーパーコンピュータでは、大容量かつ高速なメモリが必要です。
ストレージ
データの永続的な保存やアクセスのためには、大容量のストレージが必要となります。
大容量のストレージは、ハードディスクドライブ(HDD)・ソリッドステートドライブ(SSD)・高速のフラッシュメモリなどです。
ネットワーク
スーパーコンピュータ内の各部分を接続するために、高速なネットワークが必要となります。
高速なネットワークを活用して、プロセッサ間やノード間でデータを効率的にやりとりすることが可能です。
冷却システム
スーパーコンピュータは、膨大な量の電力を消費して、多くの熱が発生するため、適切な冷却システムが必要となります。
冷却システムには、冷却装置や冷却液の流れるシステムなどがあります。
電源供給システム
高性能なスーパーコンピュータは、大量の電力を必要とするため、安定した電力供給システムが必要です。
また、安定した電力供給システムには、電力の供給と配電を管理するための装置が必要となります。
【簡単解説】スーパーコンピュータの仕組み

スーパーコンピュータの仕組みは、おもに以下の要素から成り立つものです。
並列処理での同時計算ができる
スーパーコンピュータの最大の特徴は、膨大な数のプロセッサを用いて並列処理を行う能力です。
通常のコンピュータが一度に1つの計算を行うのに対し、スーパーコンピュータは複雑な問題を小さな部分に分割し、それぞれを異なるプロセッサで同時に処理します。
これにより、気象予報や分子動力学シミュレーションなど、膨大な計算量を要する問題を驚異的な速さで解くことができます。
並列処理技術の進歩により、数千から数百万のコアを持つシステムが実現し、処理能力は年々向上しています。
高性能ネットワークとメモリを持つ
スーパーコンピュータの性能を支えるのは、高速で大容量のメモリとプロセッサ間を結ぶ超高速ネットワークです。
これらのコンポーネントは、大量のデータを迅速に処理し、プロセッサ間で効率的に情報をやり取りするために不可欠です。
例えば、インフィニバンドなどの低遅延・高帯域幅ネットワーク技術や、高速なSSD、大容量のRAMが採用されています。
計算環境が最適化されている
スーパーコンピュータの計算環境は、最高の性能を発揮できるよう細部まで最適化されています。
例えば以下のような点です。
- 発熱対策として液体冷却システムを採用
- 省電力設計や再生可能エネルギーの活用
- 冗長設計
- 効率的なジョブスケジューリングシステムの導入
ハードウェアからソフトウェアまで、あらゆる面で最適化が図られています。
ソフトウェアのカスタマイズが最適化されている
スーパーコンピュータの性能を最大限に引き出すには、ハードウェアに最適化されたソフトウェアが不可欠です。
そのため、オペレーティングシステムから科学計算ライブラリ、コンパイラに至るまで、すべてのソフトウェアが特別にカスタマイズされています。
例えば、以下のような技術やソフトウェアが挙げられます。
- 並列処理を効率的に行うためのMPIライブラリ
- GPUを活用するためのCUDA
- 特定の科学分野向けに最適化されたアプリケーションソフトウェア
様々なカスタマイズが組み合わさり、研究者が複雑な計算をできるだけ簡単に実行できるようになっています。
最前線の科学技術計算をしている
スーパーコンピュータは、現代科学の最前線で活躍しています。気候変動予測、新薬開発、宇宙の起源探求、材料科学など、従来の手法では解決困難だった複雑な問題に挑戦しています。
例えば、精密な気象モデルによる長期気候予測や、複雑な分子構造のシミュレーションによる新薬候補の探索などが行われています。
また、人工知能や量子コンピューティングとの融合も進んでおり、さらに高度な問題解決能力の獲得が期待されています。
スーパーコンピュータの用途と活用例

スーパーコンピュータは、複数のプロセッサが同時に複数のタスクを実行することで高速化を実現しています。処理の高速化を活用した事例には、どのようなものがあるのでしょうか。
気象予測
大気・海洋モデルのシミュレーションにスーパーコンピュータが利用され、天候予測や気候変動の研究が行われています。
スーパーコンピュータは、複雑な大気・海洋モデルを用いて高精度の天候予測を行います。これにより、数日先の天気予報から長期的な気候変動の予測まで、幅広い時間スケールでの予測が可能になります。
例えば、台風の進路予測や極端気象現象の予測精度が向上し、防災・減災に大きく貢献しています。
物理学
核融合や素粒子物理学の分野では、スーパーコンピュータが不可欠です。
例えば、ITER(国際熱核融合実験炉)プロジェクトでは、プラズマの挙動をシミュレーションし、核融合反応の制御方法を研究しています。
また、CERN(欧州原子核研究機構)では、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の実験データ解析にスーパーコンピュータを活用し、新粒子の探索や宇宙の起源に関する研究を進めています。
医薬品開発
生体分子の模倣や医薬品のスクリーニングにおいて、スーパーコンピュータが用いられています。
スーパーコンピュータの高性能計算能力を活用して、創薬や新たな治療法の開発、バイオインフォマティクスの分野でのゲノム解析などが進むことが期待されています。
このような開発が進めば、疾患の治療や予防、個別化医療の実現が進む可能性が見えてくるでしょう。
宇宙航空工学
宇宙船の設計や飛行シミュレーションにスーパーコンピュータが活用され、宇宙探査ミッションの計画や実行が支援されています。
特にスーパーコンピュータを活用しているのが、NASA(米国航空宇宙局)やJAXA(宇宙航空研究開発機構)などの宇宙機関です。
宇宙船の設計や軌道計算、再突入シミュレーションなどにスーパーコンピュータを活用しています。例えば、火星探査機の着陸シミュレーションや、宇宙デブリの軌道予測などが行われています。
地震・地殻変動の予測
地球科学の分野では、地震や地殻変動の予測や地質の解析にスーパーコンピュータが利用されています。
地球内部の複雑な構造をモデル化し、地震波の伝播をシミュレーションすることで、地震のメカニズム解明や被害予測に役立てることが可能です。
例えば、日本の「富岳」では、南海トラフ巨大地震の詳細なシミュレーションが行われ、津波の到達時間や浸水域の予測に活用されています。
金融取引の高速処理
高頻度取引(HFT)や複雑なリスク分析において、スーパーコンピュータの高速データ処理能力が活用されています。
例えば、大量の市場データをリアルタイムで分析し、瞬時に取引を行うアルゴリズム取引や、複雑な金融商品のリスク評価などに利用されています。
人工知能の開発
スーパーコンピュータは、大規模な機械学習モデルの訓練や、複雑なニューラルネットワークの開発に不可欠です。例えば以下のようなものが挙げられます。
- 自然言語処理
- コンピュータビジョン
- 創薬
- 自動運転
人工知能を組み合わせることで、様々な分野でのスーパーコンピュータの活用を実現しています。
【2024年6月】スーパーコンピュータの世界ランキングTOP4

スーパーコンピュータは、多種多様な分野で重要な役割を果たしていることがわかりました。次に、スーパーコンピュータの世界ランキングを紹介します。
- 1位:Frontier
- 2位:Aurora
- 3位:Eagle
- 4位:富岳
それぞれのスーパーコンピュータの特徴をみながら、その違いを理解していきましょう。
1位:Frontier
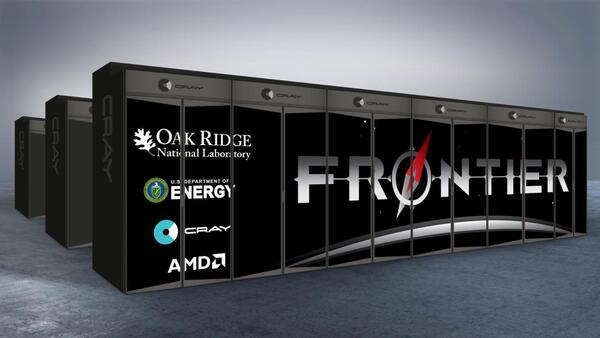
| 項目 | 詳細 |
| 名称 | Frontier |
| 設置場所 | オークリッジ国立研究所(米国) |
| 理論性能 | 1.6 エクサフロップス |
| LINPACK性能 | 1.1 エクサフロップス |
| CPU | AMD EPYC 64C 2GHz |
| GPU | AMD Instinct MI250X |
| メモリ | 4.6 ペタバイト |
| 消費電力 | 21.1 MW |
| 概算価格 | 約6億ドル |
「Frontier」は、米国エネルギー省のオークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory)に設置されたスーパーコンピュータの名称です。
AMDのEPYCプロセッサとNVIDIAのGPUアーキテクチャを組み合わせた先進的なハードウェアプラットフォームを採用しており、高度な並列処理能力と大規模なデータ処理能力が実現されています。
Frontierの性能は非常に高く、1秒間に数百ペタフロップス(数百京演算)の計算性能を持ち、科学技術計算やデータ解析などの幅広い用途に利用されています。特に、気象予測、物理学のシミュレーション、医薬品開発、エネルギー研究などの分野で重要な役割を果たしています。
2位:Aurora

| 項目 | 詳細 |
| 名称 | Aurora |
| 設置場所 | アルゴンヌ国立研究所(米国) |
| 理論性能 | 2 エクサフロップス |
| LINPACK性能 | 未公表 |
| CPU | Intel Xeon Scalable |
| GPU | Intel Ponte Vecchio |
| メモリ | 10 ペタバイト |
| 消費電力 | 約60 MW |
| 概算価格 | 約5億ドル |
「Aurora」は、米国エネルギー省のアーゴンヌ国立研究所(Argonne National Laboratory)に設置されたスーパーコンピュータです。米国のエクソスケール計算イニシアティブ(Exascale Computing Initiative)の一環として開発されており、世界で初めてのエクソスケール級のスーパーコンピュータとして期待されています。
インテルのXeonプロセッサとIntelのXe GPUアーキテクチャを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャを採用しており、高度な並列処理能力と大規模なデータ処理能力が実現されています。
膨大な量のデータを処理し、科学技術計算や人工知能などの分野で幅広い用途での利用が可能です。特に、気候モデリング、材料科学、医薬品開発、エネルギー研究などの分野での応用されています。
3位:Eagle

| 項目 | 詳細 |
| 名称 | Eagle |
| 設置場所 | ロスアラモス国立研究所(米国) |
| 理論性能 | 430 ペタフロップス |
| LINPACK性能 | 373.8 ペタフロップス |
| CPU | AMD EPYC |
| GPU | NVIDIA A100 |
| メモリ | 1.1 ペタバイト |
| 消費電力 | 40 MW |
| 概算価格 | 約1.5億ドル |
「Eagle」は、米国エネルギー省のノースカロライナ大学チャペルヒル校の共同プロジェクトによって設計および開発されたスーパーコンピュータです。Eagleは、エネルギー省のエクソスケール計算イニシアティブの一環として位置付けられており、次世代の高性能計算ニーズに応えることを目指しています。
Eagleの開発には、クレイ・ネクストジェンスパコンプロジェクトやIBMとのパートナーシップが含まれています。このプロジェクトでは、AMDのプロセッサとGPU、IBMのPOWERプロセッサ、NVIDIAのGPUなど、複数のハードウェア技術が組み合わされています。
Eagleは、高度な並列処理能力と大規模なデータ処理能力を持ち、科学技術計算、エネルギー研究、気象予測、医薬品開発などの分野で幅広い用途での利用が可能です。特に、エネルギーシステムの最適化、材料科学の研究、気候モデリングなどにおいて、Eagleの性能が重要な役割を果たしています。
4位:富岳

| 項目 | 詳細 |
| 名称 | 富岳 |
| 設置場所 | 理化学研究所(日本) |
| 理論性能 | 537 ペタフロップス |
| LINPACK性能 | 442 ペタフロップス |
| CPU | Fujitsu A64FX |
| GPU | なし(CPU内蔵) |
| メモリ | 4.85 ペタバイト |
| 消費電力 | 29.9 MW |
| 概算価格 | 約1,000億円 |
「富岳」(Fugaku)は、日本の理化学研究所(RIKEN)が開発したスーパーコンピュータです。フジツボコンピュータ、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、さらには富士通が協力して開発されました。
計算能力としては、単精度で1エクサフロップス(1秒間に10の18乗の浮動小数点演算)を超える能力を持ち、倍精度でも数百ペタフロップスの処理が可能です。ARMアーキテクチャのプロセッサを採用しており、このスーパーコンピュータが開発された背景には、省エネルギー性やスケーラビリティの向上があります。
気象予測・気候変動の解析・材料科学・医薬品開発・エネルギー分野など、さまざまな分野で幅広く活用されています。
日本政府や産業界において、富岳の能力を活かした研究や開発が進められており、その高い性能と信頼性によって、世界的な注目を集めています。
コンピューターに関して、以下の記事でも詳しく解説しているため、参考にしてください。
スーパーコンピュータに期待できること

では、私たちがスーパーコンピュータに期待できることは何でしょうか。社会や産業における重要な役割を果たしていくと言われる、スーパーコンピュータの可能性を見ていきましょう。
性能が飛躍的に向上
スーパーコンピュータの進化と性能向上の歴史は、計算機技術の発展と密接に関係しています。以下は、それぞれの時期とその性能向上の歴史をまとめたものです。
| 年代 | 歴史の概要 |
| 1950年代から1960年代 | 最初のコンピューターが登場し、初期のスーパーコンピュータの先駆けとなる大規模なメインフレームコンピューターが開発されました。 これらのマシンは、主に科学技術計算や政府機関の需要に対応していました。 |
| 1970年代 | ベクトル処理を導入したスーパーコンピュータが登場し、高性能な科学技術計算を可能にしました。 高性能な科学技術計算が可能になったことで、気象予測や物理学のシミュレーションなど、多くの分野で新たな可能性が開かれました。 |
| 1980年代 | ベクトル処理と並列処理の組み合わせが一般的になり、より高性能なスーパーコンピュータが登場しました。 特に、米国のCray Inc.が開発したCrayシリーズなどが有名です。 |
| 1990年代 | マルチコアプロセッサやグラフィックス処理ユニット(GPU)の活用が進み、並列処理能力が向上しました。 また、インターネットの普及により、分散コンピューティングの技術も進歩しました。 |
| 2000年代 | ハイパフォーマンスコンピューティングの需要が増加し、より高速で効率的なスーパーコンピュータが開発されました。 さらに、クラウドコンピューティングやビッグデータ技術の普及により、大規模なデータ処理も可能になりました。 |
| 2010年以降 | エクソスケール計算の実現が目指され、スーパーコンピュータの性能向上が続いています。 新しいアーキテクチャやハードウェア、ソフトウェア技術の開発により、さらなる性能向上が期待されています。 |
これらの進化は、科学技術の進歩や産業の発展に重要な役割を果たしており、スーパーコンピュータは現代社会において不可欠なツールとなっています。
ハイブリットシステムが登場
クォンタムコンピューティングの技術によってハイブリットシステムが登場することが期待されています。
ハイブリッドシステムでは、異なる種類のプロセッサや計算ユニットを組み合わせることで、様々な計算タスクに最適化された性能の発揮が可能です。
例えば、汎用CPUと専用のアクセラレータ(GPU、FPGA、量子チップなど)を組み合わせることで、多様な計算ニーズに柔軟に対応できるようになります。
ハイブリッドなアプローチが可能になれば、従来のコンピューターでは解決困難だった問題に対する新たなアプローチが可能となるでしょう。
AIや機械学習との組み合わせ
人工知能(AI)技術の進歩とスーパーコンピュータの組み合わせにより、高度な分析や予測が可能となります。
例えば、以下のようなことが期待できます。
- 大規模なデータセットを用いた深層学習モデルの高速訓練
- AIを活用したシミュレーションの最適化
- エネルギー効率や計算効率を向上
今後、スーパコンピューターは、AIとの組み合わせによって科学的発見の加速や、これまで解決困難だった複雑な問題へのアプローチを可能にするでしょう。
グリーンコンピューティングの実現
スーパーコンピュータの消費電力は膨大であり、環境への影響が懸念されています。そのため、エネルギー効率の高いグリーンコンピューティングの実現が重要な課題です。
現在取り組まれているグリーンコンピューティングには、以下のようなものが挙げられます。
- 低消費電力のプロセッサ開発
- 効率的な冷却システムの導入
- 再生可能エネルギーの活用
- 省エネルギーを考慮したアルゴリズムの開発
これらの取り組みにより、計算能力の向上と環境負荷の低減を両立させることが期待されています。
世界中の計算資源を連携して活用
グローバルな計算資源の連携は、個々のスーパーコンピュータの能力を超えた巨大な計算パワーを実現します。これは、グリッドコンピューティングやクラウドコンピューティングの概念を発展させたものです。
世界中のスーパーコンピュータやデータセンターをネットワークで結びます。そして、それを統合的に活用することで大規模な科学計算やデータ解析ができるようになります。
例えば、気候変動研究や宇宙観測データの解析など、グローバルな課題に対して世界中の研究者が協力して取り組むことが可能です。