近年、生体センサーへの注目が高まっています。生体センサーとは、人の体の生体情報を検知して電気信号に変換するセンサーのことです。健康管理や医療分野での活用が期待されていますが、一般の方も生体センサーについて正しく理解しておくことが大切です。そこで本記事では、生体センサーの種類や特徴、活用事例と将来性についてわかりやすく解説します。
COBOL→Java経験ありの元エンジニアです。システム開発に携わった経験から、皆さまにわかりやすいITの情報をお伝えします。
生体センサーとは?

生体センサーとは、人間や動物から発せられるさまざまな生理的情報を計測し、数値化するための技術です。体温、心拍数、血圧などの物理的な測定値や、血糖値のような化学的な値を計測するセンサーも、生体センサーに含まれます。また、非接触式のセンサーを使って、マイクロ波やミリ波のドップラー効果を利用して心拍数や呼吸などを測定することも可能です。
生体センサーの応用範囲は、医療用から一般用まで多岐にわたります。医療用途では、モーションセンサーや血圧センサ、血中酸素濃度センサ、呼吸センサなどが患者の健康状態を監視するために使われます。一方で一般向けの用途では、リストウォッチ型の心拍数計や活動量計、グラス型での視線検知や加速度センサを用いた頭部動作の検出、指輪やアクセサリ型でのUVセンサー利用などがあります。
このように生体センサーは、医療、健康管理、スポーツ科学、個人のウェルネス追求など、人々の生活の質を向上させるための重要な技術です。特にIoT(モノのインターネット)技術の発展に伴い、これらのセンサーから収集される生体データの活用が進んでいます。これにより、個人の健康状態や活動パターンに基づいたカスタマイズされた健康管理や疾病予防が実現可能になりつつあります。
生体センサーの種類と特徴

ここからは、大別して2種類ある以下の生体センサーの特徴について、詳しくみていきます。生体センサーはすでに一般向けの商品として認知度があるものが多いため、改めて知るきっかけになるでしょう。
- 接触型生体センサー
- 非接触型生体センサー
接触型生体センサー
接触型生体センサーとは、人間の体から発せられるさまざまな値を数値化し、体温、鼓動、血圧、心拍数などの物理量や、血糖値のような化学的値を計測する装置です。接触型生体センサーは、直接肌に触れるかたちで装着することで、健康状態や身体的変化をリアルタイムでモニタリングすることが可能になります。
医療用途では、モーションセンサーや血圧センサ、血中酸素濃度センサ、心電図センサなどがあり、これらは患者の状態を継続的に監視するのに役立ちます。一方、一般向けの用途では、リストウォッチ型の心拍数計や活動量計、指輪型のUVセンサーや光電脈波センサなどがあり、日常生活での健康管理や活動の追跡に使用されます。
接触型生体センサーを開発する際には、人体の皮膚への適合性や安全性を重視する必要があります。皮膚の状態は個人差が大きく、高齢者と新生児では大きく異なり、また同一人物でも季節や環境によって変わります。このため、ウェアラブル機器の開発においては、安全で使いやすい機能と形状の設計、最適な素材の選定、そして個人差による使用感の考慮が必要とされます。特に、素材の選定や皮膚への負担の最小化には、長年の経験と独自の試験方法が必要です。
このように接触型生体センサーは、その種類や使い方が多岐にわたり、医療から日常生活まで幅広い分野での活用が期待されています。開発に際しては、技術的な知見だけでなく、使用者の快適性や安全性への配慮も重要な要素となります。
非接触型生体センサー
非接触型生体センサーとは、身体に直接触れることなく心拍数、呼吸、体動などの生体情報を計測する技術です。マイクロ波、ミリ波レーダー、赤外線などさまざまな方式を利用しており、患者や利用者に物理的な負担をかけることなく連続的なモニタリングが可能です。
例えば、ミオ・コーポレーションは24GHzのマイクロ波を使用した非接触バイタルセンサーを開発しました。これにより金属板、セメント、水以外を透過し、壁を挟んだ場所からでも脈や呼吸を感知できるとされています。この技術は、睡眠障害などの状態を分析するのに利用可能で、ウェアラブルセンサーに見られる皮膚への負担がないメリットがあります。ただし、誤差や隣室の動きを拾ってしまう可能性があり、これにはセンサーの向きや感度の調整で対応が可能です。
パナソニックと京都大学は、共同研究によって非接触で心拍間隔を計測する生体情報センシング技術を開発しました。この技術により、高感度なスペクトラム拡散ミリ波レーダー技術と心拍推定アルゴリズムを組み合わせることで、離れた場所からでも高精度に心拍数や心拍間隔を計測できます。
関西大学では、血圧変動や心拍出量変動を推定する非接触センサーの応用研究が行われています。これらのセンサーはデスクワーク時のストレスモニタリングや医療・ヘルスケア分野での利用が期待されているのです。特に、冬眠中のクマの生体情報をモニタリングするなど、野生動物の観察にも応用できる可能性を示しています。
オムロンは、車載用の非接触脈拍センサーを開発し、運転中のドライバーの脈拍をモニタリングすることで眠気などの異常状態を早期に検出できる技術を提供しています。この技術は、運転者の安全を高めるために役立つでしょう。
これらの非接触型生体センサーは、医療や介護、自動車産業、動物観察など、さまざまな分野での応用が期待されています。非接触であるメリットは、利用者や患者にとってのストレスや負担を軽減することです。今後、非接触型生体センサーの技術の進化により、より精度の高い測定や新たな応用が期待されています。
生体センサーの事例紹介

接触型生体センサーは、生体から発せられるさまざまな値を数値化する装置です。これには体温、鼓動、血圧、心拍などの物理量を計測するセンサーや、血糖値のように化学的な値を計測するセンサーが含まれます。
医療用としてはモーションセンサ、血圧センサ、血中酸素濃度センサ、呼吸センサ、水分センサ、温度センサ、血糖センサ、心電図センサ、イメージセンサ、慣性センサ、圧力センサ、離床センサなどがすでに活用されているのです。
一般向けには、リストウォッチ型の心拍数計、活動量計、加速度センサ(睡眠検知など)やグラス型の赤外線センサー、カメラ(視線検知など)、眼電位センサなどがあります。
ウェアラブル端末との連携
接触式生体センサーやウェアラブルデバイスの統合技術は、個人の健康維持から専門的な研究活動に至るまで、多様な分野で活用されています。
たとえば「hitoe®の暑さ対応サービスforCloud」としてNTTの研究開発ウェブサイトに紹介されているプロジェクトでは、身体活動や高温環境での体温負担を判定するためのウェアラブル生体・環境センサーを活用しています。このシステムは、心臓の電気活動や心拍数、動きの加速度だけでなく、衣類内の気温や湿度をも測定することが可能で、これにより個々の健康状態を効果的に監視可能です。
クレアクト社が提供するウェアラブル生体センサー「biosignalsplux」は、心拍の変動、筋肉の電気活動、筋力、皮膚の電気活動、呼吸パターンなど、幅広い生体データの収集を目的とした製品です。これは医学的研究や教育用途に特化しており、BluetoothやUSBを通じて情報を伝送し、最大32GBのデータを保存できるモデルを含んでいます。
ウェアラブル技術によって測定できるデータタイプは広範にわたり、歩数や運動量の基本情報から始まり、心拍数、睡眠の質、消費エネルギー量、GPSを利用した移動経路追跡、ストレスレベルの評価、さらに血中酸素飽和度の検出に至るまで、日常生活や健康の管理に役立つ情報を提供します。
生体センサーの今後の発展と展望
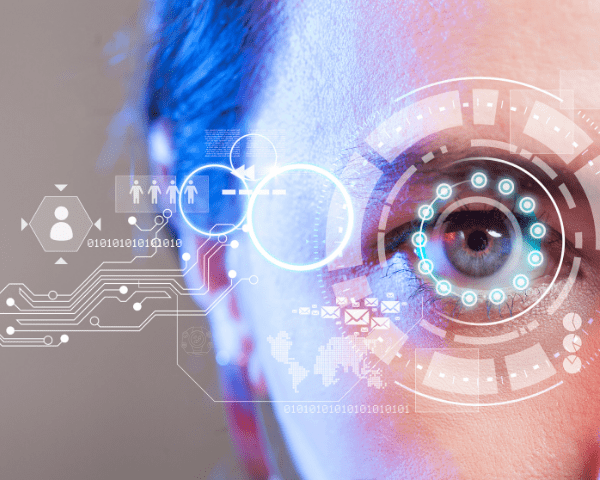
接触型生体センサーはボイス、フィンガー、ハンド、フェイシャル、アイリス、静脈スキャンなど多岐にわたる用途で利用されており、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域といった地域における需要の広がりを見せています。
バイオセンサーの分野では、医療診断、食品産業、環境分野などでの利用が拡大しています。バイオセンサーは生体分子を識別する分析装置として開発され、医療分野においては大きな変革をもたらす可能性があるでしょう。
IoTとの関連では、顔の微細な表情から感情を分析することや、集団行動の原理を解析することが可能になるなど、人間の動作と心の関係性の可視化や行動データの活用が期待されています。
IoTとの組み合わせ
生体センサーとIoTを組み合わせることで生まれる新たな技術やサービスは、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。
NTTデータの研究では、非侵襲で血糖値を測定する技術など、生活者の健康状態に応じた最適なサービス提供が可能になることが示されているのです。この技術を活用することで、医療機関での問診時間の短縮や、個人に合わせた商品の推薦、健康状態を考慮した旅行先の選定など、多方面での利用が期待されます。
しかしIoTセンサーの利活用には、データの取得と管理、医療機器としての規制遵守など、いくつかの課題があります。データを外部から調達する際のコストやプライバシー保護、医療機器としての承認・運用プロセスへの準拠など、慎重な検討と対策が必要です。
課題がありながらも、生体センサーとIoTの統合により、個人の健康管理から産業の効率化まで、多岐にわたる分野で革新が進むことが予想されます。これらの技術の発展は、より良い生活品質への道を切り開く重要なキーとなるでしょう。
生体センサーのまとめ

生体センサーは、人の生理的な情報を計測する技術です。これにより心拍数や体温、血圧といったデータをリアルタイムで取得でき、健康管理から疾病の早期発見まで幅広い応用が可能になります。
なかでもウェアラブル生体センサーは、日常生活においても違和感なく使用できるため、健康管理の新たな手段として注目されています。IoT技術と組み合わせることで、収集したデータをクラウド上で分析し、個人に最適化された健康管理や生活改善の提案が可能となるでしょう。
今後の開発では、さらに精度の高いセンサーの開発や、データの安全性・プライバシー保護の強化が求められています。このような技術的な挑戦を解決するためには、専門的な知識と経験が必要です。
株式会社Jiteraでは、生体センサーを用いた開発プロジェクトのサポートを提供しており、技術的な相談や開発に関するご相談に対応しております。生体センサーの活用を検討されている開発事業決裁者や管理職者の方は、ぜひJiteraにご相談ください。私たちは、あなたの事業が次のステップへと進むための強力なサポートを提供いたします。







