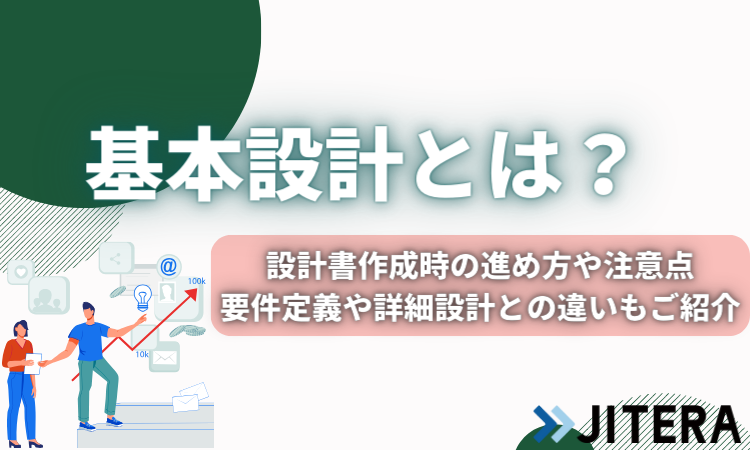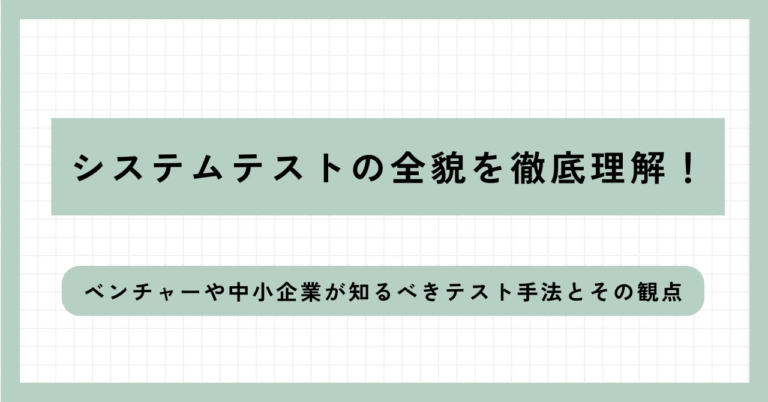ソフトウェア開発で迷走していませんか?システム構築を検討しているものの、プロセスがよく分からず立ち往生している方は多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、ソフトウェア開発の基本的なプロセスや手法、フローを理解することができます。要件定義から設計、開発、テストとシステム構築における一連の工程が順を追って解説されています。
特に、成功するソフトウェア開発には仕様書の作成が欠かせません。この記事では仕様書の種類や目的、作成のポイントを詳しく知ることができます。よくあるトラブルとその対処法も提示しているので、円滑な開発を実現する手がかりが得られるはずです。
IT関連の仕事をやっております。 様々な情報をまとめながら、よりよい記事になるよう取り組んでおります。 何卒宜しくお願い致します。
ソフトウェア開発のプロセスとは?

ソフトウェア開発におけるプロセスとは、要件定義から設計、コーディング、テスト、運用・保守に至るまでの一連の流れのことです。プロセスを決めておくことで、開発の効率化や品質の向上を図ることができます。
特に最近では、開発期間の短縮や変更への対応力が求められるため、プロセスの重要性が増しています。プロセスがない状態だと工程がずれたり、手戻りが発生するリスクが高まります。規律ある一連の流れを定めることが、開発成功のカギを握っていると言えるでしょう。
例えば、要件定義でユーザーの本当に解決したい課題をくみ取れなかった場合、完成したシステムが使われなくなる可能性が出てきます。設計段階で性能面の検討が不十分だと、想定を超えるアクセスが発生した際にサービスがダウンしてしまうことも。
開発プロセスがない状態では、このような失敗を起こしやすくなります。一方で、プロセスを明確化することで、手戻りやリスクの低減につながります。部門や担当者が変わっても一貫した開発を進めることが可能になるのです。
ソフトウェア開発の基本フロー・工程一覧

ソフトウェアやシステムを開発する際の工程は、細かく分けて作業を進めていきます。大きく分けると要件定義、設計、開発、テスト、納品、保守の6つに分けられます。
それぞれの段階で行うべきことを確実にクリアしていくことが重要です。
要件定義
要件定義では、開発するソフトウェアやシステムがどのような機能を持ち、何を実現させるべきかを定めます。
ユーザーが解決したい課題や要望をできる限り把握して文書としてまとめますが、ここで漏れなく洗い出すのが開発成功の鍵です。
例えばWebサイト制作時に掲示板機能や検索機能、商品購入機能といった、具体的な実現要件をリストアップしていきます。
ユーザー側からは「使いやすくわかりやすいサイトがほしい」という、あいまいな要望しか聞こえてこないことが多く、丁寧なヒアリングが欠かせません。
要件定義書に盛り込むべき内容としては、機能要件に加え、非機能要件と呼ばれる品質や性能等の要件の確認が必要です。
例えば同時接続数100人に耐えうることや、処理時間1秒以内を保証すること、といった品質基準を設定します。
ヒアリングで得た情報を、過不足なく要件定義書に落とし込むことがプロジェクト成功への近道です。
そして改修に強い設計へつなげることも、ここでは重要視していきましょう。
設計
要件定義で取りまとめた要件を元に、システムの設計を行います。どのような構成・枠組みで要件を実現していくか、詳細なシステム設計図面と文書を作成します。
性能面も考慮しながら、インフラ要件の抽出なども行っていきましょう。
まずは、アーキテクチャ設計といって、システム全体の構成や処理の流れを定義します。
主要な構成要素をブロック化し、各コンポーネント間の関係性を図解化していきます。
次に詳細設計として個別機能単位での処理手順やデータ構造を詳細に明記しながら、非機能要件への対応も大切です。
例えば、同時アクセス数100人という要件があれば、クラウドサーバーのスペック選定やデータベースのレプリケーション設計が必要です。
パフォーマンス面やセキュリティ面も踏まえた設計ということになります。
設計が要件定義と乖離していると、本来の目的を達成できないシステムになることも少なくありません。
要件定義と設計の整合性を十分に検証する工程を確保することが大切です。
開発
設計段階で考案した設計図に基づき、実際に開発作業に入ります。プログラムのコーディングを行い、設計通りのシステムを構築していきます。
もしも開発に向けて設計に不備があれば、見直しを行わなければなりません。
まずは設計図から個別機能を分割して担当者に割り振りますが、。各自が担当機能のコーディングを実施します。
そして単体テストを行って動作確認を取っていきますが、通過した個別モジュールを統合していきましょう。
こうして最終的には全体システムとして、コーディングと動作検証を完了させていきます。
コーディングではデータベースやOSなどサードパーティ製品とも、処理中に連携する必要があるかチェックしましょう。
この際には製品毎のインターフェース仕様に合わせて、該当システムへ実装する作業を進めなければなりません。
そして性能試験結果を見ながら、改めて設計の見直しも発生するケースもあります。
開発フェーズはとりわけ人的ミスが発生しやすい段階なので、コーディング規約の厳守やレビューによるチェック体制を確保することが重要です。
テスト
開発したシステムについて設計書や要件定義書との照合を行うため、動作テストや性能テストなどでシステムに不具合が残っていないかチェックします。
不具合が見つかれば、再度開発側にフィードバックして改修していきますが、最初に単体テストを実施して個別機能が仕様通りに動作するか確認します。
単体でテストが問題ないと判断したところで、次に複数機能間の連携動作を確認する結合テストを実施しましょう。
その後全体システムとしての総合テストで、想定通り正常にサービスが提供できることを検証します。
性能テストの面では、要件に定めた最大同時接続数などの値に対して余裕を持った耐久試験を実施します。実際の運用を模したデータ量での処理テストも欠かせません。
テスト工程では、開発者とは別の立場のテスト担当者が品質チェックを行うことが大切です。
要件から外れた動作や仕様書通りでない点を厳密にチェックし、テストを通じてシステム品質を向上させていきましょう。
納品
テストをパスしたシステムを顧客に納品しますが、データ移行や教育といった作業の支援も行います。
こうして顧客側での利用開始まで、障害対応だけでなく安定した稼働まで技術サポートを継続しましょう。
納品に先立ち顧客にシステムをデモする作業を行って最終確認を取り付けますが、要件と照らしながら漏れがないか再確認も必要です。
顧客環境へ実際にシステムを設置する作業に移行し、利用するサーバーなどの製品設定やデータ移行に向けた仕込み作業を行います。
その中でデータ移行時には既存データとの整合性や、完全性もチェックする必要も出てきます。
システム利用に関する啓蒙活動も重要で、操作マニュアルの作成や研修の実施しましょう。
顧客側での理解度を高めながら正しく利用いただけるよう配慮し、稼働開始後も数日〜数週間は顧客に常駐してサポートを提供することが一般的です。
不具合や操作上の疑問に対し迅速に対応することで、顧客に安心感を与えることができます。
保守
稼働を開始したシステムについて、バージョンアップや不具合修正といった保守も必要です。
技術動向に合わせた改修も継続的に実施し安定した稼働を目指しますが、しばらくすると顧客から改善要望も出てきます。
使い勝手の良い機能を追加してほしい、といった要望に対応する形でバージョンアップを図りましょう。
ユーザー数の拡大などもあって、スペック変更が必要になることもあります。
不具合については、迅速な原因究明と修正が求められ、稼働に影響が大きく重大な不具合の場合は緊急対応を心がける必要です。
データや設定の破損といった深刻な不具合が多いシステムの場合、冗長化などの対策強化が求められます。
BAや英語版対応といった法改正への追従も保守業務に含まれます。技術動向の変化に伴う改修にも、継続的に取り組んでいきましょう。
ソフトウェア開発プロセスを設定するメリット

ソフトウェアの開発を行う上でプロセス設定を行うと様々なメリットが有り、活用するケースは非常に多いです。
それぞれのメリットを最大限に活かしていきながら、ソフトウェア開発を円滑に進めていきましょう。
ソフトウェア開発についてプロセスを設定するメリットについて、特に注目されるポイントを見ていきましょう。
プロジェクトの成功を導けるように、開発を進める前にプロセスをしっかりと把握しておくことが重要です。
プロジェクトの計画が立てられる
開発プロセスのメリットの一つで無駄なコストを抑えながら、プロジェクト計画実行時に細かく目標や締切を決める点があります。
プロセスを定義しながらメンバーと情報を共有しつつ、開発において必要な項目を達成するために計画を立てて実行しましょう。
またタスクを分解すると担当者を明確に決めることもでき、期限を割り当てながら効率よく作業を進めることが可能です。
状況をガントチャートなどで可視化しながら、厳しいと判断すれば締切やマンパワーなどリソースの割り振りについて再検討を行えます。
リスクを早期発見できる
ソフトウェア開発ではバグなどのリスクも多数存在しており、クリアしながら完成に向けて進めていきます。
プロセスを設定すると各工程を分解でき、それぞれで抱える潜在的な問題やリスクを見つけて対処することも可能です。
リスクの早期発見によって、プロジェクトの計画にも悪影響を与えることはありません。
プロセス設定は細分化することも可能で、問題が長期化するのを防ぐことも期待できます。
プロセス設定は開発中だけでなく、問題が発生する前にも対応策を考えられます。
開発遅延やクオリティを下げる課題を未然に防ぐように柔軟に対応でき、変更時も最小限に影響を抑えることが可能です。
迅速に原因究明から、リスクを回避できる解決策を講じていきましょう。
コミュニケーションを円滑化できる
プロセス定義によってプロジェクトに参加するメンバーの中で、共通の言語で意思疎通を取ることができます。
開発時に関連するシステムやリソースなどを情報を共有しつつ、コミュニケーションを円滑に取ることが可能です。
必要な情報をメンバー全員が容易にアクセスすることができ、より強固な関係性をもたせることができます。
問題解決時のディスカッションでも意思疎通をスムーズに取ることができるため、ソフトウェア開発時の計画を狂わせることがありません。
専門的な分野で問題解決を図る時にもコミュニケーションを円滑に取れるようになるので、解決策も時間をかけずに見出すことができます。
誤解や見識違いも防ぎながら、正しくソフトウェア開発を進められることでしょう。
品質の向上につながる
プロセス設定によって品質向上につながるソフトウェア開発が実現でき、プロジェクトの成功も期待できます。
あらかじめプロセス設定を行いながらコードレビューや各種テスト、システム設計などをドキュメント化していくとクオリティを担保可能です。
プロジェクトを成功させるためには定期的にプロセスの見直しも必要で、効果的なプロセスを考えていくことによって品質向上に役立てましょう。
主要なソフトウェア開発の種類・手法
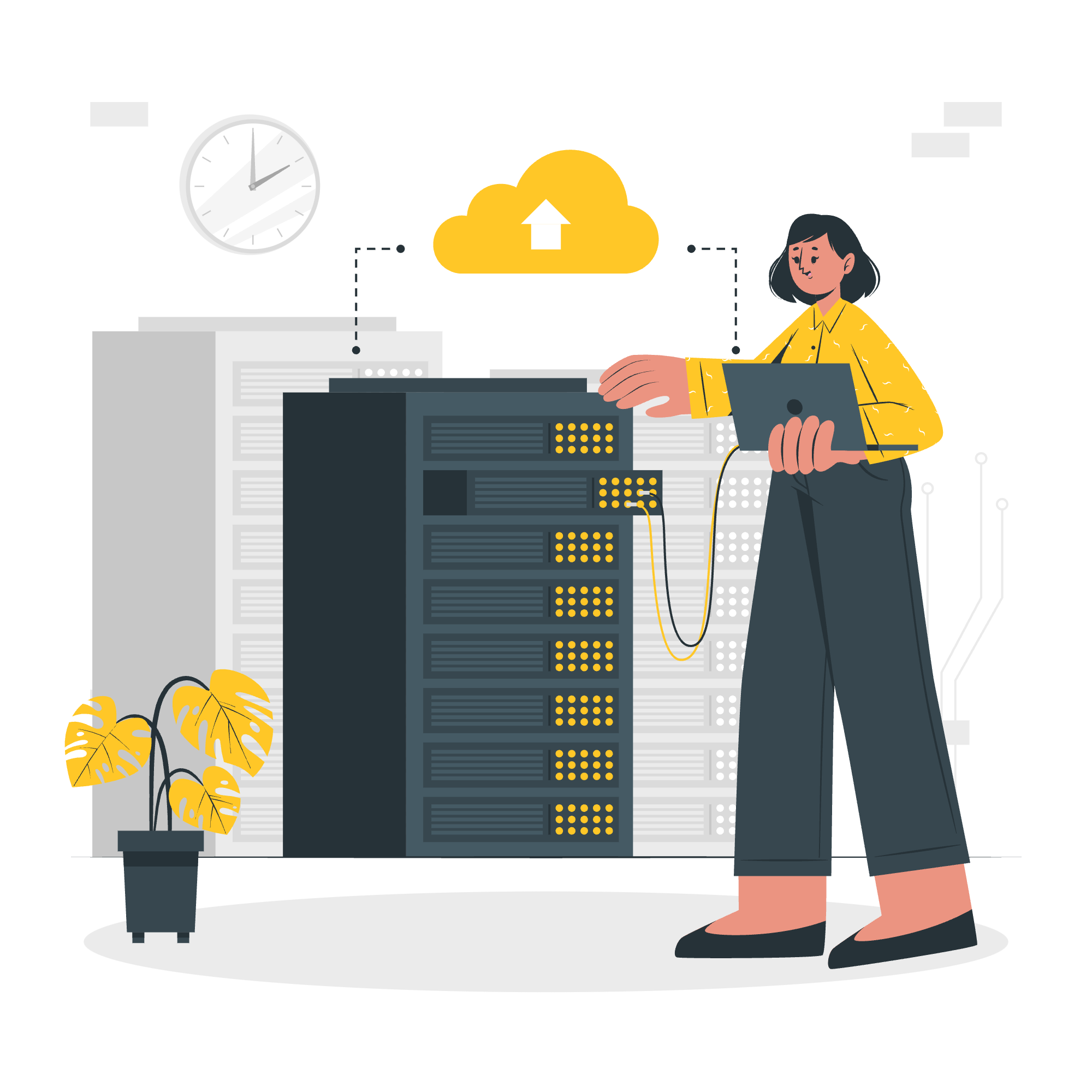
ソフトウェア開発にはウォーターフォール型やアジャイル型、プロトタイプ型といった手法があります。それぞれ特長が異なり、案件の特性に合わせて使い分けが重要です。
ウォーターフォール型
要件定義から設計、開発、テストと順を追って工程が進む手法です。手戻りが少ない反面、要件変更への対応力に乏しいデメリットがあります。大規模案件向けといえます。
ウォーターフォール型は、まず事前にしっかりと要件定義を行い、これをもとに工程ごとにフェーズを進めていく手法です。要件が固まっている大掛かりな案件向けとされています。工程が終わるごとにマイルストーンを設け、次工程に移行する前に確実にレビューを行います。
例えば、基幹システムの開発案件などは事前要件がある程度想定しやすいため、計画的に工程を進められるウォーターフォール型が向いています。反面、要件の変更に対して柔軟な対応がしづらいといった短所もあります。
ウォーターフォール型は、変化に弱いが品質は安定するという特徴があります。大規模で基本設計が固まっているようなプロジェクトに適している手法といえるでしょう。
こちらの記事では、ウォーターフォール型開発について詳しく解説しています。ぜひ、ご一読ください。
アジャイル型
小刻みに要件定義→開発→テストを繰り返し、頻繁にリリースする手法です。要件変更への柔軟性が高く、スピード重視の案件向きといえます。
アジャイル型は短期間のスプリント(開発サイクル)を連続的に回すことで、頻繁な要件反映とリリースを可能にする手法です。スプリント期間は通常2〜4週間程度とし、定期的にリリース可能な製品を出すことを目指します。
要件がまだ固まっていない段階や、変更が予想される場合に向いています。掲示板やSNSといった変化の速いサービス開発向けが適しているでしょう。反面、大規模なシステム開発には向きません。
期間が短く要件も固定しにくい、Webサービス等の開発が向いています。納期を重視するよりも、良いものを早く出すことにフォーカスした開発手法と言えます。
こちらの記事では、アジャイル型開発について詳しく解説しています。ぜひ、ご一読ください。
プロトタイプ型
まずは試作システムを開発し、実際に触って要件を確認する手法です。ユーザー要件が不明確な時に向いています。
プロトタイプ型は、まず短期間でシステムの試作版を作製します。これをユーザーに触ってもらいながら、実際の利用シーンを想定した要件定義を行っていきます。使ってみて、いろいろ改善が必要であることに気づくことも多く、要件漏れを減らすことができます。
開発したプロトタイプは一度破棄し、本番のシステム構築に移行します。プロトタイプでの要件確認をもとに、本開発の方針や設計を練り直す形です。新技術の導入検証にも向いているとされます。
一方で、コストや期間がある程度増えるデメリットがあります。要件定義と設計にあらたにプロトタイプ作成という工程が追加されるためです。
ソフトウェア開発プロセスでよくあるトラブルと解決策

ソフトウェア開発とは、万全な準備と計画の元で進められるものであっても、多くの場合思わぬ問題が発生するものです。要件定義の曖昧さや、設計上の欠陥、開発中の不具合など、様々なトラブルが頻発します。
こうした問題が生じた際、適切な対応を取らなければ手戻りや工数超過を招き、開発の失敗につながりかねません。そこで今回は、ソフトウェア開発で多くみられる代表的なトラブルと、その解決策を紹介します。未然防止に努めるとともに、もしも問題が起きた際の対処の仕方を把握しておきましょう。
仕様書の不備
要件が不足していたり、定義ミスがあることで発生します。仕様レビューを徹底して未然に防ぎましょう。
ソフト開発で最も頻発するトラブルの一つが、仕様書の内容に不備があるケースです。要件定義漏れや認識の相違により、開発後工程で方針修正が必要になることがしばしばあります。最悪の場合、当初期待した成果物が実現不可能と判明することもあります。
例えば、利用者数10万を想定した性能設計だが、実際には100万アクセス程度が見込まれる場合などです。あるいは、データ移行手法について詳細検討不足なため、複数システム間のデータ連携に失敗する場合などが考えられます。
こうした事態を避けるには、仕様書のレビューを形式的にせず、要件漏れがないかを本質から検証するプロセスが欠かせません。マネジメント側の責任で検討会を重ねる等の対応が求められます。
設計のミス
設計段階で、パフォーマンス面やセキュリティ面の考慮が不足しているケースです。レビューとテストの強化がカギです。
ソフト開発後半で発生するトラブルの多くは、基本設計時の検討不足が原因といえます。特に非機能面である性能やセキュリティを十分考慮せずに設計を組み立ててしまうことで、テスト段階や稼働後に様々な問題が噴出してしまうことがあります。
例えば、同時アクセス数に対するデータベースアクセス競合やデッドロックは、負荷テストで初めて発覚することがありえます。またセキュリティ面での脆弱性が、本番運用開始後に表面化してしまうケースも少なくありません。
このような事態を回避するには、設計フローやアーキテクチャのレビューを複数人で重ねるとともに、テスト項目・ケースを網羅的に設定しておくことが欠かせません。時間や手間を要する対応ではありますが、手戻りを減らすうえで非常に有効な手段といえるでしょう。
不具合の発生
想定外のバグやエラーが多発する事態です。 原因特定と対処に、全力を注ぎましょう。
ソフト開発でよくあるパターンとして、テスト段階や納品後の稼働で想定外の不具合が頻発してしまうケースが挙げられます。見落としていた仕様や、複雑な条件分岐が原因でバグが続出したり、サーバーやネットワークの負荷上昇に伴いシステムエラーが多発することがあります。
例えば、算出結果の桁落ちや、データ整合性が取れてなかったり、ファイルアップロード機能で想定外のフォーマットが処理できなかったりするケースが考えられます。
こうした事態への対処としては、まず原因の特定と臨時対応を最優先で実施します。並列して、根本原因の解析を行い再発防止策を練ることが欠かせません。予備機の確保など、リカバリ体制の拡充にも取り組む必要があるでしょう。
スケジュール遅延
作業量見積りミスや、要件変更が遅延の原因となります。タスクの再把握と工程見直しがポイントです。
ソフト開発の現場でよくみられるパターンとして、計画よりも作業が想定以上に遅れてしまうスケジュール遅延があります。見積りミスや、要件変更に伴う設計変更や修正が増え、結果として納期に間に合わない事態となります。
例えば、データ移行の作業量を甘く見積もっていたためにテスト期間を圧迫する、といったケースが考えられます。あるいは顧客からの変更要望が仕様に大きな影響を与え、当初のスケジュールどおりに作業を進めることが困難になってしまった、という場合も少なくありません。
この対策としては、期日に間に合わせるため工程や人員の見直しが欠かせません。業務内容を再確認し、作業工程と所要時間の再見積もりを迅速に実施し、工程計画の補強を図ることが重要です。 要件変更への柔軟な対応も同時に図っていきます。
予算オーバー
人員増や工期延長が、予算超過につながります。作業範囲の絞り込みと精査がカギです。
ソフト開発プロジェクトでは、スケジュール遅延に伴って予算も当初の見積りを超えてしまうケースがよくみられます。開発体制の拡大や、テスト期間の延長が人件費や稼働コストの増大につながり、結果的に予算オーバーを招いてしまいます。
例えば、テスト工程で多数の重大な不具合が発見され、開発側の人員を増強せざるを得なくなったために、予定の1.5倍のコストが必要になってしまったというようなケースです。
この対策としては、まず現時点での予算超過がどの程度かを正確に把握し、残工程の作業範囲を見直す必要があります。顧客との交渉のうえで、要件の優先順位付けを行い、可能な限り削減できる工程を絞り込んでいく等の対応が欠かせません。工数やリソースをある程度ひっ迫させる覚悟も必要でしょう。
まとめ:ソフトウェア開発プロセスは成功のコツ
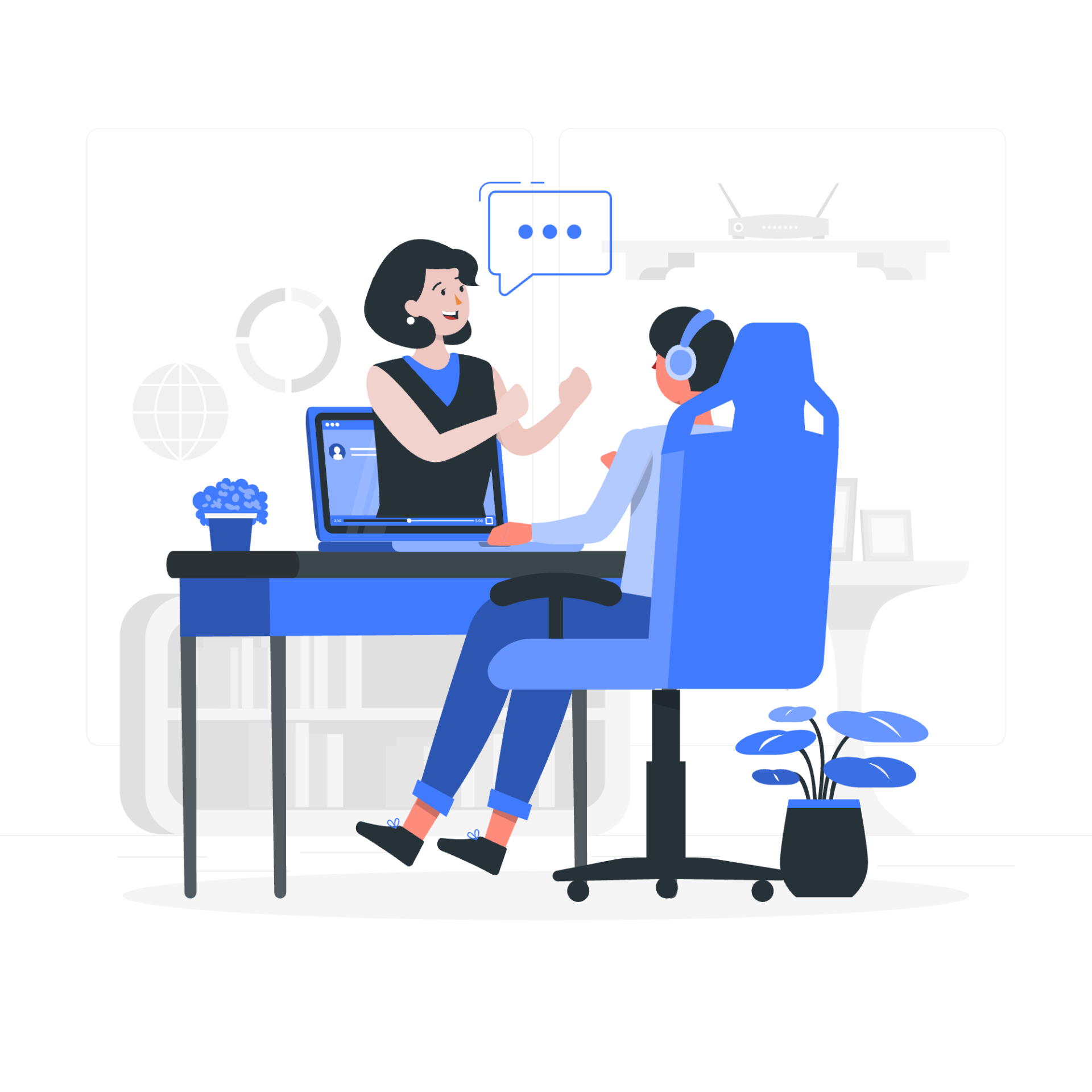
ソフトウェア開発時にはプロジェクト成功に向けたプロセスを立てていくことによって、成功確率を高めることができます。
品質向上を見込めるソフトウェア開発を進めることができ、コミュニケーションをチーム内で取りながらスムーズに効率よく開発を進めていきましょう。
ただプロセス設計はプロジェクト規模やメンバーや開発の種類を考えながら、効率よく活用することが重要です。
よりよいソフトウェアを開発するために、トラブルが起きた際の迅速な対応も考えておきましょう。
もしもソフトウェア開発において悩みがあり、ご相談やご依頼があれば株式会社Jiteraにお問い合わせください。様々な知見や情報を持っているので、最適な解決策をご提案いたします。