センサ(Sensor)は私たちの生活に欠かせない技術であり、IoT(モノのインターネット)の発展とともにその重要性が増しています。しかし、センサの仕組みや種類、活用方法については、よく分からないという方も多いでしょう。
本記事では、センサの基本的な定義から、IoTでの具体的な利用例まで、分かりやすく解説します。技術的な内容も平易な言葉で説明するので、専門知識がなくても理解できます。
制御系システムや自動化システムの新規開発を中心に、15年以上の開発経験を持つ現役エンジニアです。『デジタルは人と人をつなぐもの』という言葉が好きです。デジタルの世界をわかりやすく伝えていきます。
センサとは

センサ(Sensor)は、私たちの周りの変化を検知し、その情報を電気信号に変える装置です。人間の五感に例えると理解しやすいでしょう。
センサの基本概念について以下の表にまとめてみました。
| 項目 | 説明 |
| センサの基本 | ・センサは温度、音、光、圧力、湿度などの環境の変化を感知します。 ・感知した情報を電気信号に変換し、他の機器に伝えます。 |
| 身近な例 | ・スマートフォンの画面:指のタッチを感知し、アプリを起動します。 ・自動ドア:人の接近を感知し、ドアを開きます。 |
| センサの働き方 | ・センサ単体では特定の行動を起こしません。 ・検知した情報を他の機器に伝え、そこで処理されて初めて役立ちます。 |
| 人間の感覚との類似性 | ・目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、皮膚(触覚)は人間のセンサと言えます。 ・これらの感覚器官が外界の情報を脳に伝え、脳が反応するのと同じ仕組みです。 |
| 産業での活用例 | ・製造業:製品の品質管理 ・医療:患者の健康状態モニタリング ・農業:作物の生育環境の管理 ・スマートホーム:家電の自動制御 |
センサは、私たちの生活や産業の様々な場面で使われ、自動化や効率化に貢献しています。その仕組みを理解することで、身の回りの技術をより深く知ることができます。
【簡単解説】センサの仕組み

私たちの周りには、目に見えなくても多くのセンサが働いています。スマートフォンの画面が回転したり、自動ドアが開いたりするのも、すべてセンサのおかげです。では、センサはどのように働き、私たちの生活やIoT(Internet of Things:インターネットにつながるモノ)の世界でどう活用されているのでしょうか?
センサの仕組みについてみて詳しくみていきましょう。
1. 物理量の検出
センサの仕事は、まず周りの環境の変化を感じ取ることから始まります。この変化のことを「物理量」と呼びます。
【センサタイプと検出物理量】

それぞれの物理量に対応するセンサがあり、その特性に応じて検出を行います。例えば、温度センサの一種である熱電対は、金属の接合部で温度差が生じると電圧が発生する「ゼーベック効果」を利用しています。
2. 変換
センサが検出した物理量を電気信号に変換する過程は、センサの動作において極めて重要です。この変換プロセスは以下のように行われます。
【センサの変換プロセス】

この変換過程により、物理的な現象が測定可能な電気信号となります。例えば、熱電対を使用した温度センサでは、異なる金属の接合部での温度差によって生じる熱起電力(ゼーベック効果)を利用して温度を電圧に変換します。一方、フォトダイオードを用いた光センサでは、入射光によって生じる電子-正孔対が電流を生成し、光強度を電流に変換します。
3.信号処理
変換された電気信号は、そのままでは使用できないことが多いため、以下のような信号処理を経て有用な情報となります。
【センサの信号処理】

例えば、温度センサでは熱ノイズの除去が重要となり、光センサでは環境光によるノイズの除去が必要になります。また、両方のセンサで、最終的にはデジタル値として温度や光強度が出力されます。
4. 出力とインターフェース
処理された信号は、他の機器やシステムに送られます。この段階で、センサが検出した情報が実際に役立つ形になります。
| 出力の形式 | 説明 |
| アナログ出力 | 連続的に変化する電圧や電流 |
| デジタル出力 | 0と1の組み合わせ(バイナリ) |
| シリアル通信 | RS-232、USBなどを使用したデータ送信 |
| 無線通信 | Wi-Fi、Bluetoothなどを利用 |
例えば、温度センサが高温を検出した場合
- エアコンのコントローラーに信号を送り、冷房を作動させる
- 工場の生産ラインで、製品の品質管理システムにデータを送る
- スマートフォンアプリに温度データを送信し、ユーザーに通知する
このように、センサの出力とインターフェースは、物理的な現象を検知してから実際に有用な行動や情報として活用されるまでの最後の重要な段階です。適切な出力形式とインターフェースを選択することで、センサは様々なシステムやアプリケーションと効果的に連携し、私たちの生活やビジネスにおいて重要な役割を果たすことができます。
種類別センサの特徴と活用

センサには様々な種類があり、それぞれが異なる物理量を検出し、私たちの生活や産業に役立てられています。これらのセンサは、単独で使用されることもありますが、多くの場合、複数のセンサを組み合わせることで、より高度な機能を実現しています。
例えば、スマートフォンには、上記のセンサの多くが搭載されており、それらが連携して動作することで、私たちの日常生活をより便利にしています。
本章では、代表的なセンサの特徴と具体的な活用例を、わかりやすく紹介します。
温度センサの特徴と例
温度センサとは、周囲の温度を検出し、電気信号に変換するセンサです。
<具体例>
- エアコンの室温制御
- 冷蔵庫の温度管理
- 工場での機械の過熱検知
温度センサは、快適な環境維持や安全管理に欠かせない重要な役割を果たしています。
湿度センサの特徴と例
湿度センサとは、空気中の水分量(湿度)を測定するセンサです。
<具体例>
- 気象観測装置
- 空調システムの湿度制御
- 食品保存庫の湿度管理
湿度センサは、快適性や品質管理において重要な役割を担っています。
圧力センサの特徴と例
圧力センサとは、物体にかかる力や圧力を検出するセンサです。
<具体例>
- タイヤの空気圧モニタリング
- 血圧計
- 産業用機器の圧力制御
圧力センサは、安全性の確保や精密な制御に広く活用されています。
光センサの特徴と例
光センサとは、光の強さや色を検出するセンサです。
<具体例>
- スマートフォンの画面の明るさ自動調整
- 自動ドアの人感知
- カメラの自動露出制御
光センサは、省エネや利便性向上、画像品質の改善などに貢献しています。
音声センサの特徴と例
音声センサとは、音の大きさや周波数を検出するセンサです。
<具体例>
- スマートスピーカーの音声認識
- 騒音計
- 楽器の音程チューナー
音声センサは、コミュニケーション技術や音響環境の改善に重要な役割を果たしています。
加速度センサの特徴と例
加速度センサとは、物体の動きや傾きを検出するセンサです。
<具体例>
- スマートフォンの画面回転
- 自動車のエアバッグ作動制御
- フィットネストラッカーの歩数計測
加速度センサは、デバイスの操作性向上や安全性確保、健康管理に幅広く利用されています。
生体センサの特徴と例
生体センサとは、人体の様々な生理的情報を検出するセンサです。
<具体例>
- 指紋認証センサ
- 心拍数モニター
- 血糖値測定器
生体センサは、セキュリティ強化や健康管理、医療分野で重要な役割を担っています。
磁気センサの特徴と例
磁気センサとは、磁場の強さや方向を検出するセンサです。
<具体例>
- コンパス(方位磁針)アプリ
- 電子決済端末のカード検知
- 自動車の車輪回転数検出
磁気センサは、位置情報の取得や非接触での検出に広く活用されています。
IoTにおけるセンサのメリット

IoT(Internet of Things)の世界では、センサが重要な役割を果たしています。これらのセンサは、私たちの生活やビジネスに革新をもたらし、効率性や利便性を大幅に向上させているのです。
本章では、IoTにおけるセンサの主要なメリットについて、わかりやすく解説します。
リアルタイムでデータ収集ができる
センサを活用することで、環境や機器の状態をリアルタイムで把握することができます。これにより、即座に対応が必要な状況を素早く認識し、適切な行動を取ることが可能になります。

例えば、製造ラインでの品質管理や、農業における作物の生育状況のモニタリングなど、様々な分野でリアルタイムデータ収集が活用されています。これにより、問題の早期発見や迅速な対応が可能となり、生産性の向上や品質の改善につながっています。遠隔監視と制御ができる
遠隔監視と制御ができる
IoTセンサを使用することで、物理的な場所に縛られずに、遠隔地からシステムや機器を監視・制御することができます。これは特に、広範囲に分散したシステムの管理や、危険な環境下での作業において大きな利点となります。

例えば、スマートホームシステムでは、外出先からスマートフォンを使って家電を操作したり、セキュリティカメラの映像を確認したりすることができます。また、産業分野では、遠隔地にある設備の状態を監視し、必要に応じて調整を行うことが可能になっています。
安全性とセキュリティの向上ができる
IoTセンサは、安全性とセキュリティの向上にも大きく貢献します。異常な状態や不審な動きを迅速に検知し、適切な対応を取ることができるため、事故や犯罪の予防に役立ちます。

例えば、工場での危険ガスの検知や、ビルのセキュリティシステムにおける不正侵入の検知など、IoTセンサは様々な場面で安全性とセキュリティの確保に貢献しています。これにより、人々の生命や財産を守り、安心して生活や仕事ができる環境を実現しています。
新しいビジネスモデルに活用できる
IoTセンサから得られるデータは、新しいビジネスモデルの創出や既存ビジネスの改革にも活用できます。顧客の行動パターンや製品の使用状況など、これまで把握が難しかった情報を収集・分析することで、より価値の高いサービスを提供することが可能になります。

例えば、自動車業界では、車両に搭載されたセンサーからのデータを活用して、ユーザーの運転習慣に基づいた保険料の設定や、予防的なメンテナンスサービスの提供などが行われています。また、小売業では、店舗内の顧客の動きを分析して、商品配置の最適化や個別化されたマーケティングを実現しています。
センサを使ったIoTシステムの開発手順
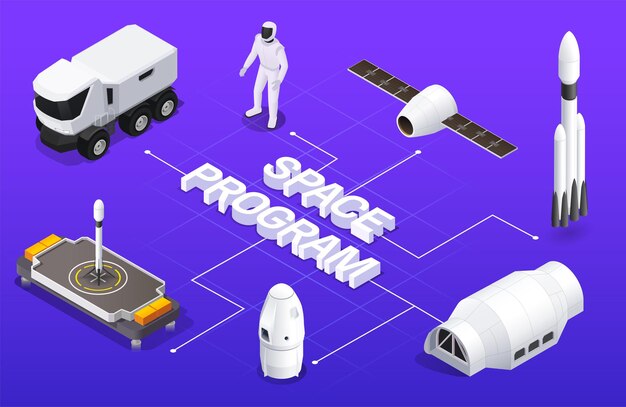
次に、IoTシステムを開発する際の手順についてみていきましょう。以下のステップで開発を進めることになります。
- センサ選定とデータ収集
- センサデータの送信方法を決定
- データ分析とアクション
- 開発環境を構築
- プロトタイピング・テスト
- 運用・保守
センサ選定とデータ収集
まず、IoTシステムの構築に必要なセンサを選びます。前述したように、センサには多種多様なものがあります。適切なセンサを選択することでユーザビリティが向上したり、コストカットができたりするため、入念にセンサを選ばなければなりません。
また、センサで収集したデータをどのように保存しておくのかも事前に決定しておきましょう。クラウド上に保管しておくのか、ローカルのサーバーに保管しておくのか、そして、セキュリティ対策はどうするのかなどについてもこの段階で考えておくことが大切です。
センサデータの送信方法を決定
センサデータの送信方法については、以下の方式があります。
- USB通信
- RS-232C通信
- アナログ電圧信号
- 無線通信
IoTでデータを収集する場合には、USBでパソコンに繋いでもらい、そこから収集するか、無線通信を使ってデータを収集するのが基本です。
データ分析とアクション
データが送信された後の分析方法についても開発段階から考えておきましょう。デバイスがどのようなセンサを搭載しているかによっても変わりますが、温度、湿度、音、振動、位置情報などのデータを収集することになります。
- 収集したデータの相関関係はあるか
- 特定の条件下で同じ行動をしていないか
- 具体的な行動はなくとも、隠れたサインが発生していないか
この収集したデータに対して、上記のような切り口で考えていくことで、機器の利便性を向上させられます。
開発環境を構築
上記で収集したデータと分析結果を自動で収集できる仕組みを作っておくと、効率的にIoT開発が進められます。サービスを提供する前に、開発できる体制を整えておきましょう。
また、中にはAIや機械学習を用いて分析ができるツールもあり、そちらを活用することで、自動化を有利に進められます。詳しくは代理店などに相談すると理解が深まるはずです。
プロトタイピング・テスト
開発環境が整ったらプロトタイプを作成し、テストを行います。
- センサが正確にデータを収集
- 適切に電気信号に変換されているかを確認
- データが通信方式を通じて正しく送信され、受信されているかをチェック
- 収集されたデータが正確に分析され、適切なアクションが引き起こされているかも検証
これらのステップが円滑に進めば、本番環境でもトラブルが起こりづらいと考えられます。
運用・保守
最後に、運用・保守体制を整えます。システムのパフォーマンスはデータ量・ユーザーの増加によって低下していくことが予想されるため、定期的にチェックをしなければなりません。
また、技術の進歩やシステムの必要性に応じて、アップデートも行いましょう。システムを常に最新の状態を保つことで、最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。
IoTに最適なセンサの選び方

IoTプロジェクトにおけるセンサの選択は非常に重要な要素です。適切なセンサの選択は、プロジェクトの成功に大きな影響を与えるため、入念に選ばなければなりません。
ここでは、センサを選択する選び方について紹介します。
収集したいデータは何か
まず最初に、どの種類のデータを収集したいのかを明確に定義します。温度、湿度、位置情報など、収集したいデータの種類によって選ばなければなりません。
まずは、開発したいIoT機器がどのような特性のもので、どんな情報を必要とするのかを考えましょう。エアコンを開発するなら温度・湿度センサが必要ですし、スマートホームを開発するなら音・位置情報などのセンサが必要です。
使用環境に耐えられるか
センサが使用される環境は、その選択に大きな影響を与えます。例えば、屋内で使用する場合、気温や湿度の変動が少ない環境に対応したセンサを選ぶことが必要です。一方、屋外で使用する場合はそれらの環境でも機能を発揮する耐久性を持つセンサが必要になります。
屋内で温度センサの使用を考えた場合、一般的な室温範囲に対応すれば問題ありません。日本の場合は余裕を持って-10〜40度付近での使用を前提とすれば基本は問題ないでしょう。
しかし、屋外や生活環境と異なる温度での使用を前提とする場合、その厳しい環境に耐えられるようなセンサが必要となります。使用される環境を考慮して適切なセンサを選択することで、正確な情報を収集でき、求めているパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
電源方式・通信方式はニーズに合っているか
電源供給の方法や通信方式も重要な要素です。まず、電源についてはバッテリー供給か電線供給かなどから選ぶ必要があります。
バッテリーの場合は突然、停電が発生したとしてもしばらくの間は使用できるため、災害時でも重要な役割を担う機器におすすめです。ただし、バッテリー方式の方がかかるコストは大きくなりがちです。
また、通信には一般的に以下3つの方式があります。
- USB通信
- RS-232C通信
- アナログ電圧信号
- 無線通信
詳細は省きますが、各通信方式によって通信速度や精度に違いがあるため、センサを導入する際はこの点にも注意して選ばなければなりません。
予算内に収まるコストか
最後に、非常に重要なポイントとしてコストが挙げられます。プロジェクトの予算が限られている中で、最もコストパフォーマンスが高く、同時に効果を出すセンサを選択することが求められます。
IoT製品を開発する場合には、お客様が手を出しやすい価格で提供する必要があるでしょう。仮に、温度センサを搭載したIoTエアコンを開発する際、人間が快適に過ごせる範囲の温度検知機能を持っていれば、エアコンとして機能します。
極端な例ですが、−100度を検知する必要はないわけです。しかし、あまり考えずにそのようなセンサを採用してしまうと、その分コストがかかってしまいます。
事前に製造にかかるコストを洗い出し、センサにはどの程度かけるべきかを考えて導入することが大切です。
データ出力形式はシステムと互換性があるか
センサが収集したデータを効果的に活用するためには、そのデータ形式が既存のシステムやソフトウェアと適合している必要があります。
センサのデータ出力形式には、デジタル出力やアナログ出力、特定のプロトコル(MQTT、CoAP、HTTPなど)があります。また、データの精度や更新頻度も考慮すべき点です。例えば、既存のシステムがJSON形式のデータを扱っている場合、JSON出力に対応したセンサを選択することで、データの統合がより容易になります。
互換性のないセンサを選択すると、データの変換や追加のハードウェア・ソフトウェアが必要になり、コストや複雑性が増大する可能性があります。適切なデータ出力形式を持つセンサを選択することで、システム全体の効率性と拡張性が向上し、長期的なコスト削減にもつながります。そのため、センサ選びの際には、データ形式の互換性を慎重に検討することが重要です。
まとめ:センサを活用してIoTを促進

センサは、IoTの世界で欠かすことのできない存在です。現実世界からの情報をデジタルデータに変換し、異なるデバイス間で情報を共有することで、機器の利便性が高まっていきます。
今回ご紹介したセンサの種類や特徴、選択のポイント、IoTシステムの開発手順を理解し、実践することで、IoTプロジェクトを成功に導けるでしょう。少し専門的な内容もあったと思いますので、わからなくなったら何度も確認してみてください。
また、今回ご紹介したセンサについて、不明点や疑問、相談、依頼などございましたら、IT業界で経験豊富な株式会社Jiteraにご相談ください。お悩みを解決するとともに、お客様のビジネスをしっかりとお聞きし、最適な内容を提案させていただきます。










