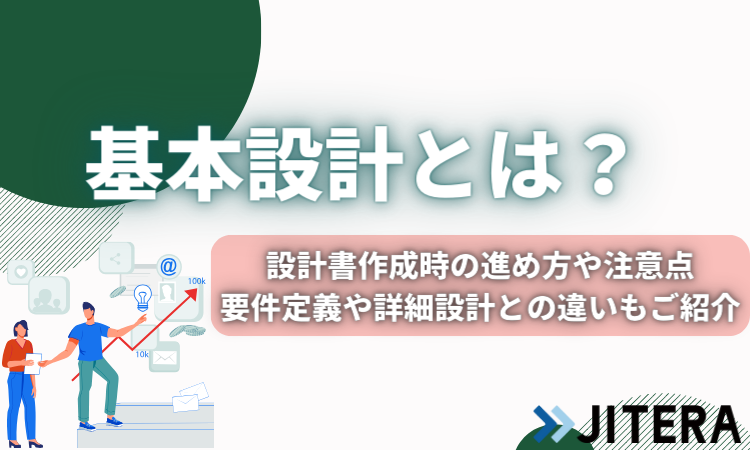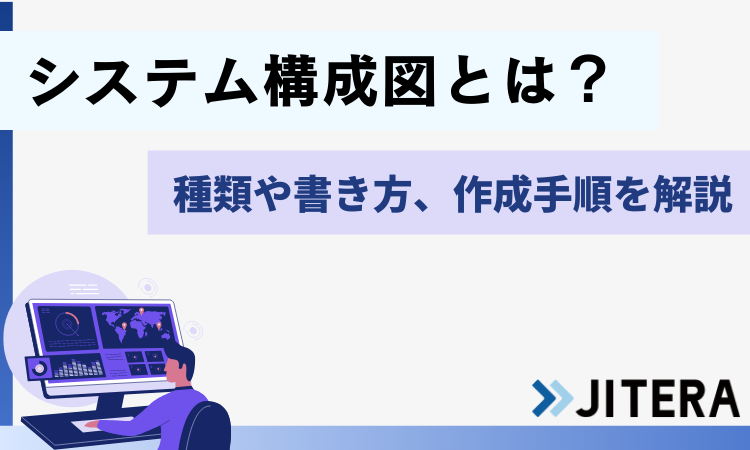システム設計書はシステム開発の全体像はもちろん、詳細部分まで細かく記載した設計書です。
開発に関わる全員が、このシステム設計書をもとに開発を進めていくため、非常に重要となります。
この記事では、システム設計書を作成するメリットや書き方のコツ、おすすめのツールなどについて詳しくご紹介します。
高校からHTML/CSS/COBOL/C++/Rubyに触れ、システム管理やCMSなど幅広く網羅。建築士から転身し、Webメディアの制作を主軸とした会社を設立。ITパスポート所有。趣味は建築物巡り。
システム設計書とは

システム設計書とは、システムをどのように開発するかを具体的にまとめたものです。
システムの構造やデータの流れ、各機能の詳しい説明が含まれており、開発チームがスムーズに作業を進めるための大切なドキュメントです。
ここでは、システム設計書の概要について詳しくご紹介します。
システム開発の流れ
システム開発は、いくつかのステップを踏んで進めていきます。
最初に要件定義を行い、システムにどんな機能が必要かを決定します。その次に基本設計で、システムの大まかな形を考えます。
さらに細かい部分を決める詳細設計を行い、それをもとに開発・実装によってプログラムを作ります。
作ったシステムが正常に動くかをテストして、最後に運用として実際に使える状態にします。この流れがスムーズにいくと、使いやすいシステムの完成です。
システム設計書がなぜ必要なのか
システム設計書は、システムを作る上で方向性を示すための重要な書類です。
設計書には、システムがどう動くかや、どんな機能があるかが分かりやすく書かれています。
これによって、開発に関わる人たちが同じ理解を持って作業を進められるのです。また、システムが完成した後も、保守や新しい機能を追加するときに設計書を見て対応できます。
つまり、設計書があれば、開発に関わるすべての関係者が迷わずシステムを作り、運用後も安心して管理できるのです。
設計書は誰が作るのか
システム設計書を作るのは、主にAIエンジニアやアーキテクトと呼ばれる開発者です。
最初に決めた要件をもとに、システムの基本的な構造から細かい部分までを考えて書きます。
この設計書は、開発チームなどの開発者と共有され、システムを正しく動作するために使われます。
大きなプロジェクトでは、複数のメンバーが協力して設計書を作り、一つにまとめていくこともあります。
AIエンジニアになる方法や必要な資格、将来性についてはこちらの記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
システム設計書と要求仕様書の違い

システム設計書と要求仕様書は、どちらもシステム開発において重要な書類ですが、役割が違います。
要求仕様書は、ユーザーやクライアントが何をしてほしいかというシステムの機能や性能をまとめたものです。
例えば、どんな機能が必要か、システムがどのように動くべきかをはっきりさせます。
一方でシステム設計書は、その要求をもとにどうやってシステムを作るかを設計します。
システムの構造や機能、データの流れなどが詳しく書かれ、開発者がそれを見ながらシステムを作ります。
つまり、要求仕様書は「何を作るか」、システム設計書は「どう作るか」を示す資料です。
| 項目 | システム設計書 | 要求仕様書 |
| 目的 | システム全体の設計・実装に関する方向性を示す | ユーザーやクライアントのニーズを明確にし、開発するシステムの範囲や目的を定義 |
| 記載する内容 | システムの構造、機能、データフロー、技術仕様など詳細な設計内容 | システムが実現すべき機能や性能、制約条件などの概要 |
| 作成者 | システムエンジニア、アーキテクト | プロジェクトマネージャー、顧客 |
| 作成するタイミング | 要件定義後、設計フェーズで作成 | プロジェクトの最初段階で作成 |
基本設計については以下の記事で解説しているので、こちらもご覧ください。
システム設計書を作成する目的

システム設計書を作成することで、メリットがいくつか生まれます。
設計書があることで、開発の無駄が減ってコストを削減できたり、責任が明確になるため開発がスムーズに進んだりします。
また、設計書にはシステムの詳細が書かれているため、後から機能を追加したり修正したりする場合にも役立ちます。
ここでは、システム設計書を作成するメリットをご紹介します。
開発コストを削減する
システム設計書があることで開発の無駄を減らすことができ、結果的にコストを削減できます。
設計書には、システムの動き方や機能が詳しく書かれているので、開発者は迷うことなく作業を進められます。
これにより、やり直しや修正が少なくなり、効率よく進められるのです。また、問題が早い段階で見つかるので、後から大きな変更に時間を取られるリスクも減らせます。
そのため、計画的で無駄のない開発ができ、コストの削減につながるのです。
責任範囲を明確にする
システム設計書を作成することで、誰がどの部分を担当しているかがはっきりと分かるようになります。
設計書には、それぞれのメンバーがどの部分を担当するかが明記されているため、作業がスムーズに進みます。
また、責任が明確になることで作業の重複や混乱を避けることができ、効率的に仕事を分担できます。
さらに、問題が起きたときも担当者がすぐに対応できるため、プロジェクト全体の進行が止まることなく進められるでしょう。
チームメンバーの情報共有を促進する
システム設計書は、チームのメンバー同士が情報を共有するために必要です。
設計書には、システムの全体像や細かな機能がしっかり書かれているため、メンバー全員が同じ情報を持って開発に取り組めます。
意思の行き違いや勘違いによるトラブルを減らすことができるため、チーム全体の連携がよくなります。
システム設計書の書き方

システム設計書を書くときは、まずシステムの目的や全体の流れを明確にして、その後で細かい部分に進むことが大切です。
各コンポーネントやデータの流れを整理し、わかりやすく書くことを心がけましょう。
ここでは、書き方について深掘りして詳しく解説します。
システムの目的や適用範囲を明確にする
システム設計書を作る時は、システムの目的と適用範囲を明確にすることが重要です。
システムが何のために作られるのか、誰が使うのか、どんな業務をサポートするのかを明確にすることでシステムの全体像がっきりし、目標が統一されます。
また、適用範囲を決めておくことで、後の開発で範囲外の作業が発生することを防ぎ、計画的な進行が可能となります。
機能要件と非機能要件にリスト化する
システム設計書には、システムが持つべき機能要件と非機能要件をリスト化することが重要です。
- 機能要件:システムが提供する具体的な機能(例:ユーザー登録、データ検索など)を定義
- 非機能要件:システムの性能やセキュリティ、可用性などの技術的な条件を定義
これらをリスト化することで、開発チームが必要な作業を正確に把握でき、要件漏れや誤解を防ぐことができます。
また、優先順位をつけることで、効率的な開発も進めやすくなります。
システム構成やフローを図解で説明する
システム設計書では、システムの全体構成やデータフローを図解で説明することも重要です。
図を使うことで、システムの動きや各コンポーネントの関係性が一目でわかりやすくなります。
データの流れを示すフローチャートや、システムの構造を示すアーキテクチャ図を使うと、複雑な仕組みも簡単に理解できます。
図を取り入れることで、チーム内での共有がスムーズになり、開発の各ステップがより明確になるでしょう。
各コンポーネントの仕様やデータベース設計を詳細化する
システム設計書にはシステムを構成する各コンポーネントの仕様やデータベース設計を詳細に記載する必要があります。
コンポーネントごとに役割や動作を細かく定義し、どう連携するかを明確にします。
また、データベース設計ではどのデータがどこに保存され、どのようにアクセスされるかを詳細に説明します。
これにより、開発者が具体的な開発作業に入る際、スムーズに進められるだけでなく、後の保守や拡張にも役立たせることが可能です。
各設計書のレビューを行う
システム設計書が完成したら、必ずレビューを行いましょう。
レビューでは、設計書に誤りがないか、要件を満たしているかを確認する必要があります。
チーム内で複数のメンバーが目を通すことで、見落としや誤解を防ぎ、品質を高めることが可能です。
また、開発者だけでなく、テスト担当者や他のメンバーにもレビューを依頼することで、システム全体を俯瞰した視点からの評価が得られ、設計の精度を高めることができます。
システム設計書を書くときに使える便利なツール4選

システム設計書を作成する時に、便利なツールを活用することで自動的に、また簡単にシステム設計書の作成が可能です。
ここでは、おすすめのツールを4つご紹介します。
Jitera

Jiteraは、システム設計書の作成を大幅に効率化できるツールです。
データベースやAPI、画面項目、ビジネスロジックの設計を自動で行ってくれる機能が便利です。
さらに、既存のシステムコードを読み取って、5分以内にシステム設計書を自動生成できるため、ドキュメント作成にかかる時間を大きく短縮できます。
また、ソフトウェア開発の各ステップを自動化して、作業をスピードアップができるため、プロジェクト全体の進行が早くなり、コスト削減にもつながります。
設計だけでなく、コード生成までサポートしてくれるので、開発者なら導入しておきたいツールです。
draw.io

draw.ioは、インストール不要で使える図表作成ツールです。
フローチャートや組織図、ネットワーク構成図、ER図など、さまざまな図を簡単に作成できます。
四角や矢印、人型の図形など、豊富な素材が用意されており、直感的に操作できるので、初心者でも使いやすいでしょう。
GoogleドライブやGitHubと連携して保存できるので、チームでの共同作業にも役立つ便利なツールです。
gliffy

gliffyは、オンラインで簡単に図を作成できるツールです。
ネットワーク図やフローチャート、UMLなど、さまざまな図を手軽に作成でき、特にConfluenceやJiraと連携して使うことで、開発チームのコミュニケーションがスムーズになります。
ドラッグ&ドロップで簡単に図を作れるので、初心者でもすぐに使いこなせるでしょう。
リアルタイムでの共同作業にも対応しているため、チームで効率よく作業を進められます。
Inkpod

Inkpodは、マインドマップや構造図、概念図、フローチャートなど、さまざまな図を作れるツールです。
作成した図をJavaScriptなどで処理できるため、カスタマイズの自由度が高い点も魅力です。
さらに、自分でアプリケーションを作ることで、Inkpodの機能を拡張することもできます。
簡単に多彩な図を作成できるため、楽しく設計作業を進めることができます。
システムの全体を表すシステム構成図については以下の記事で解説しているため、こちらもご覧ください。
システム設計書を作成する3つのコツ

システム設計書を書くときには、コツがあります。
まず、最初に全体の概要を示してから、詳細を説明することでわかりやすくなります。
次に、用語や表現を統一して、読み手にとって理解しやすい内容にしましょう。
このように一つ一つ丁寧に行うことで、開発しやすい設計書が完成します。
ここでは、3つのコツについて以下を詳しくご紹介します。
- 全体像を示してから詳細を説明する
- 用語や主語を統一して説明する
- クラウドベースで共同作業できるツールを利用する
全体像を示してから詳細を説明する
システム設計書を書くときは、まずシステム全体の概要を示してから、細かい部分の説明に入ります。
最初に全体の流れや構造を見せることで、読む人がシステム全体を理解しやすくなるのです。
全体像が分かると、各部分がどうつながっているかが見えてくるので、詳細な説明もスムーズに進みます。
複雑なシステムの場合、最初に全体を把握することで、関係者全員が同じイメージを共有しやすくなります。
用語や主語を統一して説明する
システム設計書では、使う用語や主語を統一することが非常に重要です。
違う言葉を使って同じことを説明すると、読む人が混乱したり、誤解が生まれたりすることがあります。
多くの人が関わるプロジェクトでは、用語が統一されていることで、全員が同じ理解を持つことができます。
また、主語を明確にすることで、誰がどの部分を担当しているのかや、システムがどのように動くかを分かりやすく説明できます。
クラウドベースで共同作業できるツールを利用する
システム設計書を作るときは、クラウドベースのツールを使うと非常に便利です。
クラウドツールを使えば、複数のメンバーが同時に設計書にアクセスして、一緒に編集やコメントを加えることができます。
また、変更履歴が自動的に管理されるので、間違いがあってもすぐに修正でき、以前のバージョンと比較することも簡単です。
システム設計書の要素

システム設計書には、システムを正しく動かすために必要な要素がたくさん含まれています。
たとえば、画面遷移図やデータベースの設計、システム同士の通信の流れやAPIの仕様などが挙げられます。
ここでは、システム設計書に含まれる定義や設計などについて詳しくご紹介します。
要件定義
要件定義では、システムを作る上で何を作るのかをはっきりさせます。
具体的には以下の内容を決めていきます。
- どんな機能を必要としているか
- どんな画面が必要か
- どんな操作ができるようにするか
この段階で、システムの全体像が見えてくるため、これを元に設計や開発が進んでいきます。
要件定義がしっかりしていると、後の作業もスムーズです。
方式設計
方式設計では、システムがどのように動くかを考えます。
使うコンピューターやソフトウェアを決めたり、データのやり取りをどうするかを考えたりします。
開発内容によっては、クラウドを使うのか、サーバーをどう配置するのかなどの技術的な部分の決定も必要です。
基本設計
基本設計は、システムの大まかな仕組みを決める段階です。
システム全体の構造や使いやすさを考えます。データはどのように保存するかなど、システムを作るための土台を作ります。
この基本設計がしっかりしていると、開発が進んでも大きな変更が少なくなるため、開発の戻りがありません。
システムの使い勝手や見た目もこの段階で決まっていきます。
機能設計
機能設計では、システムがどんな機能を持っているかを細かく決めます。
具体的には以下のアクションを検討します。
- ボタンを押すと何が起こるのか
- データがどう処理されるのか
機能設計がしっかりしていると、完成後にユーザーが使いやすいシステムが出来上がります。
細かい部分まで決めることで、開発が順調に進むだけでなく、システム開発中のトラブルも少なくなります。
詳細設計
詳細設計は、システムの動きやデータの扱いをさらに細かく決める段階です。
ここでは、プログラムがどう動くかや、データベースにどんな情報を入れるかなど、より具体的な作業が進められます。
詳細設計は、開発者がプログラムを書くための設計図のようなもので、正確にシステムを作るために必要です。
しっかりとした詳細設計ができれば、あとで問題が起こりにくくなります。
システム設計書のサンプル

令和時代の設計書の基本方針 | Think IT(シンクイット)
システム設計書では、上記の画像のような設計書を作成していきます。
「システム設計書を書くときに使える便利なツール4選」でご紹介したdraw.ioやgliffyなどの作図ツールを使うと、右上の関連図を作成できます。
このような設計図を作成して一つの設計書としてまとめることで、迷いや戻りのない開発が可能です。
システム設計書は、検索するとExcelやWordで作成できるサンプルが見つけられるので、開発チームに合ったフォーマットをダウンロードして作成してみてください。
システム設計書のまとめ

この記事では、システム設計書の概要やメリット、書き方などについて詳しく解説しました。
システム設計書を作成することで開発全体がスムーズになるため、チーム全員でより良い開発を目指せます。
また、ツールを活用することで設計書を簡単に作成することが可能です。
ツールの一つ「Jitera」は要件定義をはじめ、データベースや画面項目の設計をAIにサポートしてもらえます。
Jiteraの導入や、その他AIに関するお困りごとは、ぜひ株式会社Jiteraにご相談ください。
AIを活用して、さらに効率的で質の高いシステムの開発を目指しましょう。