製品開発を進めるにあたって、重要な役割を果たすのが「製品ロードマップ」。
製品ロードマップを適切に作成できれば、プロジェクトをより効率的に進められます。
この記事では、製品ロードマップの目的や書き方、作成のコツについて解説します。
おすすめの専用ツールも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【得意な分野・言語】QA(品質保証)/ テスト自動化開発(Python、Node.js)/ Google Apps Script【主な実績】20年のQA業界経験(現職)【役職】エンジニア / Developers Summit 2024 SummerとDevelopers Summit 2024 KANSAIで登壇
製品ロードマップとは

製品ロードマップとは、製品のビジョンや戦略、開発のプロセスを時系列でまとめたものです。
製品のあるべき姿を明確にしたり、開発の方針や進捗をチーム内で共有したりする目的で用いられます。
似たような言葉として「プロダクトロードマップ」もありますが、製品ロードマップとは対象となる製品の範囲が異なります。
プロダクトロードマップは、ソフトウェア製品やサービスに対して多く用いられる用語です。
そのため、機能追加やバグの修正、新しいバージョンのリリースも考慮し計画が行われます。
一方、製品ロードマップはソフトウェア製品に限らず、幅広い製品に対して用いられます。
つまり、プロダクトロードマップは製品ロードマップの一種といえるでしょう。
また、よく製品ロードマップと比較されるものとして「マイルストーン」がありますが、製品ロードマップとマイルストーンとでは、利用目的や期間のスコープが異なります。
| 製品ロードマップ | マイルストーン | |
| 概要 | プロジェクトの全体像や、製品のビジョン・戦略を記載 | プロジェクトを細分化し、具体的なタスクや期限を記載 |
| 目的 | 全体の進捗や開発方針を管理する | 詳細なタスクの進捗を管理する |
| 期間 | 長期 | 短期~中期 |
製品ロードマップは、プロジェクトの方向性や戦略を示し、長期的な視点で計画を立てたものです。
プロジェクトの全体像を把握することが目的であり、記載する期間も長期にわたります。
一方、マイルストーンはプロジェクトを細分化し、目標達成にむけた詳細な計画を示したものです。
そのため、短いスパンで開発の進捗を管理したい場合は、マイルストーンのほうが向いているといえるでしょう。
製品ロードマップの種類
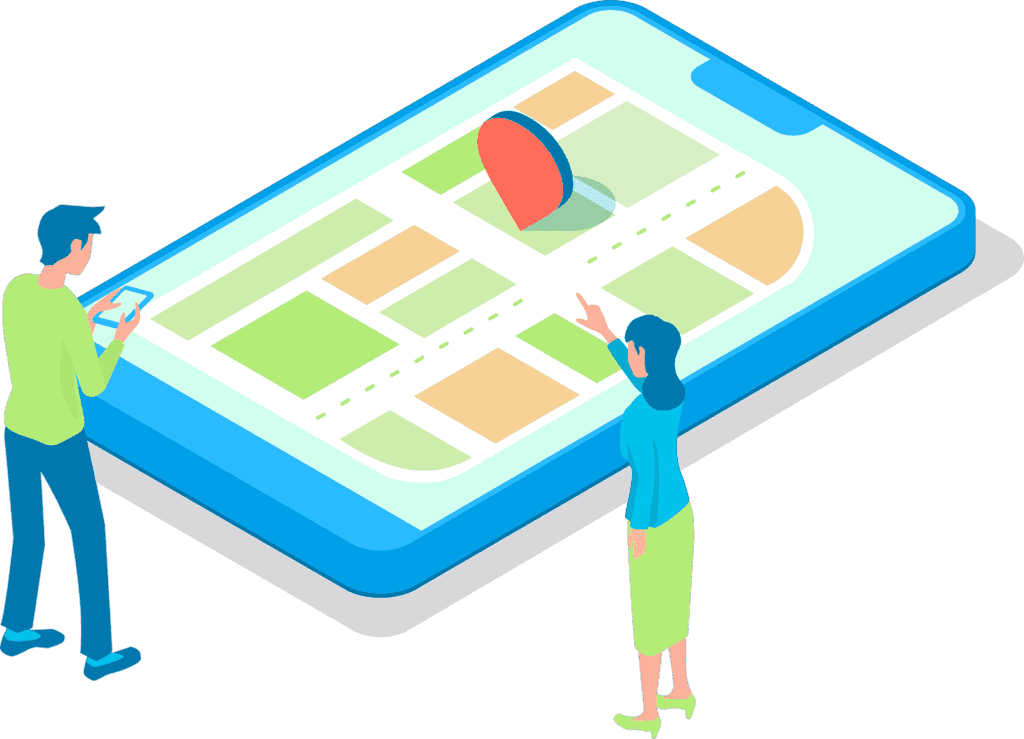
製品ロードマップには様々な種類があり、企業の目的やプロジェクトの性質に応じて適切なロードマップを選ぶことが重要です。
| 製品ロードマップの種類 | 焦点 | メリット | 注意点 |
| 戦略的ロードマップ | 企業の中長期的な成長
ビジネス目標 |
中長期的な方向性を共有できる
大きなビジョンを描くため、経営層の意思決定をサポートする |
抽象度が高くなりすぎると、具体的なタスクへの落とし込みが難しい |
| テーマベース・ロードマップ | テーマ | 変化に柔軟に対応しやすい
ビジネス目標に基づき、広範な課題を解決できる |
テーマが曖昧だと具体的な開発計画が不明確になりがち |
| 時系列ロードマップ | 時系列
(タスク実行タイミング、リリース計画) |
時間軸に基づく進捗管理が可能
プロジェクトの遅延を防ぎやすい |
計画変更が多い場合、頻繁な調整が必要になる |
| 目標ベース・ロードマップ | 目標 | 目標達成を明確に追跡できる
具体的な結果を出しやすい |
目標設定が曖昧だと、成果測定や進捗管理が難しくなる |
| Now-Next-Later形式 | タスクの優先順位
実行タイミング |
優先度を簡単に見直せる
変化に柔軟に対応しやすい |
優先度の見直しを怠ると、形骸化してしまう |
戦略的ロードマップ
戦略的ロードマップは、企業の長期的な成長やビジネス目標に沿った製品開発の方向性を示す指針です。
具体的なリリース日や機能にフォーカスするのではなく、市場動向や競争環境を踏まえ、どの技術や製品に注力すべきかを明確にします。
このロードマップは、経営層やステークホルダーに共通のビジョンを持たせ、意思決定をサポートする役割を果たします。
また、市場の変化や競争要因に柔軟に対応できることも重要です。
ロードマップが抽象的であるほど柔軟性は高まりますが、曖昧すぎるとチームが具体的なタスクを理解しにくくなるため、具体性とのバランスが重要です。
テーマベース・ロードマップ
テーマベース・ロードマップは、特定のビジネス目標や顧客体験の向上といった大まかなテーマに基づいて指針を立てる手法です。
ビジネス目標を共有する点では戦略的ロードマップに似ていますが、戦略的ロードマップが企業全体の成長や長期的な戦略に焦点を当てるのに対し、テーマベース・ロードマップは具体的な「テーマ」に基づいています。
各テーマは、特定の機能や技術ではなく、顧客体験の向上や市場での競争優位性の確保といった広範な課題に対応します。
この手法により、長期的なビジョンを持ちながら、短期的な戦略にも柔軟に対応できます。
特に技術革新の速い分野では、機能に縛られずに優先順位を調整し、持続的な開発が可能です。
時系列ロードマップ
時系列ロードマップは、製品開発の進捗やリリース計画を時間軸に沿って示す手法です。
プロジェクトの各段階で何を達成すべきか、どのタイミングで機能や製品をリリースするかが視覚的に把握でき、チーム全体の進捗管理が容易になります。
一見スケジュールやマイルストーンと似ていますが、時系列ロードマップでは、主要なリリースや進展を長期的な期間で視覚化する点が特徴です。
特に複数のリリースを伴う長期(四半期や年単位)プロジェクトで有効で、依存関係やリソース配分の調整を通じてプロジェクトの遅延を防ぐことができます。
目標ベース・ロードマップ
目標ベース・ロードマップは、製品開発やビジネスプロジェクトの進行を、達成すべき具体的な目標に基づいて構築する手法です。
短期・中期・長期のビジネス目標を設定し、それぞれに必要なアクションやステップを明確にします。
例えば、売上の向上、顧客満足度の改善、新市場への参入といった目標が設定され、チーム全体が同じゴールに向かって効率的に動けるようになります。
また、進捗は目標に基づいて測定されるため、成果の追跡や調整が容易です。
目標ベース・ロードマップでは、具体的で測定可能な目標設定が成功の鍵となります。
Now-Next-Later形式
Now-Next-Later形式は、製品開発やプロジェクトの優先順位を「Now(現在)」「Next(次にやること)」「Later(将来的にやること)」という3つのカテゴリに分類する手法です。
今すぐ取り組むべきタスク(Now)、次に着手すべきタスク(Next)、そして今後実施するタスク(Later)を視覚的に整理することで、チームの優先度を明確にし、進捗を効率的に管理できます。
Now-Next-Later形式は、柔軟性が高く、特に技術革新の速い分野や優先順位が変わりやすいプロジェクトに適しています。
ただし、優先順位の定期的な見直しを怠ると、形骸化してしまうリスクがあるため注意が必要です。
製品ロードマップの目的

製品ロードマップには、プロジェクトの方向性を明確にし、開発目標を達成するための計画を提供する役割があります。
製品ロードマップの作成目的は、具体的に以下のような要素があげられます。
- 製品ビジョンと戦略の共有
- 開発計画の策定
- 進捗管理
- コミュニケーションとチーム連携
製品ビジョンと戦略の共有
プロジェクトを進める際、自分が直接かかわらない範囲に関しては、内容を詳しく把握していないこともあるでしょう。
全員が各々の取り組みしか理解していないと、開発の方向性がさだまらず、本当に必要とする機能とは異なるものができあがってしまうかもしれません。
製品ロードマップを作成すれば、製品のあるべき姿や、目標達成のために何をすべきかが明確になります。プロジェクトの全体像を把握できるため、チーム全体の方向性を統一する際に役立つでしょう。
また、開発時の指針が明確になり、人員や予算などのリソースを最小限におさえる効果もあります。
開発計画の策定
製品ロードマップを用いると、いつまでに何をすべきかが一目でわかるため、開発計画の検討がスムーズに進みます。
必要なタスクや機能の洗い出しにともない、潜在的なリスクを把握できれば、いざ課題に直面しても慌てる心配がありません。
製品ロードマップは、意思決定を行う際にも役立ちます。
開発をとどこおりなく進めるためには、目標達成にむけてどのようなプロセスをふむべきか、意思決定の基準を定義しておく必要があります。
開発の方針に迷った場合でも、製品ロードマップに記載された「製品のあるべき姿」をもとに決定を行えば、議論に時間を割く心配がなくなるでしょう。
進捗管理
製品ロードマップの活用場面は、開発の初期だけにとどまりません。
製品ロードマップには、開発すべき機能に対して「いつまでに何を達成すべきか」が記載されています。
開発の進捗具合と照らしあわせれば、現在までにどのくらい目標が達成できているかを客観的に把握できるでしょう。
効率的な進捗管理は、目標に対する遅れの発見にもつながります。
課題をいち早く見つけて対策を立てれば、プロジェクトの遅延を最小限におさえることが可能です。
また、各メンバーが現在の進捗やステップを把握しやすくなるため、情報共有もスムーズに進むでしょう。
コミュニケーションとチーム連携
製品ロードマップを作成すると、各メンバーの役割や責任が明確になります。
自分以外のメンバーがどのような取り組みを行っているかを把握できるため、開発計画に対する議論を行ったり、チーム間で協力体制をとったりできます。
チーム全体が目標や計画に対して同じ認識を持てば、一貫した方向性をもって行動できるようになるでしょう。
開発に遅れが生じた場合でも、製品ロードマップがあれば状況を共有すべき相手が一目でわかります。
プロジェクトで関わりのあるメンバーを把握しやすいのも、製品ロードマップの強みのひとつです。
製品ロードマップを作らないとどうなる?

製品ロードマップを作成せずに開発を進めてしまうと、プロジェクトの方針がさだまらないだけでなく、さまざまなデメリットが生じます。
懸念されるデメリットとしては、以下のとおりです。
- 方向性がブレる
- 開発関係者のモチベーションが低下する
- 顧客ニーズの把握が難しい
方向性がブレる
製品ロードマップには、製品に対するビジョンや戦略とともに、開発するうえで進むべき道のりを明らかにする役割があります。
開発方針が明確でないと、メンバー内で認識のずれが生じ、異なる目標や優先順位を持ってしまう可能性があります。
そうすると、意思決定を行うにも時間がかかってしまい、プロジェクトの進行に支障が出てしまうかもしれません。
方向性のブレは、リソースの浪費にもつながります。
何を優先して進めればいいか、どのくらい時間や資金を割くべきかのすり合わせができず、せっかく割いたリソースが無駄になってしまう可能性も考えられるでしょう。
開発関係者のモチベーションが低下する
製品ロードマップを作成しない場合、開発方針が不明確なままプロジェクトを進めることになります。
すると、どのように開発を進めればいいかわからず、チーム内で混乱がおきてしまう可能性があります。
次に取り組むべき作業で議論がおきたり、予想外のタスクが発生し対応に追われたりすることもあるかもしれません。
その結果、プロジェクトが円滑に進まなくなり、チーム内のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。
また、意思決定をする際にもメンバーごとに基準が異なるため、話がまとまらずプロジェクトの進行に支障が出る可能性も考えられるでしょう。
顧客ニーズの把握が難しい
製品開発を成功させるためには、顧客ニーズの把握が必要不可欠です。
ユーザーが求める製品とは何か、どのように開発を行っていけばいいかを明確にすることで、顧客満足度の高い製品を開発できます。
製品ロードマップを作成しない場合、製品に対するビジョンや戦略が不明確になってしまうため、顧客ニーズを把握することが難しくなります。
企画段階だけでなく、開発中においても市場の変化に対応することが困難になるでしょう。
結果として、需要の低い製品を開発することになり、市場における競争力が低下してしまう可能性が考えられます。
製品ロードマップの書き方

製品ロードマップを作ってみたいけれども、何から手をつければいいかわからず悩んでいる人もいるかもしれません。
製品ロードマップを作成する際は、以下のステップをふむと良いでしょう。
- ツールの選定
- ビジョンと目標の策定
- 必要な機能の洗い出し
- 優先順位付け
- ロードマップの作成
- 共有とフィードバック
ツールの選定
製品ロードマップを作成する際には、専用のプロジェクト管理ツールを活用するのがおすすめです。
あらかじめ用意されているテンプレートや機能を使えば、はじめてのユーザーでも簡単に製品ロードマップを作成できます。
また、専用ツールのほとんどはオンライン上で管理ができるため、チーム間での編集や共有も容易に行えるでしょう。
製品ロードマップを作成できるツールは、「Trello」や「Jira」などさまざまな種類があります。
どのようなプロジェクトに向いているかはツールによって異なるため、機能や予算と相談しつつ選択してみてください。
ビジョンと目標の策定
製品ロードマップの作成にあたり、最初に決めるべき項目が製品のビジョンと目標です。
どのような製品を開発するのか、いつまでにプロジェクトを完了すべきかといったゴールを明らかにしておきましょう。
メンバー全員に理解してもらえるよう、具体性があり達成可能な目標を設定しておくと、その後の開発もスムーズに進みます。
この際、開発時のステークホルダー(関係者)もあわせて選出するようにしてください。
彼らの意見もとりいれたうえで製品ロードマップを作成すれば、検討不足により後から内容を修正するリスクが減らせます。
必要な機能の洗い出し
製品のビジョンや目標がさだまったら、必要な機能の洗い出しを行いましょう。
製品のあるべき姿に対し、達成に必要な開発項目を整理していきます。
たとえば、既存ソフトウェアのバージョンアップを考える場合は、新しく追加する機能や不具合対応すべき機能をあげていきます。
ここで重要なのは、開発に必要な機能を漏れなく抽出することです。
序盤で漏れが生じてしまうと、開発中に気づいてもリソースが足りず、プロジェクトに遅れが生じてしまう可能性があります。
顧客ニーズを整理し、ブレインストーミングを行うなどして、機能や改善点を整理するよう努めてください。
優先順位付け
必要な機能を洗い出したら、それぞれに対し優先順位をつけていきます。
優先順位を決める際は、機能の重要度と緊急性をもとに判断していきましょう。
ユーザーの満足度に対して与える影響が大きく、即座に対応が必要なものほど、優先順位も高くなります。
製品に対する影響の強い機能から開発を進めることで、時間や予算といったリソースを効果的に活用できます。
また、優先順位の低い機能にリソースを割きすぎてしまい、開発内容が無駄になってしまうリスクも減らせるでしょう。
ロードマップの作成
各機能ごとに優先順位付けができたら、いよいよ製品ロードマップの作成を行います。
これまでにあげた機能と優先順位をもとに、どのように開発を行っていくか時系列で整理していきます。
製品ロードマップを作成する際は、最初に決めたプロジェクト管理ツールを活用し、効率良く進めていくようにしましょう。
製品ロードマップの目的は、プロジェクトの全体像を把握することです。
そのため、詳細な開発計画は記載しなくて構いません。
ただし機能と優先度にくわえ、期限や担当、想定されるリスクは明確にしておくと良いでしょう。
共有とフィードバック
製品ロードマップが作成できたら、チーム内で共有し方向性のすり合わせを行っていきます。
作成にかかわったメンバーだけでは、開発に必要な視点が足りていないかもしれません。
さまざまな意見を収集し改善をかさねることで、開発計画をより確固たるものにできます。
製品ロードマップの共有は、チーム内だけでなくステークホルダー(関係者)にも行いましょう。
プロジェクトを進める前に合意形成を行うのも、製品ロードマップの役割のひとつです。
製品の目指すべきゴールについてきちんと説明を行い、ステークホルダー間の認識もあわせて統一させておくことをおすすめします。
製品ロードマップのサンプル例

ここではサンプル例を一つ示します。サンプルとして「顧客管理システムの開発」を例に考えてみましょう。
まず、ツールを選定し、次にビジョンと目標を策定します。
今回の顧客管理システムの目的は、「営業プロセスの効率化」と「顧客データ管理の精度向上」とします。
目標は、「半年以内のシステムの稼働開始」と「既存顧客の満足度20%向上」とします。
また、ステークホルダーは「営業部門」「技術部門」「経営層」とします。
目的が決まったら、次にシステムに必要な機能を洗い出します。例えば以下の機能が考えられます。
- 顧客データの統合管理機能
- 営業案件の進捗把握機能
- 顧客分析レポート機能
機能を洗い出したら、それぞれの重要度と緊急度を基に優先順位を設定します。
次に、選定したツールを活用してロードマップを作成します。
- 1-2ヶ月目:顧客データの統合管理機能の設計と実装
- 3ヶ月目:営業案件の進捗把握機能の設計と実装
- 4ヶ月目:テストフェーズ、不具合修正
- 5ヶ月目:顧客分析レポート機能の設計と実装
- 6ヶ月目:システム全体のリリースと運用開始
このように、各ステップに沿って進めることで、効果的な製品ロードマップが作成できます。
これにより、チームは一貫したビジョンのもとで開発を進め、ステークホルダーのフィードバックも取り入れながらプロジェクトを進行できます。
製品ロードマップ作成のコツ

製品ロードマップは、一度作成すれば終わりというわけではありません。
開発が進行している間も更新を行うことで、プロジェクトの成功率をぐんと高められます。
ここから先は、製品ロードマップを作成するコツについて見ていきましょう。
- 目的に合わせた製品ロードマップを選定する
- 最新情報を反映させる
- 定期的な見直しをする
目的に合わせた製品ロードマップを選定する
製品ロードマップの形式には、いくつかの種類があります。
プロジェクトの特徴であったり、どのような目的で作成したいかによって、選ぶべき形式も変わってきます。
場合によっては、複数の形式を組み合わせて活用したほうがいい場面もあるでしょう。
ここでは、さまざまなプロジェクトの目的に応じたロードマップの選定方法を紹介します。
長期的なビジネス成長を描く
企業全体の成長戦略やビジネス目標を視野に入れ、長期的な視点で製品開発の方向性を定めたい場合は「戦略的ロードマップ」が適しています。
このロードマップは、企業の中長期的な成長戦略に基づき、技術投資や市場拡大などの計画を示します。
ステークホルダーと大きなビジョンを共有し、合意形成に役立つため、将来を見据えた製品開発に向いています。
リリーススケジュールを明確にする
プロジェクトの進捗状況やリリースタイミングを時間軸に沿って整理し管理したい場合は「時系列ロードマップ」が適しています。
どの段階で何を達成するのか、どの時点で製品や機能をリリースするのかを明確にし、進捗を可視化できます。
複数のリリースがある長期プロジェクトや、スケジュールに厳格なプロジェクトに適しています。
具体的な目標達成を重視する
チーム全体が同じ目標に向かって効率的に動きたい場合は「目標ベース・ロードマップ」が適しています。
このロードマップは、短期・中期・長期のビジネス目標を設定し、それに基づいて必要なアクションやステップを整理します。
さらに、具体的な目標だけでなく、製品開発の方向性を広範な「テーマ」に基づいて整理したい場合には「テーマベース・ロードマップ」も有効です。
顧客体験の改善や市場競争力の強化などのテーマに焦点を当て、柔軟に計画を立てることが可能です。
柔軟に優先順位を管理する
優先順位が頻繁に変わるプロジェクトや、アジャイル開発のように柔軟な対応が求められる場合は「Now-Next-Later形式」が適しています。
このロードマップは、今すぐ取り組むべきタスク(Now)、次に着手すべきタスク(Next)、そして今後実施するタスク(Later)を明確に分けて整理し、状況の変化に応じて優先順位を簡単に見直すことが可能です。
チーム全体が優先事項を共有しやすく、進捗管理が効率化されるため、特に迅速な意思決定が求められる環境で効果を発揮します。
最新情報を反映させる
製品ロードマップは開発の指針となるため、つねに最新の情報を反映させる必要があります。
製品ロードマップを作成してから、製品が完成するまでには期間があきます。
はじめに想定していたニーズが、販売段階においても通用するとは限りません。
製品ロードマップが更新されていないと、せっかく完成しても顧客のニーズとは異なるものができあがってしまう可能性があります。
また、開発中に新しい技術が登場したり、競合他社から類似製品がリリースされる可能性も考えられるでしょう。
製品ロードマップには、つねに新しい情報を反映させるよう心がけてください。
定期的な見直しをする
製品ロードマップはあくまで開発時の指針であり、絶対的なルールではありません。
プロジェクトを進めていくと、計画とずれが生じたり、新たな問題が見つかる場合もあります。
プロジェクトの成功率を高めるためには、製品ロードマップの内容を守ることにとらわれすぎず、状況に応じて修正をくわえていくことも重要です。
こまめに製品ロードマップの更新を行えば、開発計画と実態との間に生じるずれを防止できます。
四半期に一回など、定期的なタイミングで見直すようにしましょう。
製品ロードマップ作成に活用できるツール4選

製品ロードマップを作成できるプロジェクト管理ツールはさまざまあります。
ツールによって機能や強みが異なるため、プロジェクトの特徴に応じて選択するのがおすすめです。
製品ロードマップ作成に活用できるツールは、以下のようなものがあります。
| ツール名 | 1ユーザーあたりの月額と有料プラン | 無料版の主な制限 | 表示形式 |
| Trello | $6〜
Standard / Premium / Enterprise Premiumは無料トライアルあり |
最大10ユーザー
他機能制限あり |
カンバン |
| Jira | 990円〜
Standard / Premium / Enterprise Premiumは無料トライアルあり |
最大10ユーザー
他機能制限あり |
カンバン含め複数の表示 |
| Miro | $10〜
Starter / Business / Enterprise |
最大3ボード
他機能制限あり ※ 無料版でのユーザー数制限はなし |
ホワイトボード |
| Notion | 1,650円〜
プラス / ビジネス / エンタープライズ |
最大10ユーザー
他機能制限あり |
カンバン含め複数の表示 |
Trello

Trelloはカンバン方式のプロジェクト管理ツールで、シンプルで使いやすいインターフェースが特徴です。
開発に必要なタスクは、「カード(カンバン)」に記載して管理を行っていきます。
ドラッグ&ドロップでカードを移動するなど、操作も直感的かつ非常に簡単であり、視覚的にタスクを管理することが可能です。
Trelloでは、ボード上にカードをならべて整理できるため、タスクの期限や進行状況を一目で把握できます。
無料版では機能が制限されているものの、小規模から中規模のプロジェクトであれば問題なく活用できるでしょう。
Jira

Jiraは、プロジェクトの一元管理が可能な管理ツールです。
タスクを効率良く管理するためのさまざまな機能が備わっています。
課題やプロジェクトごとにワークフローを設定したり、ダッシュボードをカスタマイズして進捗具合を把握したりと、プロジェクトの状況把握に役立てられるのがポイントです。
Jiraはシステム開発の思想をもとに制作されている機能が多く、ソフトウェア開発や大規模なプロジェクト管理に向いています。
拡張性の高さも強みであり、TeamsやSlack、GitHubなどさまざまなシステムと連携が可能です。
Miro

Miroは、チームの共同作業に使えるオンラインのホワイトボードツールです。
図や表、付せんなどさまざまな機能を活用でき、チーム内でリアルタイムに開発計画を立案できます。
Miroでは、マインドマップやフローチャートなどのテンプレートも用意されています。
ホワイトボード上に展開し編集を行っていくことで、さまざまな観点からアイディア出しができるのも強みのひとつです。
そのため、多様性のあるアイディアを求める場合や、プロジェクトの初期段階のプランニングに適しているといえるでしょう。
Notion

Notionは、メモや議事録、Wikiなどのドキュメント管理から、タスクやプロジェクト管理までできる多機能なオールインワンツールで、製品ロードマップの作成にも適しています。
特に、カスタマイズ性の高さが特徴で、ページやデータベースを自由に組み合わせて、プロジェクトの状況に応じた柔軟なロードマップを作ることができます。
表示形式も、テーブルビューやボードビュー(カンバン)、タイムラインビューなど複数あり、タスクの進捗状況を直感的に管理できる点が魅力です。
また、リアルタイムでの編集やコメント機能を備えており、チーム全員が常に最新情報にアクセスできます。
製品ロードマップの活用事例

製品ロードマップは、製品やサービスを開発するさまざまな場面において活用できます。
ここから先では、製品ロードマップを用いた具体的な事例について、企業の種別ごとに紹介していきます。
- ソフトウェア開発企業
- ハードウェアメーカー
- Webサービス企業
ソフトウェア開発企業
ソフトウェア開発企業の場合、新規製品の開発だけでなく、既存製品のバージョンアップにも活用が可能です。
ユーザーからの声をもとに開発計画を立てれば、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
ソフトウェア開発企業における活用事例は、以下のようなものがあります。
- ユーザーからのフィードバックをもとに、新しいソフトウェア製品を開発する
- 定期的なバグ修正やメンテナンスリリースのスケジュールを管理し、リリース時期を調整する
- OSのバージョンやハードウェアなど、新しいプラットフォームへの対応計画を立てる
ハードウェアメーカー
ハードウェアメーカーの場合、製品そのものの開発だけでなく、内部で動作するソフトのバージョンアップにも活用できます。
製品ロードマップを作成すれば、ハード・ソフトをまたいだ部署との連携も可能です。
ハードウェアメーカーにおける活用事例は、以下のようなものがあります。
- 新しいスマートフォンモデルを開発するための計画を立てる
- 既存の家電ラインナップに、新しい製品をリリースするための計画を立てる
- 既存のハードウェア製品にIoT技術を導入するため、開発計画を検討する
Webサービス企業
製品ロードマップは、Webサービス企業においても活用が可能です。
新規サービスをリリースした後でも、製品ロードマップを活用すれば保守・運用をスムーズに進められます。
Webサービス企業における活用事例は、以下のようなものがあります。
- 既存のプラットフォームについて、新機能のリリース時期を調整する
- 既存のサービスについて、新たな市場にサービスを展開するための計画を立てる
- クラウドサービスについて、システムや機能を拡張するための計画を立てる
まとめ:製品ロードマップを作成して効率よくプロジェクトを進めましょう

この記事では、製品ロードマップの目的や書き方、作成のコツについて解説しました。
製品ロードマップは、顧客のニーズにそった開発を進めるうえで非常に強力なツールといえます。
製品ロードマップを作成する際は、ぜひこの記事を参考にしつつ、製品のビジョンや戦略について検討してみてください。
ですが実際に作成してみると、書き方に困ったり判断に迷ったりする部分が出てくるかもしれません。
株式会社Jiteraでは、大企業のDX施策や新規事業、スタートアップの事業開発など多くの実績を積んでおります。製品ロードマップの作成や、タスク管理ツールの選定にお困りの際は、お気軽にご相談ください。







