企業活動に利用しているシステムは、年数の経過や環境の変化に伴いシステム移行が必要となります。その移行作業、実は新規の開発よりも難易度が高いと言われていることをご存じでしょうか。
本記事ではシステム移行の種類や手順をご紹介し、難易度が高いと言われている理由を解説します。また、スケジューリングや手戻りを発生させないコツなど、失敗しないための注意点もご紹介します。
制御系システムや自動化システムの新規開発を中心に、15年以上の開発経験を持つ現役エンジニアです。『デジタルは人と人をつなぐもの』という言葉が好きです。デジタルの世界をわかりやすく伝えていきます。
システム移行とは?

システム移行とは、既存システムから新しいものへの切り替えを意味します。英語ではSystem Migrationと書きます。
下記のような類似用語がありますが、移行の対象が異なるためご注意ください。
- データ移行:従来とは異なるデータベース、ストレージなどへデータを移す作業。
- 業務移行:新システムで業務を運用すること、および運用のための準備作業。
「使うシステムが変わるだけじゃないの?」と思われる方も居るかもしれませんが、システム移行は一歩間違えると業務不可な状況にも繋がりかねない、極めて重要な作業です。
システム移行が必要となるタイミングとは

大企業や中小企業にも、システム移行が必要となるタイミングが存在します。主なものとして、機器やOSのサポート終了、経営統合や古いシステムの刷新が挙げられます。
また、「2025年の崖」という用語もあり、業務効率化や競争力の強化のためにも移行を検討する企業が今後さらに増えると予想されます。
本章では、移行が必要となるタイミングと、失敗しないための注意点についても解説します。
ハードウェアやOSのサポートが終了するタイミング
代表的なシステム移行のきっかけに、サーバーやストレージといった機器やOSのサポート終了があります。
サポート切れの機器を使い続けることもできるのですが、関連システムやソフトウェアとの連携が不可になったり、脆弱性が高まりサイバー攻撃に晒される危険性が生じるなど総じてリスクは高いです。
以下、ハードウェアとOSそれぞれのケースについて詳述します。
ハードウェアのサポートが終了するタイミング
長期使用機器のサポート終了は珍しくありません。サポート対象外の機器使用は可能ですが、重大な問題があります。
- 障害発生時の調査や機器交換サポートが受けられず、業務継続性が脅かされる。
- 経年劣化による故障リスクが年々上昇し、サポートの重要性が増す。
移行プロジェクトには通常数ヶ月から1年以上を要します。サポート終了に間に合わない事態を避けるため、サポート期限の把握と早期の計画立案が不可欠です。
OSのサポートが終了するタイミング
OSもサポート終了の対象となります。例えば、2023年1月にはWindows 8.1のサポートが終了しました。サポート終了後のOS継続使用には以下のリスクが伴います。
- セキュリティリスクの上昇:セキュリティアップデートが停止し、脆弱性が増大。サイバー攻撃による情報漏洩やデータ損失のリスクが高ま
- 他サービスやソフトウェアとの互換性喪失:連携するサービスやソフトウェアが順次対応を停止し、使用不可能となる可能性がある。
OSのサポート終了は通常1年以上前に告知されます。例えば、2024年4月時点で、Windows 10のサポート終了が2025年10月と公表されています。メーカーの情報を定期的にチェックし、十分な余裕を持って移行を検討することが重要です。
環境の変化に伴うシステムの統合
続いて、企業統合やM&Aといった企業環境の変化も移行の要因となります。複数の企業が統合する場合、いずれか一社のシステムへ統合したり、またはまったく別のものを導入するなど必然的に移行作業が発生します。
また、複数企業の運用業務や既存データを融合しながら移行先の検討や検証をする必要があるため、移行プロジェクトは規模が大きく難易度が高いものになります。
ステークホルダーも多くなるため、事前検討や調査の工数を厚めに確保すると良いかと思います。
老朽化したレガシーシステム
長年使用し続けているシステムをレガシーシステムと呼びますが、レガシーシステムを脱却し新しい技術やフレームワークを取り入れることもシステム移行に該当します。
経済産業省が提唱する「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか。レガシーシステムを使用し続けていると競争力はどんどん低下し、2025年以降は年間で約12兆円の経済損失が発生すると言われています。
そういった事態を避けるためにもDX化を推進する必要があり、レガシーシステムを脱却しAIやIoT技術をといった新しい技術の導入が推進されています。
長年使いこまれたシステムはカスタマイズにより複雑化していたり、企業活動に深く根付いており移行が難しくなる傾向があります。ですが、新しいシステムへの移行は業務効率化や競争力向上など企業活動にメリットとなります。
慎重に進める必要はありますが、レガシーシステムを使用している企業はぜひ移行を検討してみてください。
システム移行の方式
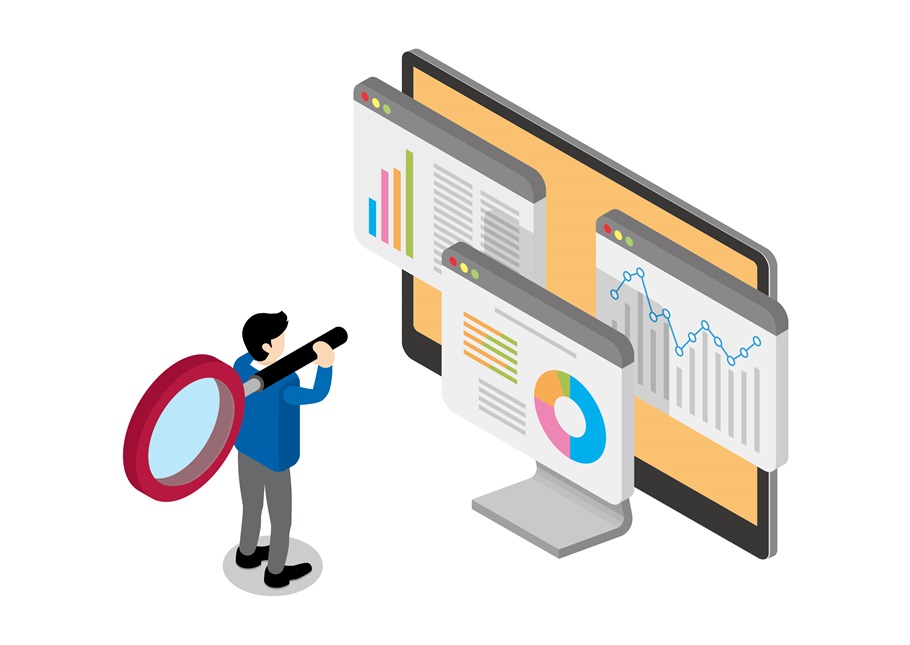
ここまで、システム移行の検討を開始するタイミングをご紹介しました。
本章では、代表的な移行方式である3つのパターンを紹介します。それぞれの、特徴、実施手順、メリット、デメリット、注意点を表にまとめましたので参考にしてください。
一括で新システムへ切り替える方式
「一括で新システムへ切り替える方式」は、旧システムの停止と新システムの稼働を同時に行います。
| 項目 | 説明 |
| 特徴 | ・大規模な切り替え作業のため、週末や連休に実施することが多い ・短期間で移行が完了する |
| 実施手順 | 1. データバックアップ取得 2. 旧システム停止 3. ネットワーク切り替え 4. 新システム稼働 5. 確認作業(問題発生時は旧システムに戻す) |
| メリット | ・移行期間が短い ・コストが低い(並行稼働期間がないため) |
| デメリット | ・問題発生時の切り戻し作業が多い ・システム利用不可の時間が発生する |
| 注意点 | ・定期的なマイルストーンと判断ポイントの設置 ・切り戻し時のシミュレーションと対策 ・BtoCなど常時利用システムには不向き |
この方式は、早期切り替えやコスト削減が必要な場合に適していますが、リスク管理と利用者への影響を十分に考慮する必要があります。
段階的に新システム切り替える方式
「段階的に新システムへ切り替える方式」では、全体を一度に切り替えるのではなく、部分的な移行を繰り返し行います。
| 項目 | 説明 |
| 特徴 | ・部分的な移行を繰り返し行う ・機能別移行またはパイロット移行(特定部署から順次)が可能 |
| 実施手順 | 1. 一部機能または部署を移行(ネットワーク切り替え、データ移行含む) 2. 新機能を利用 3. 問題がなければ次の機能または部署を移行 4. 1-3を全ての移行が完了するまで繰り返す |
| メリット | ・問題発生時の影響範囲が限定的 ・一回あたりの移行時間が短い ・移行スケジュールが立てやすい |
| デメリット | ・検討事項が多い ・プロジェクトが長期化しやすい ・コストが膨らむ可能性がある |
| 注意点 | ・各段階での十分な検証が必要 ・長期プロジェクトになることを想定した人員・リソース確保 ・コスト管理の徹底 ・移行完了までの新旧システム共存期間の運用方法の検討 |
この方式は慎重に移行を進めたい場合や、平日など短時間での移行が必要な場合に適していますが、早期完了やコスト抑制が最優先の場合には不向きかもしれません。
現行システムと新システムを同時並行で運用しながら進める方式
「システムを同時並行で運用しながら進める方式」では、移行作業が完了後、新システムの安定稼働が確認できるまで、既存システムも稼働したままとなります。
| 項目 | 説明 |
| 特徴 | ・新旧システムを一定期間並行して運用する ・新システムの安定稼働確認後に旧システムを停止 |
| 実施手順 | 1. 新システムの稼働準備(ネットワーク接続など) 2. データ入力または同期 3. 新システム起動 4. 一定期間の並行稼働と問題確認 5. 旧システム停止 |
| メリット | ・リスクが低い(問題発生時に旧システムで業務継続可能) ・利用者の安心感が高い(新システムを実際に使用して確認できる) |
| デメリット | ・コストが高い(両システムの運用・保守が必要) ・データの整合性が取れないリスク |
| 注意点 | ・両システムの使用方法の検討と利用者への負荷軽減 ・データ入力の誤り防止策や正確な同期処理の実装 ・十分な検討と検証作業の実施 |
この方式は、リスクを極力抑えたい場合や利用者が移行に不安を感じる場合に適していますが、コストを重視する企業には不向きかもしれません。
システム移行のパターンは2つ

システム移行は、移行先が自社管理システムか、ベンダーが提供するクラウド型かによって2つのパターンに分けられます。
本章では、2つの移行パターンの概要と、各移行パターンの費用やカスタマイズ性についても解説します。
サーバーを効率的に使用する技術のひとつに、仮想化技術があります。下記記事では仮想化技術の概要や導入時の注意点も記載しているので、興味がある方はぜひ参照ください。
自社に設置したサーバーやネットワークを使ってシステム運用を行う
一つめのパターンは、自社に設置したオンプレミス型への移行です。
オンプレミス型とは、自社でネットワークを構築し、自社で保守もおこなう形態です。クラウド型と比較すると初期コストはかかりますがランニングコストがかからず、自社に応じた作り込みが可能だという特徴があります。
この移行パターンの場合、移行作業は全て自社内で完結します。そのため外部要因を挟まず連携や作業をスムーズに進めることができます。
一方で、システムの総入れ替えとなるためサーバーなどの構築費用が高額になり、専門知識が必要という点は注意が必要です。
オンプレミスからクラウドに移行する
二つめの移行パターンは、クラウド型への移行です。
クラウド型ではベンダーが運用するサーバー上に自社システムを構築します。ランニングコストがかかりますが、サーバーメンテナンスや老朽化対策、セキュリティ対策もベンダーに任せることができ、その利便性から近年利用する企業が増加しています。
クラウド型へ移行する場合、サーバーやネットワークの構築作業が不要であるため、コストは低くスピーディーな移行が可能です。
注意点として、OSやソフトウェアのバージョンやネットワーク構成の都合で予期しない連携エラーが発生する可能性があります。また、オンプレミス型と比較するとカスタマイズ性は劣るため、自社に合わせた作り込みを予定している場合は不向きかもしれません。
システム移行の一般的な手順

次は、移行の一般的な流れについてご説明します。移行形式などに関わらず、システム移行は基本的に今回ご紹介する手順になるかと思います。
移行では、事前調査、計画策定、リハーサルやリリース後などプロジェクト全体にわたりマイルストーンが存在します。
失敗しないための注意点もあわせて記載していますので、参考になれば幸いです。
手順1:移行元システムとデータの調査
最初に、既存システムのスペックやネットワーク構成、データを確認します。
下記は確認観点の一例です。
- OSの種類やバージョン
- サーバーやストレージの容量
- 対応可能なファイル形式
- データ構造
- データ量
- バックアップ取得方法
データ量について、蓄積データであれば移行時にどの程度の容量となっているかシミュレーションしましょう。また、例えば直近数年分のデータなど一部データを移行対象とすると、新システムをスリム化し移行費用を抑えることが可能です。
データ量・構造の確認は今後の作業内容や工数に影響が大きい作業です。有識者を交え、手戻りのないように進められると良いですね。
手順2:移行計画書の作成
次は移行の情報をとりまとめ、計画書として記載します。
- 概要:移行時の前提条件
- 対象:データや機能、ネットワーク構成など移行対象
- 使用ツール:データ移行や確認に使用するツール
- 方式:本番移行で採用する方式。一括移行、段階機能移行、並行運用移行など
- スケジュール:移行時におこなうタスクと見積からスケジュールを策定
- 移行時の影響:移行作業中の業務への影響
- 体制:チーム編成と役割
- テスト:移行テストの範囲や実施環境
情報処理推進機構(IPA)のサイトに、より詳細な移行計画書の情報が記載されています。興味がある方は下記のリンクからご確認ください。
手順3:移行リハーサルの実施
次は、本番で使用する手順書をもとに、移行リハーサルをおこないます。本番作業時に発生しうる課題を事前に検知するため、実施時間帯や環境は可能な限り本番と同様な条件でおこないましょう。
課題が見つかった際は、リハーサル完了後に課題解消の対策を練ると思います。対策が有効であるかを確認するためにも、少なくとも2回はリハーサルを実施するようスケジュールを組みましょう。
また、問題が発生した際の切り戻し手順もこの段階で確認しておけると良いですね。
手順4:移行作業を実施
リハーサルで手順に問題ないことが確認できたら、いよいよ手順書に沿って本番の移行作業となります。
注意点として、一つの誤りが後続に大きな影響を与える可能性があります。手順書は誰が見ても分かるような明確な記載とし、チェック体制を敷いて誤りのないよう慎重に進めます。
また、環境差異の原因など、どうしても本番まで検知できない課題も発生するかもしれません。慌てずに上司や有識者へ判断を仰げるよう、緊急時の連絡先を明確にしておきましょう。
手順5:新システムのテストをする
移行作業が完了後、新システムで問題なく運用を開始できるかテストをおこないます。
実際の業務を始める前に網羅的に確認するため、下記のように非機能検証を含めてテストしましょう。
- 通常業務が問題なく実施できるか
- データ構造は正しく移行できているか
- 移行先データ量は想定通りであるか(データの移行漏れがないか)
- 高負荷に耐えられるか
- サーバーのCPUやメモリ使用率は余裕はあるか
テストケースが多く時間が長くなってしまう場合は、ツールの導入や確認用スクリプトを実装し自動化をするのも有効ですので、検討してみてください。
手順6:運用担当者への引継ぎ
移行の最後の手順は、運用担当者へ引き継ぎや教育です。運用担当者が新システムに戸惑うことがないようマニュアルを整備し、必要に応じて説明会を実施します。
大きく運用が変わる場合は、例えばリハーサル段階から引き継ぎを開始するなど引継ぎ期間を長めにとり、できるだけ不明点を潰したうえで運用を開始するようにしましょう。
また、運用担当者のみでは特定分野の知識が弱いこともあるかもしれません。移行完了後、安定稼働するまでは移行担当者と連絡が取れるようサポート体制を整えると良いですね。
システム移行のタスク一覧

システム移行は組織にとって複雑かつ重要なプロジェクトです。
本章では、一般的なシステム移行プロジェクトにおける主要なタスクを網羅的にリストアップしました。プロジェクトの初期段階から完了後のフォローアップまでをカバーしています。
| No | 分類 | タスク |
| 1 | プロジェクト計画とキックオフ | ・プロジェクトチームの編成 ・目標と範囲の定義 ・スケジュールとマイルストーンの設定 ・リスク評価と管理計画の策定 |
| 2 | 現行システム分析 | ・現行システムの機能とデータの棚卸し ・パフォーマンスと制約の評価 ・依存関係の特定 ・ドキュメンテーションのレビューと更新 |
| 3 | 新システムの設計 | ・アーキテクチャの設計 ・データベース設計 ・インターフェース設計 ・セキュリティ設計 |
| 4 | データ移行計画 | ・データマッピングの作成 ・データクレンジング計画の策定 ・テストデータセットの準備 ・データ変換ツールの選定または開発 |
| 5 | 開発とカスタマイズ | ・新システムの構築またはカスタマイズ ・必要なインテグレーションの開発 ・ユニットテストの実施 |
| 6 | テスト | ・テスト計画の策定 ・テスト環境のセットアップ ・機能テストの実施 ・パフォーマンステストの実施 ・ユーザー受入テスト(UAT)の実施 |
| 7 | トレーニングと文書化 | ・トレーニング計画の策定 ・ユーザーマニュアルの作成 ・管理者ガイドの作成 ・トレーニングセッションの実施 |
| 8 | 移行実行 | ・最終データ移行の実施 ・新システムの本番環境へのデプロイ ・切り替え計画の実行 ・ゴーライブチェックリストの確認 |
| 9 | ポスト移行活動 | ・システム安定化期間の監視 ・パフォーマンスチューニング ・問題点の迅速な対応と解決 ・ユーザーサポートの提供 |
| 10 | プロジェクト終結 | ・最終報告書の作成 ・レッスンズラーンドのドキュメント化 ・プロジェクト成果の評価 ・正式なプロジェクトクローズアウト |
このタスク一覧は、プロジェクトマネージャー、技術リーダー、およびステークホルダーが、移行プロセス全体を把握し、必要なリソースを見積もり、潜在的な課題を予測するのに役立ちます。
ただし、各組織やプロジェクトの特性に応じて、タスクの追加、削除、または修正が必要になる場合があることにご留意ください。
システム移行計画書のサンプル

「システム移行計画書」のサンプルをご紹介します。
移行の目的は、業務効率を高め、システムの安全性を高めることです。それぞれのシステムにあった計画書を綿密に作成しましょう。
| No | 項目 | ||
| 1 | プロジェクト概要 | プロジェクト名 | [プロジェクト名を記入] |
| 目的 | [システム移行の目的を簡潔に記述] | ||
| 期間 | [開始日] ~ [終了予定日] | ||
| 責任者 | [プロジェクトマネージャー名] | ||
| 2 | 現行システムの概要 | システム名 | [現行システム名] |
| 使用技術 | [使用しているハードウェア、ソフトウェア、言語等] | ||
| 課題 | [現行システムの問題点や制限事項] | ||
| 3 | 新システムの概要 | システム名 | [新システム名] |
| 使用技術 | [使用予定のハードウェア、ソフトウェア、言語等] | ||
| 期待される改善点 | [新システム導入により解決される課題や新機能] | ||
| 4 | 移行スケジュール | 1. 準備フェーズ | [日付] ~ [日付] – 要件定義 – システム設計 |
| 2. 開発フェーズ | [日付] ~ [日付] – 新システム開発 – 単体テスト |
||
| 3. テストフェーズ | [日付] ~ [日付] – 結合テスト – ユーザー受入テスト |
||
| 4. 移行フェーズ | [日付] ~ [日付] – データ移行 – 本番環境への展開 |
||
| 5. 稼働後フォローアップ | [日付] ~ [日付] – 運用サポート – 問題点の収集と対応 |
||
| 5 | リスク管理 | リスク一覧 | リスク(数値)、影響度(高/中/低)、対策|をリスト化 |
| 6 | 移行方式 | 移行タイプ | [段階的移行 / 一斉移行 / パラレル運用] |
| 詳細 | [選択した移行方式の詳細と理由] | ||
| 7 | データ移行計画 | 移行対象データ | [移行するデータの種類と量] |
| 移行方法 | [データ抽出、変換、ロードの方法] | ||
| データクレンジング | [必要なデータクリーニング作業] | ||
| 8 | 教育・トレーニング計画 | 対象者 | [トレーニングを受ける従業員グループ] |
| 内容 | [トレーニングの主な内容] | ||
| ケジュール | [トレーニングの実施時期] | ||
| 9 | コミュニケーション計画 | 主要ステークホルダー | [影響を受ける部門や役職] |
| 通知方法 | [メール、会議、イントラネット等] | ||
| 頻度 | [定期的な進捗報告の頻度] | ||
| 10 | 予算 | 総予算 | [予算総額] |
| 内訳 | – ハードウェア:[金額] – ソフトウェア:[金額] – 人件費:[金額] – その他:[金額] |
||
| 11 | 承認 | 承認者 | [役職] [氏名] |
| 日付 | [承認日] |
事前に作成した計画に従って作業を進めます。移行中に問題が起きないように、十分に注意することが必要です。
システム移行が難しい理由・注意点

システム移行は、綿密な方針検討や作業の正確性を要することから新規開発よりも難易度が高い作業だと言われています。
また、データ不適合など一つの誤りが業務に多大に影響を及ぼす可能性もあり、事前のデータ調査も高い正確性を要します。
本章では、システム移行が難しいと言われている理由を、注意点も含めて解説します。
移行を検討中の企業の方は特に役に立つかと思いますので、ご一読ください。
作業の正確性が求められる
システム移行では、調査・検証段階から本番移行時まで、すべての過程において高い正確性が求められます。これは、誤りが発生すると後続の作業に大きな影響を与え、最悪の場合、新システムの稼働に致命的なエラーをもたらす可能性があるためです。
【主な注意点】
- 本番移行時のタイムスケジュールに沿った正確な作業
- データ移行や設定の誤りの防止
- 新旧システムのデータ構造の正確な比較と判断
これらの課題に対応するためには、個人の注意力を高めるだけでなく、組織的な再鑑体制を構築することが重要です。一つ一つのタスクを正確に遂行することで、円滑なシステム移行を実現できます。
緻密な計画が必要
システム移行を成功させるためには、綿密な調査とスケジューリングが不可欠です。移行の規模や複雑さに関わらず、予期せぬトラブルが発生する可能性は常に存在します。
【計画時の考慮事項】
- 網羅的な作業の洗い出しと各作業の正確な見積もり
- データの移行漏れや不一致のリスク評価
- 新システムの処理能力向上に伴う潜在的な問題の予測
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、プロジェクトの早い段階から有識者の参画を得て、細部まで配慮の行き届いた計画を立てることが重要です。綿密な計画は、後の作業の基盤となり、スムーズな移行を可能にします。
限られた期間内に作業しないといけない
システム移行は多くのステークホルダーが関わる大規模なプロジェクトであり、通常、厳密に定められた期間内での完了が要求されます。特に、システムの利用が一時的に不可能になる場合は、ユーザーへの事前通知が必須となります。
【要な考慮点】
- 予定時間内での作業完了の必要性
- 遅延による販売機会の損失や顧客満足度低下のリスク
- バッファ時間を含めたスケジュール設計
- コンティンジェンシープランの策定
これらの対策を講じることで、予期せぬ問題が発生した場合でも柔軟に対応し、定められた期間内での移行完了を目指すことができます。時間管理と問題対応の準備は、成功的なシステム移行の鍵となります。
新旧のシステムで扱えるデータが異なる場合がある
システム移行において、新旧システム間のデータ構造の違いは特に注意を要する点です。製品やバージョンの違いにより、一見同じように見えるデータでも扱い方が異なる場合があります。
【主な確認事項】
- 空白データの処理方法
- 小数点データの四捨五入設定
- ファイル形式の互換性
- 使用ソフトウェアのバージョン確認
これらの差異に対応するためには、詳細なマッピング資料の作成が有効です。また、必要に応じてプログラムの修正を検討することも重要です。データ構造以外の要素も含めて網羅的に確認することで、移行後のデータの整合性を確保し、新システムの円滑な運用を実現できます。
システム移行の失敗事例と解決策

システム移行プロジェクトでは、様々な課題に直面することがあります。本章では、よくある失敗事例とその解決策をみていきましょう。
データ損失と不整合
データは企業の生命線です。システム移行時のデータ損失や不整合は、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
データ損失の失敗事例と解決策を以下にご紹介します。
【事例1】
- 事例:不完全なデータマッピングによる情報欠落
- 解決策:綿密なデータマッピング計画の策定と複数回のテスト実施
【事例2】
- 事例:文字コードの違いによるデータ破損
- 解決策:事前の文字コード確認と適切な変換処理の実装
【事例3】
- 事例:一意性制約違反によるデータ移行の失敗
- 解決策:データクレンジングの実施とデータ整合性チェックの徹底
適切なデータ移行計画と厳格なテストプロセスを通じて、データの完全性を確保することが重要です。
パフォーマンス低下
新システムへの移行後、予期せぬパフォーマンス低下に悩まされることがあります。これはユーザーの不満や業務効率の低下につながります。
パフォーマンス低下の失敗事例と解決策を以下にご紹介します。
【事例1】
- 事例:不適切なハードウェアリソースの見積もり
- 解決策:詳細な負荷テストの実施と適切なキャパシティプランニング
【事例2】
- 事例:非効率なデータベースクエリの移行
- 解決策:クエリの最適化とインデックス戦略の見直し
【事例3】
- 事例:新旧システム間の連携による処理遅延
- 解決策:インターフェースの最適化とキャッシング戦略の導入
移行前の綿密なパフォーマンステストと、移行後の継続的な監視・調整が、安定したシステムパフォーマンスの鍵となります。
セキュリティ脆弱性の露呈
システム移行時に新たなセキュリティ脆弱性が生まれたり、既存の脆弱性が顕在化したりすることがあります。これは深刻なセキュリティリスクを招く可能性があります。
セキュリティに関する失敗事例と解決策を以下にご紹介します。
【事例1】
- 事例:新旧システム間の認証の不整合
- 解決策:統一された認証システムの導入と厳格なアクセス制御の実装
【事例2】
- 事例:移行プロセス中の一時的なセキュリティ緩和による脆弱性
- 解決策:移行手順の見直しと一時的措置の最小化
【事例3】
- 事例:新システムの未知の脆弱性の露呈
- 解決策:包括的な脆弱性スキャンの実施と迅速なパッチ適用プロセスの確立
セキュリティを移行プロジェクトの中心に据え、継続的なリスク評価と対策の実施が不可欠です。
システム移行の失敗を防ぐポイント

では、システム移行を失敗させないためにどのようなポイントに注意すべきでしょうか。
プロジェクトの規模や特性に応じて、各ポイントの比重は変わってきますが、基本的な考え方として参考にしていただければと思います。慎重な準備と実行管理で、確実なシステム移行を実現しましょう。
計画立案と現状分析はしっかりする
現行システムの課題を把握し、移行後のゴールを明確にすることが重要です。
業務フローやデータの関連性を詳細に分析し、必要なリソースと予算を洗い出しましょう。
具体的なスケジュールを立て、プロジェクトの全体像を関係者と共有することで、スムーズな移行の土台を作ることができます。
段階的な移行を行う
一度に全てを移行するのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることをおすすめします。
試験運用期間を十分に確保し、問題が発生した際の切り戻し手順も整備しておきましょう。
新旧システムの並行運用期間を設けることで、リスクを最小限に抑えながら、安全な移行を実現できます。
データ移行の品質を確保する
データ移行は最も重要な工程の一つです。事前にデータクレンジングを実施し、不要なデータの削除や形式の統一を行います。
移行手順を文書化し、チェックリストを作成することで、抜け漏れを防ぎます。また、移行後のデータ整合性を確認する手順を確立し、品質を担保しましょう。
十分なテスト実施とユーザー部門との連携を怠らない
システムの機能テストだけでなく、実際の業務フローに沿った運用テストが必要です。
ユーザー部門に早期から参加してもらい、実務者の視点での問題点を洗い出します。本番環境に近い検証環境を用意し、性能面での問題がないことも確認しましょう。
移行後のサポート体制整備
新システムへの移行後、運用が安定するまでの期間は手厚いサポートが必要です。
ヘルプデスクの設置や、操作マニュアルの整備、トラブル発生時の対応フローを確立しましょう。
定期的に利用状況をモニタリングし、必要に応じて改善を行うことで、円滑な運用を実現できます。
まとめ:システム移行はしっかり計画して失敗を回避!

本記事では、システム移行の検討タイミングや移行方式、手順についてご説明しました。主にハードウェアやOSのサポート終了時や企業統合、効率化の際に検討されています。
移行方法には一括移行、段階移行、並行運用があり、データの確保などにより困難度が高いことが分かったのではないでしょうか。時間内に正確に作業を完了させる必要があるため、高度な計画性が求められます。
システム移行はしっかり計画して失敗を回避しましょう!
システム移行についてのご質問や、移行を企業に依頼するご相談は株式会社Jiteraへご連絡ください。実績豊富なITの専門家が貴社のお手伝いをさせて頂きます。







