Linuxの世界には、データの安全性を高めるための強力なツールが数多く存在しており、その中でも特に注目されているのが「スナップショット」です。
この機能は、システムやファイルの状態を特定の時点で保存し、必要に応じてその時点に戻すことができる非常に便利な仕組みとなっています。
本記事ではLinuxスナップショットの基本から、その仕組み、使い方、さらには復元やバックアップの手順までをわかりやすく解説していきます。
データ保護のための重要な手段としてLinuxスナップショットの活用方法を学び、システム管理のスキルをさらに向上させていきましょう。
食品商社営業からシステムエンジニアへと転職後、バックエンドエンジニア(Java, PHP)として尽力。開発リーダーを含む上流工程〜下流工程に携わる。IT関連記事から芸能・法律など幅広ジャンルにて執筆。
Linuxスナップショットとは?

Linuxスナップショットは、ファイルシステムの特定時点における状態を保持する技術です。
これにより、システムやデータの変更後に問題が発生した場合でもスナップショット時点の状態に迅速に戻すことが可能になります。
特に、データの安全性を確保しながら効率的なバックアップや復元を行いたい場合に有効といえます。
Linuxスナップショットの基本情報
Linuxスナップショットは、LVM(Logical Volume Manager)を利用して実現されます。
LVMは物理ストレージを論理的に管理し、柔軟なディスク管理を可能にするシステムです。
スナップショット機能を用いることでファイルシステムの瞬間的なコピーを作成し、その後の変更が元のデータに影響を与えることなく安全なバックアップ環境を提供できます。
この技術は、データベースやファイルサーバーなどの常時データの変更が行われるシステムに特に有効といえるでしょう。
Linuxスナップショットの仕組み
スナップショットの作成時には現在のファイルシステムの状態が保存されますが、この時全データのコピーを作成するのではなく、変更があったデータのみがスナップショット領域に保存されるため効率的にスナップショットを作成できます。
具体的には、スナップショット作成後にファイルシステムに変更が加えられると変更前のデータがスナップショット領域にコピーされるため、スナップショット作成時の状態を保持しつつシステムの正常な運用を続けることが可能となります。
そのためスナップショットは、データの整合性を保ちながらバックアップを取る必要がある場合やシステムのアップグレード前に現在の状態を保存しておきたい場合などの様々な状況で活用できます。
Linuxスナップショットの使い方

Linuxスナップショットは、システムやデータの安全なバックアップと復元を可能にするツールです。
特にLVM(Logical Volume Manager)を使用することでファイルシステムの瞬間的な状態を捉え、その後の変更が原データに影響を与えないようにできます。
ここではLinuxスナップショットの取り方、復元方法、およびバックアップ手順について具体的に解説していきます。
Linuxスナップショットの取り方
スナップショットを取る工程はLVMの機能を利用して行われます。
まず、fdiskやその他のツールを使用してLVM用のパーティションを準備し、pvcreateコマンドでこれを物理ボリュームとして登録します。
次に、vgcreateコマンドで物理ボリュームを含むボリュームグループを作成し、lvcreateコマンドを使用してボリュームグループ内に論理ボリュームを作成します。
最後に、lvcreateコマンドに–snapshotオプションを付けて、論理ボリュームのスナップショットを作成します。
この際、スナップショットのサイズと名前を指定することが重要です。
Linuxスナップショットの復元方法
スナップショットからの復元工程は、システムやデータをスナップショット時点の状態に戻すことを目的としています。
まず、mountコマンドを使用してスナップショットを読み取り専用でマウントします。
次に、cpやrsyncなどのコマンドを使用してスナップショットから必要なデータを元の場所にコピーします。
その後、必要に応じてシステムを再起動し、変更を適用します。
Linuxスナップショットのバックアップ手順
スナップショットを利用したバックアップは、データの整合性を保ちながら効率的に行うことができます。
まず、上記の手順に従ってスナップショットを作成し、作成したスナップショットを読み取り専用でマウントします。
次に、dumpやtarなどのツールを使用してマウントしたスナップショットからバックアップを取ります。
バックアップが完了したらスナップショットをアンマウントし、不要になったスナップショットはlvremoveコマンドで削除します。
Linuxスナップショットのコマンドと確認方法

Linuxスナップショットは、システムの特定の状態を記録して必要に応じてその状態に戻ることができる非常に強力な機能です。
特にLVM(Logical Volume Manager)やSnapperなどのツールを使用することで、このプロセスを簡単に実行できます。
ここでは、Linuxスナップショットに関連するコマンドとスナップショットの容量を確認する方法について具体的に解説していきます。
Linuxスナップショットのコマンド一覧
LVMによるスナップショットのコマンド
LVMを使用したスナップショットの作成、管理、削除には以下のコマンドが使用されます。
スナップショットの作成では「lvcreate --size [サイズ] --snapshot --name [スナップショット名] [元の論理ボリュームのパス]のように使用します。
例えばlvcreate --size 1G --snapshot --name snap0 /dev/vg0/lv0というような形です。
スナップショットの削除では「 lvremove [スナップショットのパス]」」のように使用します。
例えばlvremove /dev/vg0/snap0というような形です。
スナップショットの一覧表示では「 lvs 」または「 lvdisplay」を使用します。
Snapperによるスナップショットのコマンド
Snapperを使用すると、より高度なスナップショット管理が可能になります。
以下はSnapperを使用したスナップショットの基本的なコマンドです。
スナップショットの作成では「snapper -c [設定名] create --type pre/post/single」のように使用し、snapper -c root create --type preというような形で用います。
スナップショットの一覧表示では「 snapper -c [設定名] list」、スナップショットの削除では「 snapper -c [設定名] delete [スナップショット番号]」、スナップショット間の差分表示では「 snapper -c [設定名] diff [スナップショット番号1]..[スナップショット番号2]」のようにコマンドを使用できます。
Linuxスナップショットの容量確認方法
Snapperはスナップショットの容量を直接表示するコマンドを提供していませんが、snapper -c [設定名] list コマンドを使用してスナップショットの一覧を表示した後、各スナップショットのファイルシステム上での変更を確認することで間接的に容量を把握することができます。
スナップショット間の差分を確認することで、どの程度のデータが変更されたかを見積もることが可能となります。
「スナップSnapshot Replication」から「スナップショット」に移動し、共有フォルダを選択します。
次に、「スナップショット」から「サイズの計算」をクリックした後、期間を指定して計算を開始させると選択した時間枠内に撮影されたスナップショットの数を見ることができます。
削除の場合は、削除したい期間を指定して削除してあげれば容量が解放されます。
Linuxスナップショットの起動方法

Linuxスナップショットの起動方法には特に難しい手順は含まれないため、LVM(Logical Volume Manager)を利用して起動していきましょう。
ここではLinuxスナップショットの起動手順とその活用法について、具体的に説明していきます。
Linuxスナップショットの起動手順
Linuxスナップショットの起動は、主にLVMを用いたスナップショットの作成とそのスナップショットを利用したシステムやデータの復元があります。
以下では、スナップショットの作成から、そのスナップショットからのデータ復元やシステムの回復までの一連の手順です。
スナップショットの作成
fdiskやその他のツールを使用してLVM用のパーティションを準備し、pvcreateコマンドで物理ボリュームを作成します。
vgcreateコマンドでボリュームグループを作成し、lvcreateコマンドに–snapshotオプションを付けてスナップショットを作成します。
スナップショットのマウント
作成したスナップショットを読み取り専用でマウントし、データの確認や必要な情報の抽出を行います。
データの復元
スナップショットから必要なデータを選択し、元の場所や新しい場所に復元しますが、これにはcpやrsyncなどのコマンドが使用されます。
システムの再起動
データ復元後、必要に応じてシステムを再起動して変更を適用していきます。
Linuxスナップショットの活用法
Linuxスナップショットは、データ保護とシステム管理の観点から多岐にわたる活用が可能です。
ここでは、その主な活用法を紹介していきます。
データの即時バックアップ
スナップショットを利用してデータの即時バックアップを作成し、データの損失や破損のリスクを最小限に抑えます。
これにより、システムの稼働中でもデータの整合性を保ちながらバックアップを取ることが可能になります。
システムの迅速な復元
システム障害やデータ損失が発生した場合、スナップショットを利用して迅速にシステムを以前の状態に復元できます。
これにより、ダウンタイムを大幅に短縮して損失を最小限に抑えることができます。
開発環境の管理
開発環境やテスト環境での変更をスナップショットとして保存し、必要に応じて簡単に以前の状態に戻すことができるため、新しい機能のテストやバグ修正作業を効率的に行うことが可能になります。
データ分析のための時点復元
特定の時点のデータをスナップショットとして保存し、後からその時点のデータにアクセスして分析することができます。
これは、データのトレンド分析や監査などに有効といえるでしょう。
linux スナップショットのまとめ
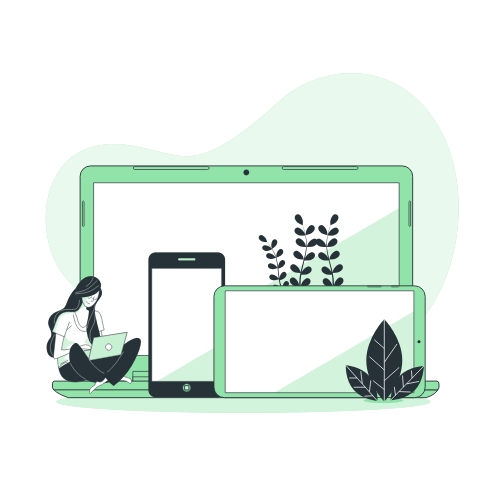
この記事では、LVMを用いたスナップショットの基本的な取り方から復元方法、バックアップ手順まで、Linuxスナップショットの仕組みや使い方について解説してきました。
Linuxスナップショットは、システムやデータの瞬間的な状態を保存してあとからその時点に戻ることができるという強力で便利な機能です。
また、スナップショットはデータの安全性を確保しつつ、効率的なバックアップや復元を行いたい場合に特に有効で、開発環境の管理やデータ分析のための時点復元などの多岐にわたるシナリオでの活用が期待されるため、これが活用できると開発・運用の上で心強い味方となってくれるでしょう。
今回のテーマであるlinuxをはじめ、システム開発やAI関連技術はJitera社の最も得意とする領域です。
お悩みがある方や案件のご依頼がある方は、Jitera社へ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。







