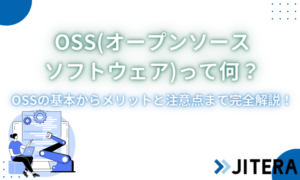最近では、パソコン本体を含め、様々なパソコン周辺機器が存在しています。中でもパソコンを自作する際、多種多様なパーツを集めて、パソコンを組んでいく必要があります。
パソコンを初めて取り扱うときに、どれがどのような役割をしているのか、解らない方が多いかと思います。そこで今回は、パソコンパーツの一部である、CPUと呼ばれる部品について、徹底解説していきます。
主にパソコンで使用されるCPUを紹介しますが、ゲーム向けCPUや、スマホ等に搭載されているCPUについても説明していきますので、それぞれ詳しく知りたい方は、最後までご参照ください。
某電子専門学校卒業後、サーバー/ネットワーク運用業務を通し、ネットワーク設計/構築事業をメインにインフラ業務全般を担当。その後、某情報セキュリティ会社にて、情報セキュリティ教育事業の教育係も担当。
CPUとは何ですか?

ここではCPUについて、概要や役割、その基本構成と動作原理について解説します。CPUと一つとっても、様々な種類があり、種類ごとに主な役割が違ってきます。
またCPUはそれぞれの種類で構成が微妙に違っていたりします。しかし、動作原理はどのCPUでもそれほど違いはありません。それぞれ詳しく説明していきます。
CPUの概要と役割
CPUの概要と役割ですが、まずCPUはCentral Processing Unitの略称であり、日本語で訳すと中央演算装置となります。CPUはパソコンが初めて登場して以来、長い間使用されているパソコンのパーツとなります。
このCPUが無いと、そもそもパソコンとして動作せず、パソコン本体はただの箱になってしまいます。元々パソコンには、CPU以外にメモリやストレージ、グラフィックボードやマザーボード及び電源とよばれるものが全て動作し、組み合わせる事でパソコン本体として動作します。これらのどれか一つでも欠けると、パソコンとして機能しません。
そして、CPUの役割ですが、CPUはパソコン本体の中でも頭脳のような役割として作動していきます。このCPUが動作することで、パソコンを操作している人間が、パソコンを介してマウスやキーボードから入力することで、その動作をCPUが読み取り、それぞれのパーツへ返答をし、結果的に人間が操作した結果に帰ってくるのです。
CPUの役割はそれだけではありません。パソコン本体のストレージにインストールしてあるソフトウェアが実行されたとき、CPUは人間の脳の速さを超えるスピードで、パソコン本体全体に様々な指示をします。それぞれのパーツへ指示された結果を再度CPUが処理をし、その結果を抽出することで、ストレージや画面に出力されます。これがパソコンにおけるCPUの役割です。
CPUの基本構成と動作原理
パソコンと呼ばれるものが登場した初期のCPUは、CPUと呼ばれていたり、MPUと呼ばれていました。何故かというと、初期のパソコンは小型化や軽量化などが考えられておらず、初期のCPUはとても巨大なものだったのです。
その問題を解決するために登場したのが、MPUと呼ばれるものです。CPUはCentral Processing Unitの略称に対して、MPUはMicro Processing Unitと呼ばれていて、MPUはCPUを小型軽量化されたものとして開発されました。その後、小型化されたCPUが一般的になっていき、MPUと呼ばれるものが無くなっていきました。
現在のCPUの構成は、演算装置と制御装置の二つのシステムから作動しています。主記憶装置から命令が出された際に、制御装置が命令を受理し、その処理を制御装置内のデコーダと呼ばれるものから、演算装置へ転送します。その演算装置の中で様々な情報交換をし、整合性が取れたら、演算装置から主記憶装置へ結果を出力します。これがCPUの基本動作です。
CPUが動作する際、CPU内部のそれぞれの装置にデータが流れる部分をパスと呼びます。CPU内部を何度も行き来しなければならない場合は、キャッシュと呼ばれるメモリにより、効率よく内部で演算をします。
演算装置は、大まかに以下の三つで構成されています。
- 算術論理演算装置
- レジスタ
- アキュムレータ
制御装置は以下の3つにより、構成されます。
- カウンタ
- レジスタ
- デコーダ
これらがCPUの動作原理とその基本構成になります。
パソコン関連についてもっと知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
ゲーム・スマホ向けCPUの性能について

ここまでCPUの役割からその詳細、CPUの基本構成と動作原理について解説していきました。ここではパソコンだけでなく、パソコンでゲームをする際のCPUや、スマホで利用されるCPUについて詳しく解説していきます。
現代では以前のように、プログラマーや、クリエイターのみがパソコンを使用するのではなく、ゲームやスマホの登場により、幅広い層のユーザーの間で様々なCPUが利用されるようになりました。それぞれ説明します。
ゲーム向けCPUとスマートフォン向けCPUの違い
| 項目 | 処理速度 | 耐熱性 |
| ゲーム向けCPU | とても速い | ある程度の冷却性能があるファンが必要 |
| スマホ向けCPU | 標準よりやや速い | 耐熱性に優れている |
ゲーミングパソコンの普及前は、それほど高い処理速度を必要とするCPUは求められておらず、安定した動作をするCPUが主に開発され、販売されていました。ゲーミングパソコンの普及により、プログラミングだけでなく、快適にゲームを遊ぶために、高い処理能力が要求されるCPUが必要になりました。
それ故に、現代の主なゲーム向けCPUは、Intel社のCore i7やCore i9シリーズと呼ばれるものが爆発的に売れるようになったのです。さらにゲーミングに特化したCPUでありながらも、コスパも高いAMD社のRyzenシリーズと呼ばれるCPUも登場しました。現代のゲーミングパソコンに利用されるCPUはこれらが一般的です。
ではスマートフォン側ではどうかというと、SoC(CPUとも呼ばれます)と呼ばれるものがメインとなっています。SoCとは、System on a Chipの略称であり、スマートフォン内部の演算処理を行います。SoCもパソコンと同じく処理速度が速ければ速い程、スマホの操作が快適になります。
パソコンのCPUとSoCの動作原理自体は同じですが、役割が違います。パソコンで必要とされるCPUは、とにかく処理をたくさんしなければならないため、電気と熱を大量に消費します。
対してSoCは発熱とバッテリーの消費を最小限にするため、処理速度はパソコン程には及びません。その代わり、電力の消費と発熱があまりなく、どちらかというとオールラウンダー的な役割をしていて、処理速度もそこそこ早いが、効率よく動作するSoCを搭載しているスマホが多いです。
これらがパソコンのCPUとSoCの大きな違いです。
CPUの性能を測定する指標とその意味
CPUの性能を測定する指標とその意味は、何度か触れていますが、CPUの性能が高ければ高い程、パソコンを操作する上で、とても快適になります。特に現代では、VTuberやWeb及び動画クリエイターなど、パソコンを使用する上でリソースをとても多く消費する職業が増えました。
これにより、高い性能を誇るCPUが必要になったのです。その高い性能のCPUは、どのような指標からなるのかというと、以下の4つとなります。
- クロック周波数
- コア数
- スレッド数
- キャッシュ
これら4つの総合的な指標で、CPUの性能がどれくらいかがわかります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずクロック周波数ですが、この数値が高ければ高い程、CPUの処理速度が高いです。クロック周波数とは、CPUが一秒間に命令できる総数を表していて、定格のクロックと、独自のオーバークロックと呼ばれる動作をCPUにさせる事で、高速にCPU動作させるものも存在します。
次にコア数ですが、CPU内部に処理させる頭脳のようなものを指します。以前までのCPUは、シングルコア呼ばれていて、内部に処理させるものが一つしかありませんでした。現代のCPUはマルチコアと呼ばれるものが一般的となり、このコア数が多ければ多い程、効率的にCPUが動作する為、コア数で、ある程度のCPUの性能の指標となります。
スレッド数ですが、コアの中で余分に余った力を、そのスレッドに割り当てる事で、よりCPUの力を発揮させるものです。主に一つのコアに対して2つのスレッドが割り当てられる事が多いです。例えば4コア8スレッドなどと表記され、基本的にはコア数とスレッド数を総合的に記載します。
最後にキャッシュですが、キャッシュメモリとも呼ばれていて、主記憶装置と演算装置を行き来する際、同じ道を何度も辿っていると無駄にCPUの力を消費してしまいます。キャッシュメモリを搭載する事で、同じ処理を何度もすることなく蓄積していき、CPUの処理効率を上げられます。キャッシュメモリ数が高ければ高い程、CPUの処理効率は上がります。
これらが、CPUにおける性能の指標と言えるでしょう。
CPUの選び方

ここまでCPUとは何か、CPUの役割、CPUの基本動作、ゲーム向けCPUとスマホ向けCPUの違いについて、それぞれ解説してきました。ここでは実際にパソコンを組み立てるとなったとき、どのような要素でCPUを選べばよいかを解説していきます。
それぞれのCPUの比較や、どのようなポイントでCPUを選ぶか、詳しく説明します。
自分のニーズに合ったCPUを選ぶポイント
CPUを選ぶ際は、自分がどのようにパソコンを使うかによって、選択肢が変わってきます。例えばビジネスでパソコンを組み立てる場合、グラフィックにそれほど力を必要としませんし、高速な処理速度を要求せず、どちらかというと長く安定した動作をしてくれるCPUを選ぶ必要があります。一方ゲーミングパソコンを組む場合は、動作の安定性よりも、より高速で動作し、グラフィックと相性の良いCPUを選んでいきます。
このように、CPUを選ぶ際は、それぞれ得意分野があるので、自分がどういった用途でパソコンを組むのかを第一の焦点で選ぶと良いでしょう。さらにCPUは、省電力性のものや、ファンを必要としないものもあります。例えばノートパソコンでの例を挙げます。ノートパソコンは主にビジネスで利用されるパソコンであり、軽量でバッテリー持ちが良いものが要求されています。
そうなった時、CPUが低電圧性に優れたものであれば、ノートパソコンのバッテリーが減ることを抑えたり、冷却ファンレスで動作するCPUであれば、ファンレスなのでノートパソコン本体が軽量であることが多いです。このようにパソコンはデスクトップだけでなく、ノートパソコンでもシーン毎に利用するCPUを想定していきます。
主要CPUメーカーの比較と特徴
主要CPUメーカーの比較と特徴を解説していきます。主要CPUメーカーは、Intel社とAMD社になります。パソコンが発売されるようになってから、長年継続的に使用されているCPUはIntel社製となっていて、CPUを選ぶ際はAMD社製よりIntel社製の方が、選定する方が多いです。
何故かというとIntel社に関しては長年のナレッジが、さまざまなBTOパソコン業者や、パソコン周辺機器メーカーに蓄積されているので、必然的にIntel社が選択されます。しかしAMD社は昨今CPUに力を入れていて、熱伝導効率やコストパフォーマンスの高いCPUを次から次へと販売し、利益を上げています。
AMD社製のCPUは、性能の割にはIntel社と比べてとても安価で販売されているので、Intel社のCPUでパソコンを組むのに予算が合わない場合、AMD社製のCPUを代わりに導入する事で、予算内に収めている方もいます。また発熱に関しても、Intel社製のCPUと比べてとても熱を持ちにくく、長時間のCPU負荷にも耐えることが特徴と言えるでしょう。
対してIntel社製のCPUは、動作がとても安定していて、高速に動作する点が特徴です。さらに先ほども述べましたが、Intel社製のCPUは沢山のナレッジが蓄積されているので、トラブルが発生した際などで、インターネット上から情報収集する際、とても速いスピードで問題解決ができます。
ただし、Intel社製のCPUは、ハイエンドであればあるほど熱を持ちやすく、熱を持ちすぎてサーマルスロットリングと呼ばれる、発熱防止機能が働き、CPUの動作が制限されてしまいます。さらに、Intel社製のCPUは、ハイエンドモデルについては、高価なものが多いです。
CPUの温度確認方法

ここまでCPUの役割、基本構成と動作原理、ゲーム向けCPUとスマホ向けCPUの違いから、CPUを選ぶ際のポイントまで解説していきました、最後にCPUの温度について詳しく解説します。CPUは性能に加えて、熱対策も重要になってきます。
CPU温度の重要性と影響
CPU温度の重要性と影響について説明します。パソコンパーツ全般に言える事なのですが、パソコンパーツはとても熱に弱いです。特にCPUは、高い温度の中で長い間稼働していると、CPUの内部制限であるサーマルスロットリングが動作し、CPUの性能が極端に低くなります。
さらに、その状態が続くと、どんどんCPUが劣化していき、最終的にはCPUが故障する可能性もあります。そうならないように推奨されているのが、CPUの熱を外に逃がす、CPUファンと、そのCPUファンへの熱伝導率を上げるためのサーマルグリスと呼ばれるものを使用することです。
CPUファンは、その名の通りCPUを冷却してくれるクーラーのようなものであり、CPUに直接ファンを取り付けて、空冷で熱を逃がすものと、ラジエーターとファンを繋げたものを使用し、ラジエーターの先からCPUを取り付ける事で、水とポンプの力で冷却する、水冷クーラーと呼ばれるものがあります。
空冷は大分前から使用されているCPU冷却方法であり、水冷と比べて安価である点と、設置が容易である点が評価されています。
対して水冷は、ラジエーターと冷却ファンをパソコン本体にネジ止めし、ラジエーターの先をCPUにマウントする事で設置をするので、設置が容易ではない点と、高価な点が難点ですが、空冷と比べて格段に熱を逃がす力が強いです。
そして、空冷ファン、水冷ファンともに使用する際、それぞれのCPUとファンの接着面にグリスを塗ります。グリスにも様々に種類があり、使用するグリスの熱伝導率により、CPUの熱をファンへ逃がす力が変わってきます。熱伝導率が高ければ高い程CPUは安定して動作しますが、グリスの値段も高価になります。
空冷ファンは5、6年は問題なく稼働しますが、水冷ファンは3年程度で劣化していきます。
一点注意点ですが、IntelのCore i9シリーズのCPUは基本的に水冷による冷却を前提に販売されています。
CPUは、こういった様々な熱問題に対して、対策をしていかなければならない為、CPUを選定する際は自身がどのようにパソコンを使用していくかをよく考えて、CPUを選んでいきます。
CPU温度を確認する方法とツール
パソコンを組み上げて、OSをインストールし、実際にパソコンを使用するとなった場合、CPU温度を計るツールを導入する必要があります。特にゲーミングパソコンやクリエイターが使用するパソコンは、基本的にグラフィックボードとCPUにとても負荷をかけるので、必ずCPU温度を確認できるツールを利用しましょう。
その際すぐ確認出来るツールは、Windows OSに予め機能として入っているパフォーマンスモニターを使用しましょう。確認方法は以下の通りです。
1.まずデスクトップ上のWindowsロゴを右クリックし、コンピューターの管理をクリックします。
2.すると新規に画面が出力されます。そこからパフォーマンスという箇所をダグルクリックすると、パフォーマンスモニターと表示されますので、そこから+ボタンをクリックします。
3.新規に画面が出力されますので、一覧の中からThermal Zone Informationをダブルクリックします。
4.出力された一覧からTemperatureをクリックしOKをクリックします。
これでCPUの温度を常時確認できるようになります。
CPUの温度が確認できるようになったら、実際に自分がパソコンを使った作業で、どれくらいCPU温度が上がるかチェックしてみましょう。もし問題になるほど温度が高くなるのであれば、CPUファンを変えるか、グリスを熱伝導率が高いものに変えるか、等の検討をするとよいです。
また、マザーボードの電圧を適宜変更する事で、CPUの電力を低電圧化し、熱が出るのを防げます。ただし、この作業はある程度パソコンに詳しくないとできませんので、基本的にファンの取り換えが必要となってくるでしょう。
CPUのまとめ

ここまでCPUの役割から基本構成、ゲーム向けCPUとスマホ向けCPUの違い、CPUの選び方からCPUの温度について解説してきました。現代では、パソコンは社会人から学生まで幅広く使用されるようになりました。
特にIT機器を使用する会社員や、クリエイターなどはパソコンの使用は必須となります。しかし、用途によって使用するCPUやパーツはさまざまに変わってきます。
自分がどのようにパソコンを使用するのか、予め想定してからパソコンをBTOメーカーに発注したり、自分で組み立てるようにしましょう。特にCPUは高価で壊れやすいパーツですので、CPUについては十分検討してから選定しましょう。
もしパソコンのキッティングを依頼したいのであれば、株式会社Jiteraに相談すると良いです。こちらのページからキッティングする案件の詳細を記載すれば、折り返し詳しい提案をしてもらえます。