オンライン診療は、医療機関で医療専門家と患者がインターネットを介して、遠隔で医療相談や診療を行うことができるものです。
この記事では、オンライン診療での手順や料金、ほかにもおすすめなアプリなどを紹介しています。
この記事を読んで、オンライン診療のことを深く理解して、利用するかどうかの参考にしてください。
20年超のシステム開発経験を活かし、AI・機械学習のエバンジェリストとして活動中。新技術の追求と、日本のAI活用を世界一に導くことに情熱を注ぐ。開発の全工程に精通し、知識と行動力で未来を切り拓く。
オンライン診療とは

オンライン診療は、情報通信技術(ICT)を活用し、患者と医療提供者が物理的に同じ場所にいない状態で行う医療サービスです。ビデオ通話やチャット、電子メールなど、多様な通信手段を用いて遠隔で診療を行うことができ、テレヘルスサービスの一つとして位置づけられています。
診察や相談、経過観察など、用途に応じて最適な通信技術が選択され、医療サービスの提供が行われます。患者の個人情報保護とセキュリティ対策が重要視され、オンライン診療プラットフォームやツールには適切な保護措置が必要不可欠です。
ただし、物理的な検査や処置ができないなどの制約があり、緊急時や症状の程度によっては、従来の対面診療を選択する必要があります。これらの特徴と限界を理解した上で、適切に活用することが重要です。
オンライン診療と遠隔医療の違い

定義と範囲の広さ
遠隔医療は、情報通信技術(ICT)を活用したあらゆる医療サービスを包括する広い概念です。医師と医師の間での専門的な連携(D to D)、医療機関同士の連携、健康管理や予防医療まで含む幅広い医療サービスをカバーしています。
例えば、離島や僻地の医療機関と都市部の専門医を結ぶ診断支援や、在宅患者の遠隔モニタリング、さらには予防医療のための健康相談なども含まれます。
一方、オンライン診療は遠隔医療の一部として位置づけられ、医師と患者(D to P)の間で行われる診療に特化したサービスを指します。
具体的には、ビデオ通話などを介して行う診察、診断、処方などの医療行為に限定されており、より狭い範囲での医療提供形態となっています。医師法や厚生労働省の指針に基づいて実施される必要があり、明確な規定のもとでサービスが提供されます。
診察形態や方法
遠隔医療では、医療機関間での画像診断の共有、専門医への相談、在宅患者のモニタリング、健康指導など、様々な形態でのサービス提供が行われます。
通信手段も電話、メール、専用システムなど多岐にわたり、目的に応じて柔軟に選択されます。また、医療データの長期的な収集や分析、AIを活用した診断支援なども遠隔医療の重要な要素となっています。
これに対し、オンライン診療は、原則としてリアルタイムのビデオ通話を用いた視覚的な診察が基本となります。医師が患者の状態を直接確認しながら診療を行う必要があり、より厳格な実施形態が定められています。
診療の質を担保するため、画質や音質の基準、プライバシーの確保、緊急時の対応体制など、具体的な要件が設定されており、これらを満たした上でサービスを提供することが求められます。
対象者
遠隔医療は、医療従事者間の連携、医療機関と患者、健康な人々への予防医療まで、幅広い対象者をカバーしています。
医師、看護師、専門医、患者、一般市民など、医療に関わるすべての人々が対象となり得ます。特に医療機関同士の連携においては、専門医の少ない地域での医療の質向上や、緊急時の迅速な対応を可能にする重要なツールとして活用されています。
一方、オンライン診療は、基本的に医師と患者の1対1の診療を前提としています。また、すべての患者が対象となるわけではなく、症状や状態によって利用可能かどうかが判断され、かかりつけ医による事前の対面診療が必要とされるなど、一定の制限が設けられています。
特に初診の場合は原則として対面診療が必要とされ、継続的な診療関係が確立されている場合に限ってオンライン診療が認められる仕組みとなっています。
提供サービス
オンライン診療のサービス内容は、主に「症状相談と診察」「処方箋の発行」「検査結果の解説」の3つに分類されます。
症状相談と診察では、患者が抱える健康上の不安や具体的な症状について、ビデオ通話を通じて医師に相談し、診療を受けることができます。
必要に応じて画像や動画を提供することで、より詳細な診察も可能です。ただし、直接の触診ができないなどの制限があることにも留意が必要です。
処方箋の発行では、医師による症状評価の後、オンラインプラットフォームを通じて電子処方箋が発行され、患者はこれを用いて薬局で薬を受け取ることができます。
検査結果の解説では、血液検査や画像検査などの結果について、医師がオンラインで詳しく説明し、必要に応じて追加の検査や治療計画を提案します。患者からの質問や不安にも丁寧に対応し、適切な情報提供とフォローアップを行います。
これらのサービスにより、患者は場所や時間の制約を受けることなく、必要な医療サービスを受けることが可能となっています。
オンライン診療のメリット
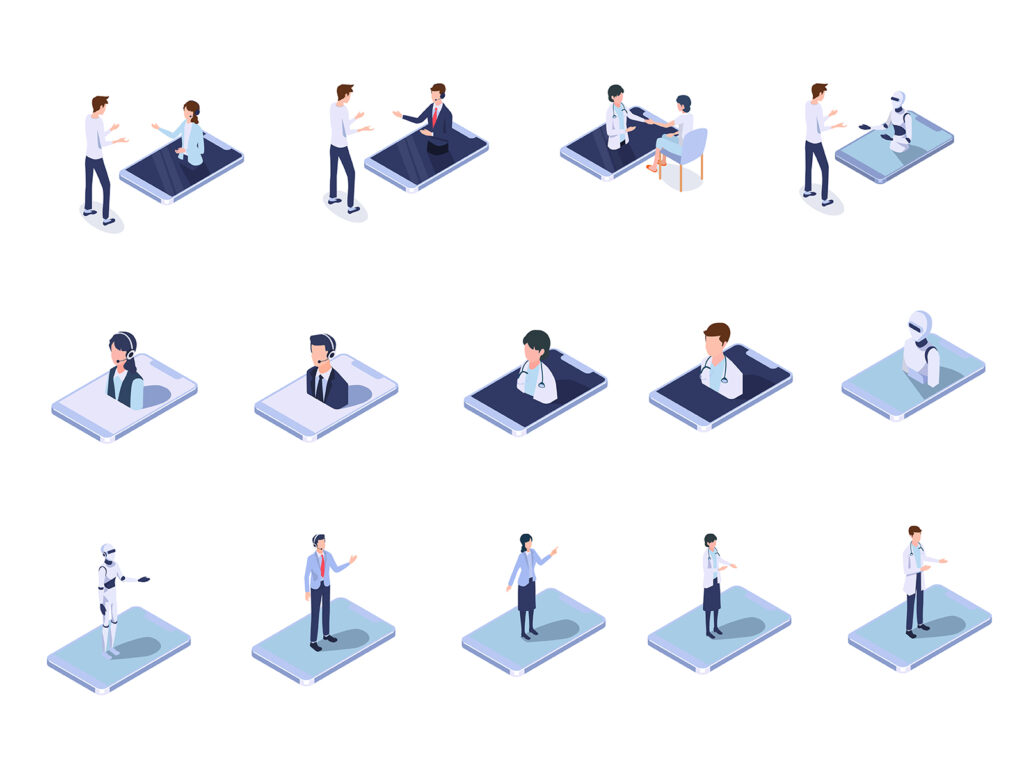
オンライン診療には多くのメリットがあり、おもに以下のようなものがあります。
- 通院の手間を省ける
- 感染リスクが減らせる
- 時間を有効に活用できる
- 地理的な制約が解消できる
- 継続的な健康管理がしやすい
それぞれ詳しく説明していきます。
通院の手間を省ける
オンライン診療の最大のメリットの1つが、通院にかかる様々な手間を省けることです。
従来の対面診療では、医療機関までの往復時間、待合室での待ち時間、さらには交通費や駐車場代などの経済的負担が必要でした。特に定期的な通院が必要な慢性疾患の患者さんにとって、これらの負担は決して小さくありません。
しかし、オンライン診療では、自宅や職場からスマートフォンやパソコンを使って診療を受けることができるため、移動の必要がなく、待ち時間も最小限に抑えられます。
また、交通費や駐車場代などの付随的な費用も不要となり、経済的な負担の軽減にもつながります。これにより、患者さんは必要な医療サービスをより手軽に、効率的に受けることができます。
感染リスクが減らせる
オンライン診療は、感染症対策の観点から非常に有効な医療提供手段です。従来の医療機関での対面診療では、待合室や診察室で他の患者さんと接触する機会が避けられず、特に感染症が流行している時期には感染リスクが懸念されていました。
しかし、オンライン診療では自宅など安全な環境から診療を受けることができるため、医療機関内での感染リスクを大幅に軽減できます。これは、高齢者や基礎疾患をお持ちの方など、感染症に対して特にリスクの高い患者さんにとって重要なメリットとなります。
また、感染症の患者さん自身が他の患者さんへ感染させてしまうリスクも防ぐことができ、地域全体の感染対策にも貢献します。
時間を有効に活用できる
オンライン診療は、患者さんの貴重な時間を効率的に活用することを可能にします。
従来の対面診療では、診療時間以外にも通院のための移動時間や待合室での待ち時間など、多くの時間を要していました。特に仕事や育児で忙しい方にとって、これらの時間的負担は大きな課題となっていました。
オンライン診療では、予約した時間に合わせて自宅や職場から診療を受けることができ、移動時間が不要で待ち時間も最小限となります。空いた時間を仕事や家事、育児などに充てることができ、ワークライフバランスの改善にもつながります。
また、医療機関の診療時間に合わせる必要がある程度軽減され、より柔軟なスケジュール調整が可能となります。
地理的な制約が解消できる
オンライン診療は、地理的な制約による医療アクセスの格差を解消する重要な手段となります。特に地方在住の方や、専門医の少ない地域にお住まいの方にとって、希望する医療機関への通院は大きな負担となっていました。
また、交通手段が限られている高齢者や、身体的な理由で移動が困難な方々にとっても、医療機関へのアクセスは重要な課題でした。
オンライン診療では、場所に関係なく必要な医療サービスを受けることができ、専門医による診療も距離を気にせず受けられます。これにより、居住地による医療サービスの質の差が軽減され、より多くの方が適切な医療を受ける機会を得ることができます。
継続的な健康管理がしやすい
オンライン診療は、患者さんの継続的な健康管理をサポートする優れたツールとなります。
定期的な診療や経過観察が必要な慢性疾患の患者さんにとって、通院の負担が軽減されることで、より確実な受診が可能となります。また、日々の体調の変化や気になる症状について、タイムリーに医師に相談することができ、早期発見・早期対応にもつながります。
さらに、血圧や体重などの健康データを継続的に共有することで、医師はより詳細な経過観察が可能となり、それに基づいた適切なアドバイスを提供できます。
このように、オンライン診療は日常的な健康管理をより効果的かつ効率的に行うことを可能にし、患者さんのQOL(生活の質)の向上に貢献します。
オンライン診療のデメリット

オンライン診療には、いくつかのデメリットがあり、注意が必要です。
以下は、そのおもなデメリットとなります。
- 診察に制限があり質が担保しにくい
- 緊急時の対応が難しい
- 技術的に課題がある
- セキュリティとプライバシーに懸念がある
- 制度が整っていない
こちらも、それぞれ詳しく解説していきます。
診察に制限があり質が担保しにくい
オンライン診察にあたり、診療科別の制限事項が考えられます。
一般診療科
- 身体的な触診や詳細な検査が必要な場合に制限あり
- バイタルサインの正確な測定が困難(血圧、体温、脈拍等)
- 緊急性の判断が視覚情報のみに限定される
- 患者の全身状態の総合的な評価が制限される
皮膚科
- 画質や照明条件により、病変の色調や性状の正確な判断が困難
- 触診による硬さや温度などの情報が得られない
- 皮膚生検などの検査が実施できない
- 写真では捉えにくい微細な変化の観察が制限される
内科
- 聴診による心音・呼吸音の評価が不可能
- 腹部触診などの重要な診察手技が実施できない
- 緊急時の即時対応が困難
- 複雑な症状の場合、総合的な判断が制限される
精神科
- 非言語的コミュニケーションの一部が把握しづらい
- 患者の微細な表情変化や身体言語の観察が制限される
- 緊急時や危機介入が必要な場合の即時対応が困難
- 重度の症状を持つ患者への対応に制限がある
緊急時の対応が難しい
オンライン診療では、急激な症状の悪化や緊急事態が発生した際の即時対応に限界があります。画面越しの診察では、患者の急変に対して医師が直接的な処置を行うことができません。
例えば、重度のアレルギー反応や急性の腹痛、呼吸困難などの症状が現れた場合、医師は救急車の手配を指示することしかできず、その場での応急処置や緊急治療が実施できません。また、通信障害や機器トラブルが発生した際に、緊急時の連絡手段が断たれてしまう危険性もあります。
このため、重症度や緊急性の高い症状がある場合は、従来の対面診療や救急医療機関の受診が推奨されます。患者自身も、自分の症状が対面診療を要するレベルなのか、オンライン診療で対応可能なのかを適切に判断する必要があります。
技術的に課題がある
オンライン診療の実施には、安定したインターネット環境と適切な機器の操作が不可欠です。
しかし、通信速度の遅延や接続の不安定さにより、スムーズな診療が妨げられることがあります。特に画質や音質の問題は深刻で、症状の詳細な観察や微妙な表情の変化、声の様子などを正確に把握することが困難になる場合があります。
また、高齢者やデジタル機器の操作に不慣れな方々にとって、スマートフォンやタブレットの設定や専用アプリの使用は大きな障壁となっています。
機器の設定方法が分からない、アプリの操作に戸惑う、予約システムの利用が難しいなど、技術的なハードルが診療へのアクセスを制限してしまう可能性があります。さらに、患者側の機器のスペックや設定によっては、必要な機能が十分に活用できないケースも考えられます。
セキュリティとプライバシーに懸念がある
オンライン診療では、患者の個人情報や診療データがインターネットを介してやり取りされるため、情報セキュリティの確保が重要な課題となっています。
データの暗号化や適切なセキュリティ対策が実施されていても、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクは完全には排除できません。また、診療中の会話や映像が第三者に傍受される可能性も懸念されます。
特に、患者が自宅や職場など、プライバシーが十分に確保できない環境で診療を受ける場合、周囲に会話が聞こえてしまうなどの問題が発生する可能性があります。
さらに、医療機関側のデータ管理体制や、使用するプラットフォームのセキュリティレベルにも差があり、統一された基準の確立が求められています。
制度が整っていない
オンライン診療に関する制度面では、まだ多くの課題が残されています。
特に処方できる薬剤には制限があり、麻薬や向精神薬、睡眠薬など、厳重な管理が必要な医薬品はオンラインでの処方が認められていません。また、保険適用の範囲も限定的で、すべての診療科や症状に対して保険診療が適用されるわけではありません。
さらに、診療報酬の設定においても、対面診療との均衡や適切な評価基準の確立が課題となっています。医療機関側にとっても、オンライン診療に対応するための設備投資やシステム導入のコストが負担となっており、特に小規模な医療機関では導入が進みにくい状況です。
このような制度面での未整備は、オンライン診療の普及と質の向上を妨げる要因となっています。
オンライン診療の料金体系と保険適用

オンライン診療では、対面診療と同じ感覚で利用できるサービス内容であることがわかりました。
では、このオンライン診療の料金体系と保険適用は、どのようになっているのでしょうか?
ここでは、以下の項目に分けて、オンライン診療の料金などをみていきます。
- 一般的なオンライン診療の料金
- 健康保険の適用範囲
各項目を見ながら、対面診療との違いを比較してみてください。
一般的なオンライン診療の料金
オンライン診療には、保険適用と自費の2種類があるため注意が必要です。保険適用となる費用は、対面診療と同じく保険が適用されますが、自費の場合は、病院やクリニックによって料金が異なります。
オンライン診療の料金は病院によって幅広く、相場は2,500〜5,000円となることが多いでしょう。なお、オンライン診療の料金には、診察代・システム利用料・処方箋代・医学管理費・診断書代などが含まれます。
診察代は、保険診療であれば700円で、3割負担の場合は210円と、国から指定された金額であるためどの医療機関でも同様の金額になります。
システム利用料は、医療機関が導入しているシステムによって異なりますが、およそ1,000円〜2,000円程度となるところが多いです。
健康保険の適用範囲
オンライン診療が健康保険の適用範囲に含まれる場合がありますが、その適用範囲や条件はいくつかの要因によって異なります。厚生労働省は、オンライン診療においては、特定の診療内容や診療期間に対して、健康保険の適用を認めています。
オンライン診療では、一部の疾患や診療内容について健康保険の適用範囲に含まれる場合がありますが、ほかの疾患や診療内容については適用されない場合があるため注意です。
負担割合は3割と変わらないですが、このほかに「オンライン診療料」という料金が追加となります。
オンライン診療の適切な実施に関する指針・ガイドライン

オンライン診療の適切な実施に関する指針やガイドラインは、医療機関や関連する専門団体、政府機関などが策定しています。
これらは、医療従事者や患者の安全性やプライバシー保護を確保するために重要です。
指針やガイドラインには、以下のような項目があります。
- 医師の資格とライセンス
- 患者のプライバシー保護
- 医療の品質と安全性
- 適切な機器と通信環境
- 診療の記録と文書化
これらは、オンライン診療を実施していくにあたっての、患者の安全性や医療の品質を確保するために重要です。
医療機関や医師は、これらに従って、その定められた内容に沿ったオンライン診療を実施していくことが求められます。
オンライン診療に利用できるアプリ5選

オンライン診療は、さまざまなアプリを利用して診療を行います。
ここでは、オンライン診療を行なっている医療機関のアプリを6つ、紹介します。
- curon(クロン)
- Omamori Clinic(おまもりクリニック)
- ココカラファイン オンライン診療
- Rakuten Medical(楽天メディカル)
- First Call(ファーストコール)
- Minna Care(みんなケア)
特徴が異なるオンライン診療のアプリをそれぞれみていきましょう。
| 概要 | 特徴 | 料金 | |
| curon(クロン) | オンラインでかかりつけ医の診療を受けられるサービス | AIチャットボットによる初診相談 オンライン問診、オンライン処方箋発行 専門家による健康管理サポート 時間・場所に制限されず利用可能 |
リーズナブル、保険適用対応 |
| Omamori Clinic(おまもりクリニック) | 心療内科・精神科のオンライン診療と服薬指導 | うつ病、ADHDなどの診療 オンラインで診療と服薬指導が可能 |
要問合せ |
| ココカラファイン オンライン診療 | オンライン服薬指導 | 病院からの処方箋データでオンライン服薬指導 薬の宅配サービスも提供 |
要問合せ |
| Rakuten Medical(楽天メディカル) | 医薬品・医療機器開発企業、オンライン診療と連携 | 楽天ペイ決済、夜間診療など機能充実 女性向けオンライン医療相談サービスも |
要問合せ |
| First Call(ファーストコール) | インターネットで医師に健康相談できるサービス | 医師とチャットやテレビ電話で相談可能 最終的に受診するかは自身で判断 |
月額550円(税込) |
| Minna Care(みんなケア) | 介護事業者向けオンラインコミュニケーションツール | ケアマネジャーや利用者が無料で利用 事業者は月額500円 |
事業者月額500円 |
curon(クロン)

「curon (クロン)」は、オンラインでかかりつけ医の診療を受けられるサービスです。AIチャットボットによる初診相談や、オンライン問診、オンライン処方箋発行などが可能で、ユーザーの状態に合わせた最適な治療プランを提案します。
医師や薬剤師、栄養士などの専門家が提供する充実したサポートにより、ユーザーの健康管理をサポートしています。利用料金はリーズナブルで、保険適用にも対応しています。
オンラインで医療サービスが受けられるため、時間や場所の制約なく気軽に利用できるのが特徴です。多忙なライフスタイルを送る人や、交通手段の不便な地域に住む人など、幅広い層に好評を得ています。
Omamori Clinic(おまもりクリニック)

川崎市宮前区にある心療内科・精神科の「おまもりクリニック」は、オンライン診療と服薬指導を行っています。
診療内容には、うつ病・双極性障害・パニック症・注意欠如・多動症(ADHD)・統合失調症・自律神経失調症・睡眠障害・適応障害などがあります。
ココカラファイン オンライン診療

ココカラファインヘルスケア調剤取扱店舗全店では、2021年1月からオンライン服薬指導を開始しています。
オンライン服薬指導では、病院や診療所から受領した処方箋データを送信して、オンラインで薬の説明を受けることができ、薬は配達されます。
医療機関から処方箋をFAXなどで薬局に送ってもらい、薬局へ処方箋を渡します。そのあと、薬を薬局から自宅などへ送ってもらったり、自身で薬局に出向いて受け取りに行ったりすることも可能です。
ほかにも、服薬指導を薬剤師からオンライン上や対面で受けることもでき、便利なサービスとなっています。
Rakuten Medical(楽天メディカル)

楽天メディカルは、医薬品や医療機器の開発を行う会社です。
楽天は、「med …: powered by Rakuten」という、アイメッド社が運営している、オンライン診療のサービスと連携しています。楽天ペイ(オンライン決済)が利用可能で、取り扱う医薬品のラインアップが充実していたり、夜間診療への対応をしていたりと、サービスが拡充されています。
また、楽天生命は女性向けオンライン医療相談・診療サービス「楽天キレイドナビ」を運営しています。
First Call(ファーストコール)

First Call(ファーストコール)は、インターネット上で医師に健康相談ができるウェブプラットフォームです。チャットやテレビ電話を使って、匿名で医師に直接相談できます。
First Callは、日常生活における自身と家族の体調の不安や悩みについて、いつでもどこからでも医師に相談できるサービスです。ただし、医師が診察・診断しているわけではないため、最終的には、自身の判断で医療機関に受診するかどうか判断する必要があります。
First Callは、月額550円(税込)でいつでも医師へのチャット相談・テレビ電話相談を行うことができます。
Minna Care(みんなケア)

みんなでケアは、介護業界向けのオンラインチャットサービスです。スケジュール共有やファイル管理、支援経過記録作成などの作業を簡略化することができます。
ケアマネジャーや利用者は無料で利用でき、介護事業者は月額500円で利用できます。業界初のダブルチャット機能を備えており、安価な料金設定も魅力です。
オンライン診療のまとめ

オンライン診療は、医療機関の医療専門家と患者がインターネットを通じて遠隔で医療相談や診療を行うことができる便利なサービスです。
物理的な検査や処置ができないといった制限はありますが、通院せずに診療を受けられ、電子処方箋を受け取って近くの薬局で薬を受け取ることができます。
また、保険適用と自費の2つのオプションがあり、医療機関によって料金が異なるため、自身が通う医療機関の料金を確認しておくことが重要です。
一方で、利用できない症状もあるため、事前に制限内容を確認する必要があります。このように、オンライン診療は便利な一方で制限もあるため、症状に応じた適切な利用が求められます。
オンライン診療には多くのサービスがありますが、どのようなサービスを利用すれば良いかわからないこともあるでしょう。このようなときは、オンライン診療に知見のある、株式会社Jiteraへご相談ください。
オンライン診療のサービスについて丁寧に解説させていただいた上で、適切なオンライン診療サービスを紹介させていただきます。







