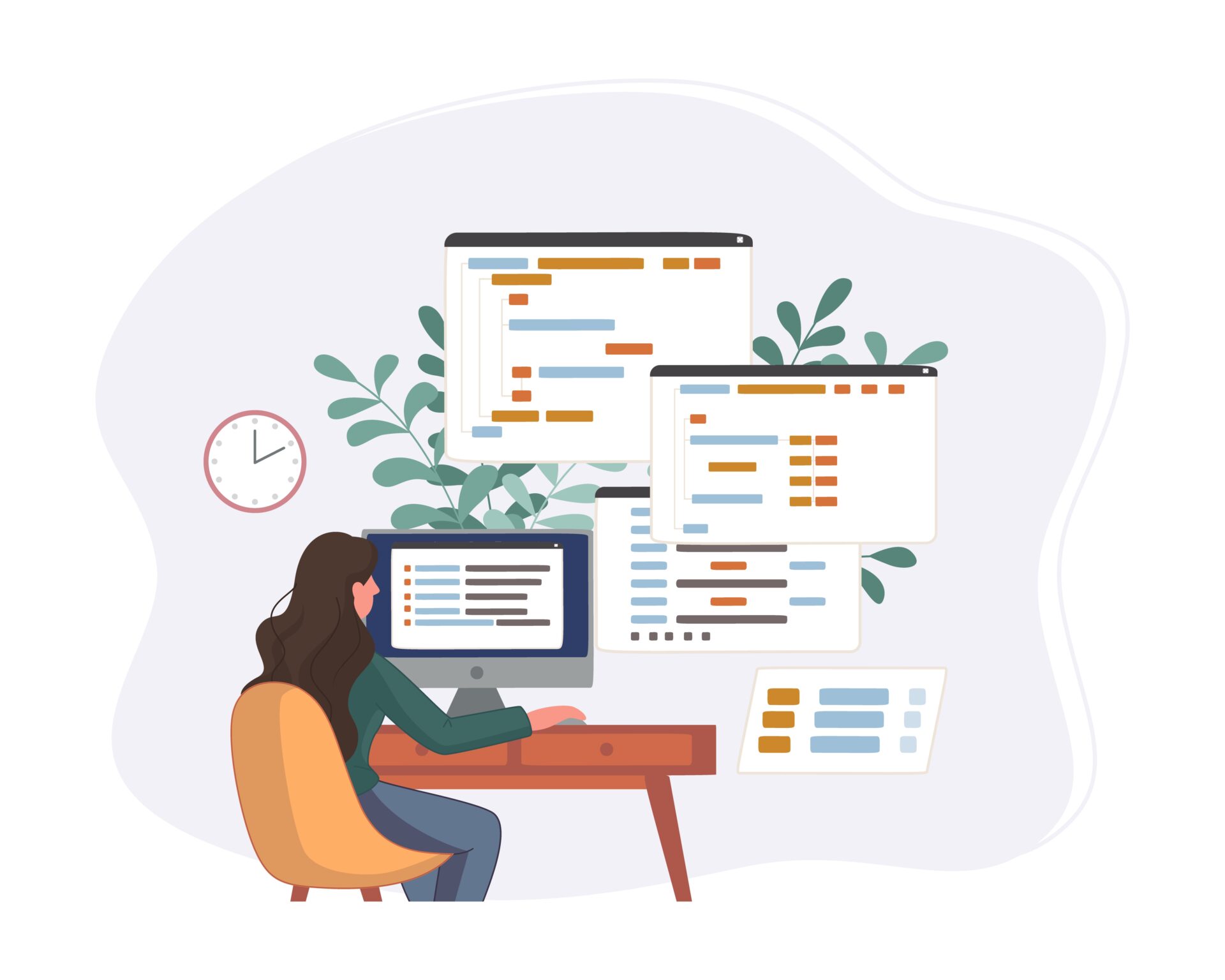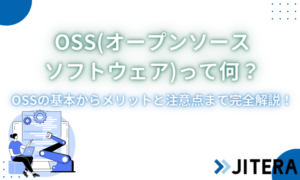現代のWeb開発において、効率的かつ効果的な状態管理は必須の要素となっています。そこで注目されるのが「Redux」です。Reduxは、JavaScriptのアプリケーションで状態を管理するための強力なツールであり、Reactをはじめとする多くのフロントエンドフレームワークやライブラリと組み合わせて使用されています。このライブラリは、アプリケーション全体の状態を一元管理することで、予測可能かつ一貫性のある動作を実現します。
本記事では、そのReduxの基礎や状態管理の仕組みなどについて解説します。
東京在住、大手IT企業出身、Web業界10年以上のアラサーです。新規事業開発やシステム開発にプロジェクトベースで関与したりこれまでの経験をもとに執筆活動を行っています。
Reduxの概要

Reduxは、JavaScriptのアプリケーションで状態管理を行うためのライブラリです。
Reduxを使用することで、アプリケーション全体で共有される状態を一元的に管理することができます。
状態の変更はアクションと呼ばれるオブジェクトを介して行われ、アクションによって状態が更新されます。
Reduxは、ReactやAngular、Vue.jsなどのフレームワークと組み合わせて使用することができます。
Reduxとは何か
Reduxは、状態管理のための予測可能なコンテナです。
アプリケーション全体の状態を1つのオブジェクト(ストア)で管理し、このストアがアプリケーション内のすべてのコンポーネントに渡されます。
コンポーネントはストアの状態を参照し、必要に応じてアクションをディスパッチして状態を更新することができます。
これにより、コンポーネント間でのデータの受け渡しや更新に関するロジックを効率的に管理することができます。
Reduxの起源と歴史
Reduxは、2015年にDan Abramovによって開発されました。
当初、ReduxはFluxというアーキテクチャの実装であるとされていましたが、後に独自のアーキテクチャとして認識されるようになりました。
Reduxは、Fluxのアーキテクチャにおけるアクションやストアの概念を受け継いでいますが、よりシンプルで予測可能な設計を目指しています。
Fluxに比べてReduxはシンプルな概念と性能の向上が特徴であり、フロントエンド開発者によって広く受け入れられています。
また、Reduxは公式ドキュメントや豊富なリソースが存在し、学習しやすいという特徴もあります。
現在では、Reactとの組み合わせで特に人気があり、多くのプロジェクトで使用されています。
Reduxの主要な概念

Reduxは、状態管理のために以下の主要な概念を使用します。
Actionとは何か
Action(アクション)は、ユーザーの入力やアプリケーション内のイベントなど、何かしらの出来事を表すオブジェクトです。アクションはtypeというプロパティを持ち、どの種類のアクションかを識別します。例えば、”ADD_TODO”や”DELETE_TODO”などの具体的なアクションタイプがあります。アクションはユーザーの意図を表現し、アプリケーション内の変更を起こすための情報を提供します。
Stateとは何か
State(状態)は、アプリケーションの状態やデータを表すオブジェクトです。Reduxでは、アプリケーション全体の状態が1つのオブジェクトとして管理されます。Stateは読み取り専用であり、アクションによって変更されます。アプリケーションの状態が変更されるたびに、新しいStateオブジェクトが生成されます。
Storeの役割
Store(ストア)は、アプリケーションの状態を保持するオブジェクトです。ストアはアプリケーション全体の状態を一元的に管理し、状態変更の監視と通知を行います。Reduxでは、唯一のストアが作成されます。ストアはアプリケーション内のすべてのコンポーネントから直接アクセスされることができ、状態の取得や更新などを行います。
Reducerの働き
Reducer(リデューサー)は、アクションを受け取り、状態を更新する純粋な関数です。Reducerは現在の状態とアクションを引数に取り、新しい状態を返します。Reducerはアプリケーションの状態の変更を担当し、アクションに応じた処理を行います。Reducerは、前の状態を変更するのではなく、新しい状態のオブジェクトを作成して返すだけなので、副作用のない純粋な関数である必要があります。
以上がReduxの主要な概念についての説明です。これらの概念を理解することで、Reduxの基礎を把握できます。
Reduxでできること

Reduxを使用すると、以下のような状態管理のメリットが得られます。
状態管理のメリット
Reduxでは、アプリケーションの状態が1つのオブジェクト(ストア)で管理されます。これにより、アプリケーション内のすべてのコンポーネントが同じデータにアクセスできるようになります。さらに、アプリケーションの状態が集中管理されるため、状態のトラッキングや更新方法を個々のコンポーネントごとに実装する必要がなくなります。
また、Reduxではアクションとリデューサーという明示的なルールに従って状態の変更が行われます。これにより、状態の変更が予測可能であり、データフローが明確になります。データの変更履歴をRedux DevToolsを使用してタイムトラベルしながらデバッグすることも可能です。
一元管理とバケツリレー問題の解消
Reduxでは、アプリケーション全体の状態が1つのストアで管理されるため、状態の一元管理が可能になります。これにより、コンポーネント間でのデータの受け渡しや更新に関するロジックを大幅に簡素化できます。個々のコンポーネントはストア内のデータに直接アクセスすることで、データのやり取りが容易になります。
さらに、コンポーネントが増えた場合でも、状態の管理が容易に行えます。コンポーネント間でデータの受け渡しがバケツリレーのように複雑になることを避けることができます。これにより、バグの発生や開発の効率性の低下といった問題を回避することができます。
純粋関数としてのリデューサー
Reduxのリデューサーは純粋な関数として定義されます。純粋関数とは、引数に対して同じ結果を返し、副作用を持たない関数のことです。リデューサーは現在の状態とアクションを受け取り、新しい状態を返します。このような設計により、テストが容易になります。リデューサーのテストでは、入力に対しての結果が予測可能であり、再現性のあるテストが実行できます。
以上が、Reduxを使用することによって得られる状態管理のメリットです。これらのメリットを活かし、効果的な状態管理を行うことができます。
Reduxの仕組み

Reduxでは、アクション(Action)のディスパッチ(Dispatch)と状態(State)の更新が中心となっています。
ActionのDispatchとStateの更新
アクションはユーザーの入力やアプリケーション内のイベントなどを表すオブジェクトであり、アクションをディスパッチすることでアプリケーション全体に何かしらの変化をもたらします。アクションはアクションクリエーター(Action Creator)という関数で作成することができ、その関数内でアクションオブジェクトが生成されます。
ディスパッチされた実際のアクションは、リデューサー(Reducer)と呼ばれる関数に渡されます。リデューサーは現在の状態と受け取ったアクションをもとに、新しい状態を生成して返します。
ストア(Store)はアプリケーション全体の状態を保持し管理します。ストアは、アクションのディスパッチとリデューサーによる状態の更新を担当し、状態が更新されるたびにコンポーネントに変更を通知します。
このように、Reduxではアクションのディスパッチとリデューサーによって状態の更新が行われ、アプリケーション全体の状態の管理が実現されます。
Stateの読み取り専用性
Reduxでは、状態は読み取り専用となっています。つまり、コンポーネントは直接状態を変更することはできず、状態を変更するためにはアクションをディスパッチする必要があります。
これにより、状態を複数のコンポーネントで共有する際に、データの整合性や変更のトラッキングが容易になります。また、予測可能な状態管理を実現し、アクションとリデューサーによって明示的に状態の変更が行われるため、不正な状態の変更やバグの発生を防ぐことができます。
さらに、状態の読み取り専用性はテスト容易性にもつながります。状態が不変であるため、リデューサーは純粋な関数としてテストすることができ、予測可能な結果を確認することができます。
以上が、Reduxの仕組みに関する概要です。アクションのディスパッチと状態の更新、そして状態の読み取り専用性がReduxの特徴となっています。これらを理解することで、効果的なReduxの使用が可能となります。
Reduxの応用

Redux Toolkitについて
Redux Toolkitは、Reduxをより簡潔で効率的に使用するための公式のツールセットです。Reduxを導入する際に必要となる各種のモジュールやミドルウェアを統合し、一連のベストプラクティスを提供します。
Redux Toolkitは、以下のような機能を提供します。
- configureStore(): ストアの作成と構成を簡素化します。既定の構成は、Redux DevTools Extensionと統合されたミドルウェアのセットを使用します。
- createSlice(): アクションとリデューサーを1つの場所で作成するためのユーティリティ関数です。この関数により、アクションの定義とリデューサーの作成が簡単になります。
- createAsyncThunk(): 非同期アクションを簡素化するためのユーティリティ関数です。この関数を使用することで、非同期のデータのフェッチやAPIリクエストの処理が簡単になります。
- createEntityAdapter(): エンティティデータのノーマライズと操作を補助するユーティリティ関数です。この関数を使用することで、データの管理が効率的になります。
Redux Toolkitは、Reduxの主要なコンセプトとユーティリティ関数を組み合わせることで、より効率的な状態管理を実現します。また、Redux Toolkitはバージョン9以上のReduxで公式に推奨されています。
以上が、Redux Toolkitについての概要です。Redux Toolkitを使用することで、よりシンプルで効率的なReduxのコーディングを実現することができます。
Redux Thunkの利用
Redux Thunkは、非同期のアクションを処理するためのミドルウェアです。通常のReduxでは、同期的なアクションのみを処理することができますが、Redux Thunkを使用することで非同期の処理を行うことができます。
Redux Thunkを使用する主なメリットは以下の通りです。
- 非同期処理の簡素化: Redux Thunkを使用することで、非同期の処理を簡単に実装することができます。APIリクエストや非同期のデータの取得などの処理を、単一のアクションの中にまとめることができます。
- 条件付きのアクションの実行: Redux Thunkは、アクション生成関数としても機能します。条件に応じて複数のアクションを一度に実行することができるため、より柔軟な処理が可能になります。
- 同期と非同期の組み合わせ: Redux Thunkを使用することで、同期的な処理と非同期的な処理を組み合わせることができます。例えば、非同期のデータの取得後に同期的にデータを更新するなどの処理が可能です。
Redux Thunkは、通常のReduxのフローに柔軟性を追加し、非同期処理をより簡単に実現するためのミドルウェアです。Redux Thunkを使用することで、より複雑なアプリケーションの状態管理をシンプルに実現することができます。
まとめ

以上で、Reduxの基礎やできること、状態管理の仕組みなどについて解説しました。Reduxは、アプリケーション全体の状態を管理するためのライブラリであり、シングルソース・オブ・トゥルースや予測可能な状態管理といったメリットを提供します。アクション、リデューサー、ストアといった主要な概念を理解し、Reduxを効果的に活用することができるでしょう。さらに、Redux ToolkitやRedux Thunkなどの応用的な機能も学ぶことで、より高度な状態管理ができるようになります。ぜひ、実際にReduxを使って開発をしてみてください。
この記事ではReduxの基礎知識をご紹介しました。Reduxについてまずはどのようなものか理解したいと考えている方、Reduxを取り入れるべきか検討されている方にとって、参考になりましたら幸いです。
Redux含めた技術選定など開発課題をお持ちの方はぜひ一度Jiteraまでご相談ください。