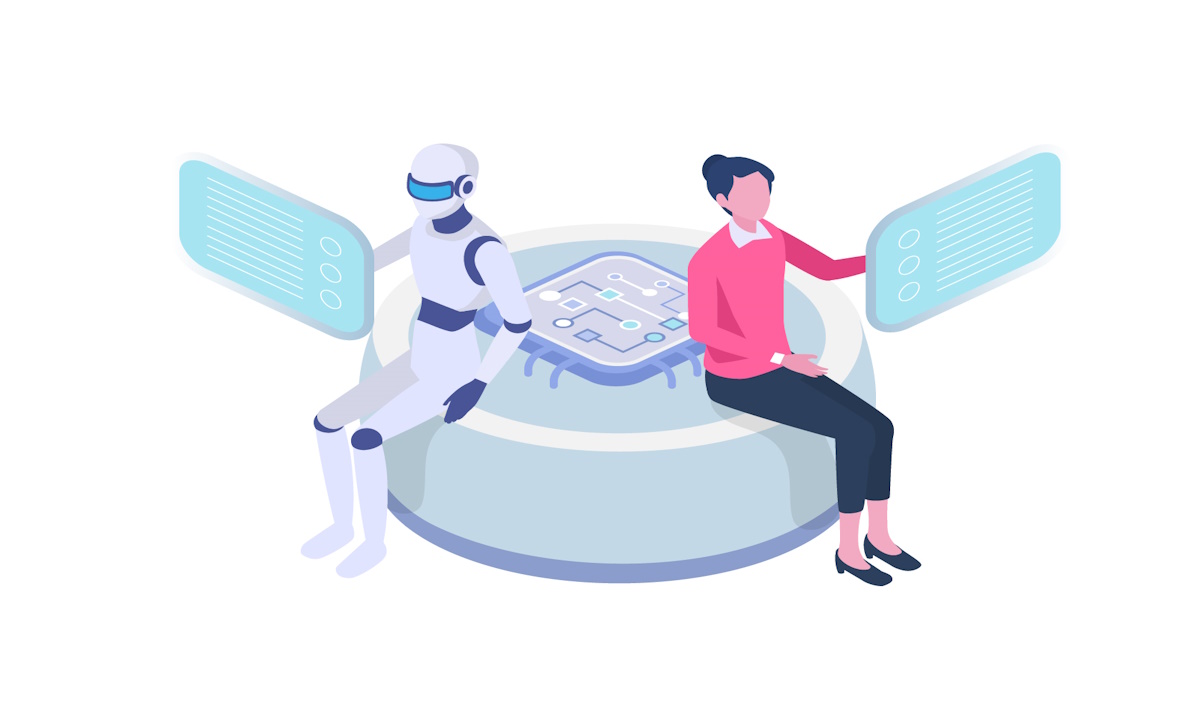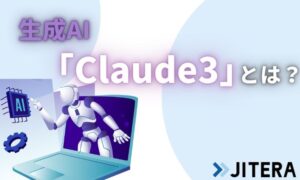人工知能(AI)は、人間の仕事を奪うと言われています。実際、2015年の野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究では、日本の労働人口の49%がAIやロボットにより代替可能であると公表されました。
これからAIがさらに社会に浸透していくと、自分の仕事はどうなるのだろうかと不安になるかもしれません。一方で、新たに生まれてくる仕事もあるでしょう。
この記事では、AIの普及で無くなる仕事、生まれる仕事について考察します。また、業界別にAIがどのように仕事を変化させるかを解説します。
コンサルティング業界に20年以上在籍。IT戦略・構想策定など上流系が得意。
仕事へのAI導入の現状と普及率

AIは既に多くの分野に実装されています。仕事の仕方にも大きく影響を与えています。
日本では一般的に、AIの導入が遅れていると言われています。ここでは、日本と海外それぞれのAI導入の現状をお伝えします。
日本におけるAI導入の現状
総務省が公表している「令和5年版情報通信白書」によると、日本のAIシステム市場規模(支出額)は、2022年に約3900億円(前年比35.5%増)で、2027年には1.1兆円まで拡大すると推測されています。
一方、同白書によれば研究をリードする企業としてランクインしたのはNTTのみで、新たに資金調達を受けたAI企業数も世界10位と、先進国の中では後れを取っているのが現状です。
日本もAI市場の急速な拡大は進んでいますが、それ以上に世界が急速にAI導入を進めており、年々その順位が低下しているのが現状です。
海外におけるAI導入の現状
同白書によると、世界のAI市場規模(売上高)は2022年に約19兆円(前年比78.4%増)であり、2030年まで年30%超の成長が見込まれています。
近年の生成AIのように、海外では世界の常識を一変させるようなAIがスタートアップ企業から生まれています。また、GAFAMや中国企業を中心としたビッグテック企業がAI開発を推進しています。
その他、AI開発を支える基盤として欠かせないクラウド技術や、画像処理を高速で行うGPUなどの基盤技術についても、米国を中心とした海外企業が地位を築いています。
業界別のAI普及率とその特徴
業界別のAI普及率については、総務省の「令和元年版情報通信白書」で、ボストンコンサルティンググループが調査したデータがあります。
| 産業 | 普及率 |
| 消費者向け産業 | 35% |
| エネルギー | 38% |
| 金融機関 | 42% |
| ヘルスケア | 23% |
| 産業財 | 32% |
| テクノロジー/メディア/通信 | 60% |
| 計 | 39% |
2018年に調査した情報であるため、現在ではもう少し普及率が高くなっていると思われますが、調査国の中でも普及率の低さが目立ちます。
その中でも、ヘルスケア産業における普及率の低さが目立っています。AIといえば、がんの早期発見など深層学習(ディープラーニング)を活用した新技術の発明や、AIによる診断など様々な活動が知られている分野です。
少なくとも2018年の時点では、まだヘルスケアの分野におけるAIの導入は本格的では無かったことが伺えます。また、ヘルスケア産業には介護業界も含まれており、介護業務の負担軽減にはまだまだ課題があることが伺えます。
AIの導入によって奪われる仕事と生まれる仕事

日本の労働人口の49%がAIやロボットにより代替可能と報告されたことは前述のとおりです。AIは、どのような仕事を奪い、また創出するのでしょうか。
ここでは、AIに奪われる仕事、AIの導入によって新たに生まれる仕事として考えられている仕事を紹介します。
奪われる仕事
AIに限らず、コンピュータが得意とする業務は、単純作業の繰り返しです。しかし、単純作業といっても人の判断があります。
これまで、人が行っている判断条件が複雑で洗い出しきれず、無人化できなかった業務の中に、AIで代替可能な業務が埋まっていることがあります。
AIはデータを学習し、データから得られる学びによって判断や予測を行うことが出来ます。人が判断するときも、あらかじめ用意されたマニュアルに書かれたルールだけでなく、過去の経験則を活かして柔軟に判断を変えることがあります。
AIが得意とするのは、過去の経験則のデータ化による判断の自動化です。この観点で、いくつかの仕事を見ていきましょう。
会計監査
監査法人が、主に上場企業を対象に実施している会計監査は、AIによる業務の代替に取り組まれている分野です。
決算期には、何人もの会計士がカンヅメ状態になって膨大なデータをチェックする必要があり、年々会計監査の負担は高まっています。人口減少により会計士の人数も減少傾向にある一方、上場を目指すスタートアップ企業は増加を続け、会計監査が必要な企業が増えています。
このことから、大量データを処理し、不正や誤りの可能性を抽出するAIの研究が進められています。
小売業のレジ担当
Amazonが展開する無人レジ店舗「Just Walk Out」は、スーパーマーケット型の無人店舗「Amazon Fresh」において、画像認識技術を用いて精算を自動化する検証が行われました。
現在、Just Walk Outは別の技術に置き換わっていくとの報道もありますが、一時的に展開が停滞したとしても、いずれはAIによって無人化店舗が増えていくことが予測できます。
現時点では実用化に課題が多い分野ですが、これからの技術発展を注視する必要があります。
バスの運転手
地方の過疎地においては、採算性の問題や運転手の成り手の問題により、バス路線が廃止されるケースが相次いでいます。高齢者にとっては、運転技能の低下も相まって行動範囲が縮小するなど、地域社会の維持に大きな課題を抱えています。
自動車の自動運転技術は、地域のバス運行を無人化することで路線を維持できる可能性があります。既に実証実験が行われており、いずれは無人バスが地方におけるスタンダードになるかもしれません。
生まれる仕事
AIは完璧ではありません。そのため、AIの仕事は誰かが監視し、問題を是正する必要があります。
また、AIによって単純作業から解放されれば、クリエイティブな仕事のための時間を確保できる場合があります。
AIは人にはできない分析と示唆の提供ができますが、発想の転換ができません。こうした観点から、AIの導入によって新たに生まれる仕事を見ていきましょう。
倫理チェッカー
AIの導入によって、倫理の問題が注目されています。2024年のG7サミットでは、ローマ教皇がAIへの規制を訴えました。ローマ教皇は、軍事利用や選挙操作などの負の側面に対し、かねてより警鐘を鳴らしてきました。
AIを悪用しないよう、倫理的な観点でチェックを行い、規制を適用する存在が必要になる可能性があります。
プロンプトエンジニア
既に生成AIの導入促進の中で生まれつつある仕事です。簡単に言えば、ChatGPTのようなチャット形式で応答するAIに対し、聞き方を構築するエンジニアです。
一見、フランクにどのような聞き方をしても適切な回答を返してくれる生成AIですが、実際にはコツがあります。
人を相手に例を取って、レストランに入ってオススメのワインを聞くことを想像しましょう。赤か白かや、甘めか辛めかなど、ある程度の好みを伝えたほうが適切なものを勧めてくれるでしょう。年代や産地にこだわるなら、回答内容に含めて欲しいと思うはずです。
こうした、聞き方や回答の方法をコントロールすることで、より適切な回答をAIから得る工夫をするのがプロンプトエンジニアの仕事です。
AIトレーナー
ChatGPTのような、非エンジニアでも簡単に使えるAIが普及することで、誰でもAIを活用して業務改善ができるようになります。
しかし、実際には非エンジニアが使いこなすのは簡単ではありません。単に開発言語やITアーキテクチャを知らなくても使えるだけのことであって、エンジニア的な思考ができない人がAIを使うには壁があります。
過去にはRPAで同様のブームがありました。誰でも簡単に使えるRPAを、本当に誰でも使って業務改善に活かせるよう、社内にトレーナーが育成されました。
生成AIでも、同じブームが起きようとしています。使い方を易しく伝授し、誰もが業務改善のためにAIを活用できるようなトレーナーの育成が急務になりつつあります。
業界別!AIの普及による仕事への変化

AIは、既に多くの業界に導入され、仕事内容を大きく変革しつつあります。
ここでは、いくつかの業界における事例を参考に、AIの普及による仕事への変化を追ってみましょう。
建築業界
点検業務の効率化は、ディープラーニングを活用できる典型的な業務です。画像を認識させて、損傷が無いかの発見等を行うことで、人の目では気づくことのできない不具合を発見することが出来るでしょう。
また、過去のプロジェクトで実施したタスクを蓄積することが出来れば、生成AIの活用幅も広がっていくでしょう。現在、建築業界では人材不足と高齢化により、技術の継承が大きな課題になっています。
過去のプロジェクトをデータベース化し、新規プロジェクトの計画時に過去の事例を探索させます。
これにより、プロジェクトに必要なタスクを自動的に組み立て、適切なWBSの組み立てとリソース割り当てなど、プロジェクト計画の大半を行ってくれる可能性もあります。
法律業界
日本でも、リーガルテックと呼ばれる分野が注目されています。
契約書の作成は、手間のかかる業務です。法務担当はいつも忙しく、契約書のレビュー等に時間がかかる会社も多いのではないでしょうか。
契約書の自動生成や、変更案に対するリーガルチェック作業などをAIで自動化することができる製品が出てきています。
一方、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を行うことは、非弁行為とされ違法です。リーガルテックにおいては、非弁行為にあたるのではないかという議論が行われてきました。
この問題に対し、2023年に法務省がガイドラインを公表しました。これにより、AIによる契約書レビューが完全に適法とされたわけではありませんが、AIの活用拡大を意図した規制改革であり、今後の規制緩和が期待されています。
教育業界
教育業界では、新しい教育手法として、アダプティブラーニングという考え方が提唱されています。
アダプティブラーニングとは、一人一人が持っている個性や能力に合わせて、教育プログラムを柔軟に変更していく手法です。このアダプティブラーニングを効果的・効率的に実行するために、AIが活用されています。
過去の膨大な学習データをAIが分析し、生徒の得意・不得意を見極めて、適切な次の学習プログラムをセットしていきます。
人が行う場合、過去の経験則に従って指導することになります。AIは、その経験則がデータに基づいており、統計的なアプローチから適切な”経験則”に基づく指導が行えることが期待されています。
医療・看護業界
医療業界でのAIといえば、ディープラーニングを用いた病巣の発見などが知られています。早期にがんなどの病変を画像分析によって発見する研究が行われています。
海外では遠隔診断にAIを使う事例が多く、スマホで撮影した画像を専用アプリでアップロードすることで、患部の診断をAIが行えるサービスが登場しています。
また、AIを搭載した会話ができるロボットの介護現場への投入も実用化間近です。会話できるロボットは以前からありましたが、大規模言語モデル(LLM)を搭載し、介護対象者との雑談から健康状態を収集する試みが行われています。
仕事にAIが普及することによる将来の課題

AIが普及し、仕事の仕方は大きく変わってきています。AIは、これまで到底行えなかった新しい価値を創造する一方、普及によって懸念される課題があることも事実です。
AIが普及することで、新たな課題として認識されているものをここではご紹介します。
働き口が大幅に減少する
AIが多くの仕事を奪うようになることは確かです。とはいえ、人口減少社会の中では多くの業界で人手不足が起きており、マクロで見ればAIは人手不足を解決する方向に作用します。
しかし、職種ごとに見れば、AIがその仕事を代替し無人化が進むことはあるでしょう。
自分の仕事は将来的に、AIに置き換えられることはないかを考えておく必要があります。特に、単純作業の繰り返しが中心の職種は注意が必要です。リスキリングや、AIを補完するような仕事の能力を磨き、自分の価値を高め続ける必要があるでしょう。
責任の所在が不明確になる
たとえば、自動運転における交通事故の扱いが議論されています。人が介在しない自動運転であるレベル4やレベル5で走行する自動車が交通事故を起こしたとき、乗車しているドライバーは事故の責任を負うのかという問題です。
人の手が介在していないため、運転手というよりは単なる乗客である利用者に責任を問えるのか。一方で製造元や運行会社等に責任を問えるのか、問えるとしたらどのような条件か等、議論はまだ決着していません。
AIの社会実装が進めば進むほど、人の手を離れて自動化した分野で同様の議論が起きるでしょう。中には、人命や財産に大きな損害を与えかねない分野もあるため、慎重な議論が必要です。
AI社会に適切な法整備も、欠かせない状況です。
情報漏えいのリスクがある
AIは、大量データの学習なしに活用することは出来ません。SaaS型で提供されるAIサービスの大半は、ユーザが登録・入力したデータを学習し、回答精度の向上に努めています。
言い換えれば、企業にとっては自社の機密情報を提供する代わりに業務効率化を得ているともいえます。また、提供した情報は間接的にとはいえ、他社の業務効率化のために活用されているということもできます。
また、サイバー攻撃等でサービス提供者から情報漏えいがあれば、自社の機密情報が漏えいすることも考えられます。
こうしたことから、企業によってはSaaSの利用禁止をしている場合もあり、特に翻訳サービスは便利なうえに機密情報の入力があるため、やり玉に上がりやすいサービスです。
情報漏えいを恐れてデータ提供しない企業が相次げば、学習データが収集できなくなり、AIの強化が停滞します。情報漏えいリスク対策は、AI企業にとって最重要事項であると言っていいでしょう。
AI依存になる
SFの世界では、AIが人間を支配する社会がよく登場します。SFは所詮フィクションですので、そこに誇張があることは確かです。
しかし、既にAIは社会に浸透していることから、人の行動を一部においては支配し始めていることも確かです。たとえば、実在の人物が問題発言を行っているように見せかけるフェイク動画は、選挙結果を操作し、民主主義の根幹を揺るがすことが懸念されています。
この技術も、元々はメッセージを届ける際、テキストや音声だけの伝達よりも、表情豊かに伝える方が効果的だからと編み出された技術です。プレゼンが得意でない人も、フェイク動画なら立て板に水のように伝えることが出来るでしょう。
このように、AIが何かを便利にするということは、AIに対する依存度がそれだけ高まっているということです。
クルマが社会に登場することで、人は遠くに行くことが出来るようになりました。一方で、人の運動能力では制御しきれずに起きる人身事故が新たに発生しました。このように、新しいテクノロジーの活用には、必ず負の側面があることにも注意が必要です。
まとめ:AIの普及に、人も追随していくべき

AIはこれからも、どんどん社会に普及していきます。この波は止めることは出来ず、我々は付いていくことしかありません。
その中でできることは、遅れないように付いていくのではなく、できるだけ先頭を走ることです。
AIが普及すれば、無くなる仕事があります。それらは、AIとは別の新たなテクノロジーが、いずれは無くしていた仕事かもしれません。
人にしかできない仕事の分野を探し出し、スキルを身に付け、いっそ新たなAIを生み出すくらいの立場になれるのが理想なのかもしれません。
Jiteraでは、AIを活用した業務改革やソリューションの開発について、ご相談をいつでも受け付けています。ご興味があれば、ぜひお問い合わせください。