近年、注目されているのは業務プロセス改善(BPI)と呼ばれる手法です。
効率化、コスト削減、顧客満足度向上を達成するためのフレームワークとして知られています。
この記事では、現代のビジネスに欠かせなくなった業務プロセス改善について、その概要や手法、おすすめのフレームワークについて紹介します。
北海道大学理学部数学科確率論専攻。 地方都市に居住していて、プロジェクトのテックリードを努めたりする傍ら、中小企業のDX支援なども積極的に行う。 後進に知識を伝えるべくライティング業務をしている。
業務プロセス改善とは

業務プロセス改善(BPI:Business Process Improvement)とは、既存の業務手順やプロセスを、より効率的・効果的な手法へと改善する取り組みです。
業務プロセスがどうあるべきかなどの観点も踏まえ、本来の業務目的に注力できるように、「既存の組織や規則、ワークフローや管理方法、情報システム(ビジネスプロセス)を見直す(改善する)こと」を指します。
具体的には、以下のようなことを指します。
- 既存業務フローを見直し、適切に合理化する
- 無駄なプロセスやリソースを削減、または最適化する
- 業務に自動化を導入する
- 煩雑な業務をシステム化し、人的なケアレスミスをなくす
業務プロセス改善と他のフレームワークとの違い

| 項目 | 正式名称 | 概要 | 説明 |
| PM | Process mining | ビジネスプロセスの掘り起こし(分析) | IT技術により整理したデータを使って業務プロセスを可視化し、業務全体やワークフローを把握・分析するための手法。 |
| BPR | Business Process re-engineering | ビジネスプロセスの再設計 | 既存の業務プロセスを根本的に考え直し、再設計する手法。
従来の枠組みを抹消し新たな仕組みを構築するため、大幅な変革を行う。 |
| BPM | Business Process Management | ビジネスプロセスの管理 | 会社組織内の業務プロセスを体系的に管理し、最適化していく取り組みやそのための枠組みのこと。 |
| BPI | Business Process Improvement | ビジネスプロセスの改善 | 既存の業務プロセスをより効率的な手法に改善する手法。 |
| DX | Digital Transformation(DX) | デジタル技術によるビジネス改革 | ITを活用して組織全体を変革し、新しい価値を作ったり生産性を上げる手法。 |
業務プロセス改善はプロセスマイニング(PM)、BPR、DX推進などと混同して語られることが多くなっていますね。
PMは現状分析、BPRは理想設計、DXはデジタル変革と、それぞれアプローチが異なります。これらは、相互に関連しながら業務改善に役立つものと言えるでしょう。
全体の改善戦略の中で、適切に組み合わせて活用することが重要です。
業務プロセス改善の目的

業務プロセス改善の目的には以下のようなことが挙げられます。
- 業務効率化
- 業務の標準化
- 適切なIT技術導入
それぞれ解説していきます。
業務効率化
日本企業の業務プロセスは属人的なプロセスであることが多くなっていました。また、とにかく長時間働くことが善とされてきた節があります。
そのような業務プロセスでは現代のグローバル社会に対応できません。そこで、「業務プロセスの改善を通した効率化」を目的にする必要があるのです。
とにかく時間当たりの生産性を上げなければなりません。日本企業の時間当たりの生産性はOECD加盟国の中で下から3番目であるというレポートもあります。
ワークライフバランスを取りながら生産性を上げていくためには、業務プロセスの改善が必要なのです。
業務の標準化
よく言われることですが、世界的には、
「ITシステムに合わせて業務プロセスを作る」
のが標準であるのに対して、日本企業は、
「業務プロセスに合わせてITシステムを作る」
のが標準だと言われます。
日本企業では、同じ業界内であっても、会社が違うと個別の業務プロセスがかなり異なります。
そのため、標準的なITシステムは業務に導入できず、かなりのカスタマイズが必要となっているのが現状です。
これがコストの高さにつながり、日本企業の国際競争力を阻害しているのです。
業務の標準化を目的にするのはこういった理由です。
ITシステムにかけるコストを削減しなければなりません。
適切なIT技術導入
日本企業では、未だに「ハンコ」や「回覧・稟議」という業務プロセスが見られます。
請求書を紙に印刷し、FAXで送付する慣習も根強く残っています。
電子帳簿保存法が施行された時には、各社で混乱が起きました。
IT技術の導入が周回遅れであることが、まるで発展途上国であるかのような光景を生んだのです。
適切なIT技術を導入し、業務のコストを下げることが業務プロセス改善の目的となるのは、もはや必然と言えるでしょう。
業務の流れを改善することで、自社の強みが明確になり、利益向上や生産性向上に繋がります。
また業務の可視化により、今後の経営計画や予測、目標達成プロセスが明確になるため、健全な経営にすることが期待できますね。
適切なIT技術の導入は、人手不足が深刻化する日本のビジネスには不可欠な目的だと言えるでしょう。
業務プロセス改善の手法と進め方

業務プロセス改善は、組織内の業務プロセスを効率的かつ効果的にするための取り組みです。
そのため、行う手法は目的や対象業務、既存の非効率プロセスの形態によって大きく異なります。ここでは、汎用的な業務プロセス改善手法の概要を説明します。
目的の明確化
まずは、改善を行う目的を明確にしておきます。
BPIの取り組みに慣れていないならば、以下のどれかを重視して取り組みましょう。
効率向上
作業手順やプロセスを最適化することで生産性を向上させます。
品質向上
エラーの削減や品質管理の強化によって、製品の品質を向上させます。
コスト削減
無駄な手間やリソースを削減し、コストの最適化を図ります。
まずは、改善を行う目的を明確にしておきます。BPIの取り組みに慣れていないならば、以下のどれかを重視して取り組みましょう。
効率向上
作業手順やプロセスを最適化することで生産性を向上させます。
品質向上
エラーの削減や品質管理の強化によって、製品の品質を向上させます。
コスト削減
無駄な手間やリソースを削減し、コストの最適化を図ります。
プロセスの可視化
現行の業務プロセスについての情報を収集・分析し、フローチャートなどに起こすことで可視化します。
話題のプロセスマイニングもここにあてはまるものです。
これによって、現状を把握しやすくなり、改善プロジェクト全体にイメージが共有されます。
問題の特定と切り分け
現行プロセスにおけるボトルネックや無駄な手順を特定し、何が課題なのか「問題の切り分け」を行います。
改善の余地を見つけたら、影響範囲や置き換えの容易さなどで評価付けし、どこから取り掛かるかを計画しましょう。
効率化と合理化、またはIT化
効率化や合理化は、不要な手続きを削減し、業務フローを最適化することで業務プロセスを改善します。
場合によってはITシステムを導入することを検討してください。
DX推進は、この「IT技術の導入によって作業を効率化する」ことに重点を置いています。
チームからのフィードバック収集
改善した業務プロセスに影響のある従業員全員のフィードバックを収集し、改善後の、評価指標の達成度を測ります。
この評価指標達成度は、効率や品質、コスト削減といった定量的指標で評価できるケースと、顧客満足度(CX)向上や従業員のモチベーション増加といった定性的評価で確認できるケースに分かれます。
また重要なのは、「改善に向けてチーム全体の理解と協力を得られているか」という観点です。チーム全体の理解を得られないままのトップダウンによる一方的な改善は、メンバーの不満を引き起こし、かえって業務トラブルを起こす原因です。
定期的な評価と改善
フィードバックの分析が終われば、また新たな課題が生まれているはずなので、最初の「目的の明確化」に戻ります。
持続可能な改善サイクルを回す構築こそ、BPIを成功させるためのカギになります。
業務プロセス改善の成功事例

このように、多数の観点、手法がある業務プロセス改善ですが、どのような事例が成功事例として挙げられるでしょうか?
トヨタ自動車と3Mカンパニーの成功事例を紹介します。
今まで述べてきたことが腑に落ちるはずです。
トヨタ自動車と3Mカンパニー以外の事例も、一覧表で紹介します。
トヨタ自動車の事例
日本国内で最も有名なBPI事例といえば、トヨタ自動車の「カンバン方式」を初めとしたトヨタ生産方式による生産性向上事例でしょう。
創業者豊田喜一郎が合目的な経営を行うために、「必要な時に必要なだけ作る」というジャストインタイム生産システム(JIT)を導入したことをきっかけに、世界的に有名な「トヨタ生産方式」が生まれました。
トヨタ生産方式の特徴を列挙しますと
- 削減すべき“7つのムダ”の提唱
- 作り過ぎのムダ
- 手待ちのムダ
- 運搬のムダ
- 加工そのもののムダ
- 在庫のムダ
- 動作のムダ
- 不良をつくるムダ
- JIT導入のための「かんばん方式」の開発
- 標準作業時間の策定
- 平準化
- 生産プロセスを均等化し、ムダを排除する原則のこと
- カイゼン(改善)文化の浸透
- 自動化の推進
- 多能工を産み出すためのチームワークとオペレータの育成
などになります。
トヨタ生産方式が生み出した手法は上げるとキリがないくらいです。それだけ独自の手法をトヨタは生み出しました。
トヨタ生産方式は、生産性の向上、在庫の最適化、品質の向上、柔軟性の確保など多様なメリットをもたらし、トヨタ自動車が世界的な自動車メーカーとして成功を収める原動力となりました。
現在トヨタ生産方式の原則や手法は、国内だけでなく世界中の製造業全体に大きな影響を及ぼしています。
Lean原則を始めとした様々な業務プロセス改善の元となりました。
3Mカンパニーの事例

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/
3Mカンパニーは、100年以上にわたり名を馳せる世界的な化学・電気製造メーカーです。
しかし、かつての3Mは、従業員の高齢化などの課題に頭を悩ませていました。
また、非効率な業務プロセスを解消できず、クレームや過去の品質トラブルが起こることもしばしばありました。
そこで、大規模なBPIに取り組みます。
3MのBPIとしては、まずLSSを用いた製造工程の再設計と廃材のリサイクル及び再利用の効率化です。
LSSについては、後ほどフレームワーク紹介にて紹介しますが、このフレームワークを用いることで年間約3,000 万ドルのコスト削減に成功しました。
また、特筆すべき人材育成課程として「15%カルチャー」を導入しました。
「15%カルチャー」とは「業務時間の15%程度を自分が興味をもつ分野の研究等に使っても良い」という方針のことです。社員が自主的に能力を磨くようになりました。
この2つの取組みは、3Mが長年にわたり行ってきた業務プロセス改善のごく一部でしかありません。
今日、3Mが今でも革新的企業として存在感を保っているのは、様々なBPIやBPRを取り入れたことで、イノベーションが起こりやすい企業文化となっているからです。
その他の事例
他にも、様々な業種の企業が業務改善に成功しています。
| 会社 | 業種 | 適用したプロセス | 効果 | リンク |
| Aegon UK | 年金、投資、保険を専門とするファイナンシャルサービス・プロバイダー | 保険の営業や顧客サービスのプロセスにLSSを適用 | 外部契約リソースにかかる年間2000万ポンドのコストを削減
従業員の教育にかかる投資コストを平均して稼働後6ヶ月以内に回収 |
https://www.aegon.co.uk/ |
| コリンズ・バス | アメリカのスクールバス製造最大手 | バスの製造工程にLean原則を適用 | ダウンタイムの削減
リソースの効率的使用によるコスト削減 |
https://www.collinsbus.com/ |
| メルセデス・ベンツ・ブラジル | メルセデス・ベンツのブラジル支社 | 自動車の製造工程にLean原則を適用 | 製造におけるHPUを10~20%削減
また、製造プロセスの全体の効率が3倍に増加 |
https://group.mercedes-benz.com/careers/about-us/locations/location-detail-page-369988.html |
| ANA ポルトガル空港 | ANAのポルトガル空港 | 顧客サービスのプロセス管理にプロセスマイニングを適用 | 顧客サービスのプロセス中にある非効率なステップを特定
顧客への付加価値がないタスクの排除 トラブルの迅速な特定 |
https://www.ana.co.jp/ |
業務プロセス改善に役立つフレームワーク5選
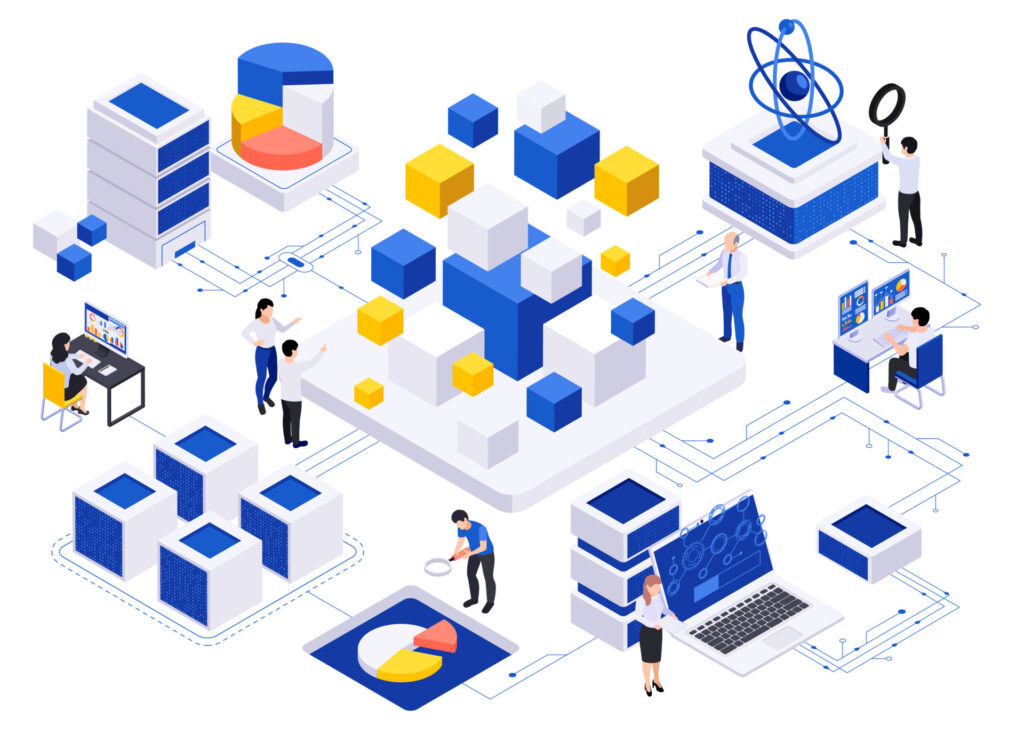
フレームワークとは、課題や問題をうまく解決するときに適用する枠組みのことです。
業務プロセスに問題があると言っても、その実態は会社によって様々であり、問題の根本が分かりにくく絡み合っていることが多く見られます。
一見どれから手を付けていいのかわからない場合も多く、他社の成功体験を眺めてみても「これはうちではできないよな」と諦めてしまうことも多いでしょう。
そのため、業務効率化を目指す上で必要なのは、様々な成功事例を一般化した「共通して適用できるような考え方や意思決定、分析方法や問題解決の手順、そしてそのための戦略についての枠組み」、すなわちフレームワークが必要になります。
フレームワークに従わない業務プロセス改善はある種のギャンブルといえます。他社での成功事例がないわけですからね。
ただし、フレームワークを利用する際は、フレームワークの特性をよく理解してから使うべきです。
業務改善に関わるフレームワークを5つほど紹介します。
リーンシックスシグマ(LSS:Lean Six Sigma)
LSSは、プロセスの効率向上と品質改善を目的とした、ムダを省くことによる業務改善フレームワークです。
トヨタ自動車による生産フレームワーク「カンバン方式」が世界中に衝撃を与えたあと、アメリカのMITとモトローラ社が日本式フレームワークについて研究を行いました。
そして、MITはカンバン方式をより一般化した「Lean方式」を、モトローラ社は日本式の品質管理を取り込んだ「Six Sigma方式」を開発します。
このLean方式とSix Sigma方式を組み合わせ、より洗練させたのがLSSであり、このフレームワークには「ムダの削減と品質管理」を継続的に取り組むためのノウハウが詰まっています。
細かい手法内容には高度なノウハウや別のフレームワークの知識が必要ですが、ざっくり言えば、
- 可能な限りデータを用いて定量的に解析を行いムダを省く(lean)
- 最終的に発生するエラーを標準偏差における6σレベルまでに抑えるために継続的な改善を行う
- 注・標準偏差における6σ(six sigma)は、正規分布のμ±6σ(全体の99.9997%)から外れる値のことです。
- つまり、「製品100万個に対してエラーは約3~4個以内に抑える」ということです。
というのがLSSです。
- 定性的データでも可能な限り定量的評価をつける
- 全てのプロセスを数値化し、解析可能にする
- データをマッピングすることで業務プロセスを可視化する
- エラー率を6σ(100万件につき約3~4件)に抑える
ことを求めるフレームワークとなります。
DMAICフレームワーク
LSSを実行する上でよく使われるフレームワークの一つとして、DMAICについても触れておきましょう。
DMAICはLean Six Sigma手法の一環で、プロセスの改善と最適化、特にSix Sigmaを継続的に達成するための手順で、Define(定義)、Measure(測定)、Analyze (分析)、Improve (改善)、Control (制御)を行い、またDに戻る継続的なサイクル型のフレームワークです。
それぞれの頭文字を行う順番に並べてDMAICと呼称します。
| 構成要素 | 目的 | 活動例 |
| Define(定義) |
を明確に定義する |
|
| Measure(測定) | 現在の状況を数値化し、測定することで問題を把握する |
|
| Analyze (分析) | 問題の原因を分析・特定し、課題を切り分けて根本を明確にする |
|
| Improve (改善) | 改善策を検討し、実行する |
|
| Control (制御) | 改善したプロセスが持続的に機能するように、日々の業務を管理・制御する。
新たな問題に対してDefineにもどる |
|
手法の形式が似通っているため、最も有名なサイクル型の改善フレームワーク「PDCA」と混同されやすいです。
DMAICは、PDCAのPlanをDMAの3要素に分けて、事前準備や目的設定を強調したフレームワークと言えるでしょう。
PDCAサイクル
エドワード・デミングが提唱した品質管理手法「PDCAサイクル」は、日本では最も有名な業務改善フレームワークです。
Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認)→Action(改善)→Planの順にサイクルし、継続的に改善を促します。
簡単に様々なケースに適応できるフレームワークとして非常に人気があり、特徴は以下になります。
- 継続的なプロセス改善が可能
- 様々な規模の組織やプロセスに対して品質向上が期待できる
- 問題の早期発見とすぐの対応が可能
- 従業員全員がそれぞれの実情に合わせたPDCAサイクルでプロジェクト参加可能
BPMN
BPMN(Business Process Model and Notation:ビジネスプロセスモデルとその表記)は、業務プロセスを可視化し理解するための表記法です。
業務プロセスの流れを図式化する表記法として国際基準(ISO19510)に定められていて、具体的には「計画している業務プロセスの開始から完了までの流れを体系的にフローチャートとしてモデル化」します。
業務プロセス全体の流れや影響するリソースを視覚化することで、全体像の把握、プロセスの詳細や進捗状況の把握、ボトルネックの把握などができるようになります。
例えば以下のようなケースにおいて大きな効果を発揮するでしょう。
- 何度も定形手順を繰り返す業務プロセス
- 決まった条件で分岐が発生する業務プロセス
- 複数の従業員が関わり、異なるチームが協調しなくてはいけない業務プロセス
- 複数の処理が同時に並列で行われ、互いに影響し合う業務プロセス
こういったプロセスは、全体像が把握しづらく、業務の進捗管理も難しくなりやすいのが通例です。
BPMNに基づいたフローチャートモデルを作成することで、全体の認識を共有し、スムーズな業務遂行が可能になります。
Kaizenと5S活動
トヨタ自動車が考案したトヨタ式生産方式の中でも有名なフレームワークの一つに「Kaizen(改善)」があります。
業務プロセスの中にある「小さな課題」を見つけ、アイデアを出し合って、小さな改善を行う。
このごく小規模な改善行為を継続的に行い、結果としてプロセス全体の効率性を上げるフレームワークです。
そのための重要な取り組みがKaizenフレームワーク「5S活動」です。
5Sは、業務改善を行うためにまず業務環境を整えることから始めるというフレームワークになります。
5Sとは
- 整理
- 要不要を区別し、不要品を迅速に処分すること
- 整頓
- 必要なときに必要なものを取り出せるように決まった位置に配置すること
- 清掃
- 職場のゴミや汚れを取り除いたり、作業従事者が自身を清潔に保ったりして、きれいな状態を保つこと
- 清潔
- 整理・整頓・清掃を遵守し、良好な状態を維持すること
- しつけ
- 以上4つを「守るべきルール」として従業員全員が徹底すること
です。
継続的な「整理された業務環境」を達成することで自然に効率化することを目指すフレームワークになっています。
業務プロセス改善における課題と解決策

業務プロセス改善の成功事例とフレームワークを見てきましたが、それでは、実際に業務プロセス改善に取り組むとなると、どのような点が課題になってくるのでしょうか。
ここでは、業務プロセス改善で陥りやすい罠を挙げ、それらについて、解決策を述べていきます。
社内のコミュニケーション不足
改善計画において起こる最も多い課題が、 部門間や関係者間、現場と経営者、営業サイドと製造サイドなどの立場の違う者同士の間で情報共有が不足し、認識の違いや意見の衝突がおこることです。
多くの人間が関わっている企業や組織を変えようとすると、関係者の間で認識の違いが発生しがちです。
それは、
- 組織文化の違いや部門ごとに異なる社内常識
- 情報の不透明性
- 適切なコミュニケーションツールや連絡方法の不備
- 特定の担当者に計画が依存していたり、または丸投げされている
などが要因です。
この社内のコミュニケーション不足の解決策としては以下のようなものが考えられます。
定期的な情報共有
情報の透明性を確保し、全体へ周知しましょう。プロジェクト管理ツールや共有プラットフォームの導入も検討することもおすすめです。
共通システムの導入
共通のシステムを使うことで、認識を共有したり相互理解を促進したりしましょう。小さな影響範囲で済むプロセスから始めれば、失敗も少なくなります。
関係者が少なければ問題は最小限で済むものなので、影響範囲の小さなところから業務プロセス改善を始めることがよいでしょう。ノウハウを築いたのち、実績をもって全体に呼びかけることができるようになります。
現場の抵抗やモチベーション不足
業務プロセス改善はBPR(ビジネスプロセス再設計)に比べると、幾分穏やかですが、それでも、業務の変化は大きくなります。
そのためしばしば従業員の不満や抵抗感が強まり、改善や業務自体へのモチベーションが大きく下がるリスクがあります。
原因の要因は様々ですが、多くは以下のような不信感が根底にあるものです。
- 今までのやり方ができなくなる
- 変更した結果どう変わるかサポートが不足している
- ゴールが分かりにくく、期待が持てない
この、現場の抵抗やモチベーション不足への解決策としては
- システムやルールの変更と管理を密室で行わず、参加型のプロセス変更を取り入れる
- 変更されていく過程でも従業員に積極的に参加してもらい、意見や提案を取り入れると、当事者意識を育めます。
- 目標と成果の明確にし、周知する
- 改善の目標や期待される成果を明確にしておき、従業員に改善の重要性を理解してもらうようにするべきです。
- また改善成果は常に可視化し、社内サイトなどで周知しましょう。
- 新しいプロセスに慣れるためのサポートを手厚くする
- プロセス変更への理解を促進するためのトレーニングやセミナー、新しいプロセスの研究会や体験会を開く。
- サポート専門の部署やスタッフを定め、いつでも業務トラブルに対応できるようにする。
などが考えられます。
現状把握が間違っている
業務改善策の多くが現状把握のための情報収集からスタートします。
この最初のプロセスで、現状を正確につかみ損ねると、最初から間違った状態でプロジェクトが進みます。
これは、不十分な情報収集による不正確なデータやデータ自体の不足によって、正確なプロセスマッピングや分析ができていないにも関わらず、表面上は業務プロセス改善が順調に進んでいるように見えるということです。
原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 既存のシステムのデータ品質が低い
- データの統合や社内間連携が不十分
- 適切なデータ管理が行われていない
- 適切なデータ収集ルールが策定されていない
とはいえ、最も大きな問題は、プロジェクトが進む中で「前提となるデータ自身が間違っていないか」という疑問を軽視してしまうことです。
解決策としては
- 情報の可視化と共有の徹底
- 定期的に、目的に向かって進んでいるのかを検討するためのフレームワークを取り入れます。
- たとえば、先述したBPMNなどです。
などが考えられます。
働き方改革における業務プロセス改善の必要性

働き方改革は数年前からのトレンドですよね。
男性の家事・育児負担割合の異常な少なさの問題もあり、「働き方を改革しないと少子化は止まらない」との認識が政府内で強まったことから、働き方改革はスタートしました。
しかし仕事量そのものが変わるわけではありません。
この記事でも述べてきた通り、日本企業にはムダな業務プロセスが数多く残っていたり、情報共有が一部の間でしかなされてなかったりして、生産性を低く留めていました。
生産性が低いのなら、同じ仕事をこなすためにはより多くの時間勤務しないといけません。情報が共有されていなかったら業務は円滑に進みません。
つまり、生産性を上げることや情報共有を進めることは働き方改革に直結するのです。
生産性を上げたり、情報共有を進める第一の処方箋は業務プロセスの改善です。
業務プロセスの改善は、働き方改革のためには必須だと言えるでしょう。多くの経営者が業務プロセス改善に関心をもつのはそのためです。
まとめ:業務プロセス改善は専門家への相談も選択肢

この記事では業務プロセスの改善について、目的や手法、フレームワークの紹介、実際に業務プロセスの改善に取り組んだ企業を紹介してきました。
ですが、自社で行う際に何から手を付ければいいんだろうと思われたかもしれません。
そんなときは外部のコンサルタント会社に委託するのも一手です。コンサルタント会社は、外部から俯瞰して業務プロセスを改善してくれます。
株式会社Jiteraでも、ビジネス課題に悩む企業様に向けてITシステム導入による業務プロセス改善支援を行っております。
自社のビジネス効率化方法にお悩みの方、豊富な成功実績をもつエンジニアが共にそのお悩みを解決します。ぜひ株式会社Jiteraへお問い合わせください。








