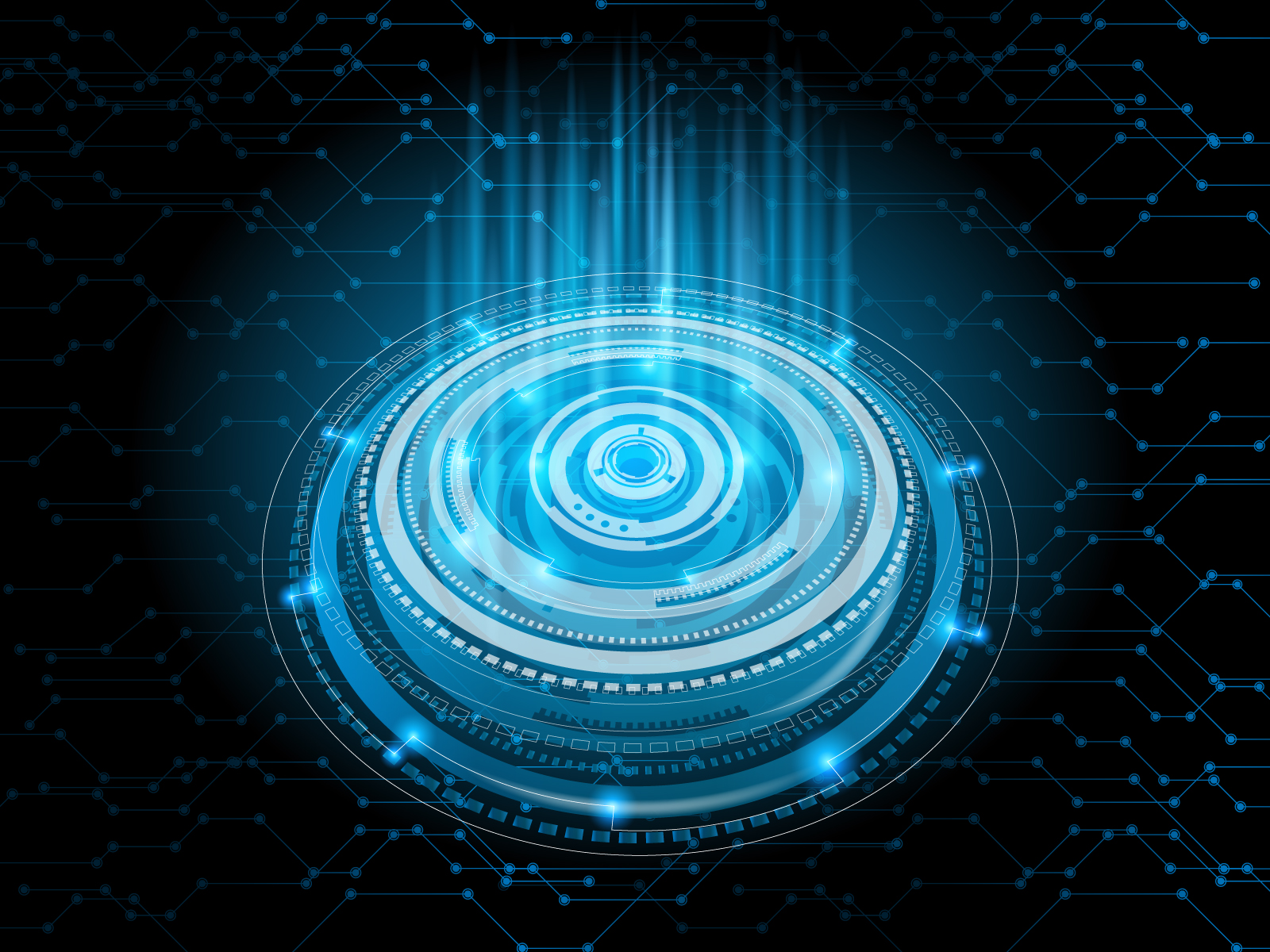スマホアプリ開発を検討しているが、コストや体制の問題で躊躇している方も多いかと思います。
この記事を読めば、マルチプラットフォーム開発の基礎からメリット・デメリットまでわかりやすく解説しています。開発言語やフレームワークの選定の参考になるでしょう。
具体的には、React NativeやFlutterといった安定したフレームワークを利用すれば、iOS/Android両対応のアプリを効率よく開発できます。
これは、コードや機能の共通化が可能なためです。1つのコードベースから、複数プラットフォームにデプロイできるので、コストと時間を大幅に削減できるのです。
アプリ開発に興味があれば、ぜひ一読をオススメします。
近畿大学理工学部生命科学科を卒業後、独学でReactやNext.jsを中心としたフロントエンド開発に特化し、2022年10月よりフリーランスエンジニアとして活動。ヨーロッパや東南アジアを旅しながら、いろんな文化や人との出会いを楽しみつつ、クリエイティブなUI/UX設計に取り組んでいます。
マルチプラットフォーム開発の基礎知識

スマートフォンの普及に伴い、多くのユーザーがアプリを利用する時代となりました。しかし、iOSとAndroidでは開発言語が異なるため、両方のOSで別々にアプリ開発を行うのはコストがかかります。
そこで注目されているのが、マルチプラットフォーム開発です。これは一つのソースコードでiOS/Androidなど複数のOSに対応したアプリを開発できる手法です。マルチプラットフォーム開発を利用することで、開発期間とコストを大幅に抑えられます。
スマホアプリを開発する際、複数のOSに対応させることで、より多くのユーザーにリーチできます。そのために有効なのが、マルチプラットフォーム開発なのです。
マルチプラットフォーム開発とは
マルチプラットフォーム開発とは、一つのソースコードでiOS/Androidなど複数のOSに対応したアプリを開発する手法です。例えば、React Nativeを利用すれば、iOSアプリとAndroidアプリを同時に開発でき便利です。コードやリソースの大部分を共有できるため、開発効率が大きく向上します。
具体的には、ビジネスロジックやUI(ユーザーインターフェース)を共通のコンポーネントとして実装します。OS依存のネイティブコードは、ブリッジを経由して呼び出していきます。このように共通部分とネイティブ部分を分離することで、一つのコードベースからiOS/Android双方のアプリを生成できるのです。
React NativeやFlutterなどのフレームワークを使えば、ジェスチャーやアニメーション、カメラ・地図などデバイス機能にもアクセス可能です。マルチプラットフォームならではの課題はありますが、技術の進歩により十分実用的なアプリが開発できるレベルにあります。
コードの8割くらいを共有できるので、iOSアプリとAndroidアプリを別々に作成するよりもはるかに開発効率が良いのが最大のメリットです。限られた開発リソースで、より多くのユーザーにリーチしたい場合に適しています。
クロスプラットフォーム開発との違い
| 比較項目 | クロスプラットフォーム | マルチプラットフォーム |
| 定義 | 異なるOS間で移植可能な共通基盤を提供 | クロスプラットフォーム技術を利用して複数OS対応アプリを開発 |
| 主な目的 | OS依存の差異を抽象化 | 複数プラットフォームでのアプリ開発効率化 |
| 技術例 | Unity, Xamarin | React Native, Flutter |
| メリット | OS間の違いを吸収しやすい | コードやリソースの大部分を共有できる |
| デメリット | アプリの性能面で制限あり | UI表現力に制限あり |
クロスプラットフォーム開発も、マルチプラットフォーム開発と同義語的に使われますが、厳密には異なります。
クロスプラットフォームは、「異なるプラットフォーム間で移植可能な共通の基盤を提供する」という意味です。つまり、OS毎に異なる言語や開発環境の違いを吸収し、アプリケーションコードを共通化する役割を果たします。
一方マルチプラットフォーム開発とは、そうしたクロスプラットフォーム技術を使って効率的に複数プラットフォーム対応アプリを開発する手法のことです。
例えば、React NativeはJavaScriptベースでiOS/Android両方のネイティブアプリが作成できるので、マルチプラットフォーム開発に適しています。React Native自体が、クロスコンパイル機能やブリッジ機能を通じて、OSごとの差異を吸収するクロスプラットフォームの役割も果たしていると言えます。
つまり、マルチプラットフォーム開発はクロスプラットフォーム技術を活用する応用の段階であると理解することができます。クロスプラットフォームな基盤の上に、アプリ開発プロセスを構築していくイメージです。
※クロスコンパイル機能・・・アプリのソースコードをターゲットとなる異なるプラットフォームのネイティブコードに変換しコンパイルする機能です。 例えばReact NativeはJavaScriptで書いたコードをiOS用のObjective-Cや、Android用のJavaにそれぞれコンパイルします。これにより、一つのコードベースから複数プラットフォームのネイティブアプリを生成できるのです。
※ブリッジ機能・・・JavaScriptベースのアプリケーションコードと、それぞれのネイティブプラットフォームのコードを連携するためのインターフェースのことです。JavaScriptとネイティブコードでは直接通信できないので、ブリッジがデータ変換を仲介することで互いに呼び出しを実現しています。これによりネイティブAPIも利用可能になります。
マルチプラットフォームの開発言語

スマホアプリのマルチプラットフォーム開発には、主にネイティブ開発とハイブリッド開発のアプローチがあります。目的と要件に応じて言語とツールを選択することが重要です。
ネイティブ型
ネイティブ開発は、ターゲットとするOSごとの公式SDKや、開発言語を利用してアプリを開発する手法です。
例えば、iOSであれば、Objective-CやSwiftを用いてXcodeでコーディングします。Androidの場合は、JavaやKotlinでAndroid Studio上で開発します。
OSが提供するUIフレームワークや配列APIをダイレクトに扱えるため、スムーズな表示動作や繊細なタッチ操作といった高いパフォーマンスを実現できます。
一方で、OSごとに専用の開発スキルが必要不可欠で、別々のネイティブコードで実装しなければならないため複数プラットフォーム対応が大変です。
React NativeやFlutterなどのハイブリッド開発も流行していますが、高い操作反応性と表現力が要求されるゲームアプリや3D、AR/VRコンテンツではまだネイティブ開発を選択するのが一般的です。
ハイブリッド型
ハイブリッド開発は、Web標準の技術スタックを利用してネイティブアプリケーションを開発するクロスプラットフォーム手法です。
例えば、JavaScriptやTypeScriptでのフロントエンド開発に加え、React NativeやFlutterなどの両プラットフォームに対応するフレームワークを使うことで、iOSとAndroidのネイティブアプリを同時に開発できます。
Web開発との相性が良いため、学習コストが低く、生産性とコードの再利用性に優れています。UI/UXを重視するビジネスアプリや、SNS・メディア・ショッピングなどの一般消費者向けアプリに向いています。
反面、3Dグラフィックスや複雑なゲームなどの高負荷処理に向いておらず、アニメーション表現力でもやや劣ります。
React Nativeでは、ネイティブ処理が必要な部分だけObjective-CやJavaコードを書けるので、ハイブリッドならではの柔軟性も魅力的です。
マルチプラットフォームフレームワークの比較

複数のOSで動作するアプリを効率的に開発するには、適切な開発フレームワークを選ぶことが重要です。ここでは主要な3つのマルチプラットフォームフレームワークを比較します。
React Native
React Nativeは、iOS/Androidの両方で動作するクロスプラットフォームなモバイルアプリ開発フレームワークです。JavaScriptとReactベースで記述できることが大きな特徴です。
Facebookが開発・メンテナンスしていることもあり、開発者コミュニティが大変活発で情報量も豊富です。UI構築の表現力が高いReactとの親和性が高く、複雑な画面設計に対応しやすいのが魅力です。
Expoといった開発プラットフォームとの連携もスムーズで、プロトタイピングから本番リリースまでを一貫して支援してくれます。
一方で、CPUやメモリといったハードウェアリソースへの直接アクセス制御が制限されるため、アプリケーションのパフォーマンス面ではフルネイティブ開発より劣る面があるのが短所です。
Flutter
Flutterは、Googleが開発を進めるオープンソースのモバイルアプリSDKです。独自UIフレームワークとプログラミング言語Dartを組み合わせた開発環境が特徴です。
高速な再描画機能があるため、UIのフレームレート性能が非常に良いのが強みです。Android/iOS双方のネイティブアプリに限りなく近い操作感と、デザインクオリティを実現できます。
SDK設計からモバイルアプリ作成に特化しているため、生産性とパフォーマンスの両立がしやすいです。一方で、ゲームや3Dグラフィックス開発には向いておらず、用途は業務アプリやSNS、メディア系サービスがおすすめです。
Dart言語も習得しやすいので、JavaScriptベースのReact Nativeよりもハードルが低いと感じる開発者も多いでしょう。
Unity
Unityは、3Dグラフィックスと物理演算機能を提供する多目的ゲームエンジンです。オブジェクトの移動や衝突、エフェクトなどを視覚的にプログラミングできるのが最大の特徴です。
3Dアニメーション制作やVRコンテンツ開発に最適化されているため、自由度の高いインタラクティブ体験が構築できます。スマートフォンからゲーム専用機、PCまで幅広くマルチプラットフォーム対応しているのも魅力的です。
基本操作の習得に多少の時間がかかりますが、視覚的な開発スタイルなので学習コストはそれほど高くありません。ただし、2Dアプリケーション開発には向いておらず、ビジネスアプリの用途には不向きです。
3Dゲームやメタバース空間、インタラクティブコンテンツを開発したい場合に強みを発揮するでしょう
自由度と表現力の高さが売りの開発エンジンと言えるでしょう。
マルチプラットフォーム開発のメリット

マルチプラットフォーム開発には以下のようなメリットがあります。1つのコードベースで、効率的に複数のアプリを開発できるので、コストや工数の大幅な削減につながります。
| メリット | 内容 |
| 開発コストの削減 | コード再利用と学習コスト低減により、最大50~80%のコストダウンが期待できる |
| 開発期間の短縮 | 共通コンポーネントと同時並行開発で、30~50%の期間短縮が可能 |
| 人員確保のしやすさ | Web開発者の採用・教育が容易で、人材需要と供給のバランスが取りやすい |
| ユーザー体験の向上 | UIの一貫性が高まり、アプリの操作性とサービス品質の向上が期待できる |
開発コストの削減
マルチプラットフォーム開発では、ビジネスロジックやUI設計などアプリの大部分を共通コンポーネントとして実装できます。
例えば、顧客管理機能を実装する場合、iOS版・Android版と全く同じ処理フローとデータ設計を使いまわせます。これが大幅なコード再利用につながり実装工数が抑えられます。
加えて、React NativeやFlutterの学習コストは、Objective-C/SwiftやJava/Kotlinに比べると格段に手軽です。JavaScript系の知見があればある程度スムーズに開発を始められます。
コード共有と学習コスト低減によって、最大で50~80%の人件費削減効果が望めると言われています。限られた開発リソースで成果を上げたい場合に、威力を発揮するでしょう。
開発期間の短縮
マルチプラットフォーム開発では、基本的なアプリのロジックからUIまで共通のコンポーネントで実装できるため、iOSアプリとAndroidアプリの同時並行開発が可能です。
例えば、ユーザー登録機能を実装した場合、名前入力フォームや登録ボタンなどの設計を一度に済ませられます。このコードを、そのままiOS/Android両アプリで利用できるので2倍のスピードで開発を進められます。
加えて、フロントエンド中心の開発体制が取れるので、複数のエンジニアが同一の機能を別プラットフォーム用にバラバラに実装する必要がありません。
これらの理由から、開発生産性とスピードが大きく向上します。時間を要するネイティブ開発と比べて約30〜50%の短縮が可能と言われています。
人員確保がしやすい
マルチプラットフォーム開発は、JavaScriptやDartなどのWeb系開発言語が利用できるため、フロントエンドエンジニアの採用がしやすくなります。
HooksやStateなどのReactの概念に明るければ、スムーズにReact Nativeの基礎を習得できます。SwiftやKotlinなどネイティブ言語よりもハードルが低いです。
人材のスキル要件をある程度緩和できるほか、社内のWebエンジニアを比較的容易にクロストレーニングできます。
加えて、外部人材の納期の面でもメリットがあります。ネイティブ開発者の需要供給がひっ迫している状況にある中、クロスプラットフォーム開発者は手配しやすい状況にあります。
以上の理由から、適切な規模・コストでの開発チーム構築がしやすくなります。
※クロストレーニング・・・ある技能を持つ従業員に追加の新スキルを習得させることで、人材の有効活用を高める手法です。
例えば、Webエンジニアにモバイルアプリ開発のスキルを身につけてもらうことがあげられます。社内人材のスキル幅を広げる狙いがあります。
ユーザーの利便性が向上する
マルチプラットフォーム開発によって、iOSアプリ・Androidアプリの同時提供が可能になるため、サービスの市場投入スピードが向上します。
アプリのUIデザインや機能メニューを共通化できるので、ユーザーがOSをまたいでも新しいアプリに違和感なくアクセスできるようになります。
例えば、多機能な金融トレーディングアプリをリリースするケースを想定すると、iOSユーザーにもAndroidユーザーにも同時展開で提供できます。
操作性の一貫感も担保されるので、アプリの使い勝手に関するユーザー評価が高まることが期待できます。
結果として、サービスの信頼性とブランディング力の向上にもつながるでしょう。
マルチプラットフォーム開発で、効率的なアプリ開発を実現しませんか?Jiteraは、React NativeやFlutterを駆使し、iOS/Android両対応のアプリを高品質かつスピーディーに開発いたします。
Jiteraでは、マルチプラットフォーム開発に精通したエンジニアが、お客様のビジネス要件を深く理解し、最適なアーキテクチャを設計・実装いたします。コードの共通化とネイティブ連携の最適なバランスを保ち、開発効率と品質の両立を実現します。
Jiteraのマルチプラットフォーム開発の強み
- React NativeとFlutterの豊富な開発実績と高度な技術力
- コード共通化による大幅な開発コスト削減と納期短縮
- ネイティブ機能との連携を考慮した最適設計
- OS差異を吸収する徹底したテストとデバッグ
Jiteraは、スタートアップから大手企業まで、様々な規模と業種のお客様のマルチプラットフォーム開発を支援してきました。その知見を活かし、お客様のビジネスに最適化されたアプリをご提供いたします。
開発だけでなく、リリース後の機能追加や改善にも迅速に対応いたします。OSのバージョンアップにも柔軟に追従し、アプリの価値を維持・向上し続けます。
マルチプラットフォーム開発で、アプリビジネスの成長を加速させませんか。まずはお気軽にご相談ください。
マルチプラットフォーム開発のご相談はこちら
マルチプラットフォーム開発のデメリットと対策

マルチプラットフォーム開発にも懸念点はあります。ここでは主な3つのデメリットと対処法を紹介します。
| デメリット | 内容 | 対策 |
| 開発事例の少なさ | 先行事例が少なく試行錯誤が発生しやすい | 関連情報の網羅的収集と共有が必要 |
| 不具合対応の複雑さ | OS差異に起因するバグが多発し対応コストが嵩む | 網羅的なテストと継続的な調整が欠かせない |
| 新機能の取り入れ遅れ | OS側の新機能にすぐには対応できないケースがある | 独自対応や一部プラットフォームのみ対応など柔軟な判断が必要 |
開発事例が少ない
マルチプラットフォーム開発はまだ歴史が浅く、具体的なアプリ開発事例の公開は十分とは言えません。先行事例を参考にすることが難しいのが現状です。
そのため、アーキテクチャ設計やテスト計画など多くの点で、自社内での試行錯誤が必要不可欠となります。特に、複数のOSにまたがる複雑なデータ同期の実装検証に時間がかかる場合があります。
この点、時間やコスト的な無駄を避けるためにもオープンソースの参照先をしっかり確保しておき、他社事例や最新の技術動向の把握に努めることが大切です。
関連するカンファレンスや技術ブログへの参加、SNSでの情報交換などを通じて、リスクを回避する必要があるでしょう。
不具合への対応が複雑
マルチプラットフォーム開発では、iOSとAndroidの両方で同じようにアプリが動作することが理想ですが、OSやデバイスによる条件差が無視できないのが実情です。
例えば、データ送受信時のタイムアウト設定や、画面回転時のレイアウト崩れなど、一方では問題なくても他方では不具合が起きるケースが少なくありません。
このため、OSや機種ごとの網羅的な動作検証とバグ修正が欠かせず、複合的な調整が求められます。加えてOSのバージョンアップごとのテストも怠れません。
リリース後も含めた、継続的検証と対応コストが嵩むリスクがある点に注意が必要です。
新機能を取り入れにくい
iOSやAndroidのOSが提供する最新の機能を、いち早くアプリに取り入れることが難しいケースがしばしばあります。
例えば、新バージョンのOSで追加された画面分割表示や、独自の絵文字機能などは基本ライブラリだけでは対応できません。時間がかかる独自実装や回避検討が必要になります。
マルチプラットフォーム上で新機能を共通利用可能にするためには、十分なテストと各OSネイティブコードとの連携実装が欠かせません。場合によっては、一部プラットフォームでのみの対応とするなどの妥協も要します。
先行投資的要素も大きいため、サービス要件と開発コストの兼ね合いを慎重に判断する必要があるでしょう。
まとめ:マルチプラットフォーム開発はアプリ開発に重要

スマホアプリの開発に際しては、iOSとAndroidの両方に対応したサービス提供が求められています。限られた時間とリソースの中で市場投入スピードを上げるには、マルチプラットフォーム開発は欠かせません。
コードの大部分を共通化できることで開発効率が大きく向上するほか、Webエンジニアの採用しやすさといったメリットも生まれます。両者への対応速度と工数を、同時に改善できる手法として、大いに有効性が高いでしょう。
ただし、万能な手法であるとは限りません。機能の細部やデバイス差異への対応など、実装上の課題も少なくありません。うまく活用していくには、技術トレンドに詳しいITベンダーと相談しつつ進めるのが無難でしょう。
アプリ開発会社の選定でお困りの際は、豊富な実績を持つ株式会社Jiteraにお問い合わせください。
ニーズに合った的確なアドバイスをご提供いたします。