分析に必要とするデータを集約し、効率的に利用するためのツールとして注目を浴びているのがデータマートです。
しかし、データウェアハウスやデータベースという言葉は聞いたことがあっても「データマート」という単語をはじめて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、データマートの基本的な概念から、データウェアハウスやデータレイクとの違い、導入する際の注意点について詳しく解説します。また、データマートの導入事例についても詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
東京都在住のライターです。わかりづらい内容を簡略化し、読みやすい記事を提供できればと思っています。
データマートとは

データマートとは、特定のビジネス部門やチームが必要とする特定のデータのみを集め、整理、格納するためのデータベースのことを指します。
データウェアハウスの一部の中から必要なもののみを取り出し、ユーザーが必要な情報に迅速にアクセスできるようにしておくのがデータマートの仕組みです。
たとえば、以下のような情報をデータマートでは収集します。
- 販売データ(商品、数量、価格、販売日、店舗など)
- 顧客データ(顧客ID、性別、年齢、地域、購入履歴など)
- 市場調査データ(競合他社の情報、市場の傾向、消費者の行動パターンなど)
- 商品在庫データ(商品ID、在庫数、再補充の予定など)
- センサーデータ
また、データマートの目的はデータを分割し、小さなデータでまとめることです。そのため、小さな部門ごとの情報を集めてできたデータマートをいくつか組み合わせて、大きなデータウェアハウスを作成することもあります。
データマートのメリット

データマートには多くのメリットがあります。ここでは主な5つのメリットを紹介します。
- 構築・運用コストが低い
- アクセス速度が速い
- 柔軟性が高い
- セキュリティリスクが低い
- データ分析がしやすい
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
構築・運用コストが低い
企業の大規模データを扱うデータウェアハウスと比較して、構築・運用コストを抑えられるメリットがあります。
実装する場合、データウェアハウスと比較して予算が比較的抑えられます。なぜなら、設備投資や人件費などのコストを大幅に抑えられるからです。そして、運用時のランニングコストも抑えることができます。
結果として、運用にかかっていたコストを他の重要なプロジェクトに投資でき、新たなビジネスに挑戦できるかもしれません。
アクセス速度が速い
特定の業務領域に特化したデータのみを含むため、アクセスが速くなるメリットがあります。
なぜなら、データマートは情報の扱い方に沿って格納されているからです。そのため、イメージとしては引き出しを開けると、そこに必要なデータが入っており、簡単に見つけられるのです。
たとえば、マーケティングチームが消費者行動に関するデータを迅速に取得したい場合、必要な情報のみを検索できるので、マーケティング戦略の策定や改善をより迅速に、効率的に行えます。
そして、データウェアハウスのようにアクセスが一極集中しないため、負荷がかかりづらい点でも大きなアドバンテージがあります。
柔軟性が高い
データベースを変更する際にかかる負荷が少なく、変更の柔軟性が高いこともメリットです。データウェアハウスの場合は、企業データのすべてに変更内容が反映されていますが、データマートは部門ごとに修正ができるため、情報源に大きな変化を与えることはありません。
たとえば、マーケティング部門が顧客の購買データを分析するためにデータマートを使用しているとします。その後、新たなマーケティング戦略を導入することになり、それに伴い顧客の地域特性についてのトピックが追加で必要となった場合に、その部門だけ変更を加えることができます。
これに対して、データウェアハウスを使っていた場合は、全てに対して変更を適応させる必要があり、その負荷は大きくなってしまうのです。
セキュリティリスクが低い
データマートは、小規模のデータを扱うデータベースであるため、万が一不正アクセスがあったとしても、企業の機密情報全体を覗き見られることはありません。
たとえば、マーケティング部門が顧客購買データを管理するデータマートが不正アクセスされた場合、その他の重要な企業データである人事データや財務データなどは別の場所に保存されているため、侵入者はアクセスできません。
これにより、企業全体に及ぶセキュリティリスクが低減されると考えられます。
データ分析がしやすい
データ分析を効率化できます。これは、データマートが特定の業務内容に焦点を当て、関連する情報のみを扱っているためです。データが混在していて、どのデータにアクセスすれば良いかという迷いを防げます。
データマート・データウェアハウス・データレイクの違い
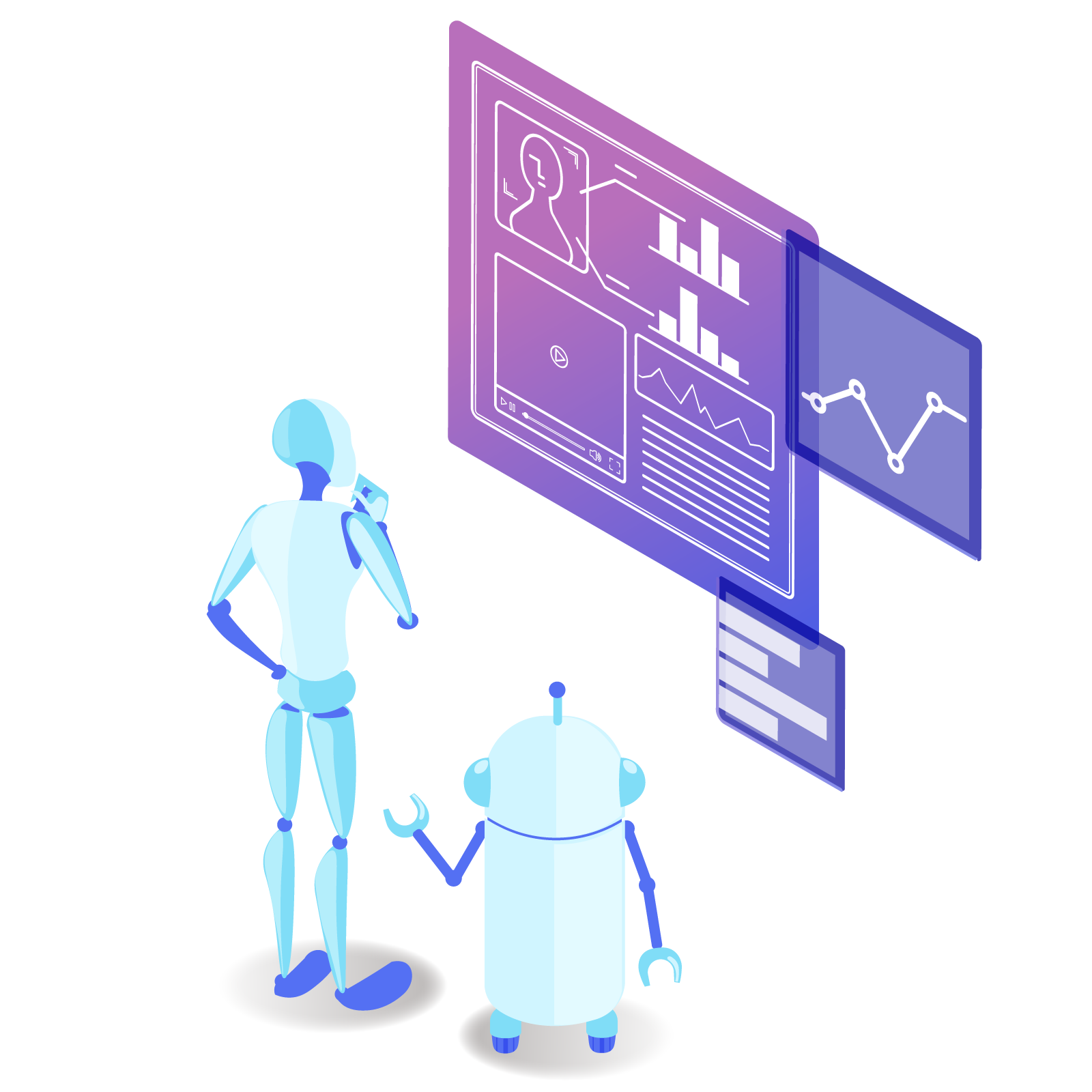
データマートと似た単語で「データウェアハウス」「データレイク」というものがあります。ここでは、各単語の違いについて以下の視点で迫ります。
- ビジネスにおける役割・用途
- 運用規模
- データの整合性
- 必要な技術やスキルレベル
- 適しているシチュエーション
また、各違いについては簡単に表にまとめたので、こちらをご覧いただいた後、詳しく知りたい方は本文をご覧いただければと思います。
| データマート | データウェアハウス | データレイク | |
| ビジネスにおける役割・用途 | ・情報を絞って格納 ・必要な情報を取り出しやすくする |
・企業全体のデータを一元管理 ・必要な情報はすべて格納されている |
・データを無加工の状態で保管する ・構造化データ、非構造化データなど形式は関係ない |
| 運用規模 | ・小規模 | ・大規模 | ・大規模 |
| データの整合性 | 整合性が低くなりがち | 整合性が低くなりがち | 整合性は高い |
| 必要な技術やスキルレベル | ・比較的簡単 | ・高度 | ・非常に高度 |
| 適しているシチュエーション | ・小規模の分析 | ・大規模の分析(経営陣など) | ・将来的に必要なデータを保管しておく |
ビジネスにおける役割・用途
まず、データマートは特定のビジネス部門のデータを格納・整理するためのものであり、情報を絞って格納しています。この特性があるため、データのマート(商店)と呼ばれており、まさに求めているニーズに対して必要な情報が提供されます。
データウェアハウスは企業全体のデータを一元化し、保管しておくためのものです。企業のあらゆるデータが格納されている、まさにデータのハウス(倉庫)のようなものです。
データレイクは、構造化・非構造化問わず全てのデータをそのままの状態で貯めておけるものです。翻訳すると「情報の湖」となるように、画像、文書、音声、メディアデータなどの情報を保存した状態でそのまま保管しています。
運用規模
データマートは比較的小規模なデータセットを管理するのに適しています。そのため、小売部門が商品の売上情報を管理し、販売トレンドを把握するために使用されます。
データウェアハウスは大規模なデータを管理できる特性上、企業全体のデータを一元化することに用いられます。部門を超えて情報にアクセスできるので、基幹システムと連携させ、経営方針を決めるといった活用が可能です。
データレイクは非常に大量のデータを保管できるため、将来的に加工されていない元データが必要になったタイミングで取り出すことができます。
データの整合性
データマートとデータウェアハウスでは、加工された状態でデータが保管されるため、誤った情報がその中に含まれている可能性があります。もしくは、複数の情報源にまたがって同じデータが保管されている場合に、両者の整合性が取れず、どちらを信用すれば良いかわからない場合があります。
しかし、データレイクは構造化・非構造化問わず、未加工の状態でデータが保管されているので、3つの中では最も信頼性の高い情報となっているでしょう。
必要な技術やスキルレベル
データマートの運用は、特定のビジネス部門の要求に対するデータ分析が主になるため、操作は比較的簡単だと考えられます。たとえば、マーケティング部門が顧客購入データを分析するために使用する場合には、その専門知識のみを必要とするので、その分野のプロフェッショナルであればデータを活用することが可能です。
一方、データウェアハウスの運用は複雑です。全社規模のデータを一元管理し、それを分析するためには、データベースの管理方法や大量のデータを効率的に分析する知識が必要です。また、組織全体の販売データや人事データを分析できる必要があり、経営陣など会社を俯瞰的な視点で見ることが求められます。
データレイクは最も高度な技術と大規模データ分析のスキルが求められます。これは、構造化データだけでなく、非構造化データも含めて全てのデータをそのままの形で保存し、必要に応じて分析できるように収集しなければならないためです。そして、分析の際には機械学習やビッグデータ分析などの高度な技術が必要となります。
適しているシチュエーション
データマートは、マーケティング部門が顧客購買データを分析し、ターゲット顧客の嗜好や購買傾向を理解したい場合に適しています。
データウェアハウスは、経営陣が企業全体の販売データや人事データを分析し、会社の経営方針や戦略を決定する際に使用することが多いです。
データレイクは、大量のソーシャルメディアデータやセンサーデータなど、構造化されていないデータを保管し、将来的にこれらのデータを分析し、ビジネスに繋げたい場合に適しています。
データマートの導入時の注意点

ここまで、データマート、データウェアハウス、データレイクそれぞれの違いを詳しく見てきましたが、理解いただけたでしょうか?
それでは、いったんデータマートの話に戻ります。ここでは、導入する際の注意点を4つ見ていきましょう。
- 導入前の計画と準備をしっかりする
- 全社的なデータ分析が難しい
- データの整合性が保ちにくい
- データ管理が複雑になる
導入前の計画と準備をしっかりする
データマートを導入する前に、入念に計画を行い、準備する必要があります。具体的には以下の表を参考に、入念に準備しておきましょう。
| 準備すること | 具体的な作業内容 |
| 目的の明確化 | どんな課題を解決するためのものか、どのような情報を取得するためのものかなど、目的を具体的に設定する |
| 必要なデータの選定 | 必要なデータの種類や必要な情報を特定する |
| データの取得元の確認 | 既存のデータベースから取得するか、新たにデータを収集する必要があるかなどを決定する |
| データの整理方法の設計 | データの変換や集計方法、分析手法などを詳細に計画する |
細かく設定しておくことで、今後作業を進める際に方針を見失わず済みます。「収集したデータが意味ないものだった」という失敗を防ぐためにも、入念に計画しましょう。
全社的なデータ分析が難しい
全社規模でのデータ分析は難しいことも注意点として挙げられます。データマートは部門やプロジェクト単位でデータを分析するのに適している構造をしているため、大規模なデータ分析には向かないのです。
そのため、全社的なデータ分析を行いたい場合は、複数のデータマートを組み合わせてデータウェアハウスを作成するか、データウェアハウスも実装し、そちらで分析を行うべきです。
データの整合性が保ちにくい
データマートは各部門やプロジェクトで独立してデータを管理するため、データの整合性を保つのが難しい場合があります。
たとえば、一部門では商品Aの売上が好調だと記録しているのに対し、別の部門では、商品Aの売上が低いと記録されていると、どちらのデータを信じるべきか判断が難しくなります。
このような場合、データの信用性が低く、誤ったビジネス判断を下す可能性があります。つまり、各データマート間での情報の一貫性を保つためのルールを設けることが重要です。
データ管理が複雑になる
データの種類や量が増え、データ管理が複雑になる可能性があります。データマートは活用しやすい情報を保管しておく目的で用いられますが、複数のデータマートを活用する場合には管理が煩雑になり、一貫性を欠いてしまうケースがあるため、注意しましょう。
たとえば、データAが複数のデータマートに保管されていて、それぞれのデータマートで名称が異なるケースを仮定します。各データマート内で加工が繰り返され、データの整合性がなくなると、どのデータを信用すれば良いのかわからなくなるでしょう。
扱う情報が増えるにつれて管理が疎かになることもあるため、情報を他のデータマートに持ち出さないといったルールを設ける必要があります。
データマートの活用事例

最後に、データマートの活用事例をみていきましょう。ここでは、実際にデータマートを活用している4つの事例を紹介します。
小売業での活用事例
小売業で各店舗の売上情報をデータマートに集約させ分析します。この方法を用いることで、どの商品がどの店舗でよく売れているのか、もしくは、どの時期にどの商品が売れているのかを明確に把握することが可能です。
また、顧客の購買データを分析することで、商品の人気が地域や性別、年齢によってどのように変化するのかを理解できます。これらの情報を利用して在庫管理を行うことで、在庫過多のリスクを減らし、売上を最大化することが可能です。
金融業での活用事例
金融業界におけるデータマートの活用例として、投資商品のリスク管理に使用している事例を紹介します。銀行は顧客からの投資商品の購入データをデータマートに集約させ、これらのデータを分析することで、各商品のリスクレベルを評価しています。
また、データマートは顧客の資産管理にも活用されています。銀行は顧客の預金、投資、ローンなどの金融商品データをデータマートに集約させます。これらのデータを分析することで、顧客の資産状況を把握し、最適な資産管理アドバイスを提供することが可能です。
製造業での活用事例
製造業界では、データマートは非常に重要なツールです。データマートを用いて様々なデータを分析することにより、生産ラインのボトルネックを特定し、問題を早期に解決することが可能となります。
たとえば、材料の供給スケジュールと実際の使用時期を比較し、材料供給の遅延が生産工程に影響を及ぼしていないかを確認するといった活用方法があります。
また、品質管理においても、製品の欠陥がどの工程で発生しているのかを明らかにし、その原因を根本から改善することができます。
サービス業での活用事例
サービス業界では、データマートを顧客サービスの改善や業績分析に使っています。企業は顧客の嗜好や行動パターンを理解し、機械学習やマーケターの分析などによってサービスを最適化させています。
たとえば、レストランチェーンが顧客の注文データを分析し、地域ごとの人気メニューや注文の傾向を把握するために、データマートを使用しています。
まとめ:データマートの今後の展望と企業戦略への影響

今回は、データマートの基本的な概念から、データウェアハウスやデータレイクとの違い、データマートを導入する際の注意点などについて詳しく解説しました。
データマートは部門やプロジェクト単位でデータを保管・分析する際に役立つツールです。
しかし、ビジネスで分析を行うには、データウェアハウス、データレイクなどとの違いを理解し、それぞれの特性と用途を踏まえた上で、最適なデータ戦略を選択することが求められます。
今回ご紹介したデータマートの活用事例などを参考に、自社のビジネス環境に最適なデータ戦略を立案しましょう。
また、AIや機械学習の進展により、大量のデータを高速で分析する技術が進化しています。これにより、データを用いて、より深く分析することが競合優位性に関わるため、データマートはますます注目されています。今後、データ分析で強みを持ちたいなら、データマートへの知識はもちろん、実践ベースで考えなければなりません。
もし、データマート実装に興味があり、疑問やこの記事への質問、ビジネスの相談、お問い合わせなどがございましたら、実績豊富な株式会社Jiteraにご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスを提供させていただきます。






